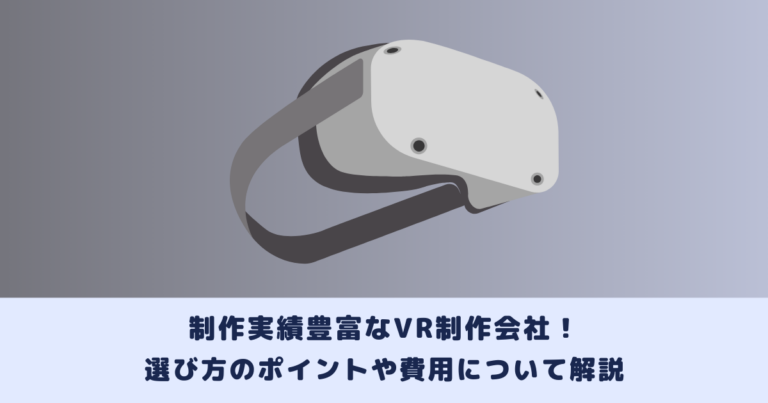「介護DX」という言葉を耳にしたことはあるでしょうか?
介護のDXとは、情報技術(IT)を活用して介護業界をより効率的で高品質なものに進化させるという概念です。
今、急増する高齢化社会に伴う介護ニーズの増大と、介護職員の慢性的な人手不足によりこの介護DXが急速に注目を集めています。
本記事では、介護DXの基本から、その具体的な事例、さらには厚生労働省も注目するスタートアップ企業について詳しく解説します。
一読すれば、介護DXがどのように介護業界の課題解決に寄与し、利用者の生活を向上させるのかを理解できるでしょう。
スキマ時間に読み切れる内容になっていますので、ぜひご覧ください。
<この記事を読むとわかること>
- 「介護DX」の概念とその重要性
- 介護DXの実際的な事例とその効果
- 厚生労働省が注目する介護DXスタートアップ企業の紹介
- 介護業界の今後の展望と介護DXの可能性
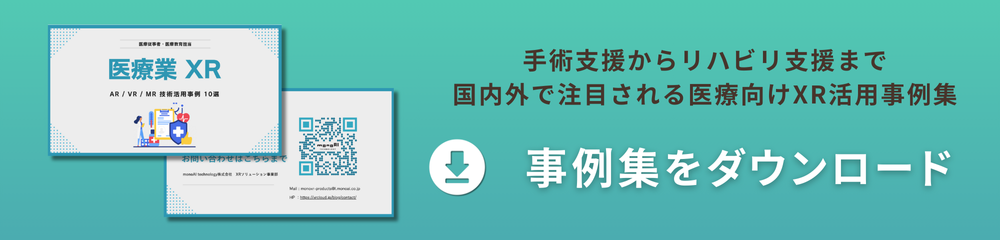
目次
|介護DXとは?
介護DX(デジタルトランスフォーメーション)とは、単に介護ソフトやロボットといったデジタルツールを導入することではありません。
デジタル技術を深く活用することで、介護業務のあり方そのものを根本から見直し、利用者へのサービス品質向上と、事業所の現場課題、ひいては経営課題を同時に解決しようとする取り組みを指します。
具体的には、以下のような変革を含みます。
- アナログ業務のデジタル化
紙ベースの記録や情報共有をタブレットやスマートフォンに移行し、業務の効率化を図ります。
これにより、介護従事者は記録業務にかかる時間を減らし、利用者様と向き合う時間を増やすことができます。 - データ活用によるサービス改善
介護記録やバイタルデータを一元的に管理・分析することで、一人ひとりの利用者様に最適なケアプランを科学的に立案・実行します。
これは介護サービスの質の向上だけでなく、リスクの早期発見にもつながります。 - 働き方の改革
ICT機器やロボットの導入により、身体的な負担が大きい業務を軽減し、誰もが働きやすい職場環境を整備します。
これは、深刻な人材不足を抱える介護業界において、人材の定着と確保に不可欠な要素です。
介護DXは、単なる業務効率化や品質向上に留まらず、高齢化が進む中で業界の未来を拓くための重要な戦略なのです。
|なぜ介護業界でDXが必要とされているのか
現在、介護業界には様々な課題が存在します。
では、介護DXが求められる背景として、具体的にどのような課題が存在し、それらがどのように解決を求めているのか、詳しく見ていきましょう。
課題①:人口高齢化に伴う介護ニーズの増大
65歳以上の高齢者人口が総人口の約30%を占める日本。
少子高齢化が進む我が国における、介護ニーズの増大は避けられません。
この増大とは、具体的には、高齢者が必要とする介護サービスの量と範囲が増加することを指します。
高齢者が多い地域では、それに伴い介護サービスを提供する事業所や介護職員の需要も増えます。
また、高齢者一人ひとりの健康状態や生活能力によって、必要とされる介護サービスの種類や程度も変わります。
病気や身体機能の衰えにより日常生活に支障をきたす高齢者が増えれば、介護サービスへの需要もそれに伴い増大します。
この課題が深刻な理由として、まず財政負担の増大が挙げられます。
多くの介護サービスは公的な介護保険により運営されており、介護ニーズの増大はその負担を増やすことにつながります。
さらに、労働力人口の減少とともに社会保障費が増加する一方で、税収は減少し、これらのバランスが崩れることで経済全体にも影響を及ぼします。
課題②:介護職員の慢性的な人手不足
介護業界は、深刻な人手不足に直面しています。
厚生労働省の報告によると、今後5年間で必要な介護職員数と供給見込みのギャップが約37.7万人にも達するとされています。
一方で、介護ニーズの増大に伴い、今後も介護職員数の増加が求められています。
この人手不足がもたらす問題点は大きく二つ。
一つ目は、介護職員の過重労働と労働環境の悪化です。
人手不足により、既存の職員に多くの業務が降りかかり、過重労働につながるケースが多く見られます。
これが職員の健康問題や離職率の上昇に繋がり、さらなる人手不足を招く悪循環に陥ります。
二つ目は、サービス品質の低下です。
必要なサービスを適切なタイミングで提供するためには、適切な人員配置が不可欠です。
人手不足によりその配置が困難になると、結果としてサービス品質が低下する可能性が指摘されています。
課題③:介護現場におけるサービス品質の維持
人手不足が引き起こす介護現場の課題の一つが、サービス品質の維持です。
介護は、高齢者が安心して生活するために必要不可欠なサービスであり、その質が低下すると高齢者の生活に大きな影響を及ぼします。
具体的には、サービスの提供時間が短縮されたり、必要なケアが行き届かない事態を招く可能性があります。
サービス品質を維持、向上するためには、介護職員の労働環境の改善と、新たな労働力の確保が必要となります。
しかし、現状では、介護職の過酷な労働環境や低賃金が課題となり、新たな人材の確保が難しくなっています。
これらの課題背景から、介護業界では、現場におけるDX化が必須となりつつあるのです。
|介護DXがもたらす4つのメリット
介護業界にDXを導入することで、現場の介護従事者から経営者まで、多岐にわたるメリットを享受できます。
ここでは、特に重要な4つのメリットをご紹介します。
1. 業務効率化による負担軽減と生産性向上
介護施設における記録業務や情報共有は、多くの時間と労力を要します。
介護DXによって、これらの業務を自動化・デジタル化することで、介護従事者は記録作業にかかる時間を大幅に削減し、利用者様と向き合う時間を増やすことができます。
これは介護従事者の負担軽減につながるだけでなく、サービスの質の向上にも直結します。
2. 介護サービスの質と安全性の向上
見守りシステムやIoT機器を活用することで、利用者様の状態を24時間リアルタイムでモニタリングできるようになります。
これにより、異変を早期に察知し、迅速な対応が可能になります。
また、日々の記録をデータとして蓄積・分析することで、一人ひとりの利用者様に合わせた、よりパーソナライズされたケアプランの作成にも役立ちます。
3. 経営改善と競争力の強化
DXは、経営面にも大きなメリットをもたらします。
例えば、業務効率化による残業時間の削減は人件費の削減に繋がり、経営のスリム化に貢献します。
さらに、データに基づいた科学的なマネジメントが可能になることで、経営者は正確な状況把握と迅速な意思決定を行えるようになります。
これは、事業の持続性を高め、他社との差別化を図る上で不可欠です。
4. 働きやすい環境整備による人材確保
深刻な人材不足は、介護業界が抱える共通の課題です。
デジタルツールを導入し、業務を効率化することで、介護従事者の負担が軽減され、働きやすい環境が整備されます。
また、ICTスキルは、これからの介護業界で働く上で必須のスキルとなりつつあり、DXへの取り組みは新しい働き方を目指す人材にとって魅力的な要素となります。
これは、人材の定着率向上と新規人材の確保に大きく貢献します。
|実際の現場はどうDX化されている?介護DX事例7選
では実際に、介護業界の現場においてどのようにDXが進められているのでしょうか。
このセクションでは、これら7つの事例について、その概要とどのように介護現場で活用されているのかについて解説します。
事例①:介護業界専門勤怠管理システム「CWS for Care」
<「CWS for Care」の特徴>
- 介護業界特有の複雑な就業情報管理に対応。
- エクセル形式のシフト表の作成が可能。
- 勤務時間やシフト人数の自動集計機能。
<導入企業の課題>
- 煩雑なシフト作成や勤怠管理による時間ロス。
- 効率化により、利用者への対応時間を増やすこと。
<導入後の効果>
- シフト作成時間が約3分の2に削減、最短で1/3に。
- 自動集計による誤差の削減と人的ミスの防止。
- 月初の一気な集計作業が分散、作業負荷と心理的な負担軽減。
「CWS for Care」は介護業界に特化した勤怠管理システムであり、職員情報を正確に登録することで、必要なデータを自動的に出力する機能を備えています。
これにより、毎月エクセルで個別に作成していたシフト表などのデータを自動で出力でき、シフト作成時間を大幅に短縮することが可能になりました。
福岡県大牟田市の「小規模多機能施設わたぜ」と「小規模多機能施設くぶき」を運営する株式会社 銀水会では、「CWS for Care」の導入により、7〜8時間かけて行っていたシフト作成作業が2/3程度に短縮。
さらに、パソコンやスマホの操作に慣れた職員では、1/3程度まで作業時間を削減することができたとのことです。
また、自動集計機能により、人的ミスを減らすとともに、業務負担の軽減を実現しました。
特に、シフトと勤務時間にズレが生じた場合の確認作業が、システム上でエラーメッセージが表示されることにより、リアルタイムに行えるようになりました。
その結果、月初に一気に行っていた集計作業が分散され、作業負荷と心理的な負担が大幅に減っています。
事例②:介護記録ソフト「Care-Wing」
<「Care-Wing」の特徴>
- ICタグを活用し、介護現場での時間管理を確実且つ正確に行える
- 介護記録を電子化し、管理を容易に行える
- 他のソフトとデータ連携が可能で、業務の効率化が実現
<導入企業の課題>
- 業務の集中と効率化の問題
- ヘルパーとサ責のICT利用への抵抗感
- 適切な導入方法の検討
<導入後の効果>
- 業務時間の大幅な削減と効率化
- ペーパーレス化によるコスト削減
- リモートワークの導入による業務運用の柔軟性向上
有限会社青空の青空ケアセンターは、テレワーク体制の構築、ペーパーレス化、業務効率化といった課題を抱えており、月末月初の業務や紙による記録書類の繁雑な管理から脱却したいと考えていました。
そんな中、「Care-Wing」の導入に踏み切りました。
なぜ「Care-Wing」を選んだかというと、介護現場での時間管理をICタグで実現できること、そして記録を電子化して管理が容易になるという点が大きかったのです。
さらに、他のソフトとのデータ連携が可能なため、請求やシフト管理、給与計算といった業務を一元化することもできました。
その結果、効率化した業務は介護職員の日常の仕事負担を大幅に軽減。紙での記録や突合作業から解放されたことは、介護職員にとって大きな負担減となっています。
ヘルパーはより余裕のある実働時間を持つことができ、事業所への記録用紙の提出も不要となりました。
さらに、コスト削減やリモートワークの導入が可能になったことで、業務運用の柔軟性が向上したとのことです。
事例③:動画型マネジメントシステム「ClipLine」
<ClipLineの特長>
- 双方向コミュニケーション:全スタッフ間で、動画を通じた相互コミュニケーションを実現。
- 暗黙知の形式化:デジタルSECIモデルを用い、暗黙知を形式知に転換。
- 映像制作と経営支援:専門チームによる映像制作とプロフェッショナルによる経営支援を提供。
<導入企業の課題>
- 増加する中途入職者による「我流介護」の是正
- 法定研修の現場負担の軽減
- 動画コンテンツの質の向上
<導入後の効果>
- 導入を通じて現場の負担が軽減
- 動画コンテンツの高評価により共同制作も実施
- 確かな技術と理解の仕組みづくりが推進された
ClipLineは、多拠点・多店舗ビジネスの実行を阻む壁を解消するために開発されたシステムです。
動画を通じた本部と現場の双方向コミュニケーションを可能にし、全スタッフ、アルバイトを含めた現場の皆さんが情報を効果的に共有できます。
ClipLineの導入によって、社会福祉法人ウエル清光会では、「我流介護」の是正や法定研修の現場負担軽減を実現しました。
また、ClipLineが制作する動画コンテンツの質は高く評価され、共同でコンテンツ作りも実施することになりました。
ClipLineの導入は、技術と理解の仕組みづくりを推進し、確かな介護サービスの提供を可能にしています。
事例④:介護業務支援サービス「LIFELENS」
<介護業務支援サービス「LIFELENS」の特長>
- 高感度センサーやパナソニックのセンシング技術を用いて、入居者の状態や生活リズムをリアルタイムで把握
- 業務効率化とケアの質の向上を両立することで、施設の価値向上とスタッフの負担軽減を実現
<導入企業の課題>
- 夜間巡視とコール対応業務の負担軽減、スタッフの心身ストレスの低減、高品質なサービス提供の必要性
- テクノロジーを用いて効率的な運営を実現し、サービスの質を向上させる要望
<導入後の効果>
- 91%の夜間巡視時間を削減し、必要な時に適切な訪室を可能にし、入居者へのサービス提供時間を増やす
- 高品質なサービス提供により入居者、家族、スタッフの満足度向上
HITOWAケアサービスは、ICTを活用した介護業務の改革を目指し、その一環としてLIFELENSを導入しました。
導入背景には、テクノロジーを活用して現場の負担を軽減し、良質なサービスを提供したいという思いがあったとのこと。
具体的な取り組みとしては、シートセンサーや映像データの収集・分析等を用いて、入居者の睡眠状態や離床を察知し、必要なときだけ訪問するという業務効率化を実現しました。
これにより、スタッフと入居者双方のストレス軽減に成功しています。
導入により、今後は転倒事故の未然防止やADLの変化の把握等、ICT/AIを活用した「先回りの介護」の実現を目指していけるようになっています。
事例⑤:介護の業務過程をDX化「HitomeQ」
<HitomeQの特徴>
- 介護施設の様子をリアルタイムで把握することが可能
- 独自のAI技術により、利用者の状態変化を即座に検知
- 通知や映像を活用し、スタッフ間のコミュニケーションや情報共有に寄与
<導入企業の課題>
- リアルタイムで介護施設の状況を把握できるシステムがない
- スタッフが利用者の異常状態を見落とすリスクがある
- 新規入所者の傾向や動き方を把握するのが困難
<導入後の効果>
- 異常状態を即座に察知し、迅速な対応が可能に
- 日々のケア業務の品質向上につながる
- 新規入所者のアセスメントが効率的に行えるように
千葉県にある住宅型有料老人ホーム カイト浦安では、HitomeQを活用して介護業務をDX化しています。
効果のわかりやすい例として、利用者が転倒し痙攣を起こすという緊急事態が発生した際、HitomeQによる通知と映像で現場のスタッフが異常をすぐに把握し、1分以内に現場に駆けつけることができるようになったとのこと。
また、同システムは利用者が日常的に行う行動パターンや反応を観察することで、異常時の対応だけでなく、日々のケアプランの最適化にも寄与しています。
更に、施設見学の際にシステムの存在を説明することで、安心感を提供し、入居者の集客にも寄与しており、スタッフの採用面でも、作業効率やケアの質の向上により、働きやすい環境を提供できると評価されています。
事例⑥:睡眠見守りシステム「みまもり~ふ」
<「みまもり~ふ」の特徴>
- マット型の見守りセンサで、心拍や呼吸まで解析可能
- 利用者の睡眠状態や生体情報をリアルタイムで確認可能
- 睡眠の質(睡眠クオリティ)を評価し、介護プラン作成に活用
<導入企業の課題>
- 利用者の睡眠状態や生体情報を適切に管理、対応する手段がない
- 利用者の居住エリアとスタッフステーションとの距離があるため、確認に時間がかかる
- 自力で移動が難しい利用者や、ナースコールボタンを押すことが困難な利用者の状態を確認する手段がない
<導入後の効果>
- 職員の巡回・介助タイミングの判断が容易になる
- 遠隔から状態確認が可能になり、効率化と高品質な介護サービスが提供可能
- 早期介助が可能となり、夜間の巡視もスムーズに行える
テクノホライゾン株式会社が開発した「みまもり~ふ」は、見守りシステムの新たな可能性を示しています。
利用者の離床検知はもちろん、心拍や呼吸の確認、さらには睡眠の質まで解析できるこのマット型センサは、導入施設である医療法人白光の「シルバーヘルス一関」で実際に利用されており、介護の現場で大きな効果を上げています。
リアルタイムで睡眠状態や生体情報を確認できる「みまもり~ふ」は、職員が巡回・介助のタイミングを適切に判断するための強力なツールとなっています。
また、自力で移動が困難な利用者や、ナースコールボタンを押すことが難しい利用者の状態も遠隔から確認でき、介護サービスの質向上と効率化を可能にしています。
さらに、「みまもり~ふ」の利用により、早期に起き上がりの情報をキャッチし、早期介助が可能となります。
これにより、夜間の職員巡視もスムーズに行えるようになり、職員の負担軽減と共に、利用者の安心と安全を高める効果を発揮しています。
事例⑦:立位補助・移乗介助機器「Sara® Flex(サラ・フレックス)」
<Sara® Flexの特徴>
- シリコン製のレッグサポートによる高い安定性
- 機器の調整が不要で使用時の手間がかからない
- 利用者の昇降とレッグの開閉動作が電動
<導入企業の課題>
- 職員の腰痛予防という課題への対策
- 自力で立つのが難しい高齢者への支援
- 安全で自然な移乗・姿勢変更の必要性
<導入後の効果>
- 職員の腰痛の軽減
- 安全で自然な移乗・姿勢変更の実現
- 高齢者の自立支援
立位補助・移乗介助機器「Sara® Flex(サラ・フレックス)」は、座位から立位、または立位から座位へと、自然な動作で姿勢を変えることが可能な製品です。
具体的な導入例としては、「社会福祉法人永寿荘」が挙げられます。この法人では、介護職員の腰痛予防と高齢者の自立支援を目指し、「Sara® Flex」を活用しています。
職員研修を通じて、”持ち上げない介護”という考え方を定着させる一方で、介助器具の導入にも積極的に取り組んでいます。
その結果、介護職員の腰痛軽減と、安全で自然な移乗・姿勢変更が可能となり、介護の質が向上しました。
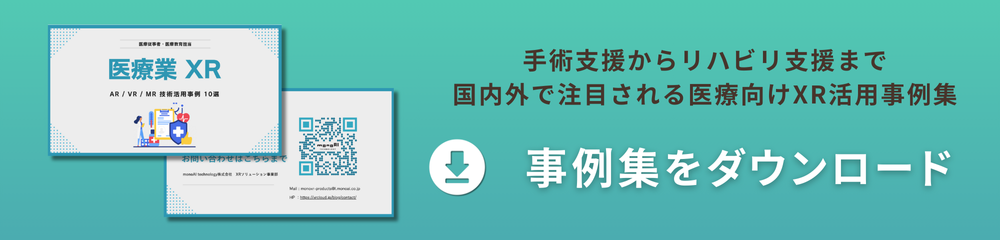
|介護DXを進めるための補助金制度
介護事業所がDXを導入する際には、補助金制度の活用が重要です。
最後に、ここでは特に主要なものを軽くだけご紹介します。
IT導入補助金
中小企業や小規模事業者の生産性向上を目的とした制度で、介護事業所も対象となります。
ソフトウェアやハードウェアの導入費用が補助対象となり、DXに不可欠な介護ソフトやタブレット端末、PCなどが含まれます。
IT導入支援事業者と協力して申請する必要がある点が特徴です。
介護テクノロジー導入支援事業(地域医療介護総合確保基金)
介護現場におけるテクノロジー導入を支援する厚生労働省の事業です。
移乗支援、見守り、入浴支援といった特定の介護ロボットや、介護業務支援システム(介護ソフト)の導入費用が補助対象となります。
事業所がある都道府県が窓口となるため、自治体ごとの公募要項を確認することが重要です。
各自治体の独自補助金
国の制度に加えて、各自治体が独自に介護事業所のDXを推進するための補助金・助成金制度を設けている場合があります。
介護ソフトやICT機器の導入、Wi-Fi環境の整備などが補助対象となるケースが多く、国の制度と併用できる場合もあります。
これらの補助金は、それぞれ対象となる機器や補助率、申請期間などが異なります。補助金の活用を検討する際は、事業所のニーズに合った制度を選び、公募要項をよく確認することが成功の鍵となります。
|まとめ:介護業界は厚労省も補助金などを出し注目の業界へ
本記事では、「介護DX」という新たな概念と、それが介護業界の課題解決にどのように寄与するのかについて詳しく解説しました。
人口高齢化に伴う介護ニーズの増大や介護職員の人手不足は、テクノロジーの活用で解決を見込めます。
また、スタートアップ企業による革新的な取り組みも、この分野の発展に大いに貢献しているのです。
しかしながら、こうした技術革新が持続するためには、企業だけでなく一人ひとりが新たな技術を理解し、それを積極的に取り入れる意識が重要です。
介護業界だけでなく、社会全体が介護DXを進めることで、より良い高齢社会を構築することが可能になります。
この記事が、皆様の介護DXに対する理解を深める一助となり、そして今後の介護サービスの利用や、介護業界への関与、さらには社会全体の高齢化対策に役立てられることを願っています。

 TWITTER
TWITTER
 FACEBOOK
FACEBOOK
 はてブ
はてブ