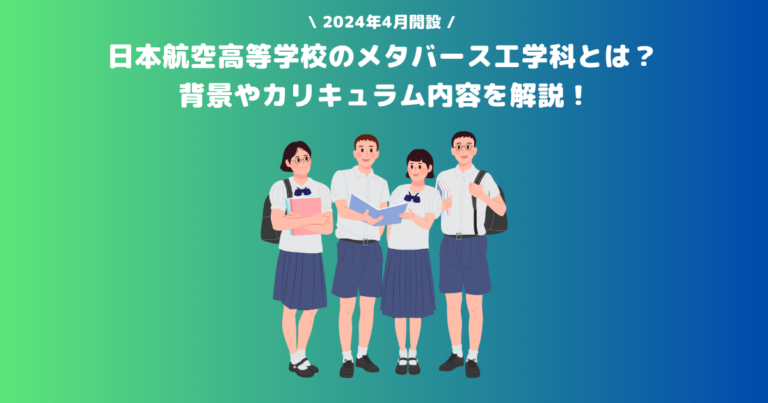学校法人日本航空学園は、設置校である日本航空高等学校通信制課程にて、山梨県認可の専門学科として2024年4月よりメタバース工学科を新規開設します。
この学科では、最新のテクノロジーを学び、未来を創造する力を身につけるための教育が提供されます。
本記事では、このメタバース工学科の背景やカリキュラム内容についてわかりやすく解説していきます。
また、以下の記事でメタバースについて詳しくまとめていますので、気になった方はぜひこちらも合わせてご覧ください。


目次
|日本航空高等学校とは
出典:https://myterminal.jp/school.html&id=16
日本航空高等学校は、学校法人日本航空学園が運営する私立の高等学校で、山梨県甲斐市と石川県輪島市にキャンパスを持っています。
この学校は、航空業界や航空関連業界で活躍したいと希望する生徒を対象としており、国内の高等学校としては珍しい「航空科」を設置しています。
航空科では、将来のパイロット、航空整備士、キャビンアテンダントを目指す生徒が必要な知識や技術を学びます。また、普通科も設置しており、大学進学を目指す生徒にも対応しています。
このように、日本航空高等学校は、航空業界への進出を目指す生徒から、大学進学を希望する生徒まで、幅広い進路を目指す生徒を支援しています。
|日本航空高等学校にメタバース工学科が開設!
出典:https://jaa-tsushin.ed.jp/assets/images/course/metaverse_course.pdf
日本航空高等学校は、2024年4月に通信制課程にて新たに「メタバース工学科」を開設しました。この新設学科は、メタバース(仮想現実)の制作者を育成することを目指しています。
専門学科としてメタバース、ITテクノロジー、CG(コンピューターグラフィックス)などに関する専門教科が単位認定され、個々の学生が関心を持つ領域に焦点を当て、彼らの強みや個性を伸ばす上での新たな学習機会を提供します。
さらに、学科の目指す将来の展望として、学生たちが地域社会や企業と協力し、専門的な技術を通じて地方の再生と活性化に貢献するというものがあります。これは同時に、彼らがより実践的な学びを受けられる場の提供を目指します。
日本航空高等学校は新たな時代の教育ニーズに応え、未来を創り出す人材を育てる役割を果たしています。
開設された背景
日本航空高等学校が「メタバース工学科」を開設する背景には、社会での重大な変化があります。
総務省の令和5年版「情報通信白書」によれば、新型コロナウイルスの影響で仮想空間の利用が広がり、特にメタバースの利用が増えています。これはバーチャル展示会、社内イベント、そしてネット通販などのさまざまな領域で顕著で、結果的に日本のメタバース市場が拡大しているのです。
この市場の膨張に伴い、メタバース(仮想空間)を構築する人材がさらに必要となる予測が立てられています。
一方で、デジタル世代の子供たちは既にコンピューターやプログラミング、メタバースに関心を持っていますが、それらの学習選択肢はまだまだ不足しています。
このことから、子供たちが個性を発揮でき、自身の興味を深めるための新たな選択肢として日本航空高等学校は「メタバース工学科」を設立しました。
|メタバース工学科で学べるカリキュラム
日本航空高等学校の新設「メタバース工学科」では、未来を見据えた革新的なカリキュラムが提供されます。仮想空間の設計からプログラミング、AIの活用まで、メタバースの創造に必要な全てを学びます。
ここからは、次世代のメタバース開発者を育成するためのカリキュラムについて詳しく説明いたします。
1年次
1年次にはITの基礎知識や、メタバースプラットフォームでの空間制作、アバター制作、AIの利活用などを学びます。具体的には、プログラミング言語の基礎、3Dモデリング、VR/ARの基礎などが含まれます。
また、FORTNITE、Cluster、Spatial、VRChat、Vket Cloudなど国内外のメタバースプラットフォームを活用してさまざまな技術習得を行います。
これらのスキルは、メタバースの世界で活躍するための基盤となります。
2年次
2年次には、ブロックチェーンやNFT、Web3などの先進的なテクノロジーに焦点を当て、より専門的な知識と技術を深めます。
これにより、学生たちはデジタル世界を理解し、操作するために必要な技術を磨き上げることが可能となります。
今後のデジタル社会における中心的なテーマを扱うことで、学生たちはデジタル化が進む社会における問題解決のための手段として、これらの技術を活用する力を身につけることができます。
3年次
3年次では、これまでの学習を生かして、独自のメタバース空間の設計や開発に挑戦します。
また、BlenderやUnity、UnrealEngineなどのツールを使用して、CG制作やゲーム開発のスキルを磨きます。
最終的には、ITエンジニアとして社会に出て活躍するための実践的な力を身に着けることを目指します。
取得が可能な資格
日本航空高等学校メタバース工学科では、在学中に以下の資格の取得を目指すことができます。
- ITパスポート
- 基本情報技術者
- Unity Certified Associate:Programmer
- CGクリエイター検定
- 色彩検定
特にITパスポートと基本情報技術者試験は、どちらもIT系の基礎的な資格です。
資格を取得することで未経験からIT業界に転職する際に有利になることも多いです。
卒業後の進路
日本航空高等学校では、幾つかの興味深い経路が卒業後の主な進路として挙げられています。
それらは、メタバースクリエイター、ゲーム/CGクリエイター、ITエンジニア、そして起業家といった職業です。
これらの進路を見てみると、メタバース工学科の卒業生が目指しているのは、単に航空業界だけでなく、ITやメタバースに関連した分野への進出、さらに自身でビジネスを立ち上げる道も視野に入れていることが見受けられます。
これは、日本航空高等学校が、ただ知識を教えるだけではなく、さまざまな可能性を追求する力を学生たちに育んでいることを示しています。
|メタバース工学科の学費は?
メタバース工学科の学費は、初年度の総額が417,000円、2年次以降は年間357,000円となっています。以下に具体的な内訳を示します。
初年度費用
| 入学検定料 | 10,000円 | 入学初年度のみ |
| 入学料 | 50,000円 | 入学初年度のみ |
| 教育充実費 | 50,000円 | 毎年度 |
| システム料 | 5,000円 | 毎年度 |
| 事務所経費 | 2,000円 | 毎年度 |
| 授業料(単位料) | 250,000円 | 1単位10,000円(25単位の場合) |
| 受講料 | 50,000円 | 毎年度 |
| 合計 | 417,000円 |
これらの学費は2回分納となり、入学時に入学検定料、一回目で入学金・教育充実費、システム料、事務諸経費を請求し、二回目の授業料(単位料)の請求は国から就学支援金の支給額が決定次第、相殺した額を請求します。
なお、授業料の25単位は、卒業までに必要な74単位以上を達成するための数です。
詳しい情報は日本航空高等学校の公式サイトをご確認ください。
https://jaa-tsushin.ed.jp/admission/fee/
|高校生でメタバースについて学べる学校
学科としては日本航空高等学校が日本初です。
しかし、学科としての形態を持たないものの、高校生がメタバースについて学べる新たな形態の学校、「MEキャンパス」というものがあります。
最後に、この学校について詳しくご紹介します。
MEキャンパス
出典:https://mecampus.org/
MEキャンパスは、メタバース空間で学べる新しい形態の学校です。2023年4月に開講し、メタバースの基礎から応用技術まで幅広く学ぶことができます。
誰でも入学できる1年間コースと、提携通信高校との同時入学による3年間コース(高校卒業の資格取得が可能)を設置しています。動画教材や課題制作を通して、メタバース構築や運営に必要な専門技術を習得できます。
以下の記事で詳しくMEキャンパスの内容についてまとめていますので、気になった方はぜひこちらも合わせてご覧ください。
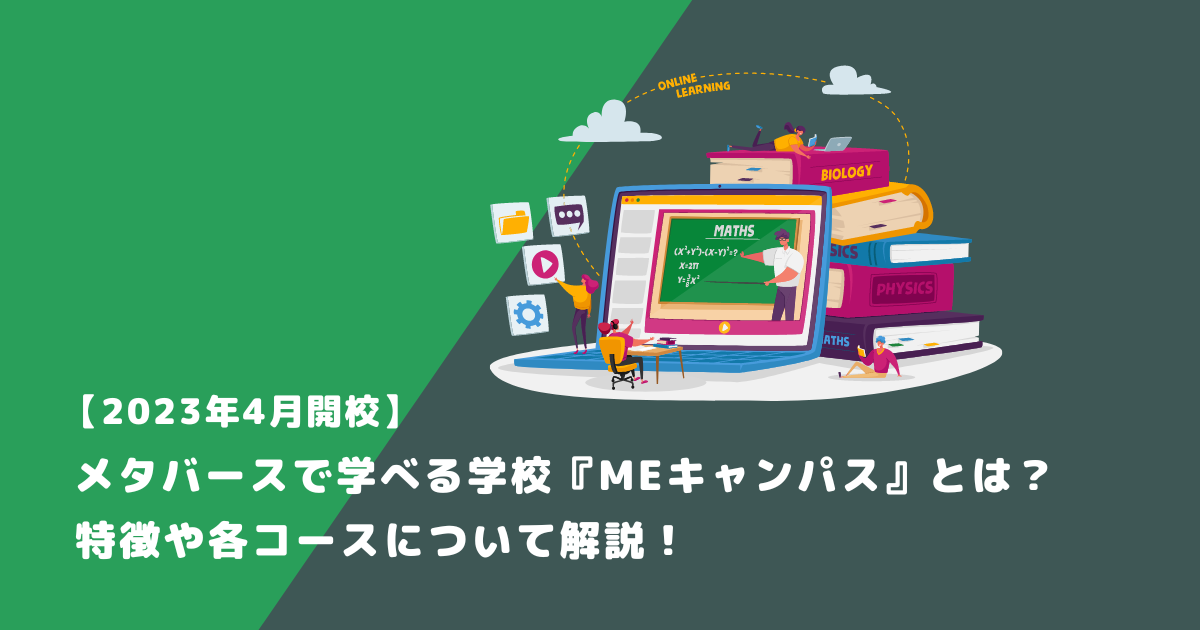
|まとめ
いかがだったでしょうか。
この記事では、日本初のメタバース工学科を設置した日本航空高等学校の取り組みを詳しく紹介しました。
その背景やカリキュラム内容を通じて、メタバースという新たなデジタル空間での教育の可能性を知ることができました。
また、学科としての形態を持たないものの、高校生がメタバースについて学べる新たな形態の学校、「MEキャンパス」についても取り上げました。
これらの教育機関は、新たな学びの場を提供し、次世代の技術者を育成するための重要な役割を果たしています。
この取り組みから、メタバースという新たな世界での教育の可能性が見えてきます。
これからも、このような教育の進化に注目していきましょう。

 TWITTER
TWITTER
 FACEBOOK
FACEBOOK
 はてブ
はてブ