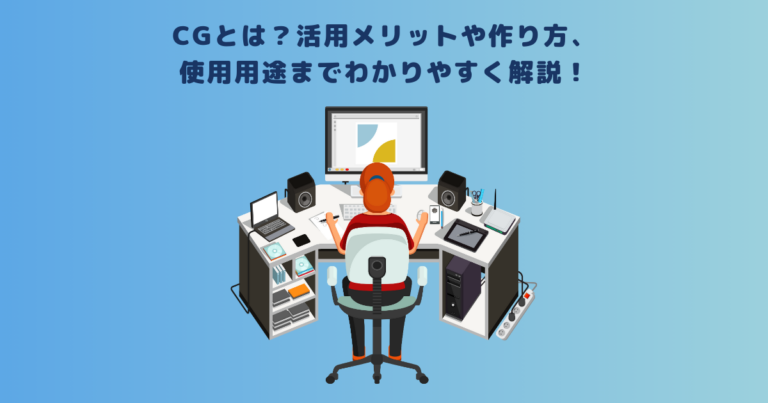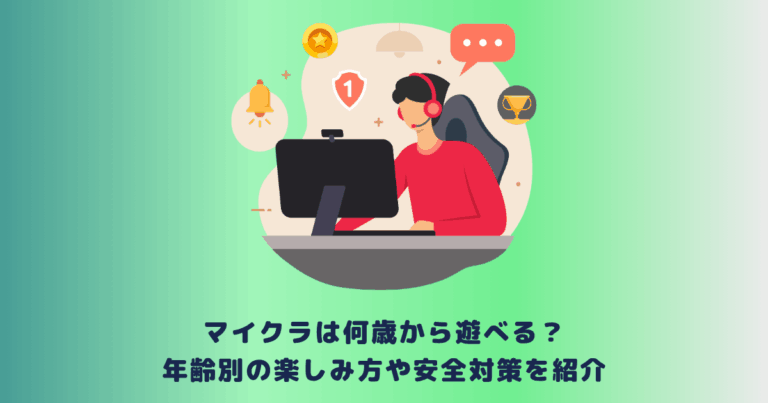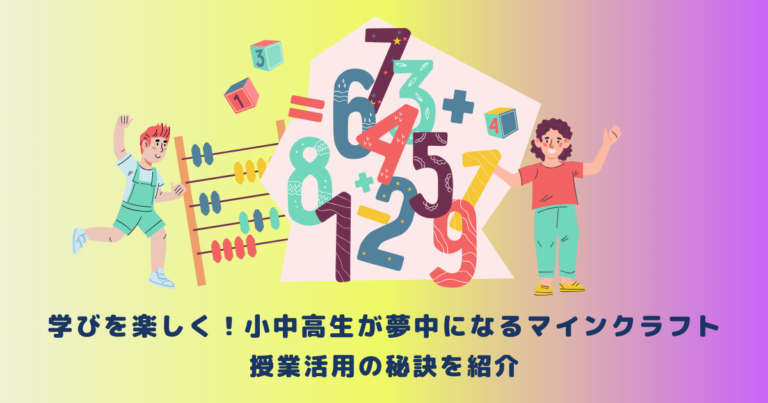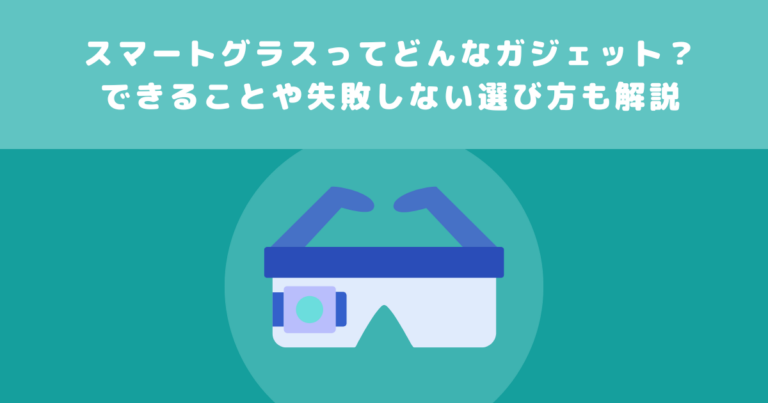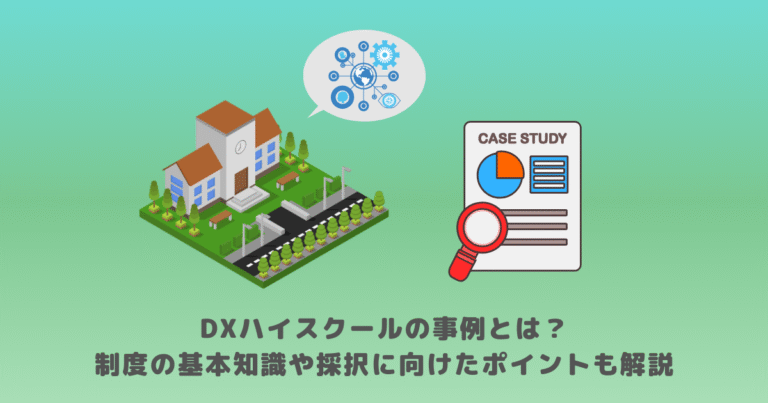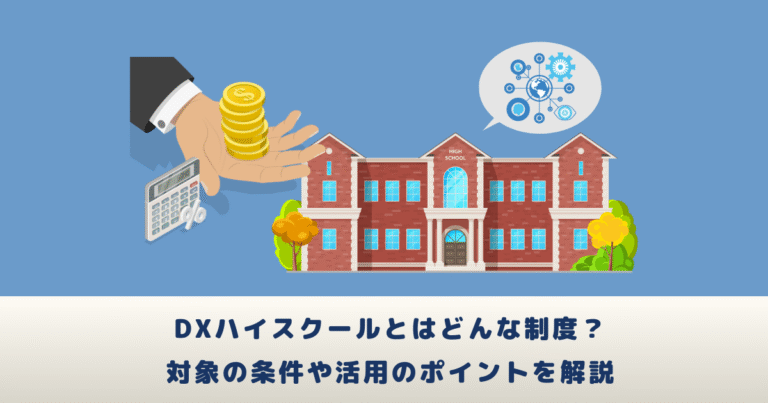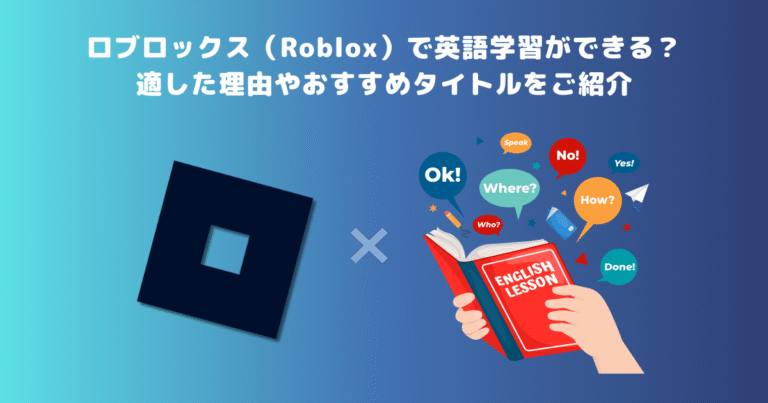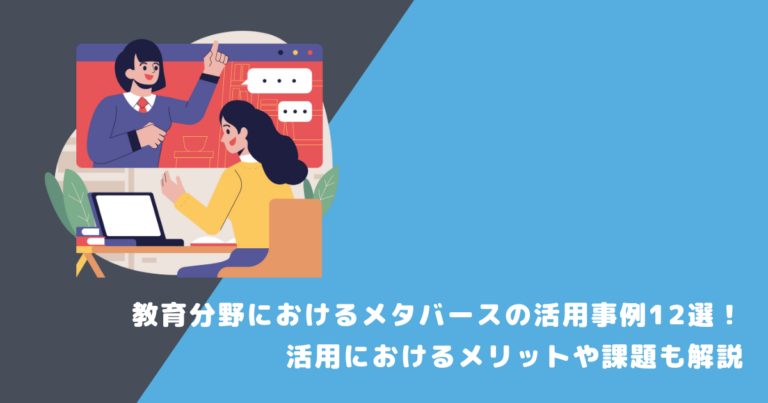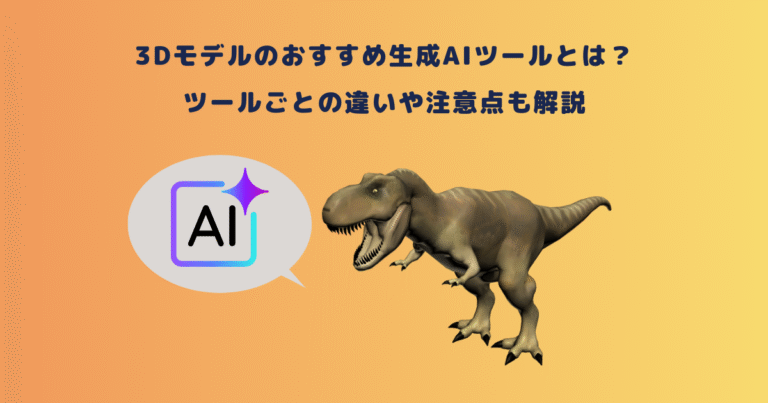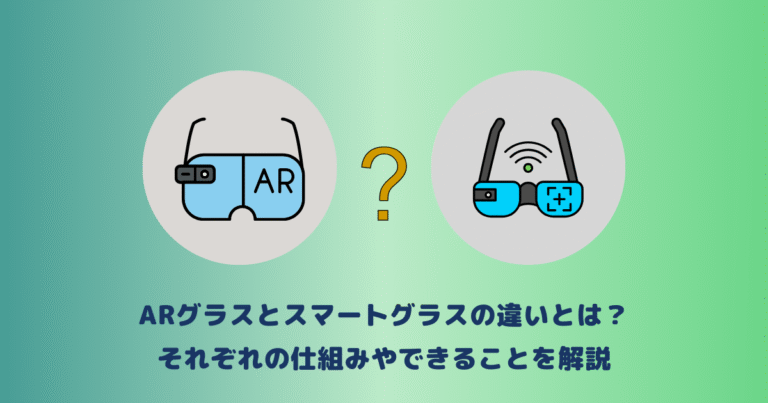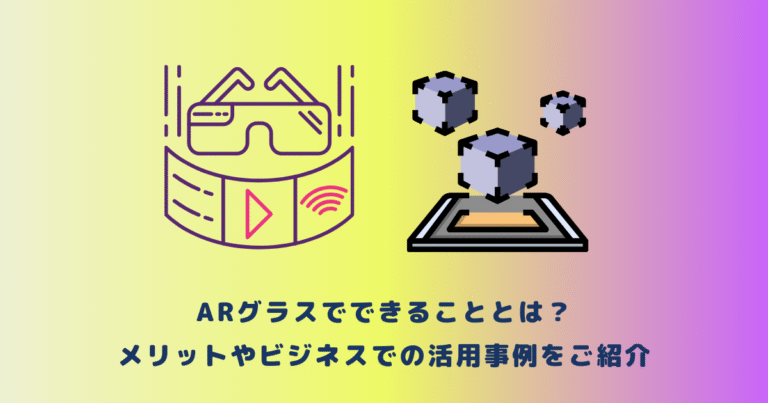最近のCGは驚くほどリアルで、ゲームや映画の世界にとどまらず、CMや広告の世界でも活用の幅が広がってきています。
様々な業種でCGの知識が必要になる場面も増えてきているのではないでしょうか。
しかし、CGの世界は専門用語も多く、どこから学べばいいのかわからない方も多いはず。
この記事では、CGの基礎から具体的な制作手順まで体系的に解説していきます。2DCGと3DCGの特徴、CGの使用用途、制作プロセスに至るまで、CGの全体像を漏れなくお伝えします。
それでは、一緒にCG入門の扉を開いていきましょう。
「医療研修に時間やコストがかかりすぎる…」その悩みをVRで効率化!
コストを抑えながら反復練習が可能な事例を含む『monoVR』サービスの資料をダウンロードいただけます。

monoVRサービス紹介資料の無料ダウンロードはこちら
資料をダウンロードする目次
|CGとは?
CGとは、「Computer Graphics(コンピュータグラフィックス)」の略で、コンピュータを使って作成された画像や映像のことを指します。
従来の手描きやアナログ撮影と異なり、デジタル技術を駆使して制作されるCGは、2次元(2DCG)から3次元(3DCG)まで、様々な表現が可能です。
画像編集ソフトで写真を加工する簡単なものから、映画やゲームで使用される3Dアニメーションまで、その範囲は多岐にわたります。
身近な例では、VFXといわれる映画の特殊効果やアニメ、ゲームのキャラクター、商品の広告など、幅広い分野で活用されます。
近年では、VR(仮想現実)やAR(拡張現実)など、よりリアルな表現も可能となり、私たちの生活に身近な技術になりつつあります。
CGは、私たちの想像力を形にする、まさにデジタル時代の魔法の筆と言える技術です。
|CGの種類
CGは大きく分けて2Dと3Dの2種類があります。
どちらもコンピュータを使って描かれた画像や映像という点では同じですが、制作方法や表現方法が異なります。
用途や予算、目的に応じて使い分けられるよう、正しく理解しておきましょう。
2DCG
2DCGは、平面的な画像や映像を指します。
イラストやアニメーションをはじめ、Webデザイン、広告、漫画制作など、幅広い用途で利用されています。
色彩や線を用いたフラットな表現で、データ容量が小さく処理も軽いため手軽に扱えることが利点です。
奥行きや立体的な表現はされませんが、親しみやすく、情報伝達力にも優れています。
PhotoshopやIllustratorなど一般的な画像編集ソフトで制作でき、制作コストや期間が比較的抑えられるのも強みです。
3DCG
3DCGは、三次元の立体的な画像や映像を指します。
ゲーム開発、映画の特殊効果、建築や製品のデザイン、VRコンテンツの制作など、リアルな立体表現ができるのが特徴。
3次元空間に仮想的な立体物を作り、質感や光源を設定することで、現実さながらの表現を可能にします。
圧倒的にリアルで迫力のある映像が作れるのが3DCGの最大の強みです。
ただし、制作にはMayaやBlenderといった専用ソフトを必要とし、高度な専門技術が必要なため、2DCGと比べて制作期間やコストはかかってしまいます。
|CADとの違い
3DCGとよく似た技術にCAD(Computer-Aided Design)という技術があります。
どちらもコンピュータを用いて3次元の物体を作成する技術ですが、その目的と特徴は大きく異なります。
CADは工業製品や建築物の設計に特化したツールで、正確な寸法や構造の再現を重視します。
例えば、建築図面や工業製品の設計図に使用され、実際の寸法や形状など詳細なデータを含みます。
一方、3DCGは視覚的な表現を重視します。製品や建築物のプレゼン映像、広告用のビジュアル、エンターテインメントコンテンツなど、見た目の美しさやリアルさが求められる場面で活用されます。
両者は相反するものではなく、魅力的なクリエイティブ制作の場面では連携が重要となります。
例えば、車のデザインを行う場合、CADで正確な設計図面を作成し、3DCGで実物に近い質感や色合いを表現する、といったように使い分けられます。
|CGの主な活用用途
CGは、多様な分野で活用されており、その用途は年々拡大しています。
エンターテインメントの世界での派手な演出から、ビジネスシーンでの実用的な活用、さらには医療や教育といった専門分野まで。
それぞれの分野で、CGならではの特徴を活かした活用方法が確立されています。
以下で代表的な事例を見ていきましょう。
エンターテインメント業界
映画、アニメーション、ゲームなど、エンターテインメント業界はCG技術を最も活用している分野の一つです。今やCGを活用してない作品の方が珍しくなってきました。
特にCGアニメーションの進化は目覚ましく、2024年に公開された「インサイド・ヘッド2」は北米で約6.5億ドルの興行収入を記録し、ピクサー史上最高の成績を収めました。
また、実写映画でも「スパイダーマン」や「アイアンマン」といったマーベル作品に代表されるように、CGを駆使した映像作品が世界で大ヒットしています。
近年のアニメーション制作では、従来のセル画とCGを組み合わせるハイブリッド手法が主流となっています。
背景やキャラクターの一部をCGで表現することで、手描きの温かみを残しながら、制作効率を大幅に向上させることに成功しています。
このようにエンターテインメント業界では積極的にCGを活用しており、新たな表現手法が次々と生まれています。
ビジネス分野
ビジネス分野では、CGが商品やサービスの魅力を効果的に伝えるツールとして欠かせない存在となっています。
不動産業界では、建物の完成前から内外装を精密に再現したCGイメージ制作が一般的となっています。最近では、バーチャルモデルルームによる内覧体験も活発に行われています。
例えば、東急不動産が手掛ける高級マンションブランド「BRANZ」では、高度なCG技術を活用し、Web内覧システムを展開しています。
実際の建物が完成する前に、住戸からの眺望や素材の質感まで忠実に再現。物件の魅力をリアルに伝えます。
自動車業界でも、VR技術を活用して車両のカスタマイズをリアルに体験できるバーチャルショールームが登場するなど、顧客体験の革新が進んでいます。
このように、ビジネス分野でのCG活用は、商品価値の可視化や顧客体験の向上に大きく貢献しています。
今後も技術革新とともに、さらなる活用シーンの拡大が期待されます。
その他の分野
その他にも様々な分野でCGの活用が広がっています。
例えば、医療や教育の分野です。
教育分野では、バーチャル教室での遠隔授業や、実験シミュレーションなどに活用されています。
危険を伴う実験や、普段は目にできない自然現象なども、CGを使えば安全に体験できます。
歴史上の出来事を再現したり、目に見えない分子や原子構造を視覚化したりすることで、より深い理解を得られます。
医療分野では、手術のシミュレーションや医療教育に活用されています。
患者さん一人一人の体の状態を3Dデータ化することで、より安全で効果的な手術計画を立てることが可能になっています。
このように、CGは専門的な知識や複雑な情報を、誰にでもわかりやすく伝えるツールとして、さまざまな分野で活用の幅を広げています。
|CGを使用するメリット
CGを活用することで以下のメリットが得られます。
- 現実では難しい表現の実現
従来の撮影や制作では実現できなかった表現が可能になります。未完成の建築物を実物のように表現したり、理想的な商品イメージを作り出したりと、想像を形にします。
- 制作プロセスの効率化
一度作成したCGデータは様々な角度や設定で再利用でき、修正も容易です。商品カタログの制作では、実際の撮影を行うことなく、季節や時間帯に合わせた表現を効率的に作れます。
- 精密な表現力
製品設計では微細な部分まで正確に表現でき、建築では内装の素材感まで忠実に再現できます。この精密さは、プレゼンテーションの質を高め、クライアントとのコミュニケーションを円滑にします。
- コスト削減
実物の試作品や撮影にかかる費用を抑えられ、データの再利用による制作費の圧縮も可能です。修正や変更にも柔軟に対応できるため、手戻りのコストも削減できます。
- 教育・トレーニングへの活用
複雑な製品の使用方法や作業手順を視覚的に示すことで、効率的なトレーニングができます。また、危険を伴う作業も安全に訓練が可能です。
このように、CGは表現力の向上から業務効率化まで、ビジネスに多様なメリットをもたらしています。
|CGの作り方
CGの制作は、企画から完成まで7つの重要な工程があります。
各工程が密接に関連し合い、最終的な作品の品質を左右します。順を追って見ていきましょう。
企画・コンセプト設計
まず、作品の目的やターゲット、表現したい世界観を明確にします。
この段階では、ラフスケッチや絵コンテを使って具体的なイメージを固めていきます。
例えば、商品PRの場合、商品の特徴をどう魅力的に見せるか、視聴者の心に響くストーリー性をどう組み込むかなどを検討します。
モデリング
3D空間上で物体の形を作り出す工程です。
例えるなら、粘土で形を作るような作業です。
基本的な立体(直方体や球体など)を組み合わせたり、変形させたりしながら、目的の形を作っていきます。
例えば、人物を作る場合、全身の比率を整えた後に、顔の細かいパーツや衣服のしわなど、より細かいディテールを追加していきます。
建造物なら、まず全体的な構造を作り、その後に窓や装飾などの細部を追加していく形です。
このように、大きな形から細部へと作り込んでいく手法は、「ラフから詳細へ」というCGモデリングの基本的なアプローチとなっています。
テクスチャ・カラーの追加
作り出した形に色や質感を付ける工程です。
この工程は、物体の「見た目」を決定する重要な要素です。
単なる色付けだけでなく、物体の表面がどのように光を反射するか(ツヤの有無)、凹凸感(でこぼこした感じ)、透明度(ガラスのような透け具合)なども設定します。
例えば、革製品を表現する場合、基本の色に加えて、細かいシワや光沢の具合まで設定することで、本物のような質感を実現します。
リギング
主にキャラクターや動物を動かすために、骨格構造を設定する工程です。
実際のCGキャラクターには、人体の骨格のように複雑な階層構造が設定されています。
例えば腕を動かす場合、肩から指先まで連動して自然に動くよう、それぞれの関節の動きが連携するように設定します。
また、表情の変化をつけるために顔の各パーツや、服のしわを表現するための補助的な骨組みなども必要です。
この骨格設定の精度が、後のアニメーションの自然さを大きく左右します。
アニメーション
実際に動きを付ける工程です。
主に「キーフレームアニメーション」という手法を使用し、動作の重要な場面でポーズを設定すると、その間の動きをコンピュータが自動的に生成します。
より自然な動きが必要な場合は「モーショントラッキング」という技術で、実際の人の動きを記録してCGに反映させることもあります。
動きの速さやタイミング、スムーズさなどを調整して、意図した演出を実現します。
ライティング
3D空間内に光源を配置し、陰影をつける工程です。
CGでは様々な種類の光源を使い分けます。
太陽光のような遠くからの平行光線、スポットライトのような局所的な光、空間全体を柔らかく照らす環境光など、それぞれの特性を活かして表現を作り込みます。
また、物体の表面での光の反射や、他の物体に反射した間接光なども計算されます。
映画やゲームのシーンで印象的な雰囲気が作られるのは、このライティング技術によるものです。
レンダリング
レンダリングは最終的な画像または動画を生成する工程です。
写真でいう現像に当たります。
3D空間上のすべての要素(モデル、テクスチャ、ライティング)を計算、統合し、2D画像に変換します。
例えば、光の反射や影、透明なガラスを通した光の屈折など、物理的な現象を計算しながら画像を生成していきます。
品質を上げれば上げるほど計算量が増えるため、数秒のアニメーションでも、レンダリングに数時間から数日かかることもあります。
最近では、リアルタイムレンダリング技術の発展により、即座に結果を確認できるようになってきています。
|まとめ
いかがでしたか?
この記事では、CGの基本的な概念から具体的な活用事例、そして制作プロセスまで詳しく解説してきました。
CGの活用は、エンターテインメントからビジネス、さらには医療や教育の分野まで、その活用範囲は私たちの想像をはるかに超え広がっています。
コスト削減や業務効率化といった実務的なメリットも、CGの大きな魅力ですよね。
制作には専門的な知識や技術が必要ですが、各工程の基本を理解することで、より効果的な活用が可能になるはずです。
この記事が、みなさんのクリエイティブな挑戦への第一歩となることを願っています。

 TWITTER
TWITTER
 FACEBOOK
FACEBOOK
 はてブ
はてブ