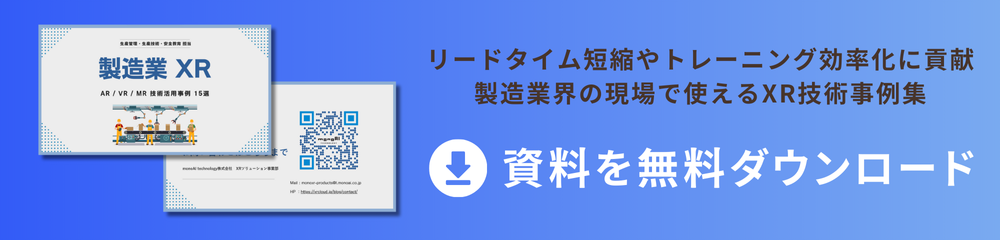「自社の工場見学の満足度がいまいちパッとしない、、。」
「自社の工場見学をもっと有効活用したい。」
このようなお悩みは、VR技術を活用した工場見学で解決できるかもしれません。
VR工場見学とは、実際の工場内部を360度映像や3DCGで再現し、ユーザーが自宅や学校などからオンラインで工場内を見学できるサービスです。
近年、製造工程の可視化や企業ブランディングの強化を目的として、導入が増えています。
本記事では、VR工場見学の概要から企業が導入するメリット、作成方法、最新事例を詳しくご紹介しますので、是非までご覧ください!
|VR工場見学とは?
VR工場見学とは、VR技術を活用して、ユーザーがオンライン上で工場内部を見学できる仕組みです。
従来の工場見学では、企業秘密や安全性、品質管理などの理由で立入禁止な場所があったり、工場”見学”なので、参加者に足を運んでもらう必要があったりと、様々な制約がありました。
また、案内用の社員も都度駆り出す必要があり、工場によっては少し負担のかかる体験コンテンツになっているケースもあります。
そこで、VR工場見学では、専用のVRゴーグルやPC、スマートフォンを使い、360度の映像・画像によって実際に工場を歩いているかのような臨場感を体験できます。
|企業がVR工場見学を導入するメリット
企業がVR工場見学を導入する最大のメリットは、時間・場所・コストなど従来の制約を超えた新たな「見学体験」を提供できる点にあります。
24時間365日アクセス可能
VR工場見学は、オンライン上にコンテンツを公開することで、24時間365日、世界中のどこからでもアクセス可能となります。
これは、自社工場に興味を持ってくれる一般客の他にも、海外顧客や求職者など、物理的に工場に来ることが難しい人々にも情報提供できるというメリットになります。
プロモーションとして活用可能
工場見学をVRコンテンツ化することで、プロモーションへも活用することが可能です。
現地での工場見学における参加者の感想に加え、体験した視点の映像も発信できるため、興味段階から
自由度の高い表現
VRでは、ナレーション付きの案内、製品内部の3DCG表示、クイズゲームなど、多彩な演出が可能です。
物理的な制約を受けないため、見学者にとってより理解しやすく、印象に残る体験を提供できます。
例えば、自動車メーカーではエンジンの内部構造をCGで可視化することで製品理解を深めたり、飲料メーカーでは通常立ち入れない場所への見学を可能にし、品質へのこだわりを体験してもらったりと活用されています。
コスト削減
一度コンテンツを制作すれば、その後は人員を割くことなく何度でも利用できます。
従来の工場見学では、案内担当者の人件費、資料印刷費、交通費など細かい様々なコストが発生していましたが、VRでコンテンツ化することでこれらのコストを削減可能になります。
安全性の向上
工場によっては、見学する上で重機や工場の環境など安全性への配慮が必要な場所もあります。
勿論最大限の安全性を確保し、工場見学を行っている場所がほとんどですが、VRであれば、そうした安全面でリスクのある場所でも、安全に見学が可能になります。
特にコロナ禍以降、感染症対策の観点からも、非接触・非対面のVR工場見学は安全な代替手段として注目されています。
|VR工場の作り方
工場見学へVRを導入するには、大きく4つのステップで制作していきます。
企画
まず最初のステップとして、どのような体験コンテンツにするか企画を行います。
自社がどういう目的で工場見学を運営しているのか、参加者に自社の工場のどういった部分を体験し魅力に感じてもらいたいのか、などVRコンテンツによって伝えたい内容の方向性を定めましょう。
また、方向性の企画と並行し、実現に向けて工場内の誰と協力し進めていくか、予算設定を行っていくか、なども重要です。
撮影準備
続いて、実際の工場をVRコンテンツとしてデジタル化するには、現場の撮影が必要です。
撮影した素材をもとに3DCGを制作するため、撮影前の準備は非常に重要です。
具体的には、見せたいポイントの洗い出しや見学導線の設計、現場の整理整頓、照明の確認など、細かな点まで事前に整えておく必要があります。
さらに、ナレーションやテロップを加える場合には、台本の作成や関係部署とのすり合わせも欠かせません。
たとえば、製造ラインを追う構成にしたい場合には、撮影ポイントの順番やセリフのタイミングなどを事前にしっかりと決めておくことが重要です。
360度映像の撮影
撮影は360度カメラやドローンなどを用いて行います。
1か所だけでなく複数の撮影スポットを設けることで、見学者が自由に視点を移動できる設計が可能になります。
特に臨場感を出すためには、カメラの設置高さやアングルにも工夫が必要です。
実際、製品の流れに沿って複数の360度映像を連結し、シームレスに移動できるVR体験を実現している事例もあります。
こうした工夫により、リアルな「空間体験」に近いVR工場見学を実現できます。
コンテンツの作成
撮影した映像に編集を加えることで、より理解しやすく魅力的なコンテンツになります。
テロップやナレーション、説明ポップアップ、クイズ機能などを加えることで、教育的・広報的な価値を高められます。
視聴者の理解度や滞在時間の向上にもつながります。
たとえば、製品の組み立て工程を表示しながら、その部品の役割や品質管理について説明を加えることで、専門知識のない人でも直感的に理解できます。
このように、編集は「見る」から「理解する」体験へと昇華させる重要な工程です。
VRプラットフォームへのアップロード
完成したコンテンツは、視聴者に届けるために適切なプラットフォームに公開します。
YouTube VR、Matterport、独自開発のWebアプリ、メタバース空間など、目的に応じた配信方法を選びます。
ターゲットや使用環境に応じて、PC・スマートフォン・VRゴーグルそれぞれに対応した形式に最適化することも必要です。
たとえば、採用イベント向けにはスマートフォン対応を重視し、企業研修用にはVRゴーグルを前提とした高解像度コンテンツを準備するなど、使い分けも重要になります。
このように、届けたい相手に最適な形で公開することで、VR工場見学の効果を最大化できます。
|VRコンテンツの制作にかかる納期と費用の目安
数分間のVRコンテンツとして制作する場合、一般的に「360度VR映像」と呼ばれる形式で制作されることが多いです。
この形式は、視聴者がVRゴーグルやスマートフォンを使って、工場の様子を360度自由に見渡せるようにするものです。
ここでは、このタイプのコンテンツを制作する場合の目安をご紹介します。
費用:約100万円〜300万円
数分間の360度VR映像制作費用は、撮影日数と編集の複雑さによって大きく変わります。
- 撮影費用: 1日あたり10万円〜20万円が目安です。撮影場所(工場内の複数箇所)が多岐にわたる場合や、撮影日数が複数日に及ぶ場合は、その分費用が増加します。
- 編集・開発費用: 映像のつなぎ合わせ、テロップ(文字情報)の挿入、ナレーションやBGMの追加、簡単なインタラクティブ機能(特定の場所をタップすると情報が表示されるなど)の有無によって変動します。
- CG制作費用: 360度映像に、機械の構造を説明するためのCGアニメーションや、普段見ることのできない部分をCGで表現するなどの演出を追加すると、その分費用が加算されます。
シンプルな工場見学映像であれば100万円〜200万円程度から制作が可能ですが、高画質(8Kなど)での撮影や、複雑なCG、高度なインタラクティブ機能を盛り込む場合は、300万円を超えることもあります。
納期:約1〜2ヶ月
数分間のコンテンツであれば、企画から完成までの納期は比較的短くなります。
- 企画・構成(約1〜2週間): 工場内のどのエリアを、どのような順番で見せるか、ナレーションの内容などを具体的に決めます。
- 撮影(約1日〜3日): 実際に360度カメラで工場内を撮影します。撮影場所やスケジュールは事前に綿密に打ち合わせが必要です。
- 編集・仕上げ(約3〜6週間): 撮影した映像を編集し、テロップやナレーション、BGMを追加します。ナレーション収録やCG制作が必要な場合は、この期間が長くなります。最終的な調整とVR機器での動作確認を行います。
コンテンツの複雑性や、クライアントからのフィードバックにかかる時間によって納期は前後しますが、通常は1〜2ヶ月を目安として見ておくのが良いでしょう。
|実際のVR工場見学の事例
では、実際にどのようにVR工場見学が実施されているのでしょうか。
最後にそれぞれの企業がVRを活用してどのような取り組みをしているのかご紹介します。
株式会社ヤクルト本社:ヤクルト ビューティエンスタウン

ヤクルト本社は、神奈川県湘南地域にある湘南化粧品工場をイメージしたバーチャルコンテンツ「ヤクルト ビューティエンスタウン」を展開しています。
このコンテンツでは、360度カメラによる臨場感あふれる映像を通じて、まるで現地を訪れたかのようなバーチャル工場見学を体験できます。
また、ヤクルトの化粧品やお肌のお手入れ方法について楽しく学べるコンテンツも充実しており、湘南エリアのおすすめ観光スポットも紹介されています。
トヨタ自動車株式会社:トヨタバーチャル工場見学

トヨタ自動車は、オンラインで車ができるまでの現場を見学できる「トヨタバーチャル工場見学」を公開しています。
このコンテンツは、製造工程の映像だけでなく、トヨタ生産方式(TPS)の基本思想や現場の改善活動なども学べる構成になっており、教育性の高い見学体験を提供しています。
さらに、ナビゲーターによる解説やインタビュー形式のパートも取り入れられており、専門知識がなくても楽しむことができます。
ハーゲンダッツ ジャパン:Häagen-Dazs ICE CREAM FACTORY TOUR

ハーゲンダッツ ジャパンは、アイスクリームの製造工程を楽しく学べるバーチャル工場見学「Häagen-Dazs ICE CREAM FACTORY TOUR」を公開しています。
このコンテンツでは、ハーゲンダッツアイスクリームができあがるまでの工程やこだわり、秘密を3DCGや実写、アニメーション映像などを通じて紹介しており、大人も子供も楽しく学べる内容となっています。
|まとめ
いかがでしたでしょうか。
VR工場見学は、時間や場所の制約にとらわれず、多くの人々に製造現場の魅力を伝える新しい手段として注目されています。
顧客との新たな接点を創出し、ブランド価値を高めたいという企業にはぴったりの施策と言えるでしょう。
今後、より高度な3DCGやAIとの連携によって、VR体験の質はさらに向上することが予想されるとともに、企業のデジタル化推進やブランド戦略の一環として、ますます重要性を増していくでしょう。
弊社では、VRコンテンツを始めとする産業向けの様々なXRソリューションの受託開発を行っております。
AR、VR、MR技術の導入にご興味がある方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

 TWITTER
TWITTER
 FACEBOOK
FACEBOOK
 はてブ
はてブ