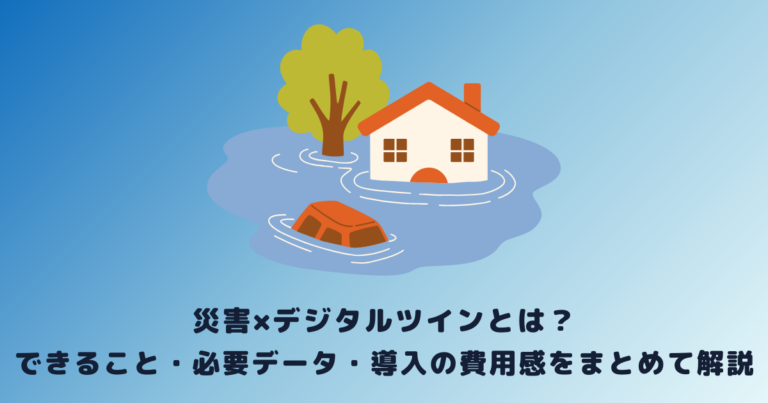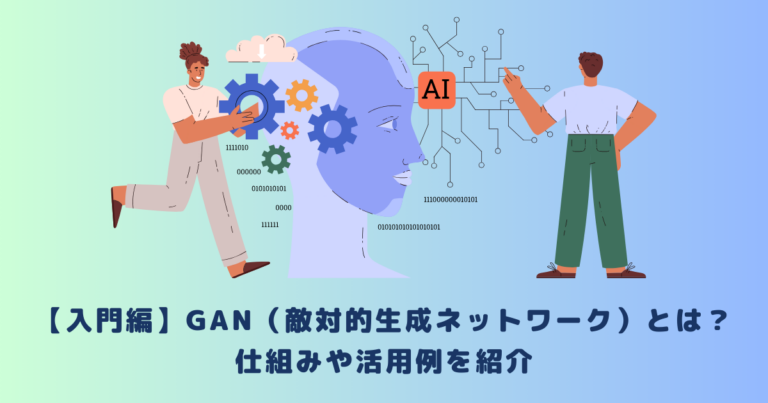バーチャル(Virtual)とは、「実体はないが実際のように感じられるもの」を意味する言葉です。
現代では特にデジタル分野でよく使われ、バーチャルリアリティ(VR)やバーチャル空間といった文脈で耳にする方も多いのではないでしょうか?
本記事では、バーチャル(Virtual)の意味や語源、リアルとの違いについてわかりやすく解説しますので、是非最後までご覧ください!
「設計図だけでは分からない…」そんな課題をVRで解決!
CADデータを活用した建築VRなら、設計・施工段階の合意形成から竣工後の保守運用まで長期的に活用可能。

monoVRサービス紹介資料の無料ダウンロードはこちら
資料をダウンロードする|バーチャル(Virtual)の意味と語源
バーチャル(Virtual)とは、「現実には存在しないが、あたかも存在するかのように感じられるもの」を指す言葉です。
語源はラテン語の「virtus(力、効力)」に由来し、英語では「virtual」として13世紀ごろから使われ始めました。
当初は「実際の力を持っているが、物理的に存在しないもの」というニュアンスで用いられ、現代においては、特にコンピューター技術の発展により、「仮想空間」「仮想現実(VR)」などの文脈で頻繁に使われています。
たとえば、バーチャル会議やバーチャルオフィスなど、実際に人が物理的に集まらなくても体験や交流が可能な技術を指す言葉として定着しています。
このように、バーチャルという言葉は、現代のビジネスやテクノロジーにおいて非常に重要な概念となっています。
|バーチャルとリアルの違い
バーチャルとリアルの違いは、「物理的な実在があるか否か」にあります。
リアルとは、五感で認識できる現実の世界を指し、物質的な存在や直接的な体験が伴います。
一方、バーチャルはデジタル空間に構築された非物質的な世界で、感覚的には現実に近くても、物理的な実在は存在しません。
この違いは、メタバースやVR技術が普及する中でますます重要になっています。
たとえば、リアルな会議室での打ち合わせでは実際に人が集まりますが、バーチャル空間での会議はアバター同士が対話する形式となります。
実際の移動や物理的な接触は不要で、利便性や効率性が向上する一方、感情や空気感の伝達が難しい場合もあります。
このように、リアルは現実世界の物理的制約に基づく一方、バーチャルは技術によって自由度の高い体験が可能になります。
それぞれにメリット・デメリットがあるため、目的に応じた使い分けが重要です。
バーチャルのメリット・デメリット
■メリット
時間や場所にとらわれない
遠隔地でも参加可能で、通勤や移動のコストを削減できる。
コスト削減
物理的な会場や設備が不要で、イベントや会議の費用を抑えられる。
自由な表現や拡張が可能
現実では不可能な体験(空を飛ぶ、異世界に行くなど)も実現できる。
データ収集や分析が容易
ユーザー行動やログを詳細に記録・分析できる。
■デメリット
身体的な実感が乏しい
触覚や匂いなど、五感のうち一部しか再現できない。
没入感に差がある
環境や個人差によってリアリティの感じ方にばらつきがある。
技術的な課題
インターネット環境や端末性能に依存する。VR酔いの懸念も。
社会的・心理的な距離感
対面よりも感情や空気感が伝わりにくく、誤解が生じることも。
リアルのメリット・デメリット
■メリット
五感をフルに活用できる
視覚・聴覚だけでなく、触覚・嗅覚・味覚なども活かせる。
コミュニケーションの精度が高い
表情、身振り、空気感などが伝わりやすく、信頼関係を築きやすい。
トラブルが少ない
機材トラブルや通信障害など、技術的な問題が少ない。
深い没入と集中が可能
周囲の環境が統一され、より集中しやすい。
■デメリット
時間・場所の制約が大きい
移動や集合の必要があり、スケジュール調整が難しい。
コストがかかる
会場、交通費、設営などに費用が発生する。
柔軟性に欠ける
天候や災害などの影響を受けやすく、代替が難しい。
データ取得が困難
参加者の行動ログや分析データを得るには手間がかかる。
|まとめ
バーチャルとは、現実には存在しないが、デジタル技術によって現実のように体験できる「仮想」の世界を指します。
現代ではメタバースやVRといった先進技術が語られる際に、登場する言葉でもありますので、意味を正しく理解し、これからのビジネスや生活にお役立てください。
「設計図だけでは分からない…」そんな課題をVRで解決!
CADデータを活用した建築VRなら、設計・施工段階の合意形成から竣工後の保守運用まで長期的に活用可能。

monoVRサービス紹介資料の無料ダウンロードはこちら
資料をダウンロードする
 TWITTER
TWITTER
 FACEBOOK
FACEBOOK
 はてブ
はてブ