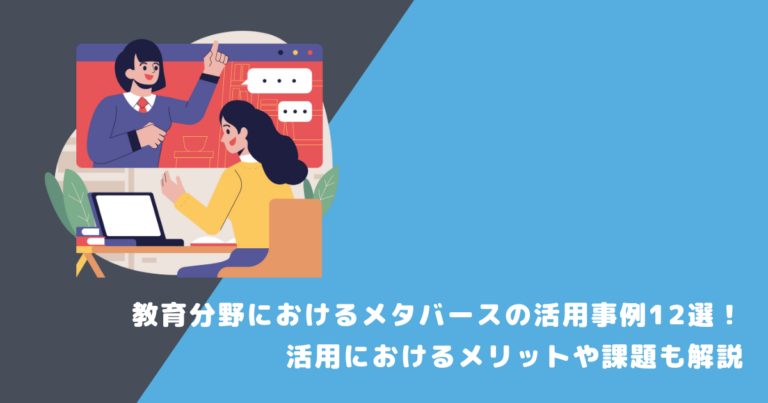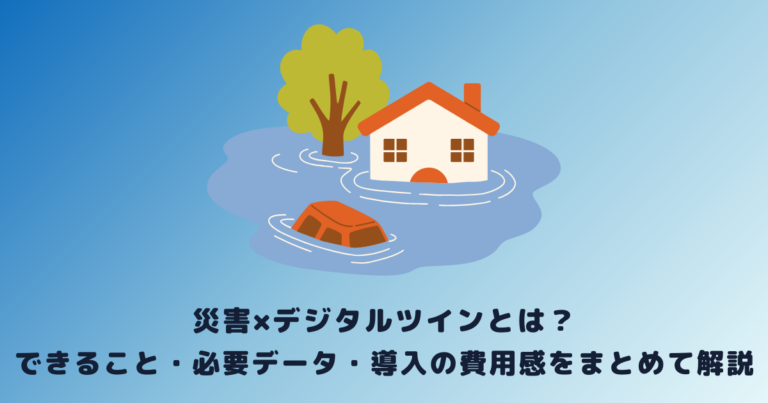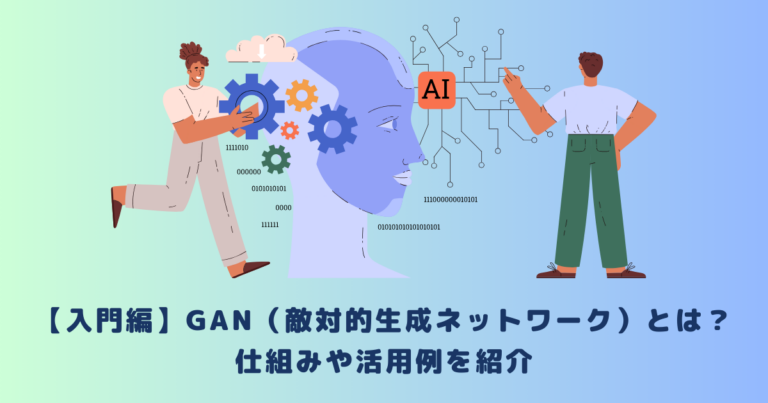AR(拡張現実)は、現実空間にデジタル情報を重ねる技術としてビジネスでの活用が進んでおり、今やゲームやエンタメの領域だけでなく、あらゆる産業で導入されています。
本記事では、ARの基本から、ビジネスへの導入事例、メリット、さらには業界別の活用例まで網羅的に紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。
ARコンテンツ制作!自社開発による柔軟性でお客様のビジネスをリードする『monoAR』
サービスの特徴や導入事例をまとめた資料をご用意しました。

monoARサービス紹介資料の無料ダウンロードはこちら
資料をダウンロードする目次
|ARとは?
ARは、現実世界にデジタル情報を重ね合わせる技術です。
スマートフォンやARグラスを通じて、実際の風景にCGやテキスト、音声などの情報をリアルタイムで表示し、現実空間の体験を拡張することができます。
この技術は、単に視覚情報を補足するだけでなく、業務支援や教育、エンターテインメント分野など多岐にわたる領域で活用が広がっています。
特に近年では、5G通信の普及やスマートグラスの進化により、よりリアルタイム性・高精度なAR体験が可能となり、ビジネス利用が加速しています。

ARとVRの違い
ARとよく混同されがちな技術に、VRがあります。
両者はともに没入型体験を提供する技術ですが、用途や仕組みに明確な違いがあります。
ARは「現実+デジタル」を融合する技術であり、ユーザーは現実世界を見ながら、その上に重ねられた情報を操作・体験できます。
一方、VRは「完全な仮想空間」を生成し、ユーザーをその中に没入させる技術です。
現実から完全に切り離された環境で、シミュレーションやゲームなどを体験するのが主な活用方法です。
VRについては、以下の記事で詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

|ARがビジネスに注目されている理由
ARがビジネス分野で注目されているのは、「顧客体験の向上」と「業務効率化」という2つの大きな効果が期待できるためです。
企業にとって、顧客に対して新しい価値を提供しながら、同時に現場の業務を効率化できる技術は非常に魅力的と言えるでしょう。
特に、非接触対応やリモート支援など、コロナ禍を経て定着したニーズとの親和性も高く、導入が急速に進んでいます。
さらに、ARは既存のハードウェア(スマートフォンやタブレット)を活用できる点でも導入障壁が低いのが特徴です。
これにより、中小企業でも比較的低コストでPoC(概念実証)を行い、その後の本格展開へとスムーズに移行しやすくなっています。
このように、ARは顧客満足度と業務効率の両立を可能にする実用的な技術として、さまざまな業界から注目を集めているのです。
|AR技術の特徴
AR技術にはいくつかの実装方式が存在しますが、大きく分けて「ロケーション型」と「ビジョンベース型」の2つに分類されます。
ロケーション型
ロケーション型ARは、GPSや加速度センサー、ジャイロスコープなどを活用し、ユーザーの位置情報に基づいてコンテンツを表示する仕組みです。
たとえば、観光地でスマートフォンをかざすと、その場所に関する歴史情報や写真が表示されるといった使い方が挙げられます。
この方式は、広範囲にわたる情報配信や、移動中のユーザーに対してリアルタイムで情報提供することに適しています。
商業施設や観光業など、地理的な情報と連動させたプロモーションに強みがあります。
ロケーション型ARは、スマートフォンのGPS機能さえあれば手軽に実装できる点が魅力であり、特別なマーカーや事前の環境設定が不要なため、ユーザー体験の敷居も低いのが特長です。
ビジョンベース型
ビジョンベース型ARは、カメラを使って現実の映像を認識し、そこにデジタルコンテンツを重ねる手法です。
特定の画像や物体(マーカー)を認識して表示する「マーカーベース型」と、マーカーを使わず現実空間を認識して表示する「マーカーレス型」に分けられます。
たとえば、家具の配置シミュレーションアプリでは、ユーザーの部屋をカメラで映し出し、その空間にバーチャル家具を配置して比較検討できるようになっています。
これにより、購買前の不安を軽減し、ユーザーの満足度向上に貢献します。
また、マーカーレス型は機械学習やSLAM(Simultaneous Localization and Mapping)など高度な技術を用いることで、空間の立体的な把握や動的な対象物への追従が可能となり、製造業や建設業の現場でも活用が広がっています。
このように、ロケーション型とビジョンベース型はそれぞれ異なる技術的特性と用途があり、どちらを選択するかは目的やユーザーの利用環境によって大きく変わってきます。
|今、どんな業界でARが使われているのか?
AR技術は、特定の業種に限らず、さまざまな業界で実用化が進んでいます。
ここでは、4つの分野における活用事例を紹介しながら、それぞれの業界がARをどのようにビジネスに取り入れているのかを解説します。
小売・EC
小売業やEC業界では、ARが「購買前の不安」を解消するツールとして注目されています。
たとえばアパレル分野では、ARによるバーチャル試着が可能となり、自宅にいながら商品のサイズ感や色合いを確認できます。
家具業界では、ARを使って自宅の空間に商品を配置し、実際のインテリアとの相性をシミュレーションできます。
米国の調査会社によると、AR体験を提供しているECサイトでは、購買率が平均20%以上向上したとの報告もあり、ARはコンバージョン率の改善や返品率の低下にも寄与しています。
製造業
製造業においては、ARが「現場の可視化」と「技術継承」の手段として活用されています。
たとえば、ARを用いて作業手順を目の前に表示すれば、熟練技術者でなくても正確な作業が可能になります。
これにより、作業時間の短縮とミスの削減が実現します。
また、設備保守や点検業務では、ARで設備の構造や異常箇所をリアルタイムに可視化することで、効率的なメンテナンスが可能となります。
特に高齢化が進む製造現場では、ARによるノウハウ共有が技術伝承の重要な手段となっています。
不動産・建築
不動産・建築業界では、ARが「完成予想の可視化」に役立っています。
図面やパースでは伝わりにくい建築物のスケール感や空間設計を、ARを通じてリアルに体験できるため、施主や購入希望者にとって大きな判断材料となります。
たとえば、建設予定地にスマートフォンをかざすと、建物の完成イメージがその場に浮かび上がるといったプレゼンテーションが可能です。
また、施工管理でも、ARによる進捗確認や施工ミスの発見が活用されており、現場の品質と安全性向上にもつながっています。
教育・研修
教育や研修の分野では、ARが「体験型学習」を実現するツールとして広がっています。
特に医療、機械整備、建築などの専門的な分野においては、ARを活用することで、リスクのない仮想環境での実習が可能となります。
たとえば、解剖学の授業では人体の構造を3Dで視覚化したり、工場研修では実機を使わずに工程を理解できるような教材がARで提供されています。
これにより、学習効率の向上とコスト削減が同時に実現でき、企業内研修にも応用が進んでいます。
|ARの導入メリット
ARをビジネスに導入することは、顧客体験の革新と業務効率の改善という両面において、大きなメリットをもたらします。
企業は単なる「話題性」ではなく、明確な効果を期待してARを導入しており、その成果が数値でも裏付けられています。
ここでは、導入によって得られる2つの主要なメリットについて解説します。
顧客体験の向上とブランディング強化
ARを活用することで、顧客に対して直感的かつ没入感のある体験を提供できるようになります。
たとえば、ECサイトでのバーチャル試着、ARマニュアルによるセルフメンテナンス、ARゲーム連動型プロモーションなど、従来の情報提供では得られなかった“体感型”の訴求が可能となります。
このような新しい体験は、顧客の満足度や購入意欲を高めるだけでなく、ブランドイメージの向上にも直結します。
ARによるユニークな顧客接点は、競合との差別化ポイントにもなり、ブランディング強化の有力な手段といえるでしょう。
業務効率化と人的コストの削減
ARは、現場業務においても大きな効果を発揮します。
たとえば、製造現場や保守点検業務では、作業マニュアルや手順をARで表示することで、作業者が迷わずに対応できるようになります。
これにより、作業の標準化が進み、熟練者に頼らずとも高い品質を維持できます。
また、ARによる遠隔支援では、現場の映像をリアルタイムで本部や専門家と共有しながら作業指示を受けることができ、出張や訪問に伴う時間とコストを削減できます。
このようにARは、人手不足や働き方改革が課題となる今の時代において、業務効率を高めながらコスト最適化を実現する手段として導入が進んでいます。
|【2025年7月更新】AR導入事例
業種・業態を問わず、顧客接点の強化や業務効率化のためにARを活用する事例が増えています。
ここでは、各社がどのようにARを取り入れているか具体例をもとに紹介します!
ニトリ

ニトリは公式スマートフォンアプリに、家具や設置場所のサイズをARで計測できる機能を導入しています。
自宅でスマホを使い簡単に寸法を測定できるため、家具選びで重要なサイズ確認の手間が大幅に軽減され、サイズ違いの不安を解消した上でECサイトで購入できるようになりました。
スマホカメラで家具本体や設置予定箇所を撮影すると、自動的に寸法入りの画像が生成されます。
この画像は編集・保存してメモとしても活用可能で、採寸のために店舗へ行く負担を減らし、自宅にいながら適切な商品選びをサポートするサービスです。
特に大型のソファや家電などでも、事前に部屋のスペースを測ってサイズを照合できるため、失敗のない買い物につながります。
こうした取り組みにより、サイズ違いによる返品リスクの低減や顧客満足度の向上が期待されています。
ZOZOTOWN(ZOZOCOSME)

ファッション通販大手ZOZOTOWNが運営するコスメ専門モール「ZOZOCOSME」では、スマホのカメラで自分の顔にメイクをバーチャルに試せる新機能「ARメイク」が提供されています。
商品詳細ページからワンタップで起動でき、簡単な操作で自身の顔に化粧品を適用するシミュレーションを行うことが可能です。
AR上でメイクの濃淡を調整したり、ワンタッチでメイクの有無を切り替えて素顔との比較もできるため、実際にコスメを使った際の色味や質感を手軽にイメージできます。
さらに、AR画面内の「カートに入れる」ボタンからそのまま商品購入に進めるため、気に入ったコスメを試した直後にスムーズに購入できます。
このAR試着機能により、店舗に行かなくても複数のコスメを自由に試せるため、オンラインでの購買体験が向上し、コンバージョン率の改善にも寄与しています。
花王

花王株式会社では、ヘアカラー剤選びを支援するためAR技術を活用したサービスを展開しています。
スマートフォン等で自分の髪色にカラー剤の仕上がりイメージを重ねて確認できるため、美容室や店頭で用意される毛束サンプルに頼らず、いつでもどこでも好みの色味を試せます。
従来の毛束見本では実際の仕上がりを想像しづらい課題がありましたが、ARによる視覚的なシミュレーションで消費者のイメージギャップを埋め、購入前の不安軽減につながっています。
また、毛束見本に用いられるプラスチック資材を削減できるため、環境負荷低減にも寄与しています。
こうした取り組みにより、消費者は手軽に理想の髪色を見つけることができ、購買意欲の向上も期待されています。
サンリオ

サンリオは2025年1月31日(金)から3月31日(月)まで、原宿の街頭大型ビジョン「CHANGE ViSiON Harajuku」において、人気キャラクターと連動したインタラクティブなAR体験イベントを実施しました。
同ビジョン前を歩く人が手を振ると、画面上に「ハローキティ」「クロミ」「シナモロール」などサンリオのキャラクターが隣に現れ、一緒に手を振り返してくれる仕掛けです。
ビジョンに設置されたカメラが歩行者を検出し、ジェスチャー(手を振る動作)を認識すると、即座に対応するキャラクターを合成表示し、遅延なくキャラクターが登場するため非常に臨場感が高く、現実と仮想の垣根を越えた新鮮な驚きを提供しました。
この施策により、参加者はサンリオキャラクターへの愛着を一層深め、SNSで体験を共有する人も多く見られました。
|自社に合ったAR活用の見つけ方
ARを導入するにあたり重要なのは、「どのような目的で、誰に向けて、どのシーンで活用するか」を明確にすることです。
闇雲に技術を導入しても成果につながらないため、自社の課題や顧客ニーズに即した活用方法を見極める必要があります。
まずは、自社の業務やサービスにおいて「非効率な工程」や「顧客との接点に課題がある部分」を洗い出しましょう。
たとえば、小売業であれば「商品選定時の情報不足」、製造業であれば「熟練技術の継承」など、業種ごとの課題が明確になります。
次に、ARによってそれらの課題をどのように解決できるかを検討します。
情報の視覚化によって業務がどれだけ簡素化できるか、あるいは顧客にどのような付加価値が提供できるかを、定量的に評価することが大切です。
可能であれば、小規模なPoC(概念実証)を実施し、実際の業務やユーザー行動に与える影響を検証するのが理想です。
また、自社に適したAR技術の選定も欠かせません。ロケーション型が適しているのか、ビジョンベース型が効果的か、それぞれの技術特性と自社の環境を照らし合わせて判断しましょう。
外部のAR開発会社やコンサルティング企業と連携することで、専門的な視点からの提案を受けることも可能です。
AR導入は、単なる一過性のトレンドではなく、長期的な競争力強化につながる戦略的投資です。
現場視点と経営視点の両方を持ち、自社にとって最も価値のある使い方を検討してみてください。
|まとめ
ARは、顧客体験の向上と業務効率化を同時に実現できる革新的な技術として、さまざまな業界で導入が進んでいます。
単なるデジタル化にとどまらず、企業の競争力やブランド価値を高めるための戦略的な取り組みとして位置づけられている点も特徴です。
導入を検討する際は、自社の課題や目的を明確にしたうえで、段階的に取り入れていくことが成功への近道となるでしょう。
ARコンテンツ制作!自社開発による柔軟性でお客様のビジネスをリードする『monoAR』
サービスの特徴や導入事例をまとめた資料をご用意しました。

monoARサービス紹介資料の無料ダウンロードはこちら
資料をダウンロードする
 TWITTER
TWITTER
 FACEBOOK
FACEBOOK
 はてブ
はてブ