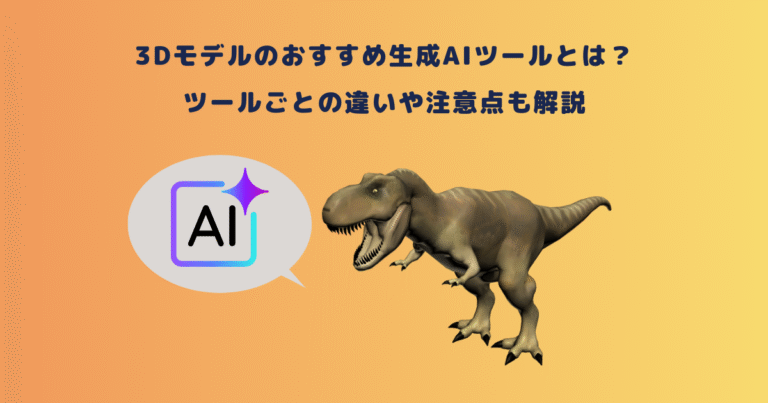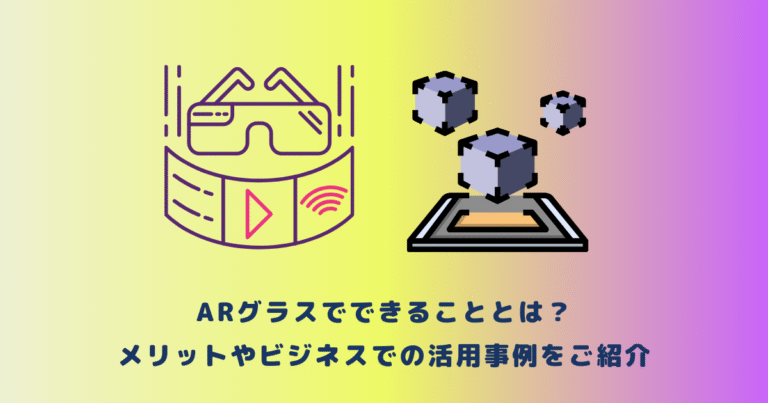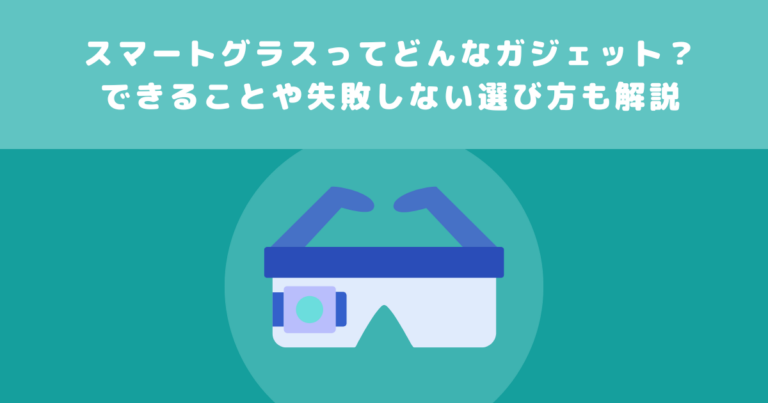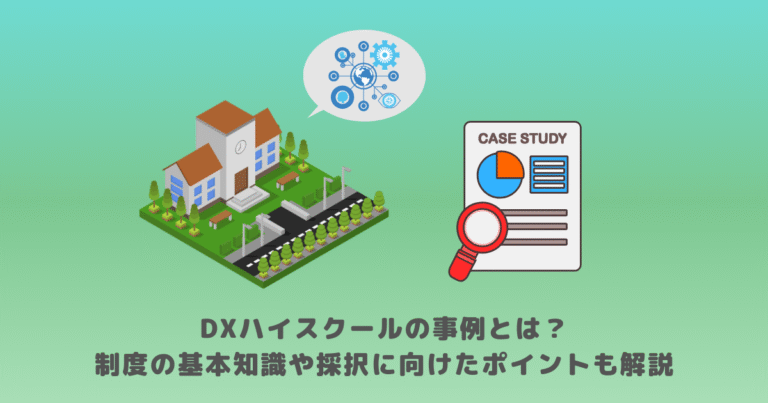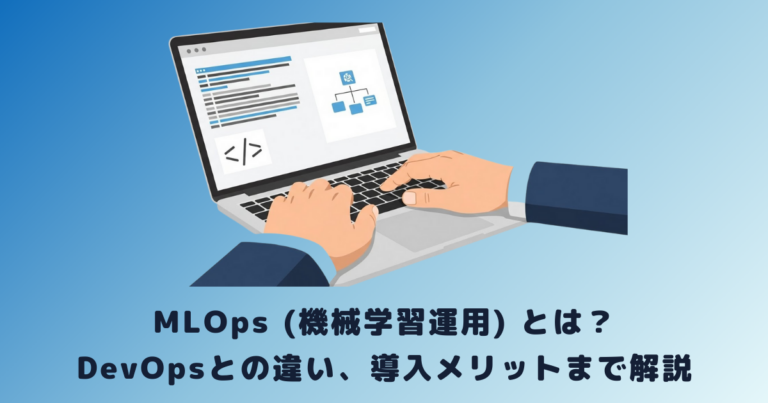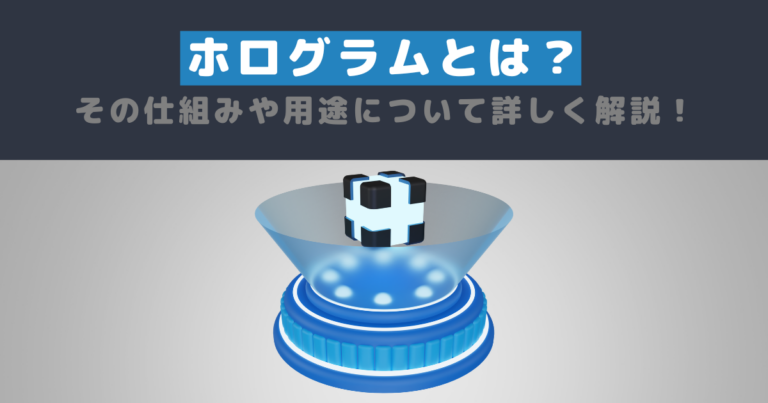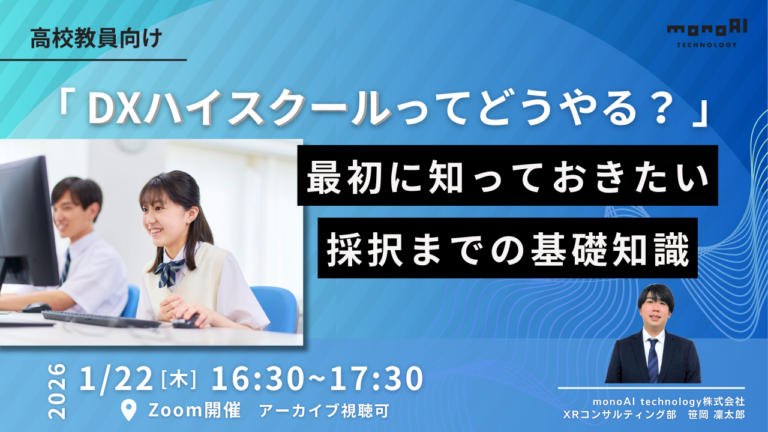「あのベテラン社員が辞めたら、うちの現場は回らなくなる…」
「若手への業務教育で思うような研修効果が出せない…」
このようなお悩みや課題を抱える方は多いのではないでしょうか。
このような課題に対し、DXの一環として注目されているのが「ナレッジマネジメント」です。
この記事では、製造業の経営者・管理職の皆様が直面する「技術継承」や「業務の属人化」といった課題を基に、ナレッジマネジメントの基本的な考え方から、具体的な導入メリット、さらにはAR(拡張現実)などの最新技術を活用した事例まで解説します。
製造業で業務研修や教育、OJTの改善に興味がある方は、ぜひご覧ください。
製造・建設・観光・小売・教育…
あらゆる業界で活用が進むAR!

ARのビジネス活用をご検討の方必見の事例集!無料ダウンロードはこちら
資料をダウンロードする目次
ナレッジマネジメントとは?目的と基本的な考え方
ナレッジマネジメントとは、社員一人ひとりが持つ知識や経験を組織全体の資産として共有・活用し、企業の競争力を高める経営手法です。
業務が特定の人に依存する「属人化」は、その人が不在の際に通常の業務レベルが担保されず、事業が停滞するリスクを招く為、よくある課題として挙げられます。
そこでナレッジマネジメントは、このリスクを解消し、企業の持続的な成長を支えることを大きな目的としています。
この考え方の中心には、ベテランの「勘」や「コツ」といった言語化しにくい「暗黙知」を、マニュアルや手順書のような誰もが理解できる「形式知」へと変換するプロセスがあります。
単なる情報共有システムやツールの導入に終わらせず、この「暗黙知」から「形式知」への変換と共有を通じて、属人化を減らしていくことが基本的な考え方となっています。
製造業でナレッジマネジメントが注目される背景
ではなぜ、ナレッジマネジメントが製造業の分野において注目されているのでしょうか。
主な業界課題から、注目されている背景を解説します。
課題①:ベテラン従業員の退職による技術・ノウハウの喪失
まず一つ目が、ベテラン従業員の引退による技術を持った人材の減少です。
彼らが経験の中で培ってきた、マニュアル化されていない「勘」や「コツ」といった貴重な技術・ノウハウが、引退により徐々に失われつつあります。
この「技術のブラックボックス化」は、製品の品質低下や、トラブル発生時に対応できる人材の不足に直結する深刻な問題です。
課題②:業務の属人化による生産性の低下と業務停止リスク
「この機械の操作はAさんしかできない」「あのトラブルはBさんでなければ直せない」といった業務の属人化は、多くの製造現場で見られる光景です。
特定の個人に業務が依存する体制は、その人が不在の際に生産計画が狂うだけでなく、業務が標準化されていないため改善も進みづらくなってしまいます。
結果として、組織全体の生産性が頭打ちになり、いざという最悪の場合、業務停止という経営リスクに繋がります。
課題③:図面や手順書など、必要な情報の散在と探索の手間
最新の図面がどこにあるか分からない、過去のトラブル報告書が見つからない、といった経験はないでしょうか。
ある調査では、企業の従業員は勤務時間のうち約1.5時間を「情報を探す」ことに費やしているというデータもあります。
情報がサーバーや個人のPCに散在している状態は、こうした無駄な時間を生み出し、従業員のストレスを増大させるだけでなく、企業全体の生産性の低下に繋がりかねません。
ナレッジマネジメント導入がもたらす3つのメリット
製造業における主な現場課題をご紹介しましたが、ナレッジマネジメントはそれらをどう解決できるのでしょうか。
ここでは、その代表的な3つのメリットを解説します。
メリット①:教育コストの削減
ナレッジマネジメントの導入は、ベテラン従業員が持つ「暗黙知」を、AR/VRや動画を使ったマニュアル・手順書といった「形式知」へ変換する仕組みを構築します。
これにより、若手や新人の従業員は、ベテラン従業員の業務知識をいつでも繰り返し学べるようになります
結果として、教育コストが大幅に削減され、若手の早期戦力化に繋がります。

メリット②:製品品質の安定と生産性向上
属人化されていた業務やスキルを、形式知化し全社で共有することで、業務の標準化が促進されます。
業務が標準化されることで、作業者による品質のバラつきが減り、誰が担当しても一定の品質を保てるようになるため、製品の品質が安定します。
また、業務の属人化が解消されることで、特定の従業員が休んでも生産ラインが滞ることがなくなり、組織全体のリスク低減や生産性向上に繋がります。
メリット③:トラブル・クレーム事例の活用
製造現場で発生した設備トラブルや顧客からのクレーム対応といった事例を、原因や対処法と共にデータベースとして蓄積・共有します。
これにより、同様の問題が再発した際に、担当者は過去のナレッジを検索するだけで迅速に解決策を見つけ出すことが可能になります。
問題解決までの時間が劇的に短縮されるだけでなく、同じ過ちを繰り返すこともなくなり、組織としての対応能力が向上します。
【3ステップ】製造業におけるナレッジマネジメントの始め方
ではナレッジマネジメントを導入するには、どのような流れになるのでしょうか。
ここでは、製造業の現場で実践するための具体的な3つのステップを解説します。
ステップ①:対象業務と範囲の決定
まずは、従来の現場業務の中で、どの業務を「形式知化」すべきかを見極めます。
この際に最も重要なのは、形式知化する業務範囲を欲張らないことです。
「業務の属人化が特に深刻な工程」「特定の機械の操作・保守マニュアル」「若手がつまずきやすい作業」など、課題が明確で、かつ成果が見えやすい領域を一つ選びましょう。
対象を限定することで、取り組みの負担を減らし、成功体験を積みやすくなります。
ステップ②:共有ルールと推進体制の構築
次に、ナレッジを共有・蓄積するための簡単なルールを定めます。
例えば、「トラブル発生時は、必ず指定のフォーマットに写真付きで記録する」「マニュアルはA4用紙1枚にまとめる」など、現場の従業員が負担に感じないシンプルなルールが望ましいです。
また、同時にこの取り組みを主導する責任者やチームを任命することも大切です。
旗振り役の存在を立てることで、活動の形骸化を防ぎ、継続的な運用を可能にします。
ステップ③:ツールの選定と導入
最後に、定めたルールを運用するためのツールを選定します。
Excelや社内ファイルサーバーでも始められますが、より効率的に運用するには専用ツールの導入が効果的です。
特に、複雑な機械操作や作業手順の継承には、現実の視界にデジタル情報を重ねて表示するAR(拡張現実)マニュアルのようなXR技術の活用も、近年非常に有効な選択肢となっています。
目的と運用ルールを明確にした上で、それに最適なツールを選ぶという順番を間違えないことが重要です。
【業種別】ナレッジマネジメントの成功事例2選
理論やステップを理解した上で、他社がどのようにナレッジマネジメントを実践し、成功を収めているのかを知ることは、自社で導入する際の具体的なイメージを持つ上で非常に役立ちます。ここでは、異なる業種の製造業が、それぞれの課題をどのように克服したのか、2つの成功事例を紹介します。
事例①:金属加工業|ARマニュアルで技術継承を加速
【課題】 精密な金属加工を手掛けるA製作所では、熟練工の経験と勘に頼る工程が多く、若手への技術継承が大きな課題でした。
特に、複雑なNC旋盤の段取り作業は、OJTだけでは習得に半年以上かかり、品質のバラつきも発生していました。
【解決策】 そこで同社は、熟練工の作業手順を撮影し、AR(拡張現実)技術を活用したデジタルマニュアルを作成・導入しました。
作業者がタブレットやスマートグラスをかざすと、現実の機械設備にCGの矢印やテキスト、注意点などが重ねて表示され、まるで熟練工が隣で指導してくれるかのように、直感的に作業を進められるようにしました。
【成果】 結果、段取り作業の習得期間は従来の半分以下である3ヶ月に短縮され、新人でも初日から一定水準の作業が可能になりました。
作業ミスによる手戻りも約40%削減され、品質の安定と生産性向上に貢献しました。
事例②:素材メーカー|トラブル報告DBで再発を防止
【課題】 24時間稼働のプラントを持つB化学工業では、設備トラブル発生時の対応が、その日の担当者の経験や知識に依存していました。
過去の対応記録が整理されておらず、同様のトラブルが別の部署で再発することも少なくありませんでした。
【解決策】 同社は、シンプルなフォーマットの「トラブル報告データベース」を構築し、現場の誰もがタブレットからアクセスできるようにしました。
トラブル対応後は、症状・原因・対処法を写真付きで記録することをルール化。
これにより、全社のトラブル事例がリアルタイムで共有され、検索可能なナレッジとして蓄積される仕組みを作りました。
【成果】 トラブル発生時、担当者はまずデータベースを検索し、過去の事例を参考にすることで、迅速かつ的確な初期対応が可能になりました。
これにより、設備の平均停止時間は約25%短縮。
さらに、蓄積されたデータを分析することで、トラブルが頻発する箇所の特定と、計画的な予防保全へと繋げることができました。
導入前に知るべきナレッジマネジメントのよくある失敗パターン
これまでナレッジマネジメントについてご紹介しましたが、失敗してしまうケースも大いにあります。
ここでは、特に注意すべき3つの失敗パターンを解説します。
失敗パターン①:ツール導入が目的化してしまう
最もよくある失敗が、高機能なツールを導入しただけで満足してしまうケースです。
「このシステムを入れれば、情報共有が自動的に進むはずだ」と考え、導入自体が目的化してしまう失敗は、現場レベルで陥りやすいパターンです。
ナレッジマネジメントのツールは、あくまで業務知識を共有するための「手段」に過ぎません。
「何のためにナレッジを共有するのか」「それによってどんな課題を解決したいのか」という目的が社内で共有されていなければ、新しい手法の反発を招いたり、継続的な運用が困難になってしまいます。
失敗パターン②:推進担当者がおらず形骸化する
ナレッジマネジメントは、一度仕組みを作れば終わりではありません。
日々の業務の中で知識を蓄積・活用していく「文化」を醸成する、継続的な活動です。
しかし、この活動を主導する責任者やチームといった「旗振り役」がいないと、導入当初の熱意はすぐに薄れてしまいます。
多忙な日常業務に追われる中で、いつの間にか誰もナレッジを更新しなくなり、仕組みそのものが形骸化してしまうのです。
失敗パターン③:情報共有のルールが曖昧で定着しない
従業員にナレッジの共有を促しても、「どんな情報を、いつ、どのような形式で登録すれば良いのか」というルールが曖昧では、行動に移すことはできません。
また、ルールが複雑すぎても、入力が面倒に感じられてしまい、定着の妨げになりかねません。
「まずはトラブル報告書だけを登録する」「フォーマットはこの3項目を埋めるだけ」のように、誰でも迷わず、かつ負担なく実践できるシンプルで明確なルール作りが、ナレッジマネジメントの考え方を定着させるための鍵となります。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
本記事では、製造業が直面する「技術継承」や「業務の属人化」といった課題を解決する鍵として、ナレッジマネジメントの基本的な考え方から、具体的な始め方、成功事例、そして導入時の注意点までを網羅的に解説しました。
ベテラン従業員の退職や労働人口の減少といった人材不足の課題が浮き彫りになり、個人の「暗黙知」を、組織全体で共有できる「形式知」へと変換・蓄積していく取り組みは、今後より必要性が高まっていくでしょう。
ナレッジマネジメントを導入し、成功させることで、スムーズな技術継承や業務標準化が実現し、製品品質の安定と生産性向上といった明確な成果に繋がります。
弊社では、ARやVRを始めとするXRコンテンツの開発を行っております。
ナレッジマネジメントのサポートとなるARやVRを活用した業務マニュアルなどの開発実績もございますので、ご興味がある方はぜひお気軽にお問い合わせください。
製造・建設・観光・小売・教育…
あらゆる業界で活用が進むAR!

ARのビジネス活用をご検討の方必見の事例集!無料ダウンロードはこちら
資料をダウンロードする
 TWITTER
TWITTER
 FACEBOOK
FACEBOOK
 はてブ
はてブ