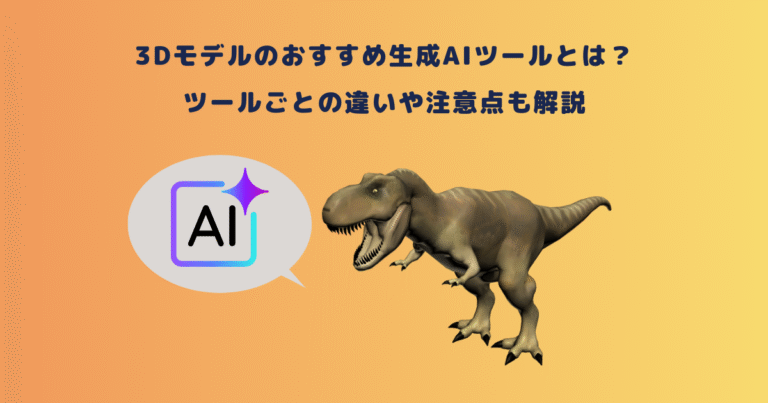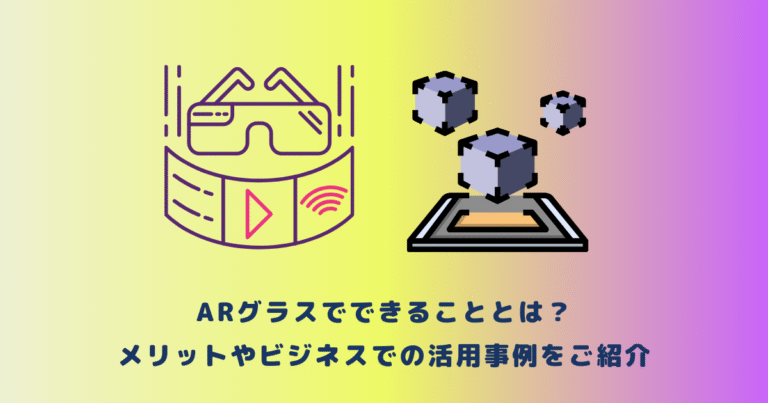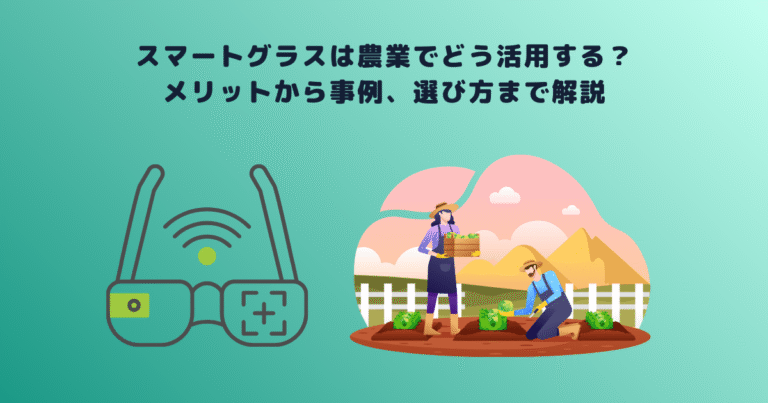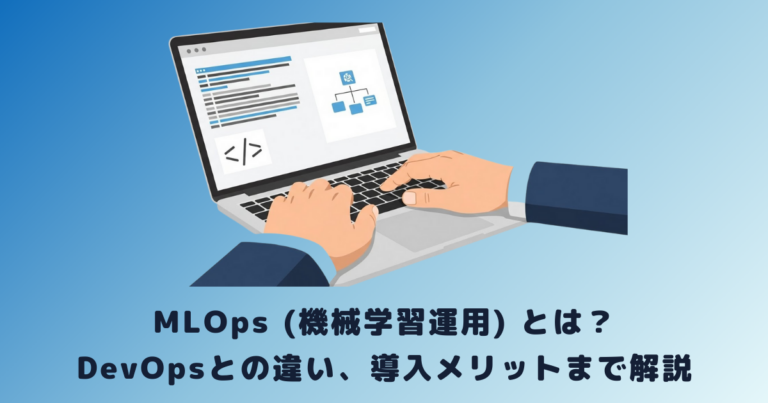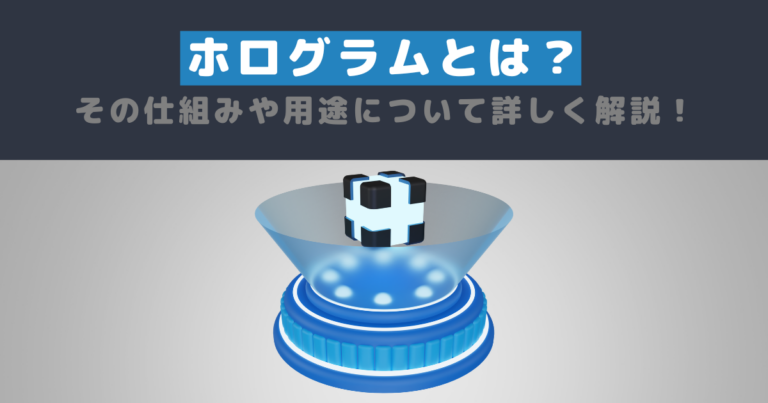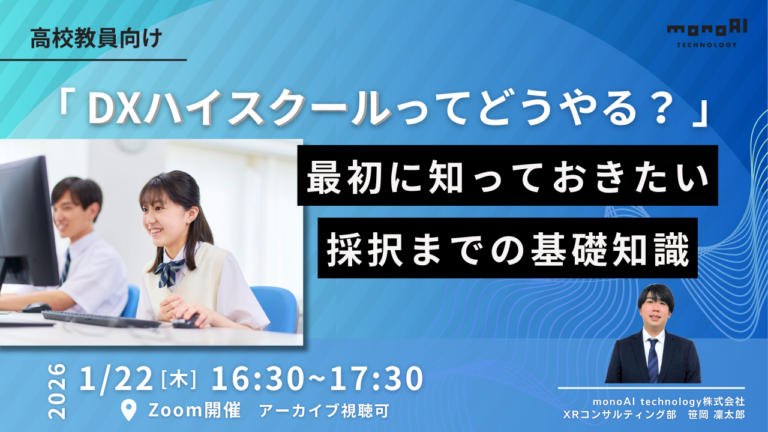「設備保全にどうデジタル技術を取り入れればいいかわからない」
「設備保全のDX化を言われるも、どう活用すればいいかわからない」
このように感じる現場リーダーや担当者の方は多いのではないでしょうか。
本記事は、XRを活用した設備保全の可能性について、メリットや導入ステップなど基本知識から解説していきます。
熟練者の技術を遠隔で共有したり、ARマニュアルで作業ミスを撲滅したりと、
あなたの現場課題を解決するヒントのきっかけとなれば幸いです。
VRコンテンツ制作!自社開発による柔軟性でお客様のビジネスをリードする『monoVR』
サービスの特徴や導入事例をまとめた資料をご用意しました。

monoVRサービス紹介資料の無料ダウンロードはこちら
資料をダウンロードする目次
XR技術とは?AR・VR・MRの違い
では本題に入る前に、XRというについて理解しておきましょう。
XR(クロスリアリティ)とは、VR・AR・MRといった、現実世界と仮想世界を融合させる先端技術の総称です。
これらの技術は混同されがちですが、それぞれに特徴があり、解決したい課題によって最適な選択肢が異なります。
まず、XRがこれら全ての技術を包括する「傘」の役割を果たす言葉だとご理解ください。
その上で、主要な3つの技術を見ていきましょう。
VR(仮想現実):危険な場所でのトレーニングなどに活用
VR(Virtual Reality)は、専用のゴーグルを装着し、視界を360度の立体映像で覆うことで、まるでその場にいるかのような没入体験を生み出す技術です。
現実とは別の仮想空間を創り出すため、例えば「高所や狭所など、危険を伴う場所での作業トレーニング」や「巨大な装置の操作シミュレーション」などを再現し、安全教育として活用されます。

AR(拡張現実):目の前の機械にマニュアルを表示
AR(Augmented Reality)は、スマートフォンやスマートグラスを通して見る現実の風景に、デジタル情報を重ねて表示する技術です。
あくまで現実世界が主役であり、それを補強(Augment)する形で情報を提供します。
設備保全の現場では、「目の前の機械に点検マニュアルや稼働データを表示させる」「熟練者からの指示を、矢印やマーカーとして現実の映像に重ねて表示する」といった活用が代表的です。

MR(複合現実):空間に立体図面やモックアップを置いて共同作業
MR(Mixed Reality)は、ARをさらに自由に扱える技術と言えます。
現実空間を3Dデータとして正確に認識し、まるでそこにもともと存在するかのようにデジタル情報を表示させて、そのデジタル情報を操作することができます。
ARとの大きな違いは、表示した3Dモデルの裏側に回り込んだり、複数人で同時に同じデジタル情報を共有し、操作したりできる点です。
「現実の工場内に、これから導入する設備の3Dモデルを原寸大で配置し、動線を確認する」や「目の前にモックアップを表示させ、デザインやサイズパターンを実寸大で検討する」といった高度な活用が可能になります。

製造現場でありがちな3つの共通課題
XR技術について理解した上で、次に「なぜ今、設備保全の現場でXRが必要とされているのか」を解説します。
昨今の製造現場では、以下の3つの課題に慢性的に悩まされている方も多いのではないでしょうか。
課題①:年々減少する熟練工の技術継承
長年、現場を支えてきた熟練技術者が次々と定年を迎え、彼らが持つ「暗黙知」としての技術やノウハウが失われつつあります。
「背中を見て覚えろ」という従来のOJTは、多忙な現場では機能しづらくなっています。
口頭や文書では伝えきれない勘所や微妙な力加減といった感覚や経験に頼られた貴重なスキルが、継承されないまま現場から消えていくことに、強い危機感を抱いている方も少なくないでしょう。
課題②:人手不足による少人数での生産体制
若手の担い手も不足しており、工場によっては一人ひとりの業務負荷が増大してしまう一方です。
その結果、特定の熟練者にしか対応できない作業が増え、業務の「属人化」が常態化してしまいます。
その担当者が不在の際にトラブルが発生すると対応が大幅に遅れ、生産ラインが停止してしまうといったリスクは、多くの製造業にとって避けたい懸念事項でしょう。
課題③:より効果的な作業ミスや事故防止策の必要性
設備の点検や修理作業は、今もなおペーパーマニュアルや動画マニュアルで実施しているケースは大いにあるでしょう。
しかし、メンテナンスの該当箇所を探すのに時間がかかったり、情報が古かったり、些細な機微に気づけなかったりと、非効率かつミスの温床になりがちです。
手順の勘違いや確認漏れといったヒューマンエラーは、些細なものであっても、大きな事故や品質問題に直結する危険性を孕んでいます。
XR技術は、これらの課題に対してのアプローチが可能であり、従来の設備保全を改善していける可能性を秘めています。
【課題別】設備保全XRでできる3つのシンプルな使い方
では、先ほど挙げた根深い課題に対して、XRは具体的に何ができるのでしょうか。
XR技術を活用することで、設備保全の現場は「遠隔支援」「作業ナビゲーション」「教育・トレーニング」という3つの強力な解決策を手に入れることができます。
課題別に、それぞれの使い方を詳しく見ていきましょう。
使い方①:【遠隔支援】移動時間ゼロで、どこでも熟練者が隣にいる環境を創る
これは主に「人手不足」や「属人化」の課題に対して効果を発揮します。
現場の作業員がスマートグラスを装着すると、その視界がリアルタイムで遠隔地にいる熟練技術者のPCやタブレットに共有されます。
熟練者は、現場に行かなくても現地の状況を正確に把握し、音声で指示を送ったり、作業員の視界にARで矢印やマーカーを表示させたりして、直感的な指示を出すことが可能です。
これにより、熟練者自身の移動にかかっていた時間とコストをゼロにし、一人の熟練者が複数の現場を同時にサポートできる体制を構築できます。
使い方②:【作業ナビゲーション】ARマニュアルで、誰でもベテランと同じ手順を再現
この使い方は、「作業ミス」の撲滅や「技術継承」の効率化に関わる使い方です。
紙のマニュアルの代わりに、スマートグラスやタブレットを通じて、目の前の設備に作業手順やチェックリストをARで表示させます。
作業員は視線を大きく動かすことなく、次に何をすべきかを確認でき、尚且つ両手がふさがらないため作業に集中できます。
熟練者の手順をデジタル化してナビゲーションさせることで、経験の浅い作業員でも正確で質の高い作業を遂行できるようになり、品質の均一化に繋げることが可能です。
使い方③:【教育・トレーニング】没入体験学習で、安全かつ効率的にスキルアップ
こちらは特に「安全教育」や「業務トレーニング」に貢献します。
現実の工場や設備を忠実に再現したVR空間の中で、実践的なトレーニングを行います。
例えば、高価な設備や危険を伴う作業の訓練、あるいは数年に一度しか発生しないようなレアなトラブルへの対処法などを、安全な環境で何度でも反復練習することが可能です。
失敗しても現実世界に影響はないため、受講者は萎縮することなく試行錯誤でき、尚且つVRの高い没入感により、学習効果を大幅に高めることができます。
このようにXRは、単なる目新しい技術ではなく、現場が抱える課題を一つひとつ解決しうる実践的なツールなのです。
設備保全XRで失敗しない3つの手順
XRの具体的な使い方が見えてくると、次に気になるのは「どうやって導入を進めるか」でしょう。
XR導入は、大規模な投資が可能な大企業だけの特権ではありません。
むしろ、現場の課題が明確な中小企業こそ、ここで紹介する「スモールスタート」によって、失敗のリスクを抑えながら大きな効果を得られる可能性があります。
スモールスタートで始めるための手順を解説していきます。
手順①:課題の特定|「一番痛いところ」を1つだけ見つける
まず最も重要なのは、あの課題もこの課題も、、、と欲張らないことです。
あなたの現場で「最も時間がかかっている」「特定の人物しか対応できない」「ミスが頻発している」といった、誰もが感じている「一番痛い(ペインの深い)」課題を、たった一つだけ特定してください。
例えば、「〇〇装置の定期点検作業」や「海外製設備のトラブル発生時の一次対応」のように、具体的な業務レベルまで絞り込むことが理想です。
課題を一つに絞ることで、導入目的が明確になり、後の効果測定も容易になります。
手順②:PoC計画|最小構成で「お試し導入」を計画する
次に、特定した課題を解決するためにPoC(Proof of Concept:概念実証)、つまり「お試し導入」の計画を立てます。
ここでのポイントは、全てを完璧にやろうとせず、最小構成で始めることです。
例えば、「対象業務は〇〇点検のみ」「期間は1ヶ月」「参加メンバーは3名」「機材はスマートグラス2台とソフトウェアの1ライセンス」といったように、必要最低限の範囲を定めます。
このPoCを通じて、本格導入の前に「現場のWi-Fi環境で安定して使えるか」「デバイスは作業の邪魔にならないか」といった技術的・物理的な懸念点を低コストで洗い出すことができます。
手順③:効果測定|費用対効果を「見える化」して次を判断する
PoCを実施したら、必ずその効果を客観的に評価します。
この評価は、次のステップ(本格導入、あるいは計画見直し)を判断するための重要な根拠となります。
評価は、数値で測れる「定量的効果」と、感覚的な「定性的効果」の両面から行いましょう。
・定量的効果の例:作業時間が平均20%短縮、エラー発生率が0になった、など。
・定性的効果の例:作業員から「精神的な安心感が大きい」「若手でも自信を持って作業できる」といった声が上がった、など。
これらの結果を基に、費用対効果を可視化することが重要です。
この「課題特定 → PoC → 効果測定」というサイクルを回すことで、XR導入の失敗リスクを最小限に抑え、あなたの会社に合った最適な活用法を見つけ出すことができるのです。
設備保全XRに向けた導入前の3つのポイント
スモールスタートの手順が見えたら、次はその計画をより確実なものにするための準備に取り掛かりましょう。
XR導入を成功させるためには、技術的な検討と並行して、事前に「インフラ」「運用体制」「現場の協力」という3つの重要なポイントを確認しておく必要があります。
なぜなら、これらのいわば「土台」となる部分を見落としてしまうと、せっかく導入したツールが「いざという時に繋がらない」「情報が古くて使えない」「誰も使ってくれない」といった事態に陥りかねないためです。
PoC(お試し導入)を始める前に、ぜひ以下の点を確認してみてください。
Point①:現場のインフラ|Wi-Fi環境は安定しているか?
スマートグラスを用いた遠隔支援など、多くのXRソリューションは安定したインターネット接続を前提としています。
しかし、工場などの現場は、金属製の壁や大型設備が電波を遮断し、Wi-Fiが繋がりにくい「死角」が生まれやすい環境です。
PoCを計画しているエリアで、事前にスマートフォンのアプリなどでWi-Fiの強度や通信速度を計測しておくことを推奨します。
もし電波が弱い場合は、業務用の中継器を設置するといった対策を併せて検討する必要があります。
Point②:運用体制|誰がXRコンテンツを作成・管理するのか?
ARマニュアルなどのデジタルコンテンツは、一度作ったら終わりではありません。
設備が更新されたり、より効率的な作業手順が見つかったりした際には、その都度コンテンツをメンテナンス(修正・更新)していく必要があります。
このメンテナンス作業を「誰が(どの部署が)」「どのくらいの頻度で」担当するのか、あらかじめ決めておくことが重要です。
PoCの段階からこの運用体制を意識しておくことで、本格導入後のスムーズな定着に繋がります。
Point③:現場の協力|使うのは「現場の担当者」という意識があるか?
実はこれが最も重要なポイントです。
どんなに優れたツールであっても、実際にそれを使う現場の担当者が「操作が面倒だ」「今のやり方を変えたくない」と感じてしまっては、決して定着しません。
導入を検討する企画段階から、現場のリーダーや若手のキーパーソンを巻き込み、彼らの意見に耳を傾けることが成功のカギです。
「これは自分たちの仕事を楽にし、安全にするためのツールだ」という当事者意識を共有してもらうことで、現場は強力な推進パートナーになります。
このように、技術、環境、そして「人」という3つの側面から事前に準備を進めることが、XR活用の成功確率を大きく引き上げるのです。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
今回は設備保全におけるXR技術の活用に関して、ご紹介しました。
XR導入を成功させるための課題の整理、具体的な使い方、そしてスモールスタートの手順まで、具体的なイメージが湧いてきたのではないでしょうか。
ゲームやエンタメ領域でも使われることの多いXRですが、今回のような産業分野でも徐々に活用が広まっています。
導入のハードルこそあれど、昨今の製造業界の慢性的な課題を解決しうるツールに化ける可能性は十分に秘めているので、ぜひ検討してみてはいかがでしょうか。
弊社では、VRなどXR技術を用いた安全教育、VRマニュアルなどの産業向けXRコンテンツを開発しております。
XR技術の現場活用についてご興味のある方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。
VRコンテンツ制作!自社開発による柔軟性でお客様のビジネスをリードする『monoVR』
サービスの特徴や導入事例をまとめた資料をご用意しました。

monoVRサービス紹介資料の無料ダウンロードはこちら
資料をダウンロードする
 TWITTER
TWITTER
 FACEBOOK
FACEBOOK
 はてブ
はてブ