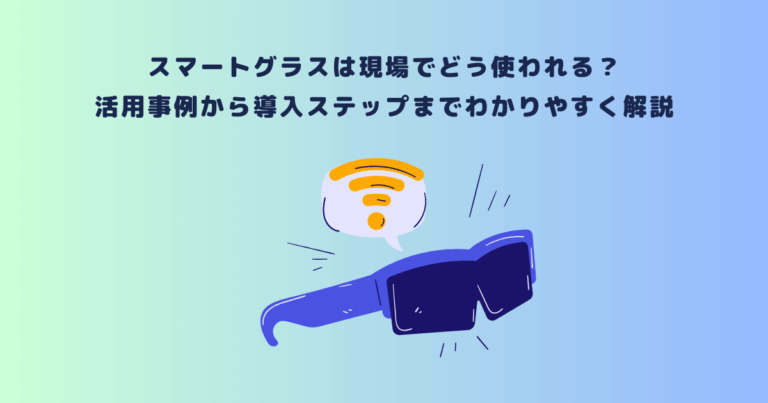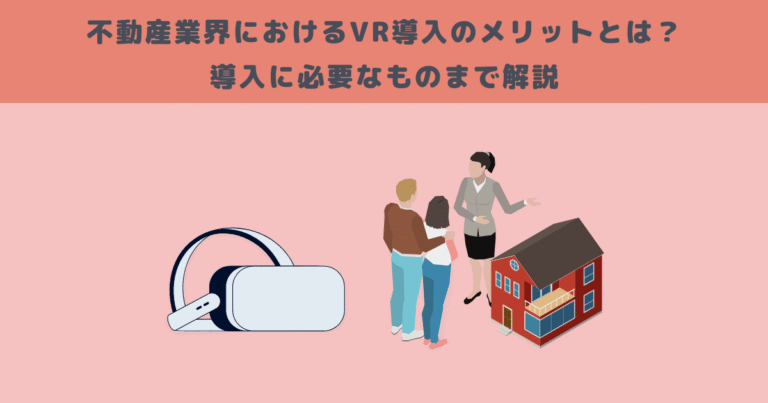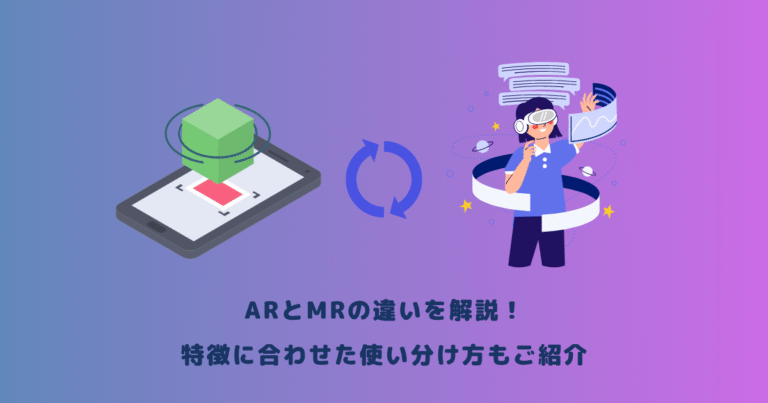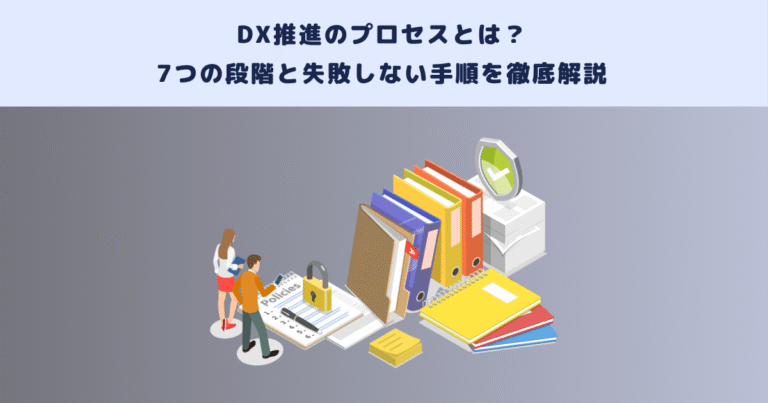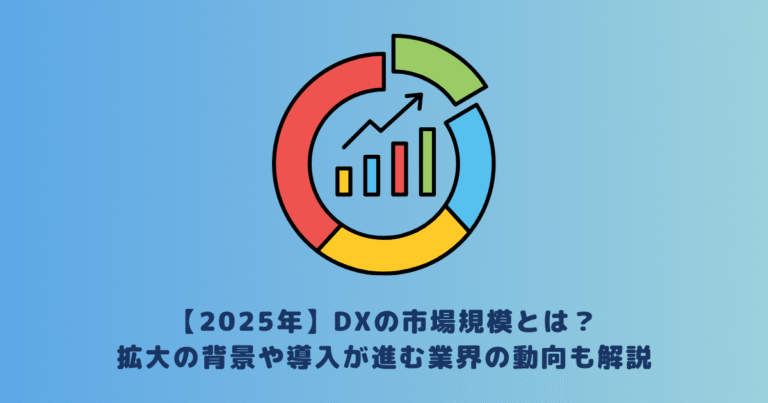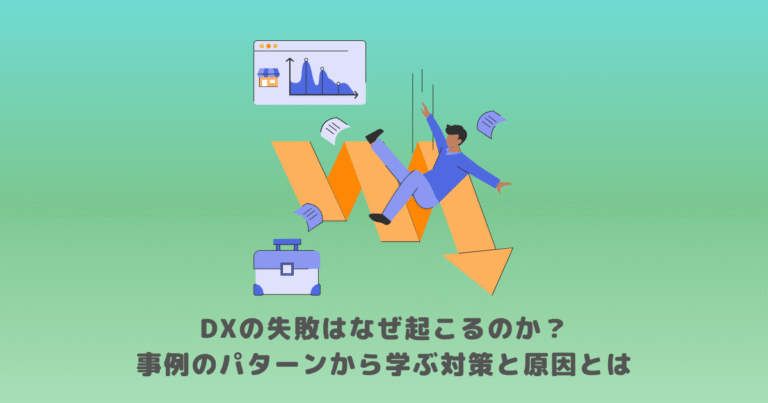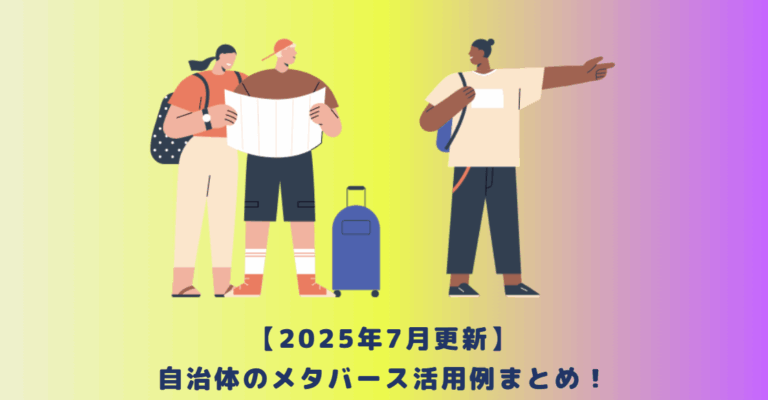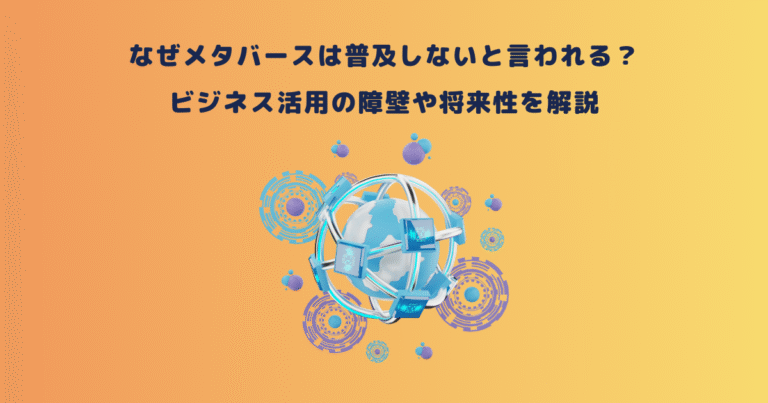「人手不足なのに、若手への技術継承が進まない」
「電話やチャットで対応しきれないトラブルで、また現場への移動が必要になった」
このような課題は、多くの製造現場が直面する現実ではないでしょうか。
実は、それらの課題を解決する鍵として「スマートグラス」の活用が進んでいます。
遠隔地からでも熟練者がまるで隣にいるかのように支援できたり、作業手順を視界に直接表示したりすることで、業務効率を飛躍的に向上させられるからです。
本記事では、製造業などを中心としたスマートグラスの活用事例から、費用対効果の示し方から、失敗しない選び方、導入を成功させる3つのステップまで解説します。
製造・建設・観光・小売・教育…
あらゆる業界で活用が進むAR!

ARのビジネス活用をご検討の方必見の事例集!無料ダウンロードはこちら
資料をダウンロードする目次
製造業の人手不足と技術継承の現状
製造業をはじめとする現場では、少子高齢化による労働人口の減少に加え、熟練技術者が持つ「暗黙知」の継承がうまくいかず、、「人手不足」「技術継承」「生産性の停滞」といった課題に直面しています。
実際に、帝国データバンクの調査(2024年4月)では、正社員が「不足」していると感じる企業は全体の52.7%ですが、製造業では60.9%と特に高い水準です。
経済産業省の「ものづくり白書」でも、技能継承の重要性が指摘されており、紙のマニュアルや従来のOJTだけでは、勘やコツといった暗黙知の継承や若手の育成が追いついていません。
さらに、トラブル対応のために専門家が遠隔地の工場へ長時間かけて移動する必要があり、この移動時間やコストが迅速な問題解決と生産性を大きく妨げています。
このような現状により、製造業の現場では省人化や技術継承、生産性向上の重要性が高まっています。
製造業でスマートグラスが注目される3つの理由
前述した製造現場の課題を解決するソリューションとして、スマートグラスの導入が急速に進んでいます。
スマートグラスとは、メガネのように装着し、視界に作業指示やマニュアルなどのデジタル情報を重ねて表示できるメガネ型のウェアラブルデバイスです。
①ハンズフリーによる作業効率と安全性の向上
スマートグラスを活用すれば、両手で工具や部品を扱いながら、視界の隅にマニュアルや設計図を常に表示させておくことが可能です。
これにより、作業を中断してタブレット端末や紙の資料を確認する手間が省かれ、作業効率が飛躍的に向上します。
また、両手が常に自由になることで、安全性が求められる高所作業や精密作業におけるヒューマンエラーの削減にも繋がります。
②遠隔支援による「移動ゼロ」での技術継承
現場作業員が見ている映像を、そのまま遠隔地にいる熟練技術者や管理者のPC画面にリアルタイムで共有できます。
これにより、熟練者はオフィスにいながら複数の現場の若手に対し、まるで隣にいるかのように具体的な指示を出すことが可能になります。
専門家の移動時間と出張コストをゼロにし、迅速なトラブル解決と新しい形での技術継承を同時に実現するのです。
③作業記録の自動化による品質向上とデータ活用
スマートグラスに搭載されたカメラを使えば、作業の証拠となる写真や動画をハンズフリーで、かつ正確なタイミングで撮影・保存できます。
これまで手作業で行っていた検査記録や報告書作成の工数が大幅に削減されるだけでなく、作業手順の遵守を客観的な証拠として残せるため、品質保証の強化にも貢献します。
さらに、蓄積された映像データは、後の技術教育用の教材や、AIによる作業分析を通じたさらなる業務改善へと活用できる可能性を秘めています。
【課題別】製造業におけるスマートグラス活用事例5選
それでは、実際に製造業をはじめとする様々な現場で、スマートグラスがどのように活用され、課題解決に繋がっているのかを見ていきましょう。
ここでは、代表的な活用パターンを5つの具体的な事例として紹介します。
事例①:熟練者がオフィスから現場の若手を遠隔支援

これは、熟練技術者が遠隔地から現場作業をリアルタイムに支援する、最も代表的な活用法です。
現場作業員のスマートグラスに映る「一人称視点」の映像を共有することで、遠隔地にいる専門家は、まるで現場にいるかのように状況を正確に把握できます。
例えば、地方の工場で発生した設備の突発的なトラブルに対し、遠隔地の熟練者が映像を見ながら具体的な指示を送れます。
スマートグラスの画面上に、指示箇所をマーカーで示したり、資料を送ったりできるソリューションも実用化されています。
これにより、熟練者の移動時間を完全に削減し、設備のダウンタイムを最小限に抑えることが可能です。
事例②:紙のマニュアルからARのマニュアルへ

作業手順やチェックリストをAR(拡張現実)技術で視界に表示し、作業者をナビゲートする活用法です。
これまで紙やタブレットで確認していた情報をハンズフリーで確認できるため、作業員は両手での作業に集中でき、ヒューマンエラーを防止します。
例えば、物流倉庫でのピッキング作業において、次に取るべき商品の保管場所や数量を視界に表示させたり、組み立て工程の多い複雑な製品の製造ラインで、次に締めるべきネジの位置をARでハイライトしたりする、といった活用が進んでいます。
結果として、経験の浅い作業員でも熟練者と同等の精度で作業を遂行できるようになり、新人教育にかかるコストと時間の大幅な削減に繋がります。

事例③:ベテランの“暗黙知”を目線映像で記録・共有

熟練技術者の作業そのものを一人称視点の映像データとして記録し、教育コンテンツとして活用する方法です。
熟練者が「何を見て、どのタイミングで、どのように手を使っているか」という、マニュアル化が難しい“暗黙知”を、映像で克明に記録できるからです。
例えば、溶接や研磨といった繊細な手技が求められる作業において、熟練者の目線の動きや工具の角度を録画し、スロー再生や解説テロップを加えて研修教材を作成します。
若手はこれを繰り返し視聴することで、感覚的なスキルを効率的に学ぶことが可能になります。
これにより、OJTだけに頼らない、質の高い技術継承の仕組みを構築できます。
事例④:ハンズフリーでの写真・動画撮影で品質保証を強化

インフラ設備の点検や製品の保守作業内容を、写真や動画でハンズフリー記録する活用法です。
作業者は両手で作業を続けながら、必要な瞬間の映像を確実に記録できるため、報告業務の効率化と信頼性の向上に繋がります。
プラント設備の定期点検でボルトの締め付け確認やメーターの数値を撮影したり、製品の最終検査で傷や汚れがないことを証明する映像を記録したりする際に活用されています。
撮影したデータに時刻や位置情報が自動的に付与されるソリューションもあり、報告書作成の手間を大幅な削減など、効率化にも貢献します。
事例⑤:発注元や海外拠点とのリモート検品・検収

発注元の担当者や品質管理者などが、遠隔地から製品の検品や工場の監査に立ち会う活用法です。
関係者が現地に一堂に会す必要がなくなり、出張コストやスケジュール調整の手間を大幅に削減できるという大きなメリットがあります。
例えば、海外の委託工場で製造された製品の出荷前検査に、日本本社の担当者がスマートグラスを通してリアルタイムに立ち会います。
担当者は現地の作業員が見ている映像で製品の細部を確認し、その場で指示を出しながら品質をチェックできます。
これにより、リードタイムの短縮とコスト削減を両立させながら品質管理体制を構築することが可能になるのです。
スマートグラス導入、費用対効果の“3つの示し方”
スマートグラスの具体的な活用イメージが湧いたところで、次に重要となるのが「費用対効果」です。
①生産性の向上
最も分かりやすいのが、作業時間と移動コストの削減による効果です。
スマートグラスの導入により、これまで移動や確認作業に費やしていた非生産的な時間を大幅に削減できるため、定量的に効果を試算できます。
例えば、専門技術者1名が月に5回、往復4時間かけて遠隔地の現場対応をしていたとします。
遠隔支援を導入すれば、この月20時間の移動時間がゼロになり、技術者の時給が4,000円であれば、人件費だけで月8万円、年間で96万円もの直接的なコスト削減に繋がると示せます。
また、作業員がマニュアル確認のために1日30分作業を中断していた場合、この時間を削減することで創出される工数も大きな効果です。
これらの具体的な数値を基に試算することで、導入コストをどれくらいの期間で回収できるか(ROI)を明確に提示できます。
②品質の安定化
次に重要なのが、品質向上による間接的なコスト削減と、企業としての信頼性向上です。
作業ナビゲーション機能によるミスの防止や、作業記録によるトレーサビリティの確保は、不良品の発生や手戻り工数の削減に直結します。
例えば、「ヒューマンエラーに起因する不良品の発生率が0.5%から0.2%に改善した場合、それに伴う廃棄コストや再生産コストが年間でいくら削減されるか」といった試算は、強力な説得材料になります。
また、新人でもベテランと同じ水準で作業できるようになることで、製品やサービスの品質が安定します。
これにより、顧客からのクレームや、その対応に追われるコストが削減されるといった二次的な効果も期待できます。
③教育コストの改善と従業員満足度
そして最後は、教育コストの改善効果です。
「新人教育の期間が従来の3ヶ月から2ヶ月に短縮できた」
「先進技術の導入で、現場の働きがいやモチベーションが向上した」
といった効果は、従業員の満足度向上に繋がります。
これらの定性的なメリットは、優秀な人材の定着率向上や、採用活動の強化にも繋がり、持続的な企業成長の基盤となるのです。
失敗しないスマートグラス選びの3つのポイント
導入による費用対効果への期待が高まったところで、次に考えるべきは「どのスマートグラスを選ぶか」です。
スマートグラスは製品によって性能や特徴が大きく異なるため、目的や利用環境に合わないものを選ぶと、せっかくの導入が無駄になってしまう可能性があります。
ここでは、製造現場での導入を成功させるために、最低限チェックすべき3つのポイントを解説します。
Point①:防塵・防水・耐衝撃性能は十分か
まず最初に確認すべきは、利用する現場の環境に耐えうるハードウェアとしての性能です。
オフィスでの利用を想定した軽量なモデルと、工場や屋外での過酷な利用を想定したモデルでは、耐久性が全く異なります。
例えば、粉塵が舞う工場や、屋外での雨天作業で利用する場合は、防塵・防水性能を示す「IPコード」の確認が必須です。
「IP65」といった高い等級を持つ、業務利用に特化したモデルを選ぶ必要があります。
また、落下のリスクがある高所作業や、高温・低温環境下での利用が想定される場合は、耐衝撃性能や動作温度範囲も重要な選定基準となります。
さらに、ヘルメットへの装着が可能か、普段使用している安全メガネの上からでも装着できるか、といった現場ならではの利用シーンも事前に確認しておきましょう。
Point②:既存の業務システムとスムーズに連携できるか
次に、ソフトウェア面での拡張性、特に既存の業務システムと連携できるかを確認します。
スマートグラスを単独のツールとして使うのではなく、既存の業務フローにシームレスに組み込むことで、導入効果を最大化できるからです。
例えば、スマートグラスで撮影した点検データを、自社の品質管理システムに自動で転送したり、顧客管理システム(CRM)から作業指示をグラスに直接表示したりすることが考えられます。
また、企業で利用する以上、情報漏洩を防ぐための強固なセキュリティ対策が施されているか、自社のセキュリティポリシーに準拠しているかも必ず確認すべきポイントです。
Point③:導入後の運用まで見据えたサポートはあるか
最後に、見落としがちですが非常に重要なのが、導入を支援するベンダーのサポート体制です。
スマートグラスは現場の作業員にとって新しいデバイスであるため、導入初期には操作方法に関する問い合わせや、予期せぬトラブルが発生する可能性があります。
そのため、以下のようなサポートが提供されているかを確認しましょう。
・導入時の初期設定や、従業員向けのトレーニングの支援
・運用開始後にトラブルが発生した際、迅速に対応してくれるヘルプデスクや保守サービス
・本格導入前のPoC(概念実証)段階からの、活用のコンサルティングや効果測定の支援
デバイスの価格やスペックだけでなく、導入から運用、さらなる活用までをトータルで支援してくれる、信頼できるパートナーを選ぶことが導入成功の鍵を握ります。
スマートグラス導入を成功させる3つのステップ
自社に合ったスマートグラスのイメージが固まったら、いよいよ導入プロジェクトの開始です。
新しいツールの導入は、進め方を間違えると現場の混乱を招き、期待した効果が得られないことも少なくありません。
ここでは、スマートグラスの導入を成功に導くための、重要な3つのステップを順に解説します。
Step1:目的の明確化
導入プロジェクトの最初のステップであり、最も重要なのが「目的を明確に定義すること」です。
目的が曖昧なままでは、適切な製品選定や効果測定ができず、プロジェクトが迷走してしまいます。
「スマートグラスを導入すること」自体が目的になってはいけません。
まずは、「どの部署の、どの業務における、どのような課題を解決したいのか」を具体的に言語化します。
例えば、「A工場の組み立てラインにおける、新人の作業ミス率を30%削減する」や、「全国の拠点への技術者派遣コストを年間200万円削減する」といった、具体的で測定可能な目標(KPI)を設定することが理想です。
Step2:スモールスタートで始める
目的が明確になったら、いきなり全社展開を目指すのではなく、特定の部署や業務に限定して小さく始める「スモールスタート」が有効です。
影響範囲を限定することで、リスクを最小限に抑えながら、実際の現場での有効性や、本格導入に向けた課題点を洗い出すことができるからです。
この検証段階は、一般的にPoC(Proof of Concept:概念実証)と呼ばれます。
「まずは技術サポート部門の3名で、1ヶ月間、遠隔支援業務に限定して試用してみる」といった具体的な計画を立て、操作性や通信環境、現場作業員からのフィードバックなどを収集します。
そのPoCで得られた「小さな成功体験」と具体的な改善点が、その後の全社展開に向けた知見となるのです。
Step3:現場への運用サポート
最後のステップは、実際にツールを利用する現場の作業員にいかにスムーズに受け入れてもらうか、という「現場へのサポート」です。
導入に際しては、「なぜこのツールを導入するのか」「これを使うことで、皆さんの仕事がどう楽になるのか」といった目的やメリットを、プロジェクト担当者が丁寧に説明する場を設けることが不可欠です。
また、直感的に使える操作性の高いソリューションを選ぶとともに、分かりやすいマニュアルの整備や、導入初期の重点的なサポート体制を構築することも重要となります。
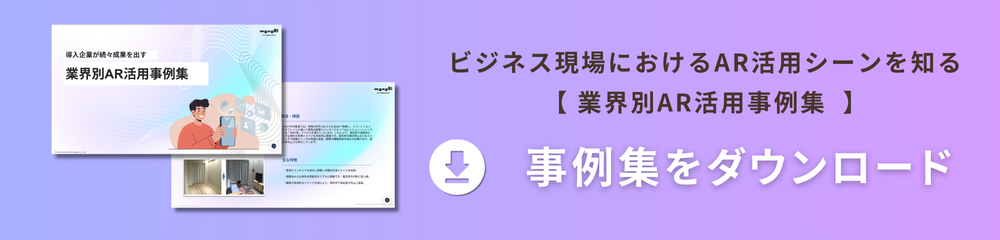
まとめ
いかがでしたでしょうか。
今回は製造業などを中心としたスマートグラスの活用事例から、費用対効果の示し方、選び方、そして導入を成功させるためのステップまでを網羅的に解説しました。
スマートグラスが、人手不足や技術継承といった現場の根深い課題を解決し、生産性を飛躍的に向上させるポテンシャルを持つツールであることをご理解いただけたかと思います。
弊社では、ARをはじめとするXRコンテンツの開発を行っております。
産業向けに特化したXRコンテンツの導入にご興味がある方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。
製造・建設・観光・小売・教育…
あらゆる業界で活用が進むAR!

ARのビジネス活用をご検討の方必見の事例集!無料ダウンロードはこちら
資料をダウンロードする
 TWITTER
TWITTER
 FACEBOOK
FACEBOOK
 はてブ
はてブ