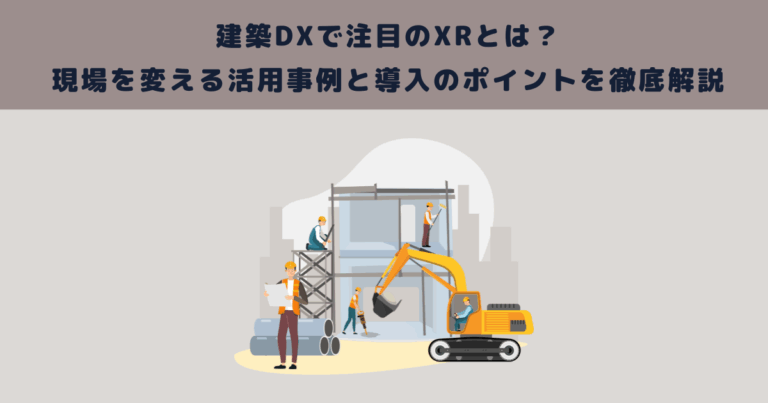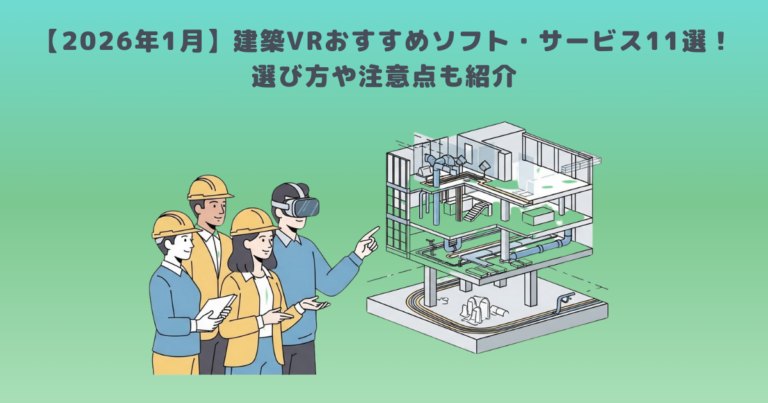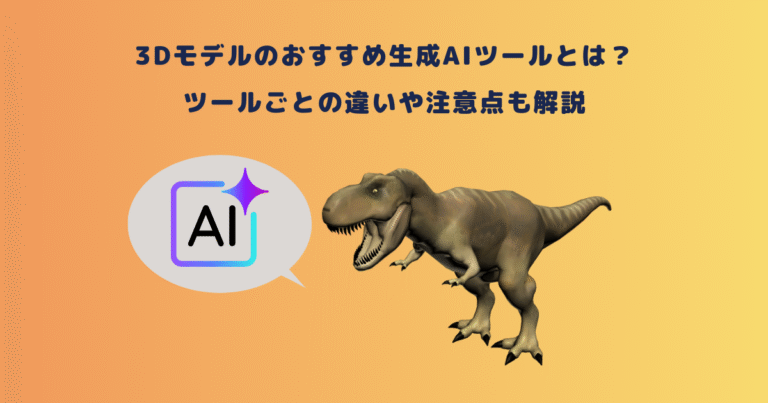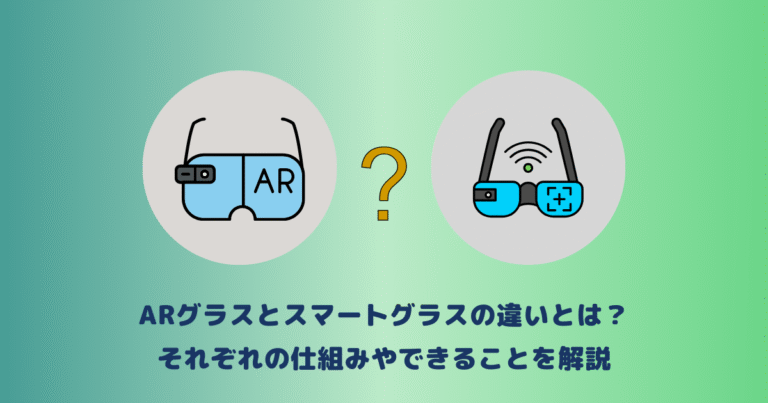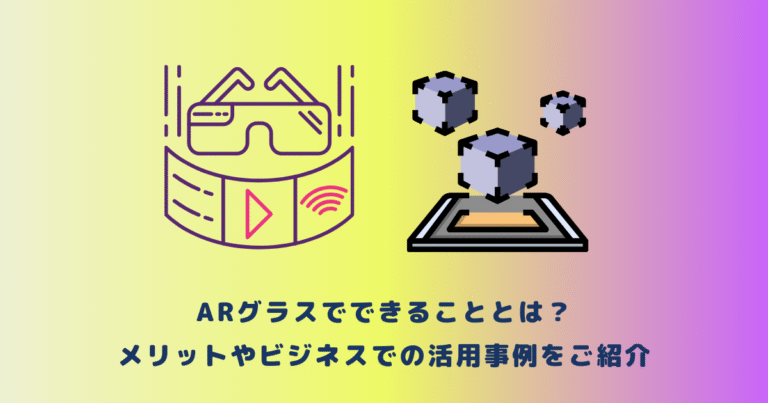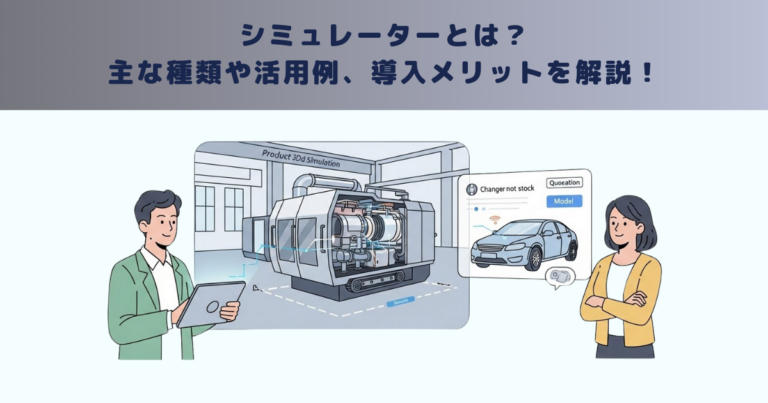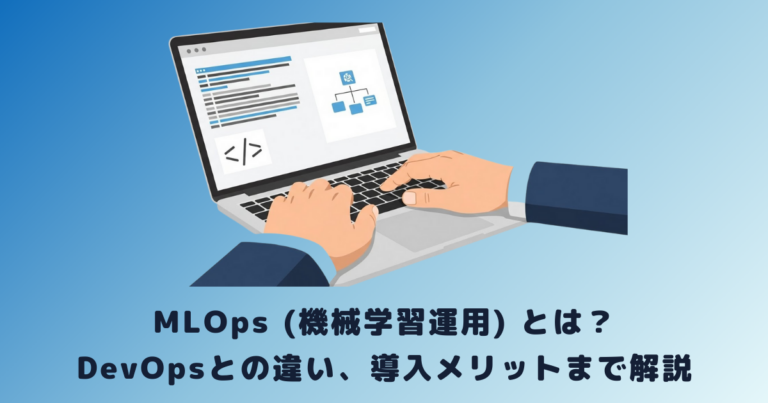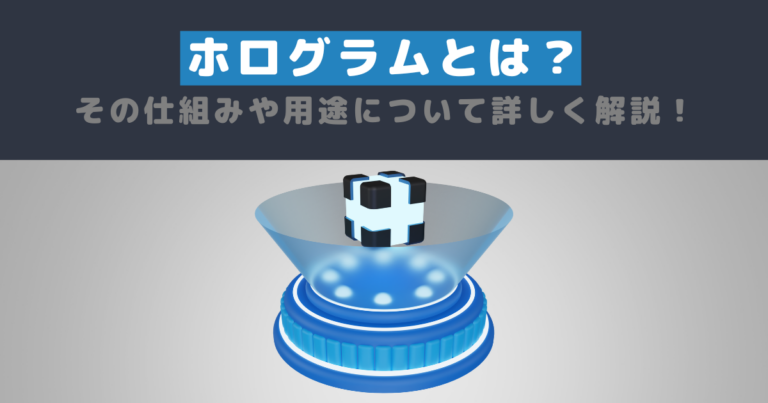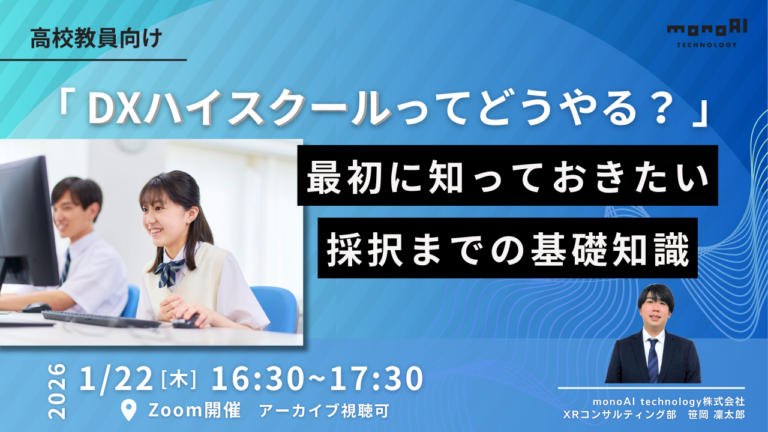「BIMモデルを設計だけで終わらせるのは、もったいない」
「施主とのイメージ共有がうまくいかず、また手戻りが発生してしまった」
「業務改善や効率化に繋がる新しい手法がないか探している」
もし、このような課題に一つでも心当たりがあれば、XR技術がその解決の鍵になるかもしれません。
XRは、VR(仮想現実)やAR(拡張現実)といった技術の総称であり、現実世界とデジタル情報を融合させることで、これまでの建築プロセスを根底から変える可能性を秘めてます。
本記事では、建築業におけるXRの基礎知識から、活用事例、導入のメリット、そして失敗しないためのポイントまでを網羅的に解説します。
DXの一環として、XR技術の導入にご興味がある方はぜひご覧ください。
VRコンテンツ制作!自社開発による柔軟性でお客様のビジネスをリードする『monoVR』
サービスの特徴や導入事例をまとめた資料をご用意しました。

monoVRサービス紹介資料の無料ダウンロードはこちら
資料をダウンロードする目次
今さら聞けない「建築XR」とは?AR/VR/MRの違いを1分で図解
建築業界で注目されるXRとは、AR(拡張現実)、VR(仮想現実)、MR(複合現実)といった先端技術の総称です。
これらの技術は、現実世界にデジタル情報を融合させ、ユーザーに新たな体験を提供するという共通点から「X Reality(クロスリアリティ)」、略してXRと呼ばれています。
それぞれの技術には明確に違いがあり、建築業務のフェーズによって効果的な活用方法が異なります。
VR(Virtual Reality:仮想現実)
3DCGで作られた立体映像と立体音響で構築された、仮想空間へ没入できる技術です。
例えば、専用のゴーグルなどを装着し、仮想の建物の内部を歩き回る(ウォークスルーする)といった、設計段階での合意形成や完成イメージの共有に活用することができます。

AR(Augmented Reality:拡張現実)
現実世界の映像に、デジタル情報を重ねて表示する技術です。
例えば、スマートフォンのカメラを実際の建設現場にかざすと、画面上に設計図(BIMモデル)が原寸大で表示され、配管の位置などを正確に確認する際に役立ちます。

MR(Mixed Reality:複合現実)
ARをさらに発展させ、現実空間に表示されたデジタル情報を、配置し操作できる技術です。
例えば、MRデバイスを装着した複数の作業者が、現実の空間に表示された3Dモデルを共有し、遠隔地から共同でレビューや修正指示を行うといった、より高度なコラボレーションを実現できます。

このように、一言にXRといっても、AR、VR、MRと特徴が異なるため、それぞれどのような技術なのかを理解しておきましょう。
【業務別】建築XRは何ができる?
では実際に、建築XRの活用によってどのようなことが実現できるのでしょうか。
従来のプロセスが抱えていた課題を、XRがどのように解決するのか。 業務別の具体的な変化を見ていきましょう。
《設計・合意形成》「完成形が伝わらない…」を防ぐ。BIMモデルの実寸大体験で手戻りをゼロに
まず、設計・合意形成のフェーズでは、XRが関係者間の認識のズレという長年の課題を解決します。
これまでの2D図面やCGパースでは、空間のスケール感や細かな納まり、素材の質感までを正確に共有することは困難でした。
結果として、施工段階や完成後に「イメージと違う」といった手戻りが発生するケースが少なくありませんでした。
しかしVRやMRを活用すれば、BIMモデルから生成した仮想空間を建築関係者は同時に実寸大で体験し、施主は完成後の建物を自由に歩き回り、コンセントの位置から天井高、窓からの景色までを直感的に確認できるため、よりスムーズな合意形成に繋がります。
これにより、設計段階で問題を徹底的に洗い出すことが可能となり、コスト増や工期遅延の原因となる手戻りのリスクを減らすことができます。
《施工管理》移動と指示のムダを削減。現場の生産性を劇的に向上させる遠隔臨場
次に、施工管理の現場では、深刻化する人手不足と生産性の課題にも活用可能です。
現場監督が複数の現場を掛け持ち、遠隔地の確認のために多くの移動時間を費やす、といった非効率は業界全体の課題です。
そこでARやMR技術を活用した「遠隔での作業支援」が注目されています。
これは、現場の作業員が装着したスマートグラスの映像を、事務所や別の現場にいる監督者がリアルタイムで確認し、ARやMRで適切な指示を出せる仕組みです。
これにより、これまで掛かっていた移動時間が不要になり、熟練の監督者は一日でより多くの現場を管理できるようになります。
さらに、先ほどのようなBIMモデルを現実の現場に重ねてシミュレーションすることで、配筋や設備配管の施工精度を高めることも可能です。
《人材育成》危険作業も安全に体験できるリアルな新人研修
さらに、人材育成の領域でもより高い効果を期待できます。
建設業界では、若手への技術継承が急務ですが、「見て覚える」という従来のOJT(On-the-Job Training)には限界がありました。
特に、高所作業や重機事故といった危険を伴う作業の訓練は、再現に必要なリソースの問題もありますが、何より高い危険性を伴うため、現実の現場では容易に実施できません。
しかし、VR研修はその課題を解決します。
仮想空間内で、足場の倒壊やクレーンの転倒といった重大災害につながるシナリオを、完全に安全な環境でリアルに体験させることができます。
”体験”として学習させることで、座学だけでは伝えきれない危険感受性を高め、若手作業員の安全意識を従来以上に向上させることが可能です。
建築XRの導入がもたらす3つのメリット
一般的な業務におけるXRの活用イメージをご紹介しましたが、改めてXR技術が建築業においてもたらすメリットを整理してみましょう。
① 品質向上と手戻り削減
まず1つ目のメリットは、建築プロジェクトにおける品質向上に繋がる点です。
XR技術によって3Dかつ自由な大きさでシミュレーションできるため、関係者間の「完成イメージのズレ」をなくします。
設計段階のVRウォークスルーで、施主や設計者、施工者が実寸大の空間を共有し、図面だけでは気づけなかった課題を施工前に発見できます。
これにより、従来プロジェクトのコストと工期を圧迫していた「手戻り」を大幅に削減し、より完成イメージに沿った品質を実現することが可能です。
② 現場作業員の生産性向上とコスト削減
2つ目のメリットは、時間と場所の制約を軽減し、生産性向上に繋がる点です。
遠隔での作業支援によって熟練技術者が移動することなく複数の現場を管理できれば、人件費や交通費といった直接的なコストを削減できます。
また、ARを用いたナビゲーションやマニュアルによって作業員の迷いやミスをなくし、施工精度とスピードを高められます。
国土交通省が推進する「i-Construction」においても、デジタル技術の活用による生産性向上は最重要テーマの一つです。
XR導入は、こうした国策の流れにも合致する、企業の成長に不可欠な投資と言えるでしょう。
③ 技術継承の促進と安全性向上
3つ目は、技術継承と安全教育の課題へ活用できる点です。
先ほどのARやMRを用いた作業支援は勿論、熟練技能者の技術をデジタルデータとして保存・共有し、若手がVR空間で繰り返し訓練できる環境は、技術継承へも有効な手法となるでしょう。
また、現実では試せない危険作業を安全に疑似体験させる安全教育VRは、受講者の学習体験を強化し、労働災害のリスク低減に繋がります。
導入で失敗しないための3つの注意点
建築業界におけるXR技術は様々な恩恵をもたらしますが、その一方で、その導入プロセスにはいくつかのハードルが存在します。
ここでは、導入担当者が直面しやすいハードルと、成功のためのポイントを解説します。
初期コストは? 費用対効果のリアル
まず、多くの担当者が直面するのが、初期コストの問題です。
高性能なPCやVR/MRデバイス、そしてソフトウェアのライセンス費用など、建築XR環境の構築には一定の初期投資が必要となります。
ここで重要なのは、単にコストだけを見るのではなく、費用対効果(ROI)の視点を持つことです。
例えば、XR導入によって削減できる手戻りの修正費用や、現場への移動経費、向上するであろう受注率などを具体的に試算し、投資額を何年で回収できるか計画することが、社内合意を得る上での鍵となります。
また、最近ではPoC(概念実証)という事前検証の取組もあり、初期投資を抑えながらスモールスタートで始めることも可能です。
BIMデータはどうする? データ連携の壁
次に、技術的な課題として「データ連携の壁」が挙げられます。
設計で使用しているBIM/CADデータが、そのままXRツールで快適に動作するとは限りません。
データ容量が大きすぎて表示に時間がかかったり、テクスチャやBIM情報が正しく反映されなかったりするケースがあります。
そのため、XRで活用するためには、多くの場合、データの軽量化や最適化といった一手間が必要になることを理解しておく必要があります。
導入を検討するツールが、自社でメインに使用しているBIMソフト(例:Autodesk Revit, Graphisoft Archicadなど)とスムーズに連携できるか、事前に十分な検証や要件定義を行うことが不可欠です。
「目的の明確化」と「現場を巻き込む」こと
こうした課題を乗り越え、建築XRの導入を成功に導くためには、2つの重要なポイントがあります。
一つ目は、「導入目的の明確化」です。
「施主へのプレゼン品質を向上させる」「遠隔での配筋検査を全現場で実現する」など、何のためにXRを導入するのか、最も解決したい課題を一つに絞ることが成功の鍵です。
二つ目は、「現場を巻き込む」ことです。
どんなに優れたツールでも、実際に使う現場の従業員がその価値を理解し、積極的に使わなければ形骸化してしまいます。 トップダウンで導入を決めるだけでなく、現場の意見をヒアリングし、彼らにとって本当に使いやすいツールを選定するプロセスが極めて重要です。
まずは特定の部署やプロジェクトで試験的に導入し、成功体験を社内に共有しながら段階的に展開していく「スモールスタート」が、最も確実な進め方と言えるでしょう。
自社に合うツールは?建築XRサービスの選び方と比較ポイント
建築XRの導入効果を最大化するためには、自社の目的と状況に合致したサービスを選ぶことが最も重要です。
多機能で高価なツールが、必ずしも自社にとって最適とは限りません。 例えば、施主へのプレゼンを主目的とするならビジュアルの美しさが、現場での利用を想定するなら操作の簡便性やモバイル対応が、それぞれ重要な判断基準となります。
ここでは、自社に最適な建築XRサービスを選ぶために確認すべき、6つのポイントを解説します。
ポイント1:導入目的との合致
まず、「設計レビュー」「施主プレゼン」「遠隔臨場」「安全教育」など、前章で明確化した導入目的を達成できる中核機能が備わっているかを確認します。
ポイント2:BIM/CADデータとの連携性
自社で利用しているBIMソフト(Revit, Archicad等)からのデータインポートがスムーズか、属性情報を保持できるかなどを確認します。
可能であれば、実際のデータを用いてトライアルで検証できるツールが良いでしょう。
ポイント3:操作性とUI(ユーザーインターフェース
ITの専門家でなくても直感的に操作できるかは、社内への浸透度を左右する重要な要素です。 特に現場での利用を想定する場合、ITに不慣れな作業員でも簡単に使えるシンプルなUIは必須条件と言えます。
ポイント4:対応デバイスと動作環境
高性能PCや特定のVR/MRデバイスが必須か、あるいはスマートフォンやタブレットでも利用できるかを確認します。
2025年現在では、クラウドベースでマルチデバイスに対応しているサービスが、利便性の観点から主流となりつつあります。
ポイント5:価格体系とコスト
初期費用が必要な買い切り型か、月額・年額のサブスクリプション型かを確認します。
利用ユーザー数に応じた課金体系かなど、自社の予算や利用規模に合った価格体系のサービスを選びましょう。
ポイント6:サポート体制とセキュリティ
導入時のトレーニングや、トラブル発生時に日本語で迅速なサポートを受けられるかは、円滑な運用のために不可欠です。
また、機密性の高い設計データを扱うため、クラウドサービスのセキュリティポリシーも必ず確認してください。
これらの比較ポイントを元に、いくつかのサービスで実際にデモやトライアルを試してみることが、最適なツール選定への近道です。
まとめ
本記事では、建築XRの基礎知識から具体的な活用事例、導入のメリットと注意点、そしてサービスの選び方までを網羅的に解説しました。
設計段階では手戻りをなくし品質を向上させ、施工現場では時間と場所の制約を超えて生産性を高め、人材育成では安全かつ効果的な技術継承を可能にします。
BIMの登場が建築のプロセスを大きく変えたように、XRの浸透は、関係者間のコミュニケーションのあり方そのものを、より直感的で豊かなものへと進化させていくでしょう。
重要なのは、完璧な準備を待つことではなく、まずはスモールスタートで第一歩を踏み出し、自社の課題解決にXRがどう貢献できるか試してみることです。
この記事が、貴社にとってその第一歩を踏み出すきっかけとなれば幸いです。 まずは、より詳細な情報収集から始めてみませんか?
弊社では、お客様の課題やご要望に合わせたXRコンテンツの受託開発・運用支援を行っております。
貴社のご状況に応じた最適なXRソリューションを、柔軟に開発致します。
XRコンテンツの導入にご興味がある方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。
VRコンテンツ制作!自社開発による柔軟性でお客様のビジネスをリードする『monoVR』
サービスの特徴や導入事例をまとめた資料をご用意しました。

monoVRサービス紹介資料の無料ダウンロードはこちら
資料をダウンロードする
 TWITTER
TWITTER
 FACEBOOK
FACEBOOK
 はてブ
はてブ