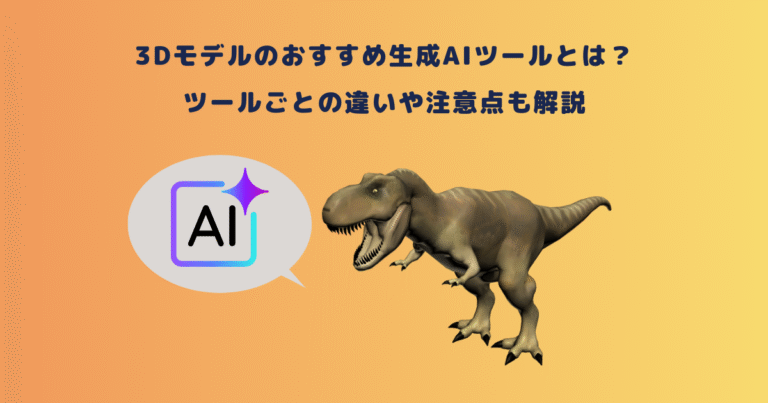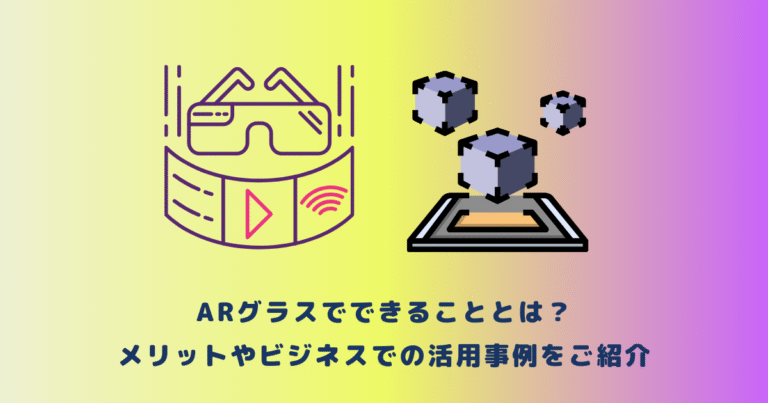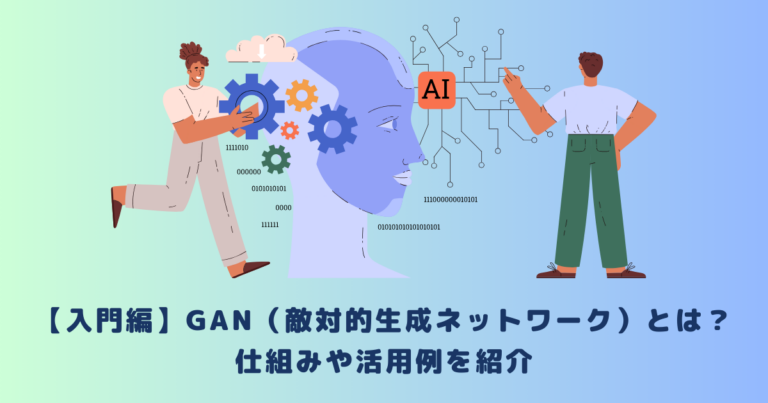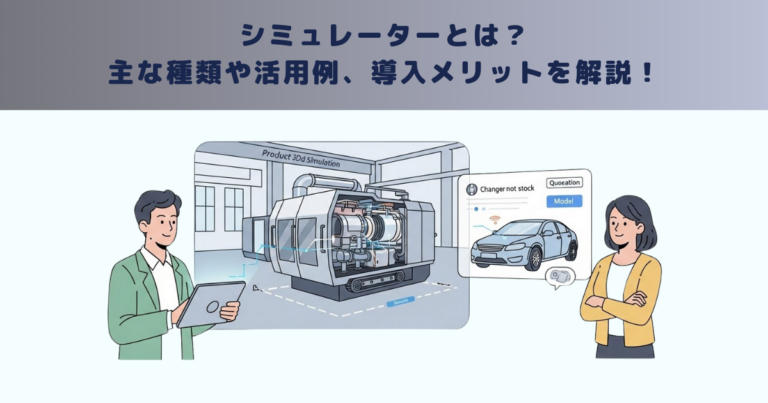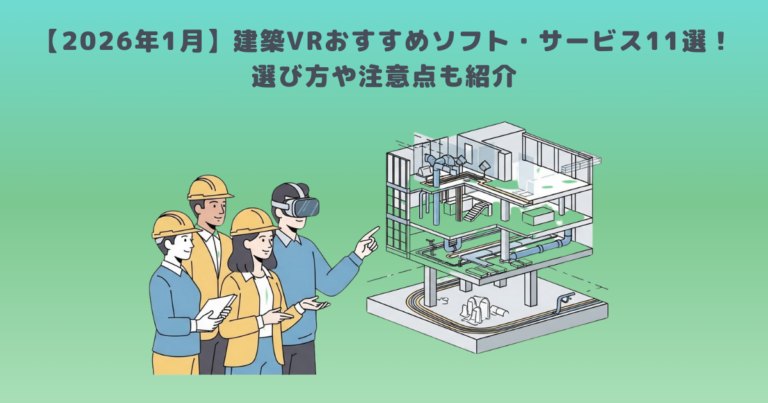手作業の製造現場におけるヒューマンエラーの多さに悩んでいる工場長や現場管理の方は多いのではないでしょうか。
ダブルチェックや注意喚起といった従来の手法だけでは、エラーの根本的な再発防止には至りません。
なぜなら、エラーを引き起こす本質的な原因は、作業者を取り巻く環境や手順そのものに潜んでいるからです。
本記事では、製造業で起こりがちなエラーの典型パターンを分析し、明日から実践できる物理的な対策から、XR(クロスリアリティ)技術などを活用した次世代の防止策までを体系的に解説します。
VRコンテンツ制作!自社開発による柔軟性でお客様のビジネスをリードする『monoVR』
サービスの特徴や導入事例をまとめた資料をご用意しました。

monoVRサービス紹介資料の無料ダウンロードはこちら
資料をダウンロードする目次
製造業で起こりがちなヒューマンエラーのパターンとは?
ヒューマンエラーとは、意図しない結果を引き起こす人間の行為や判断の誤りを指します。
製造現場のエラーは、主に以下の3パターンに大別されます。
パターン①:うっかりミス(スリップ)|「見ていなかった」「押し間違えた」
スリップとは、作業者が正しい手順や知識を持つにも関わらず意図せず実行段階で生じてしまう、いわゆる「うっかりミス」です。
慣れた作業中に一瞬注意がそれてボタンを押し間違える、といったケースなどが該当し、頭の中での手順は正しかったものの、その通りに実行が伴わなかった状態を指します。
主な原因としては、作業者の疲労の蓄積、作業環境の騒音、複雑な作業・操作手順などが引き金となります。
パターン②:思い込み・勘違い(ミステイク)|「いつも通りで大丈夫だと思った」
ミステイクとは、知識不足や不適切な判断により、そもそも作業の開始段階で誤りが生じている状態です。
行動自体は意図通りでも、前提となる計画やルール解釈が間違っているためエラーに繋がってしまうケースです。
「いつも通りで問題なかった」という思い込みから仕様変更に気づかず作業を進めるのが典型例で、古いマニュアルや想定外の事態に対する不十分な教育訓練などが原因で、発生しやすくなります。
パターン③:意図的な手抜き(ヴァイオレーション)|「面倒だから手順を省略した」
ヴァイオレーションとは、定められたルールや手順を意図的に逸脱する行為です。
必ずしも悪意とは限らず、「この方が効率的だ」「ルールが現状に即していない」といった作業者なりの判断や、納期へのプレッシャーから安全確認を省略するケースが多く見られます。
現場の実態と乖離した非現実的なルールや、生産ノルマに対するプレッシャー、それを黙認する組織風土などが根本原因となり得ます。
このように、エラーは発生メカニズムごとに原因が異なるため、各パターンに応じた的確な対策を講じていく必要があります。
ヒューマンエラーが再発する根本原因とは?
エラー対策として「注意喚起」「ダブルチェック」「再教育」を繰り返しても、なぜミスは再発するのでしょうか。
その根本原因は、対策が「人」に依存し、エラーを引き起こす「仕組み」に踏込めていない点にあります。
なぜ「注意喚起」や「再教育」だけでは不十分なのか?
人間の集中力は、体調や環境によって変動するため、常に完全な状態を維持できません。
「もっと注意しろ」という指示は精神論に過ぎず、持続的な効果が期待できないのです。
ダブルチェックも、ルール化した最初の頃は意識的に守られることも多いですが、時間が経つにつれて形骸化したり、「次の人が見てくれる」という責任感が薄れてしまうリスクもあります。
定期的な再教育が有効なのは知識不足による「ミステイク」のみで、疲労からくる「スリップ」には効果を発揮しきれない場合もあるのです。
エラーは“作業環境や手順”の仕組みが原因?
ヒューマンエラーの撲滅において重要なのは、失敗した作業者を責めるのではなく「なぜエラーが起きる状況(仕組み)になっているのか」を適切に分析することです。
例えば、似た形状の部品が隣り合って置かれていれば、誰でも取り違えるリスクは高まりますし、複雑なマニュアルは手順の誤解や省略を誘発してしまいます。
エラーの根本原因は、工具の配置、マニュアルの質、職場のコミュニケーションといった、作業者を取り巻く「仕組み」自体に存在するのです。
そのため、ヒューマンエラーを撲滅するには、個人への責任追及から脱却し、エラーを誘発しない「仕組み」を設計するという視点を持つことが重要になります。
ヒューマンエラー対策の3つの基本アプローチ
エラーを誘発する「仕組み」への対策として、視点を「個人」から「システム」へ転換させる3つの基本アプローチを解説します。
エラーの発生を物理的に防ぐ「ポカヨケ(フールプルーフ)」
ポカヨケとは、作業者が間違えようとしても物理的にエラーが発生しないように設計された仕組みや装置です。
人の注意力に頼らず、仕組みでミスを強制的に防ぎます。
特定の向きでしか差し込めないUSBコネクタのように、製造現場では「正しい部品しかセットできない治具」や「蓋を閉めないと作動しない機械」などが該当し、特に「スリップ」に効果を発揮します。
エラーが発生しても損害を最小化する「フェイルセーフ」
フェイルセーフは、エラーや故障の発生を前提とし、その際に必ず安全側にシステムが作動する設計思想です。
万が一の際の被害を最小限に食い止めることを目的とします。
地震を感知すると停止するストーブのように、現場では危険エリアへの侵入をセンサーが検知して機械を緊急停止させる安全装置がこれに該当します。
最悪の事態を回避する重要なリスクマネジメント手法です。
エラーの背後要因を深掘りする「なぜなぜ分析」
なぜなぜ分析は、「なぜ?」という問いを繰り返すことで根本原因を追求する手法です。
重要なのは、「なぜ」の矛先を作業者の不注意に向けず、「作業者が確認を怠ったから」で分析を止めないことです。
「なぜ確認を怠ったのか?(例:マニュアルが見づらい)」「なぜ見づらいのか?(例:照明が暗い)」というように、環境やシステムの問題へと深掘りする必要があります。
正しく実践すれば、現場を悩ませている根本的な原因を特定できるでしょう。
事例で学ぶ!仕組みで解決する製造現場の改善策
基本アプローチが現場でどう活用されているか、2つの改善事例で見ていきましょう。
工具の置き場所の工夫で部品の組み付けミスをゼロに
ある組立ラインでは、数種類の似たネジの選択ミスによる品質不良が慢性化していました。
そこでチームは、作業者の「注意力」に頼るのをやめ、1回の組立で使うネジだけを使用順に穴が空いた専用トレイで供給するように変更。
その結果、作業者は順番通りにネジを取るだけでよく、作業後にトレイにネジが残っていれば締め忘れも一目でわかるようになりました。
この「部品供給の仕組み化」により、2つのヒューマンエラーがゼロになりました。
写真付きマニュアルとチェックリストの刷新で確認漏れを撲滅
別の工場では、機械の段取り替えで手順の確認漏れが多発していました。
そこでチームは、文字ばかりのマニュアルを、誰でも直感的に理解できる画像中心の「ビジュアルマニュアル」に刷新し、OK/NG例の比較写真で判断の迷いをなくしました。
さらに紙のチェックリストを廃止してタブレット端末を導入し、手順完了の証拠写真を添付しないと次に進めない仕組みを構築しました。
この「作業管理の仕組み化」で、確認漏れによるトラブルは撲滅されました。
【最新トレンド】ヒューマンエラー対策を変えるXR技術とは?
XR技術とは、現実世界にデジタル情報を重ね合わせたり、デジタル世界の中に没入できたりする技術です。
VR(仮想現実)やAR(拡張現実)の総称であるXRは、製造業のヒューマンエラー対策を大きく改善できる可能性を秘めています。
どのような活用ケースがあるのか、ご紹介します。


熟練者の“暗黙知”を可視化・共有する「AR遠隔作業支援」
ARグラスやタブレットなどの専用デバイスを使うことで、遠隔地の熟練者へと現場作業員が自分の視界を共有し、映像に直接指示を書き込んだり話しかけたりと、まるで横に居るかのように支援できます。
これまでOJTでしか伝えきれなかった「暗黙知」や「勘どころ」をデジタルデータとして可視化・共有し、経験の浅い作業員でも熟練者のように正確な作業を遂行できます。
危険を安全に体感し、対応力を養う「VR安全体感研修」
VRは、機械への巻き込まれといった労働災害をリアルなCG空間で安全に疑似体験させます。
座学では得られない危険への感受性を高め、安全な環境で緊急時の対応力を養うことが可能です。
結果として、危険な状況下での判断ミスといったヒューマンエラーを大幅に低減することができます。
現実空間に手順書を投影する「ARマニュアル」
ARマニュアルは、作業者の視界に直接、作業手順や指示をデジタル情報として表示します。
作業者は視線を対象物から外すことなく、ハンズフリーで正確な情報を得られます。
マニュアル確認時の集中力の中断や記憶違いといったエラー発生源を構造的に排除し、組立やメンテナンスの精度を飛躍的に向上させます。
XR導入を成功させるための3つのステップ
XR技術の導入はもはや特別なことではありません。
しかし、投資対効果を最大化するためには、以下のポイントに注意しましょう。
①:解決したい課題(ヒューマンエラー)の明確化
まず行うべきは、技術選定ではなく、解決したい課題の定義です。
「組立ラインBの部品取り付けミスを月5件からゼロにする」のように、対象業務、課題、数値目標(KPI)を明確にします。
どのエラーパターンをどの程度削減したいか具体化することが、後のROI測定とソリューション選定の鍵です。
②:スモールスタートで費用対効果を検証する
全社展開ではなく、特定の業務にスコープを絞り、小規模な実証実験(PoC)から始めることが成功の鍵です。
初期投資を抑えつつ、エラー削減率などの具体的な効果を定量的に測定できます。
PoCで得た成功事例とROIデータは、本格展開に向けた有効な説得材料となります。
③:専門家の知見を活用し、失敗リスクを回避する
XRは専門性の高い分野であり、自社だけでの導入は時間とコストを要します。
そのため、産業用途での導入実績が豊富な外部パートナーの知見を活用するのが賢明です。
専門家との連携は、導入期間を短縮し成功確率を高める重要な投資です。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
本記事では、製造業におけるヒューマンエラー対策について、その本質的な課題から具体的な解決策までを解説しました。
起こったエラーを個人の資質の問題とせず、その背景にある「仕組み」に目を向けることが重要です。
エラーに強い現場とは、完璧な人間を求めるのではなく、人間がミスを犯すことを前提とした「カバーができる仕組み」を持つ現場です。
ヒューマンエラーに悩む現場管理の方々は、ぜひ今回の内容を参考にしてみてください。
弊社では、ARやVRを始めとするXRコンテンツの開発を行っております。
ARやVRを活用した業務マニュアルや学習コンテンツなどの開発実績もございますので、ご興味がある方はぜひお気軽にお問い合わせください。
VRコンテンツ制作!自社開発による柔軟性でお客様のビジネスをリードする『monoVR』
サービスの特徴や導入事例をまとめた資料をご用意しました。

monoVRサービス紹介資料の無料ダウンロードはこちら
資料をダウンロードする
 TWITTER
TWITTER
 FACEBOOK
FACEBOOK
 はてブ
はてブ