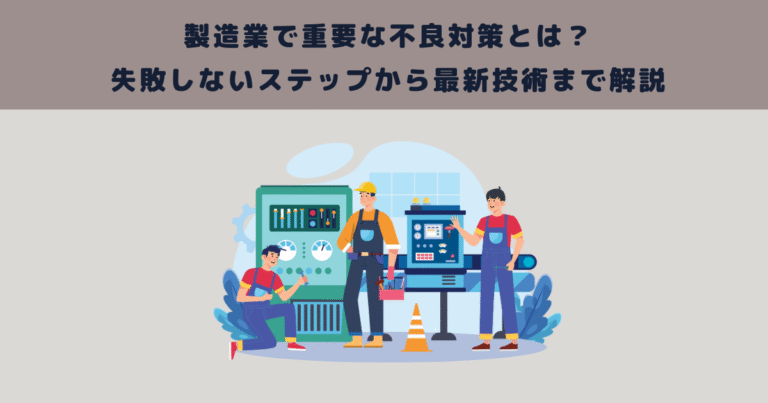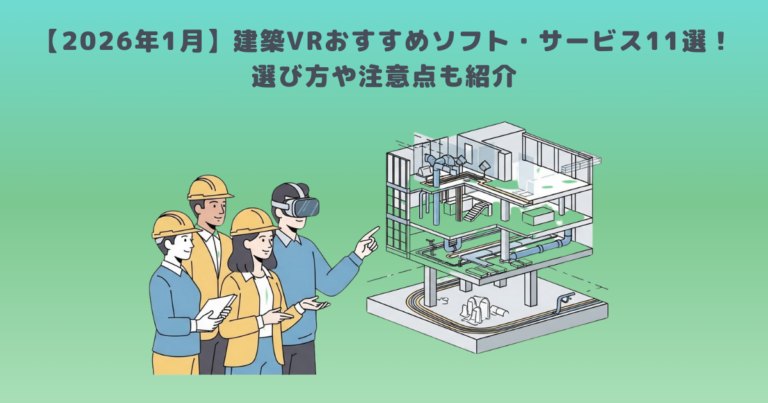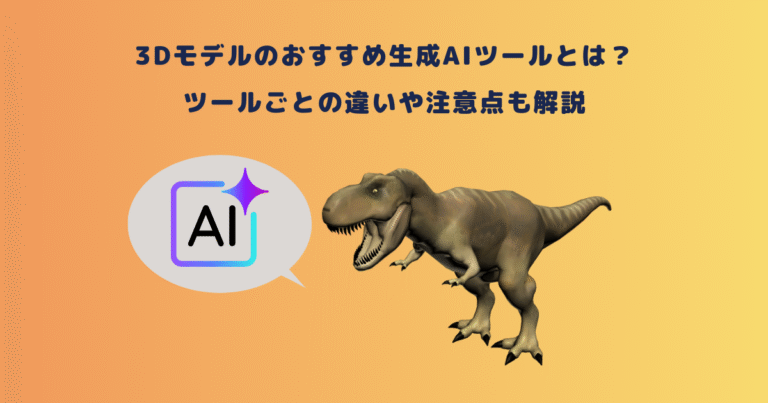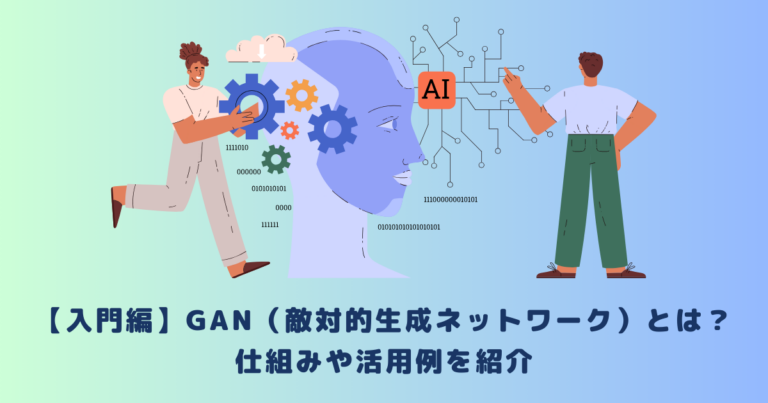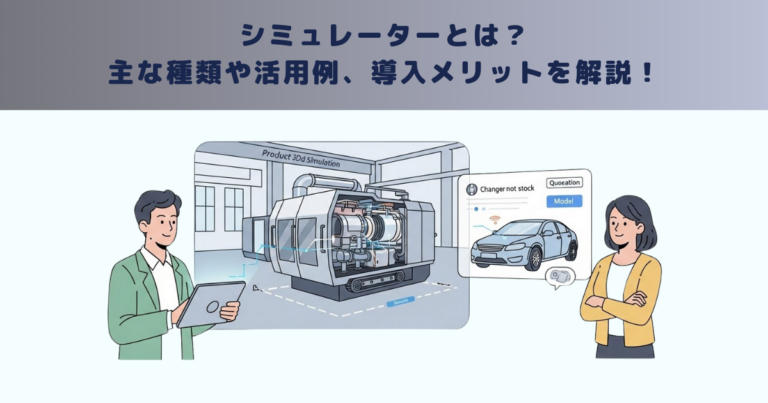QCサークル活動の形骸化や、繰り返される同じ原因の不良、「なぜなぜ分析」を繰り返しても、「作業者の不注意」で片付けてしまい、製造業の不良について根本的な解決に至らないケースは少なくありません。
その原因は、従来の対策手法が「人に起因する問題」や「不良発生後の対応」に留まっているケースが多くなってしまっているためです。
本記事では、製造業における不良対策ステップに加え、最新技術での対策方法として、AI・IoTによる「設備」へのアプローチと、XR技術による「人」へのアプローチについてご紹介します。
不良対策が上手くいかずお悩みの工場長や現場管理の方は、ぜひご覧ください。
ARコンテンツ制作!自社開発による柔軟性でお客様のビジネスをリードする『monoAR』
サービスの特徴や導入事例をまとめた資料をご用意しました。

monoARサービス紹介資料の無料ダウンロードはこちら
資料をダウンロードする目次
なぜ製造業の不良対策は「堂々巡り」に陥りやすいのか?
製造業の不良対策が「堂々巡り」に陥る本質的な原因は、発生した問題の「真因」にたどり着く前に、表層的な原因で対策を打ってしまうことにあります。
日々の生産活動に追われる中、原因究明に十分な時間を割けなかったり、データに基づかない過去の経験や勘に頼った判断を下してしまったりするためです。
例えば、「作業者の確認ミス」という直接的な原因に対し、「注意喚起の張り紙を増やす」「ダブルチェックを徹底する」といった対策を立てることは多いでしょう。
勿論、作業者側の意識もより改善すべきですが、これらはあくまで対症療法に過ぎません。
なぜその作業者は確認をミスしたのかを考え、「作業手順書がそもそも分かりにくい」「類似した部品が多く、見分けがつきにくい」「作業場の照明が暗く視認性が悪い」といった、作業環境や仕組みそのものに潜む根本的な原因を特定し対策を打たなければなりません。
この真因究明を怠ると、担当者が変わったり、時間が経ったりした際に、また同じ問題が形を変えて再発してしまうのです。
結果として、いつまでも終わらない「もぐら叩き」のような対策に、貴重なリソースを奪われ続けることになります。
貴社の不良対策、「マンネリ化」していませんか?
- 「なぜなぜ分析」が「作業者の不注意」や精神論で終わることが多い
- 対策書は作るものの、現場に定着せず形骸化している
- 若手への技術伝承がOJT頼みで、作業者によって品質が安定しない
- 特定のベテラン従業員のスキルに依存しており、その人がいないと対応できない
1つでも当てはまった方は、この記事で紹介する新しいアプローチがきっと役立ちます。
【脱・場当たり対策】製造業の不良対策に不可欠な3つのステップ
では、不良対策が「堂々巡り」に陥ってしまわないように、どういった点に注意すべきでしょうか。
失敗しないための3つのステップをご紹介します。
STEP1:データの「見える化」で問題の急所を特定する
最初に取り組むべきは、漠然とした問題意識を、客観的なデータによって具体的なターゲットに絞り込むことです。
収集した不良データを、「パレート図」や「ヒストグラム」といった、QC七つ道具の手法を用いて分析し、可視化します。
例えば、パレート図を作成すれば、「不良全体の8割は、特定の2割の原因によって引き起こされている」といった問題の急所が明確になります。
「どの製品に」「どの工程で」「どの時間帯に」不良が多発しているのかをデータで示すことで、対策を打つべき真のボトルネックが浮かび上がってくるのです。
この「見える化」のプロセスを経ずに、やみくもに対策を始めても、リソースが分散し、大きな成果には繋がりません。
STEP2:「なぜなぜ分析」の限界を超える真因究明のアプローチ
問題の急所を特定したら、次はその根本原因である「真因」を深く掘り下げます。
多くの現場で用いられる「なぜなぜ分析」は有効な手法ですが、分析者のスキルに依存しやすく、最終的に「作業者の不注意」といった個人の資質に行き着いてしまう限界も指摘されています。
そこで重要になるのが、システム全体を俯瞰する視点です。
例えば、「FTA(故障の木解析)」のように、発生した不良(事象)から、その原因となりうるハードウェア、ソフトウェア、人的要因の組み合わせを論理的に洗い出していくアプローチが有効です。
「なぜ」だけでなく、「他にどんな要因が重なったら発生しうるか?」という視点を持つことで、これまで見過ごされてきたシステムや設計上の問題点を発見できます。
STEP3:対策を「仕組み化」し再発を確実に防ぐ
真因を特定できたら、最後はその対策を個人のスキルや意識に依存しない「仕組み」として現場に定着させます。
対策が「注意喚起」や「周知徹底」といった精神論で終わってしまっては、時間が経てば必ず風化し、再発の原因となります。
真因が「作業手順の複雑さ」であれば、写真や図を多用した「作業標準書(SOP)」に改訂する。
「類似部品の取り違え」であれば、物理的に間違った部品をセットできないようにする「ポカヨケ」を導入する。
このように、誰が作業しても、どのようなコンディションであっても、品質を一定に保てるようなプロセスを構築することが「仕組み化」の本質です。
これら3つのステップを着実に実行することが、持続的な不良対策及び品質改善の土台となっていきます。
AI・IoTは不良対策をどう変えるか?【モノ・設備へのアプローチ】
前章で解説した王道の3ステップをさらに進化させるのが、AIやIoTといった先進技術の活用です。
これらの技術は、従来の「問題が発生してから対処する」という事後保全的な不良対策を、「問題が発生する前に予知し、未然に防ぐ」という事前保全的な不良対策へと変えてくれます。
大まかな仕組みとしては、IoTセンサーが生産設備や製造環境から収集する膨大なリアルタイムデータを収集し、AIがそれらを解析し学習していくことで、より効率的な改善を図っていくことが可能です。
これにより、人間の五感や経験だけでは到底捉えきれない、不良発生に繋がる微細な変化や異常の予兆を検知することが可能になるのです。
具体的な活用例を2つ紹介します。
一つ目は、設備の異常を事前に察知する「予知保全」です。
工作機械のモーターなどに振動や温度を計測するIoTセンサーを設置し、平常時の稼働データをAIに学習させます。
AIはリアルタイムでデータを監視し、過去の故障データと類似した僅かな異常を検知した際に、管理者にアラートを発します。
これにより、設備が突然故障し、大量の不良品を生み出すといった最悪の事態を回避し、計画的なメンテナンスが実現できます。
二つ目は、「AI画像認識による外観検査の自動化」です。
高解像度カメラで撮影した製品画像をAIが解析し、熟練の検査員でも見逃すようなマイクロメートル単位の微細な傷や汚れを瞬時に検出します。
これにより、検査精度の向上と安定化はもちろん、これまで検査工程にかけていた人的コストの大幅な削減にも繋がります。
このように、AIとIoTをモノや設備に適用することで、製造業の不良対策はより科学的で高精度な次元へと進化するのです。
XR技術で「人」に起因する不良を撲滅【人へのアプローチ】
AIやIoTがモノや設備からのアプローチであるならば、XR(クロスリアリティ)は不良原因の大部分を占める「人」の問題を直接解決する、もう一つの強力なソリューションです。
XR技術とは、AR(拡張現実)やVR(仮想現実)など、現実世界とデジタルを融合させる技術の総称であり、エンタメ領域を超えて様々なビジネス利用が進んでいます。
製造現場においても、これまでヒューマンエラーやスキル不足として片付けられがちだった、人的な課題に対し、XR技術は有効策としての可能性を秘めています。


AR作業支援:人の”うっかりミス”や手順飛ばしを未然に防ぐ
AR(Augmented Reality:拡張現実)は、現実の視界にデジタルの情報を重ね合わせる技術です。
作業者がスマートグラスを装着すると、目の前の部品や設備に、作業手順や注意点、使用すべき工具などが3DCGやテキストでリアルタイムに表示されます。
例えば、複雑な組み立て作業において、次に使うべき部品がハイライトされたり、正しい締め付けトルク値が表示されたりします。
これにより、作業者は分厚いマニュアルを確認するために作業を中断する必要がなくなり、両手を使ったまま、迷うことなく正確な作業を遂行できます。
これは、いわば「デジタル化されたポカヨケ(ミス防止策)」です。
「注意する」「確認する」といった個人の意識に頼るのではなく、システムが物理的にミスを防ぐため、ヒューマンエラーに起因する不良の発生を削減することが可能です。
VR教育訓練:ベテランの”暗黙知”を誰もが安全に学べる
VR(Virtual Reality:仮想現実)は、現実世界と同様の環境をCGで創り出し、その中で様々な体験を可能にする技術です。
製造業では、工場など実際の作業環境をVR空間として再現することで、リアルに近しい効果的なトレーニングが可能です。
例えば、高価な装置の操作訓練や、危険を伴うメンテナンス作業、あるいは発生頻度の低い特殊な不良品の見極め訓練などを、安全な環境且つ時間や場所の制約なく、何度でも繰り返し行えます。
現実の製品や設備を仮想空間に再現する「デジタルツイン」を活用すれば、現実では試せないようなトラブルシューティングも可能です。
これにより、OJTでは伝えきれなかった熟練者の判断基準や感覚といった「暗黙知」を、誰もが体験を通じて効率的に習得できます。
結果として、作業者全体のスキルレベルが底上げされ、品質のばらつきが解消し、組織全体の不良対策の品質向上に繋げることができます。
【事例】AR作業支援の導入による不良対策
ではXR技術が、実際の製造現場でどのように活用され、成果を上げているのでしょうか。
ある自動車部品メーカーA社の、AR作業支援システム導入事例を紹介します。
このA社では、多品種少量生産へのシフトに伴い、製品の組立工程が日に日に複雑化していました。
特に、経験の浅い作業者が担当するラインでは、類似部品の取り違えやボルトの締め忘れといったヒューマンエラーが頻発し、不良率の高さが長年の課題となっていたのです。
紙のマニュアルの定期的な更新や、熟練者によるOJTの強化といった従来の対策だけでは、品質の安定化に限界を感じていました。
そこでA社が解決策として導入したのが、スマートグラスを活用したAR作業支援システムです。
作業者がスマートグラスを装着すると、視界には次のような情報がリアルタイムで表示されます。
- 作業ナビゲーション: 数百種類ある部品の中から、次にピッキングすべき部品の棚が光って指示される。
- 3Dモデル表示: 取り付けるべき部品の3Dモデルが、実物の組付け位置に重ねて表示され、向きの間違いなどを防ぐ。
- 作業チェック: ボルトを締めると、規定のトルク値が達成されたかをシステムが自動で判定し、OKのサインが表示される。
導入の結果、作業者達は安定して正確な作業を行えるようになり、対象工程におけるヒューマンエラー起因の不良は減少し、さらに、新人作業員の教育時間も短縮されるなど、生産性の向上にも大きく貢献しました。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
本記事では、製造業における不良対策について、従来の王道的なアプローチから、DX技術を活用した最先端のアプローチまでを解説しました。
不良対策が「堂々巡り」になってしまう課題に対し、まずは「データの見える化」「真因究明」「仕組み化」という3つのステップで改善の土台を築くことが重要です。
そして、その土台の上で、AI・IoTなどの「モノ・設備」を起点とした不良対策や、XR技術のような「人」を起点とした不良対策によって、これまで限界とされてきた課題を乗り越えることが可能になります。
もはや、不良対策は精神論や個人の頑張りだけで乗り切る時代ではありません。
モノと人、双方のパフォーマンスをテクノロジーによって最大化させることが、これからの製造業における品質管理の新常識となるでしょう。
弊社では、ARやVRを始めとするXRコンテンツの開発を行っております。
現場の省人化や技術継承に繋がる業務マニュアルや学習コンテンツなどの開発実績もございますので、ご興味がある方はぜひお気軽にお問い合わせください。
ARコンテンツ制作!自社開発による柔軟性でお客様のビジネスをリードする『monoAR』
サービスの特徴や導入事例をまとめた資料をご用意しました。

monoARサービス紹介資料の無料ダウンロードはこちら
資料をダウンロードする
 TWITTER
TWITTER
 FACEBOOK
FACEBOOK
 はてブ
はてブ