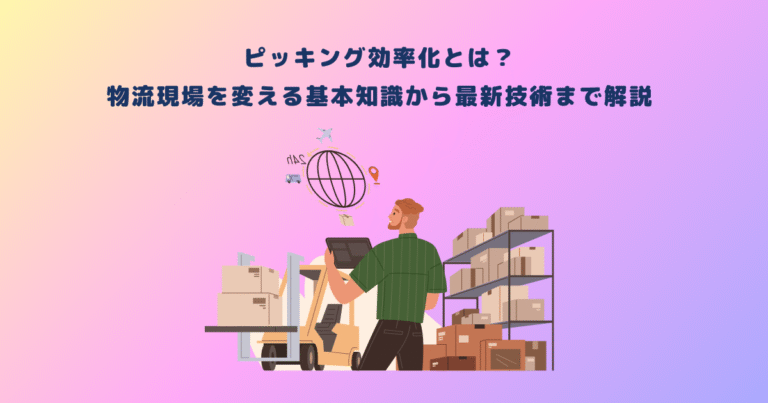ピッキング作業の効率化は、多くの物流現場が抱える喫緊の課題です。
「探す・歩く・迷う」という無駄が、生産性のバラつきや残業の常態化に繋がってしまっている倉庫現場も多いのではないでしょうか。。
本記事では、コストゼロで始められる改善策からExcel活用術、さらにXR(Cross Reality)のような最新技術まで、ピッキング効率化の全手順を具体的に解説します。
目次
なぜあなたの現場のピッキングは遅い? よくある3つの原因
ピッキング効率化を妨げる原因は、「探す」「歩く」「迷う・間違える」という3つの要素に集約されます。
これらは「ロケーション管理」「作業動線」「作業の標準化」という現場の仕組みに起因しています。
自社の課題を把握するため、まずはこれらの原因を見ていきましょう。
原因①「探す」時間の多発:ロケーション管理の問題
ピッキング作業における最大の無駄は、商品を「探す」時間です。
主な原因は、ロケーション管理、つまり商品の置き場所のルールが曖昧なことにあります。
どこに何があるかが個人の記憶に依存する「属人化」した状態では、担当者以外は商品を見つけるのに時間がかかります。
例えば、新人がベテランに場所を尋ねたり、似た箱の中から探し回ったりする光景がこれにあたるように、ロケーション管理の不備が、「探す」という非効率を生んでしまっているのです。
原因②「歩く」距離の増大:非効率な作業動線
次に効率を低下させるのが、必要以上に長い距離を「歩く」時間です。
これは、倉庫のレイアウトや商品配置が出荷頻度などを考慮していない、非効率な作業動線によって引き起こされます。
例えば、頻繁にセットで注文される商品同士が倉庫の両端に保管されているケースです。
これでは注文ごとに何度も往復する必要があり、膨大な歩行距離が発生します。
1回の差はわずかでも、1日で考えれば数キロの差になることも珍しくありません。
この積み重ねが、非効率的な作業を招き、生産性の低下に直結してしまうのです。
原因③「迷う・間違える」の発生:作業の標準化不足
作業中の判断に「迷う」時間や、商品を「間違える」ミスも、ピッキング速度を著しく低下させます。
これらの問題は、作業手順が標準化されず、個人のやり方に任されていることに起因します。
作業者ごとにリストの確認方法や商品の扱い方が異なれば、品質は安定せず、誤出荷のリスクが高まります。
特に数量や類似商品の間違いは、再発送コストだけでなく、顧客の信頼を損なう深刻な問題に発展しかねません。
このように作業の標準化不足も、全体の効率を大きく悪化させているのです。
【ステップ1】コストゼロで始める!ピッキング効率化の基本「5S」と「動線改善」
ピッキング効率化の第一歩は、大規模な投資ではなく、現場の環境とルールを見直すことから始められます。
その基本が、製造業や物流業で広く実践される「5S」と、移動を最適化する「動線改善」です。
これらはコストをかけずに即効性が期待できる重要な改善活動です。
まずは「整理・整頓」から。不要なモノを捨て、置き場所を決める
5S(整理・整頓・清掃・清潔・躾)とは、職場環境を改善する活動です。
ピッキング効率化では特に「整理」と「整頓」が重要になります。
「整理」は、必要なものと不要なものを分け、不要品を処分することです。
「1年以上出荷実績のない在庫」などを基準に不要品を処分し、保管スペースを確保します。
「整頓」は、必要なものを誰でもすぐ取り出せるよう、置き場所を決めて表示することです。
棚や床にロケーション番地を振り、「どこに・何が・いくつあるか」を「見える化」します。
この定位置管理の徹底が、感覚や記憶に頼った「探す」時間を削減します。
ABC分析で変わる!商品の置き場所(ロケーション)最適化
商品の置き場所を最適化するには、「ABC分析」という管理手法が有効です。
全商品を「出荷頻度」でA・B・Cの3ランクに分け、ランクごとに保管場所を変えることで「歩く」距離を最小化する考え方です。
- Aランク:出荷頻度が最も高い売れ筋商品群(例:売上上位20%)。
ピッキング開始地点に最も近い、腰の高さなど最も取り出しやすい場所に配置します。 - Bランク:出荷頻度が中程度の商品群。 Aランク商品の周辺に配置します。
- Cランク:出荷頻度が低い商品群。
倉庫の奥や棚の上下段など、アクセスしにくい場所に配置します。
この分析は、販売データがあればExcelでも簡単に行えます。
データに基づく配置の見直しも、ピッキングの効率化にとって重要な手法になります。
作業動線を「I字」か「U字」に。一方通行で迷わせない
作業者の「歩く」時間をさらに短縮するため、倉庫内の作業動線そのものを見直します。
効率的な動線の基本は、ルートを単純化し、一方通行にすることです。
これにより、作業者同士の衝突や無駄な往復を防ぎ、スムーズな流れを作れます。
代表的なレイアウトは以下の2つです。
- I字動線:入口から出口へ一直線に進むレイアウト。シンプルな倉庫に向いています。
- U字動線:入口からスタートし、折り返して同じ場所に戻るレイアウト。入荷と出荷場所が同じ場合に効率的です。
どちらの動線でも床に矢印テープを貼るなどルートを「見える化」し、全員が同じルールで動くことが重要になります。
【ステップ2】ミスを減らす在庫管理・ピッキングリスト作成術
多くの現場で使うExcelも、工夫次第でピッキング効率化の強力なツールになります。
システム導入の前段階として、Excelの標準機能を活用するだけでも、ヒューマンエラーを削減し、管理業務を高度化できます。
ここでは、すぐに使える3つの実践的なテクニックを紹介します。
関数(VLOOKUP)を活用して商品マスタから自動入力
ピッキングリスト作成時の手入力ミスは、「VLOOKUP関数」で解決できます。
VLOOKUP関数は、商品コードなどをキーに、関連データ(商品名や棚番)を自動で呼び出す機能です。
あらかじめ商品コードやロケーションを一覧にした「商品マスタ」シートを用意します。
ピッキングリストで商品コードを入力すると、VLOOKUP関数が商品マスタを参照し、関連情報を自動で入力するように設定します。
これにより、リスト作成者はコード入力に集中でき、転記ミスを防ぎ、作成の正確性とスピードが向上できるでしょう。
バーコードフォントで手作りハンディターミナル環境を
高価な専用端末がなくても、Excelと市販のバーコードスキャナで簡易的なデジタル検品を構築できます。
これを可能にするのが、無料の「バーコードフォント」です。
このフォントをPCにインストールすれば、Excel上の商品コードをスキャナで読み取れるバーコード画像に変換できます。
ピッキングリストにこのバーコードを表示させ、作業者は棚から取った商品のバーコードをスキャンします。
スキャンした情報をExcel上でリスト情報と照合させることで、類似商品の取り違えといったミスを削減できます。
条件付き書式で危険在庫(欠品・過剰)を可視化する
在庫管理では、「条件付き書式」機能で注意すべき在庫を直感的に把握できます。
これは、ルールに応じてセルの色を自動で変える機能です。
例えば、在庫数が一定数を下回った場合にセルが赤くなるように設定します。
これにより「欠品間近」の商品が一目で分かり、発注漏れによる機会損失を防げます。
逆に、滞留在庫や過剰在庫を別の色でハイライトすることも可能です。
在庫状況の「見える化」が、データに基づいた的確な在庫コントロールを実現します。
【ステップ3】Excel管理の限界の先にある、効率化の2つの選択肢
Excelによる改善は効果的ですが、事業の成長と共に必ず限界が訪れます。
「ファイルがロックされて更新できない」「担当者不在時に最新在庫が不明」といった問題は構造的な課題です。
これらの根本的な課題を解決し、ピッキング効率化をさらに高いレベルへ引き上げるには、システム化が不可欠です。
その際には、大きく分けて2つの選択肢があります。
選択肢① 現在主流の解決策:WMSとハンディターミナル
一つ目は、多くの現場で導入実績がある「WMS(倉庫管理システム)」とハンディターミナルを組み合わせる方法です。
WMSは、入荷から出荷まで倉庫業務を一元管理する専門システムです。
作業者はハンディターミナルでピッキング指示を受け、商品のバーコードをスキャンすると、作業実績がリアルタイムにWMSへ登録されます。
これにより在庫情報の正確性が飛躍的に向上し、誰が作業しても標準化された品質を維持できます。
これは現在の最も確立されたDXの手法と言えるでしょう。
ただし「作業中は片手が塞がる」「画面と棚を交互に見る必要がある」といった物理的な制約は残ります。
選択肢② 次世代の解決策:XR(AR)技術による”見るだけ”ピッキング
二つ目が、WMSの物理的な制約さえも解消しうる、XR(AR)といった次世代技術です。
これは、現実世界に情報を重ねて表示し、作業者の視覚を直接サポートする技術です。
例えばARグラスを装着すると、視界にピッキングすべき棚が光って見えたり、取得数量が矢印と共に表示されたりします。
作業者はリストや端末を見る必要がなく、両手が自由な「ハンズフリー」の状態で、視覚的な指示に従うだけで作業が完了します。
これは「ビジョンピッキング」とも呼ばれ、「見るだけ」でピッキングが完了する未来の選択肢なのです。
ピッキング効率化を実現するXR技術とは?
XR、特にARを活用したビジョンピッキングは、「探す・間違える・教育する」という従来の課題を解決できる可能性を秘めています。
それは、作業指示を「記憶」から「視覚」へ変えることで、人間の負担を極限まで減らせるためです。
ここでは、XR技術の3つの導入メリットをご紹介します。

ARグラスが実現する「探さない・間違えない」作業風景
ARグラスを装着すると、現実の倉庫風景にデジタル情報が重ねて表示され、「探す」行為が不要になり、「間違える」リスクも原理的に低減されます。
例えば、視界に最短ルートを示す矢印が表示され、目的の棚ではピッキングすべき商品が光ってハイライトされます。
「3個」といった数量もその横に浮かび上がり、作業者は表示通りに取るだけで、システムが作業完了を自動認識します。
これにより誤出荷率は限りなくゼロに近づき、作業精度が向上します。
教育時間”ほぼゼロ”へ。新人でも即戦力になれる理由
続いてのXR導入の大きなメリットが、新人教育コストの削減です。
作業者は、商品知識や倉庫レイアウトを覚える必要がなく、ARグラスの視覚指示に従うだけで業務を遂行できます。
その為、従来なら数週間かかっていた業務も、トレーニング初日から一人で正確にこなすことが可能になります。
物流大手DHL社の事例では、AR導入で生産性が平均15%向上し、トレーニング時間の大幅な短縮が報告されています。
これは、人の入れ替わりが激しい現場でも生産性を安定させ、人手不足や属人化への強力な解決策となり得ます。
実はスモールスタート可能?導入のリアルと費用感
実は現在のXR技術は、スモールスタートが可能です。
近年、ハードウェアの性能向上と低価格化に加え、ソフトウェアも月額課金制(SaaS)が増えているためです。
倉庫全体ではなく、まずは特定エリアや特定の工程に限定して試験導入できます。
数台のARグラスとライセンスでPoC(概念実証)を始め、費用対効果を検証しながら段階的に範囲を拡大するアプローチが一般的です。
XRはもはや未来の技術ではなく、現実的なプランで検討できるソリューションになりつつあります。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
本記事では、ピッキング効率化の具体的なステップを段階的に解説しました。
ピッキング非効率の原因である「探す・歩く・間違える」という無駄の解消が全ての基本です。
まずはコストのかからない「5S」や「動線改善」、身近な「Excel」活用で現場の土台を固めることが重要です。
その上で、自社の規模や課題に合わせ、主流の「WMS」や未来の「XR」といった次の選択肢を検討していくのが良いでしょう。
弊社では、ARやVRを始めとするXRコンテンツの開発を行っております。
物流のシーンにおけるARコンテンツの企画・作成・運用もトータルでサポート可能ですので、XRの導入にご興味のある方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

 TWITTER
TWITTER
 FACEBOOK
FACEBOOK
 はてブ
はてブ