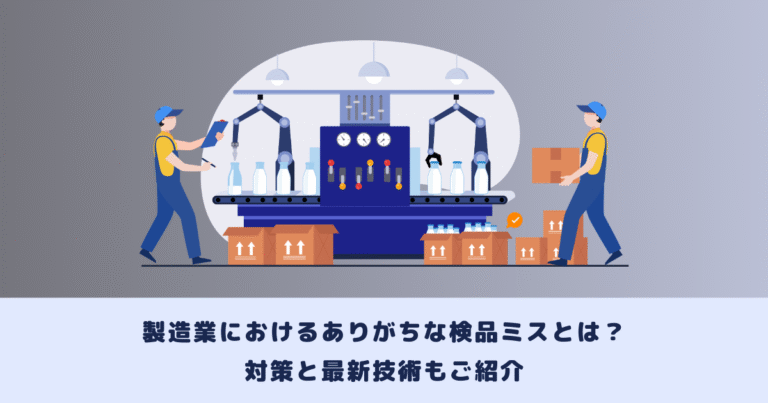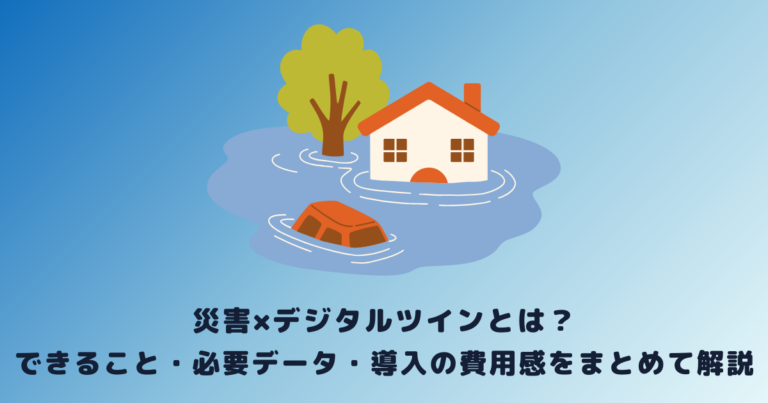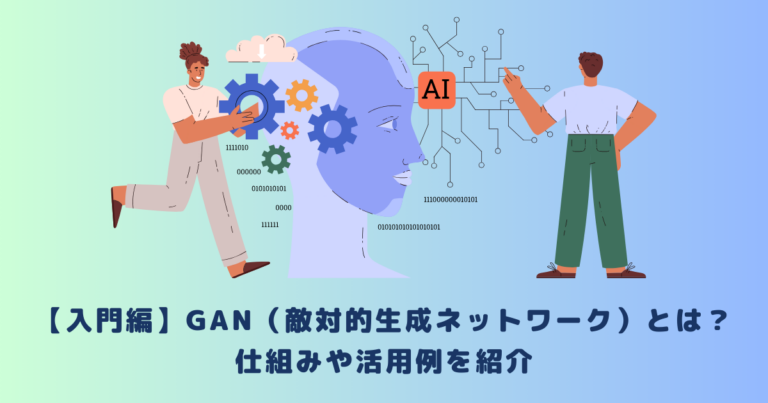日々の製造工程の中で、度々起こる検品ミスの対策に頭を悩ませていませんか。
多くの現場では、発生したミスへの場当たり的な対応に追われ、ミスが起きる「仕組み」そのものが見過ごされがちです。
本記事では、まず現場で頻発する「よくある検品ミスのパターン」から、ミスの真因を特定するシンプルな分析手法、そして明日から実践できる対策まで、網羅的に解説します。
さらに、AR(拡張現実)技術などを活用した、人に依存しない未来の検品体制についても触れていきます。
製造業における検品ミスの改善に興味がある方は、ぜひご覧ください。
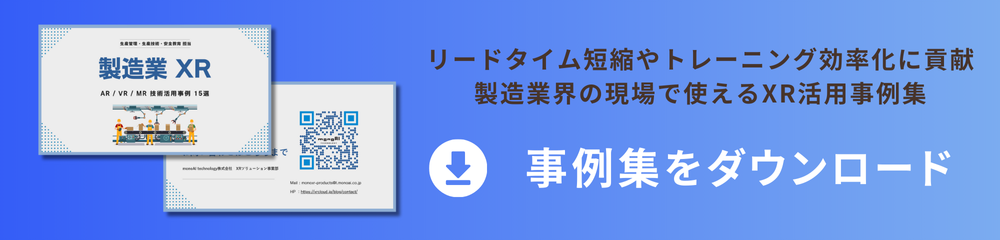
ARコンテンツ制作!自社開発による柔軟性でお客様のビジネスをリードする『monoAR』
サービスの特徴や導入事例をまとめた資料をご用意しました。

monoARサービス紹介資料の無料ダウンロードはこちら
資料をダウンロードする目次
検品とは
検品とは、製品や部品が、定められた仕様書や品質基準(外観、寸法、機能、数量など)を満たしているかを確認・検査する作業です。
製造業や物流業における品質管理の重要なプロセスであり、不良品が後工程や市場へ流出するのを防ぐことを目的とします。
この工程により、製品の品質を保証し、最終的に企業の信頼性や顧客満足度を維持・向上させることに繋がります。
一般的な検品の流れ
一般的な検品作業は、以下の5つのステップで進められます。
- 検品準備
仕様書、図面、作業指示書、限度見本(良否判定の境界を示す見本)など、検品基準を明確にする資料を準備します。
- 受入と照合
検品対象の製品や部品を受け入れ、品番や数量が発注内容と一致しているかを確認します。
- 検品実施
準備した基準に基づき、目視(キズ、汚れ、異物)、測定、動作確認などを行います。
- 判定と仕分け
検査結果を基準と照合し、「良品」「不良品」「保留(B級品など)」に正確に仕分けします。
- 記録とフィードバック
検品結果(不良の内容、数量、発生箇所など)を記録し、製造部門や購買部門などの関連部署に共有、報告します。
製造業でありがちな検品ミスとは
製造業にありがちな検品ミスとして、主に以下の5つのパターンに分類できます。
パターン1:数量ミス
数量の数え間違いや規定数の製品の入れ忘れといったミスは、最も基本的かつ頻発するパターンです。
「10個入りの箱に9個しか入っていなかった」「ピッキングリストの指示数より多く商品を取ってしまった」などが典型例です。
作業への慣れや「いつも通りだろう」という思い込み、あるいは出荷期限で急ぐあまりの焦りが主な原因として挙げられます。
パターン2:品質ミス
製品そのものに問題があることを見逃してしまうミスも、重大なクレームに繋がりかねません。
製品表面のわずかなキズや汚れ、小さな破損、異物の付着など、検品基準で定められた不良を見落とすケースがこれにあたります。
作業場の照明が暗い、長時間作業による集中力の低下など、作業者本人だけでなく作業環境に起因することもあります。
パターン3:仕様・品番ミス
類似品が多い製品を取り扱う現場で、特に発生しやすいのが仕様や品番の取り違えです。
同じ形状で色が違う製品や、わずかなサイズ違いの部品、末尾の型番だけが異なる商品などを「これだろう」と思い込みでピッキングしてしまうケースです。
保管棚の整理が不十分であったり、品番の表示が小さく見にくかったりすることも、このミスを誘発する一因となります。
パターン4:梱包・付属品ミス
製品本体の検品に集中するあまり、付随する作業でミスが起きることも少なくありません。
取扱説明書や保証書、充電ケーブルといった付属品の入れ忘れや、配送先ラベルの貼り間違いなどが代表例です。
メインの作業が完了したという安心感から、最終工程で注意が散漫になってしまうことで発生しやすくなります。
パターン5:伝票不一致
現物と各種伝票(ピッキングリスト、納品書など)との照合ミスは、最終的な誤出荷に直結してしまいます。
複数の注文を同時に処理している際に、A社の伝票を見ながらB社の製品をピッキングしてしまう、といった状況が考えられます。
このミスは、他の4つのミスが複合的に絡み合って発生することも多く、業務プロセス全体の見直しが必要となるケースもあります。
なぜ検品ミスは再発してしまうのか
上記のような検品ミスはなぜ起こってしまうのでしょうか。
「チェックリストの項目を増やした」「ダブルチェックを徹底させた」といった対策を講じても、なぜか検品ミスが再発してしまうケースは少なくありません。
例えば、品番の見間違いというミスに対し、チェックリストに「品番を指差し確認」という項目を追加したとします。
しかし、品番ラベルの印字が小さく見づらい、あるいは保管棚が分かりづらいといった「作業環境」にそもそもの問題があれば、いくら注意を促してもヒューマンエラーは再び発生しやすくなります。
このような「対症療法」のような対策では、一つのミスを潰しても、真因が残っている限り、別の場所や別の担当者が新たなミスを引き起こすという悪循環に陥ってしまうのです。
効果的な検品ミス対策を実現するためには、ミスの背景に潜む「仕組み」や「環境」そのものに目を向け、より本質的なアプローチが重要となります。
検品ミスの真因を突き止める方法
検品ミスの根本原因を特定するための有効な手法が「なぜなぜ分析」です。
これは、発生した一つの事象に対して「なぜ?」という問いを繰り返し、問題の本質的な原因を深掘りしていく思考フレームワークです。
表面的な原因ではなく、その背後にある業務プロセスやルールといった「仕組み」の問題を明らかにできるため、再発防止の策定に繋がります。
ここでは、現場で実践するための3つの簡易ステップをご紹介します。
STEP1:「誰が」ではなく「なぜ起きたか」に注目
なぜなぜ分析を始める上で最も重要な心構えは、分析の対象を「人」ではなく「事象」に置くことです。
「〇〇さんの不注意が原因だ」という結論で思考を停止させてしまうと、それは単なる個人の責任追及、いわゆる「犯人探し」で終わってしまいます。
スタート地点は、必ず「なぜそのミスが起きたのか?」という問いが重要になります。
「なぜ、〇〇さんは見落としてしまったのか?」と問いの主語を「事象」に転換することで、初めて本質的な原因への道筋が見えてきます。
STEP2:問いを真因にたどり着くまで繰り返す
「なぜなぜ分析では、なぜを5回繰り返す」と一般的に言われますが、これはあくまで目安に過ぎません。
重要なのは回数そのものではなく、具体的な改善アクションに繋がる原因にたどり着くまで、問いを続けることです。
例えば、「作業員が品番を間違えた」という事象から考えてみましょう。
- なぜ? → 思い込みでピッキングしてしまったから
- なぜ? → 類似品が多く、非常に紛らわしかったから
- なぜ? → 類似品が同じ棚に混在して保管されていたから
- なぜ? → 保管場所に関する明確なルールがなかったから
この場合、4回の問いで「保管ルールの不備」という具体的な対策(ルールを策定し、棚を分ける等)に繋がる原因に行き着きました。
このように、回数に固執せず本質的な原因が見つかるまで掘り下げることが重要です。
STEP3:「仕組み・ルール」の問題に行き着いたかを確認する
分析のゴールは、最終的な原因が「個人のスキルや意識」ではなく、「仕組み・ルール・環境」の問題に行き着いているかを確認することです。
もし最終的な原因が「注意力が足りなかった」「確認を怠った」といった個人の資質に行き着くのであれば、それは分析が不十分である可能性が高いです。
真因は、「注意力が散漫になるほど作業環境が悪かった」や「確認を忘れても次の工程に進めてしまうプロセスだった」といった、誰がやっても同じミスを起こしうる不完全な「仕組み」にあるはずです。
個人の責任で終わらせず、組織として改善できる「仕組み」の問題を発見することが、なぜなぜ分析の最終目的となります。
【原因別】検品ミス対策と改善アイデア9選
「なぜなぜ分析」でミスの根本原因を特定したら、次はいよいよ具体的な対策の立案です。
前の章で行った原因分析の結果と照らし合わせ、「最も効果がありそう」かつ「明日からすぐに試せる」と感じたものから一つだけ選んで、スモールスタートしてみましょう。
対策は、原因のタイプ別に「仕組み化」「標準化」「環境整備」の3つの軸でご紹介します。
【仕組み化】ヒューマンエラーを防ぐアイデア
人に頼るのではなく、仕組みの力でミスを強制的に防ぐアプローチです。
- ポカヨケを導入する
「ポカヨケ」とは、作業者が意図せずミス(ポカ)をしても、それが不良に繋がらないようにする物理的な仕組みのことです。
例えば、正しい向きでしか部品がはまらない治具(じぐ)を用意したり、規定数量を入れるとちょうど満杯になる専用ケースを作成したりといった工夫が挙げられます。
- ダブルチェックのルールを見直す
単に「二人で確認する」だけでは、チェックが形骸化しがちです。
1人目と2人目でチェック方法を変える(例:1人目はリストから現物、2人目は現物からリストを確認)、あるいはチェック項目を分担するなど、お互いが緊張感を持って確認作業を行えるような明確なルールを設けることが重要です。
- バーコード・RFIDを活用する
ハンディターミナルで商品のバーコードをスキャンし、ピッキングリストと自動で照合する仕組みを導入すれば、品番や数量の確認ミスを大幅に削減できます。
不一致の場合はエラー音や振動で知らせるため、ヒューマンエラーが介在する余地をなくせます。
【標準化】作業のバラつきをなくすアイデア
作業者による解釈の違いやスキルの差をなくし、誰がやっても同じ品質を保てるようにするアプローチです。
- 写真や動画を用いたマニュアルを作成する
文章だけのマニュアルは、人によって解釈が分かれることがあります。
OK品とNG品の比較写真を掲載したり、一連の作業手順を動画で撮影して共有したりすることで、新人でもベテランと同じ判断基準を持つことができます。
- 「限度見本」を設置する
キズや汚れといった品質基準は、言葉で正確に伝えるのが難しい領域です。
「このレベルのキズまでは許容(OK)」「これ以上は不良(NG)」といった実物の「限度見本」を検品場所に設置することで、作業者の主観による判断のバラつきを防ぎます。
- 作業手順をシンプルにする
複雑な作業手順は、ミスを誘発する大きな要因です。
一つの工程に複数作業を詰め込まず工程を細分化する、類似品の梱包方法を統一する等、作業者が「迷わない」「考えない」で済むような、シンプルで直感的な手順に見直しましょう。
【環境整備】作業員の集中力と効率を上げるアイデア
作業者が能力を最大限に発揮できるよう、物理的な作業環境を整えるアプローチです。
- 5S(整理・整頓・清掃・清潔・躾)を徹底する
5Sは品質管理の基本ですが、非常に効果的です。
特に、不要な物を処分する「整理」と、物の置き場所を明確に決める「整頓」を徹底するだけで、工具や伝票を探す無駄な時間が削減され、作業への集中力を高められます。
- 作業場の照度を改善する
手元が暗い環境は、品質ミスの見落としに直結します。
JIS(日本産業規格)の照明基準では、工場での精密な組立・検査作業には750ルクス以上の照度が推奨されています。
手元を照らすスポットライトを追加したり、照明を省エネで明るいLEDに交換したりといった改善が有効です。
- 保管棚のロケーション管理を見直す
商品の保管場所(ロケーション)を最適化することも重要です。
品番や形状が似ている類似品を物理的に離れた場所に保管する、逆に出荷頻度の高い商品をピッキングしやすい手前の棚に配置するなど、ミスを誘発しにくく、かつ効率的に作業できる配置を検討しましょう。
AR技術を用いた最新の検品ミス対策とは
これまでご紹介した対策は、既存の「人の作業」を改善し、効率化するアプローチでした。
しかし人手不足の状況の中で、熟練者の属人化や技術継承など、様々な人的課題が深刻化しつつあります。
その中で注目されているのが、AR技術(Augmented Reality:拡張現実)です。

ARは、現実の風景にデジタルの情報を重ね合わせることで、作業者の「認知」や「判断」を直接サポートし、ヒューマンエラーが発生する余地そのものを最小化します。
ARグラスを用いたピッキング・検品指示
作業者がARグラスを装着すると、現実の視界に作業指示がデジタル情報として表示されます。
例えば、目の前の棚のどこにピッキングすべき商品があるのかが強調表示されたり、取るべき商品の個数が視野の中に数字で表示されたりします。
これにより、作業者は紙のリストやハンディターミナルの画面に視線を落とす必要がなくなり、作業手順がハンズフリーで直感的に分かります。
ARグラスを用いたリアルタイムでの遠隔支援
現場にいる新人作業員が見ている視界の映像を、事務所など遠隔地にいる熟練者がPCやタブレットでリアルタイムに共有することも可能です。
熟練者は、その映像上に矢印や指示を書き込むことができ、そのデジタル情報が新人作業員のARグラスに直接表示されます。
これにより、まるで熟練者が隣で指導しているかのような、質の高い遠隔OJT(On-the-Job Training)が実現し、教育コストの大幅な削減とスキルの標準化が可能になります。
導入効果や費用感の目安とは
近年では、物流倉庫や製造工場においてAR技術の実証導入され、徐々に効果が表れています。
ピッキング作業におけるミス率が30%削減されたり、新人作業員がベテランと同等の作業スピードに達するまでの時間が半分になったりといった効果が報告されています。
数年前までARソリューションの導入には高額な初期投資が必要でしたが、近年はデバイスの進化とSaaS型(サブスクリプション)サービスの登場により、状況は大きく変わりました。
現在では、中小企業でも導入を検討できる価格帯のサービスが増えており、初期費用を抑えてスモールスタートすることも可能です。
AR技術はもはや未来の技術ではなく、検品ミス対策を大きく変える現実的なソリューションとなりつつあります。
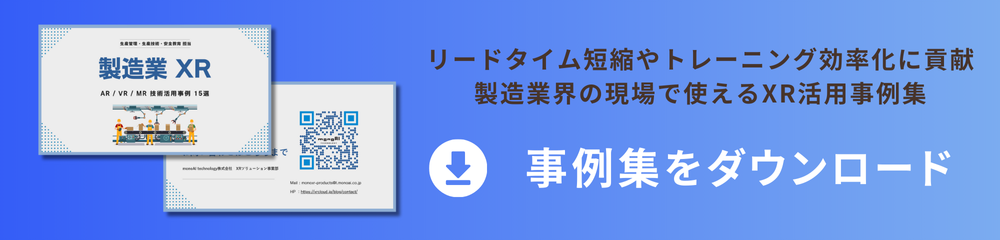
まとめ
いかがでしたでしょうか。
本記事では、検品ミスの根本原因を探る「なぜなぜ分析」から、明日から実践できる具体的な改善策、そしてAR技術を活用した未来のソリューションまで、検品ミス対策を体系的に解説しました。
最適な対策は、それぞれの現場が抱える課題の深さや、目指すべき生産性のゴールによって異なります。
今回の内容を踏まえて自社の課題をより深く分析し、ぜひ検品ミスの改善に繋げていただければ幸いです。
弊社では、ARを活用したピッキング支援などのソリューションを始め、産業向けのXRコンテンツを開発しております。
AR、VR、MRといったXR技術の導入にご興味がある方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。
ARコンテンツ制作!自社開発による柔軟性でお客様のビジネスをリードする『monoAR』
サービスの特徴や導入事例をまとめた資料をご用意しました。

monoARサービス紹介資料の無料ダウンロードはこちら
資料をダウンロードする
 TWITTER
TWITTER
 FACEBOOK
FACEBOOK
 はてブ
はてブ