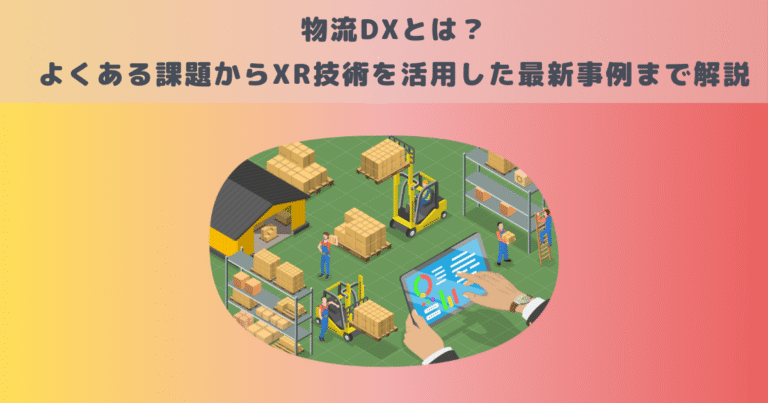昨今より話題となっていた「2024年問題」や、深刻化する人手不足など、多くの物流現場が構造的な業界課題に直面しています。
そういった中で、物流DXといった言葉を耳にする方も多いのではないでしょうか。
しかし、実際にどのような課題に対してどのような打ち手を打つべきか、DXとはどのようなものなのかをイメージしきれていない方も多いことでしょう。
本記事では、ありがちな業界課題を踏まえ、物流DXに繋がる課題への対策やステップを解説します。
物流におけるDXについてご興味がある方は、ぜひご覧ください。
物流DXとは?
物流DXの本質は、デジタル技術を手段としてビジネスモデルや組織を変革し、新たな企業価値を創造することです。
これは、経済産業省が『DX推進ガイドライン』で示す「企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して(中略)競争上の優位性を確立すること」という定義と一致します。
単にアナログ業務をデジタルに置き換えるだけの部分的なデジタル化に留まっていては、業界課題に対応し、競合との差別化や自社の成長を図ることは困難でしょう。
例えば、紙の伝票をスキャンしてデータ保存することは「デジタル化」の一例ですが、物流DXではそのデータをAIで解析し、高精度な需要予測や在庫の最適化に繋げることまで可能です。
さらには、その情報を荷主や配送パートナーとリアルタイムで共有し、サプライチェーン全体の効率化を実現します。
このように、物流DXはデジタルを起点に、新たな価値を生み出す活動を指します。
従って、物流DXの導入・検討においては、「デジタル技術で何を実現したいか」という明確なビジョンを持つことが重要になります。
物流業界で深刻化する3つの課題
物流DXが、なぜこれほどまでに求められているのでしょうか。
その背景となる、物流業界の3つの構造的な課題についてご紹介します。
① 「2024年問題」と労働規制の強化
第一の課題は、2024年4月1日から適用が開始された「働き方改革関連法」による、トラックドライバーの時間外労働の上限規制、通称「2024年問題」です。
これにより、ドライバーの時間外労働は年間960時間に制限されました。
結果としてドライバー1人あたりの走行距離が短くなり、長距離輸送が困難になるなど、輸送能力の低下が懸念されています。
株式会社野村総合研究所の試算によれば、このまま対策を講じなければ2030年度には国内の輸送能力が3割近く不足する可能性も指摘されています。
② 慢性的な「人手不足」と技術の属人化
第二に、業界全体で深刻化する人材不足と、それに伴う特定スキルへの依存です。
トラックドライバーの有効求人倍率は、全職業平均の約2倍という高い水準で推移しています。
さらに、ドライバーの年齢構成は40〜50代が全体の約45%を占めており、高齢化が著しく進行している状況です(総務省統計局「労働力調査」より)。
この状況は、長年の経験で培われた熟練作業員のノウハウが「属人化」する温床となります。
熟練者の引退と共に、現場のオペレーション品質が低下するリスクは、多くの企業にとって喫緊の課題となっています。
③ EC市場拡大による「小口多頻度化」
第三の課題は、EC(電子商取引)市場の急速な拡大に伴う、物流ニーズの変化です。
経済産業省の調査では、日本のBtoC-EC市場規模は2022年に22.7兆円に達するなど、右肩上がりの成長を続けています。
これにより、配送件数は爆発的に増加する一方、1件あたりの荷物は小さくなる「小口多頻度化」が進行しました。
結果として、倉庫内でのピッキングや仕分けといった作業は従来よりも複雑化し、積載効率も低下するなど、現場の負担は増大しつつあります。
【課題別】基本的な物流DX
では実際に、物流DXではどのような手法があるのでしょうか。
ここでは、多くの物流現場にありがちな3つの課題ごとに、それを解決する基本的なDXの手法をご紹介していきます。
【人手不足】物流ロボットによる作業の自動化・効率化
物流ロボットの導入により、作業の自動化や効率化を図ることが可能です。
例えば、AGV(無人搬送車)やAMR(自律走行搬送ロボット)といったロボットは、倉庫内の棚入れ・ピッキング作業を代替します。
作業員が定位置で待機し、ロボットが商品棚を運んでくる「Goods-to-Person」方式は、移動時間を削減し、生産性を大きく向上させます。
また、自動倉庫やコンベヤ、ソーターといったマテリアルハンドリング(マテハン)機器の導入も、重量物の搬送や煩雑な仕分け作業を自動化し、作業員の負担を大幅に軽減します。
【作業ミス】倉庫管理システムによる作業の標準化・精度向上
アナログな目視や紙のリストに頼った作業では、ヒューマンエラーを完全になくすことは困難です。
誤出荷は顧客からの信頼を失うだけでなく、返品対応など多大なコストに繋がるリスクもあります。
この課題には、業務の標準化と精度向上を実現するWMS(倉庫管理システム)が有効です。
WMSは、倉庫内の「どこに・何が・いくつあるか」を正確に管理し、作業員に最適なピッキングルートや手順を指示します。
さらに、RFIDといったハンディターミナルで商品をスキャンする作業を組み合わせれば、経験の浅い作業員でも、熟練作業者と同じ精度で、ミスなく効率的に作業を遂行することが可能になります。
【機会損失】在庫管理システムによる最適化
勘や経験に頼った在庫管理は、欠品による販売機会の損失や、過剰在庫によるキャッシュフローの悪化を招きます。
この問題は、在庫データをリアルタイムで可視化する在庫管理システムで解決できます。
正確な在庫数を常に把握することで、需要予測の精度を高めて発注業務を最適化し、欠品と過剰在庫を同時に抑制することが可能です。
また、非効率な配送ルートは、燃料費や人件費を圧迫する大きな要因にもなります。
TMS(輸配送管理システム)を導入すれば、天候や交通状況、納品先の時間指定といった多様な条件を考慮した最適な配送計画を自動で立案できます。
これにより、配送品質を維持しながら、コストを削減することも可能です。
人材価値を高めるXR技術とは
WMSやAGVといった上記のDXは、いわゆる物流現場の「基盤」を整えるものでした。
しかし、今後物流のDX化が進んだとしても、人の手で作業が行われるケースはまだまだ残っていくでしょう。
そこで、人材の価値をより高めていくべく、XR(Extended Reality)技術が注目されています。
XRは、AR(拡張現実)やVR(仮想現実)、MR(複合現実)といった技術の総称です。
物流業界において、どのように活用されるのかご紹介します。
《 AR技術 》「ビジョンピッキング」・遠隔作業支援
AR技術(Augmented Reality)とは、現実空間にデジタル情報を重ねて表示する技術です。

例えば「ビジョンピッキング」では、作業員の視界に最適なルートが表示され、目的の棚に到着すると、ピッキングすべき商品の場所が光って示されます。
数量などの情報も視野内に表示されるため、作業員はリストを見る必要なく、「見るだけ」で正確な作業を完結できます。
これにより、ピッキングミスを限りなくゼロに近づけ、新人作業員のトレーニング時間を短縮することが可能です。
また、遠隔作業支援もARの得意分野です。
具体的には、現場の作業員の視界映像を、遠隔地にいる熟練者へとリアルタイムで共有します。
熟練者は視界に直接、矢印や指示を書き込むことで、まるで隣にいるかのように的確なサポートを行うことが可能となり、技術継承の課題にもアプローチができます。
《 VR技術 》安全教育トレーニング・倉庫シミュレーション
VR技術(Virtual Reality)とは、仮想空間に現実世界を再現する技術です。

物流現場においては、特に従業員の教育や施設設計でその力を発揮します。
例えば、フォークリフトの操作トレーニングをVR空間で行えば、実際の機材や商品を使用することなく、実践的な訓練を何度でも反復できます。
また、事故現場を再現し、危険状況を体験学習させることで、安全意識の向上にも大きく貢献します。
さらに、倉庫の新設やレイアウト変更の際には、建設の前にVR空間で「デジタルツイン」を構築し、AGVの動線や作業員のワークフローをシミュレーションすることで、最適なレイアウトを追求することも可能です。
これにより、後から発生しうる設計や建設の手戻りコストを未然に防ぎます。
【事例】WMSとARピッキングで生産性を改善
理論だけでは、自社での導入をイメージしにくいかもしれません。 ここでは、物流DXによって大きな成果を上げた、ある中堅物流企業「A社」の代表的な事例を紹介します。
A社は、WMSとARピッキングを組み合わせることで、倉庫全体の生産性を1.5倍(150%)に向上させることに成功しました。
導入前の課題:アナログ作業によるミスと教育コストの増大
A社の倉庫では、かつて紙のリストを基にしたピッキング作業が主流でした。 そのため、商品の取り間違いや数量ミスといったヒューマンエラーが一定の割合で発生し、その確認と修正に多くの時間が割かれていました。
また、新人スタッフの教育にも課題を抱えており、一人前になるまで数週間のトレーニング期間を要するなど、教育コストの増大が経営を圧迫していました。
解決策:WMSを基盤としたAR「ビジョンピッキング」の導入
この状況を打破すべく、A社は物流DXへの投資を決断します。 まず基盤となるWMS(倉庫管理システム)を導入し、在庫とロケーション情報を完全にデジタル化しました。
次なる一手として、最もボトルネックとなっていたピッキング作業に、ARスマートグラスを活用した「ビジョンピッキング」システムを導入。 WMSから送信された作業指示が、作業員の目の前のスマートグラスに直接表示される仕組みを構築しました。
作業員は、グラスに表示される最適なルートに沿って移動し、視野内にハイライトされる棚から商品をピッキング。 最後に商品のバーコードをグラスのカメラで読み取るだけで、作業が完了します。
導入後の成果:生産性と品質の劇的な向上
結果は目覚ましいものでした。 両手が自由に使えるハンズフリーの状態になったことで、作業効率は大幅に向上。 確認作業や修正時間が削減されたことも含め、倉庫全体の生産性は導入前の1.5倍を達成しました。
さらに、システムが作業をナビゲートするため、ピッキングミスはほぼゼロに。 新人スタッフでも導入初日からベテラン作業員に近い精度で作業できるようになったため、トレーニング期間はわずか1〜2日にまで短縮されました。
A社の事例は、WMSというデジタル基盤の上にARという先進技術を組み合わせることが、いかに強力な成果を生むかを示す好例と言えるでしょう。
物流DXで失敗しないための3つのポイント
では物流DXの導入において、「一体何から手をつければ良いのか?」と思われたかもしれません。
失敗しないための、3つのステップをご紹介します。
【重要】よくある失敗パターンと導入前に押さえるべき3つのポイント
DXの導入における代表的な失敗は、解決すべき課題が曖昧なまま、ツール導入そのものが目的化してしまうケースです。
「話題のAI」や「最新のロボット」を導入したものの、現場の業務フローに合わず、誰にも使われないまま高価な置物になってしまう例は、有り得ない話ではありません。
また、現場の意見を聞かずにトップダウンで導入を進めてしまうことも、失敗の大きな要因です。
これらの失敗を避けるために、導入前には必ず以下の3つのポイントを押さえておきましょう。
- 目的の明確化: 「何を解決するためにDXを行うのか」を具体的に定義する。
- 現場の巻き込み: 計画の初期段階から現場の担当者を巻き込み、意見を吸い上げる。
- 経営層のコミットメント: DXを一過性のIT投資ではなく、全社的な経営戦略として位置づけ、継続的な支援体制を築く。
上記のポイントを押さえた上で、具体的な最初の一歩は「課題の可視化」です。
例えば、「ピッキングミスが月間で何件発生し、その対応コストはいくらか」「一人の作業員が一日に歩く平均距離は何kmか」といった数値を計測します。
データによって最もインパクトの大きい課題が明らかになれば、おのずと優先順位が見えてきます。
そして、取り組むべき課題が決まったら、「スモールスタート」を徹底してください。
倉庫全体を一気にDXによって変革しようとせず、まずは特定の一つの工程や、一部分のエリアに限定してPoC(概念実証)を行います。
このアプローチは、低リスクでノウハウを蓄積できるだけでなく、「小さな成功体験」を生み出します。 この成功が、現場の協力体制をさらに強固にし、全社展開に向けた大きな推進力となります。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
本記事では、業界課題を踏まえた物流DXとはといった基本的な内容から、具体的なDX手法までを解説しました。
2024年問題や人手不足といった避けては通れない業界課題から、WMSやAGVといった、現場の悩みを解決する基本的なDX手法、そして、人の能力を拡張し、生産性を飛躍させるAR/VRといったXR技術の最前線など、物流DXの全体像から、その具体的な導入ステップまでをご理解いただけたかと思います。
特に、スマートグラスを活用したARピッキングや、VRによる安全教育は、これからの物流現場において、人の価値を最大化する選択肢として、徐々に導入が増えています。
弊社では、ARやVRを始めとする様々な産業向けXRコンテンツの開発を行っております。
物流シーンにおけるXRコンテンツの導入にご興味がある方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

 TWITTER
TWITTER
 FACEBOOK
FACEBOOK
 はてブ
はてブ