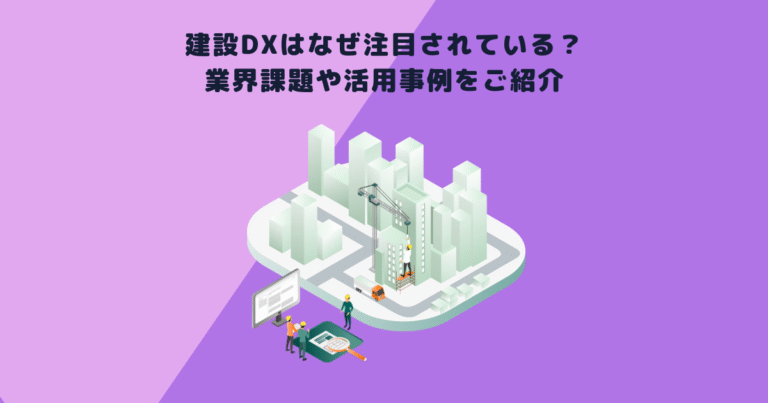建設DXとは、建設業界が直面する人材不足や生産性の課題を解決する、今最も重要な経営戦略です。
熟練工の高齢化や「2025年の崖」問題が迫る中、従来のやり方だけでは企業の成長が見込めないためです。
本記事では、建設DXの基本から現場でもありがちな業界課題、BIMやAI、そして特に注目されるXR(AR/VR)といった最新技術が、現場課題をどう解決できるのかを解説します。
業界の課題と解決策、具体的な始め方までを網羅し、建設DXの全体像を掴むための一助となれば幸いです。
目次
そもそも建設DXとは?
建設DXとは、AIやIoTなどのデジタル技術を活用して、業務プロセスやビジネスモデルそのものを変革し、新たな価値を創出する取り組みです。
これは、単にITツールを導入する「IT化」とは根本的に目的が異なります。
なぜなら、IT化が既存業務の効率化を目的とするのに対し、建設DXはIT技術やデータの活用を軸に、ビジネス全体の競争力を高めることを目指すためです。
特に、経済産業省が警鐘を鳴らす「2025年の崖」が目前に迫っており、旧来のシステムや業務フローのままでは、企業が競争力を失うリスクが高まっています。
「2025年の崖」とは、複雑化・老朽化した既存ITシステムを放置した場合、2025年以降に最大で年間12兆円の経済損失が生じる可能性を指摘した問題です。
この問題を乗り越え、持続的に成長するためには、業務のデジタル化に留まらない、組織全体の変革が不可欠なのです。
例えば、紙の図面をPDF化してタブレットで見るのは「IT化」にあたります。
これにより、図面の持ち運びは便利になりますが、業務フロー自体に大きな変化はありません。
一方、BIM/CIMを導入し、設計から施工、維持管理までの全工程で3Dデータを連携・活用するのは「建設DX」です。
この変革により、設計段階での手戻り防止、正確な資材発注、AR技術による施工シミュレーションなどが可能になり、生産性向上だけでなく、新たな付加価値を生み出します。
このように建設DXは、単なるデジタルツールの導入ではなく、データを駆使してビジネスのあり方を変える経営戦略そのものと言えます。
建設DXが求められている背景とは
建設DXの導入が急務とされる背景には、どういったものがあるのでしょうか。
主に以下の業界課題によって、建設DXの必要性が高まっています。
課題①:深刻な人材不足と進まない技術継承
第一に、業界は深刻な人材不足と熟練技術者の高齢化に直面しています。
国土交通省のデータによれば、建設技能労働者のうち約3分の1(35.5%)を55歳以上が占める一方、29歳以下は約12%に過ぎません(2022年時点)。
若手入職者が少ない中でベテランの大量離職が進むと、長年培われてきた貴重な技術やノウハウが失われる「技術継承」の問題が現実のものとなります。
課題②:過重労働と生産性の低さ
第二に、業界全体で過重労働と生産性の低さが常態化しています。
建設業の年間総実労働時間は1,900時間を超え、全産業平均より90時間以上も長い状況が続いています(2023年時点)。
その原因として、紙ベースの書類作成や非効率な情報共有が挙げられ、特に2024年4月から適用された時間外労働の上限規制により、生産性向上が待ったなしの経営課題となっています。
課題③:労働災害と安全管理の限界
第三に、労働災害のリスクが他産業に比べて依然として高い水準にあります。
厚生労働省の統計でも、建設業は労働災害による死亡者数が全産業の中で最も多く、長年ワースト1位が続いています。
現場の状況は刻々と変化するため、人の経験や注意だけに頼る従来型の安全管理には限界があるのが実情です。
このように、人材・時間・安全という経営の根幹を揺るがす課題が山積しており、これらを根本から解決する手段として建設DXへの期待が高まっているのです。
建設DXで解決できる3つの現場課題
ここでは、DXによって現場のどのような課題が解決され、具体的にどう変わるのかを3つのポイントに絞って解説します。
課題① 技術継承
建設DXは、これまで個人の経験に依存していた技術やノウハウを、デジタルデータとして誰もがアクセスできる形に変えます。
例えば、熟練技術者が遠隔地からでも、現場の若手作業員にリアルタイムで正確な指示を送ることが可能になります。
また、複雑な施工手順を仮想空間で繰り返し練習できるため、経験の浅い作業員でも安全かつ効率的にスキルを習得できます。
これにより、人材不足を補いながら、質の高い技術を次世代へとスムーズに継承する体制が構築されます。
課題② 生産性の向上
建設DXは、情報共有のあり方を変え、全体の生産性を向上させます。
図面や日報、各種書類をデジタルデータで一元管理することで、関係者はいつでも最新の情報にアクセスでき、非効率な電話連絡やFAXでのやり取りが不要になります。
写真整理や書類作成といった、これまで現場監督が事務所に戻って行っていた多くの手作業が自動化されるため、本来注力すべき現場の管理業務に多くの時間を割けるようになります。
結果として、無駄な移動時間や残業が削減され、働き方改革の実現にも繋がります。
課題③ 安全性の向上
建設DXは、現場の安全管理品質をより高めることも可能です。
現場に設置されたセンサーやカメラからの情報をAIが分析し、重機と作業員の接近や、危険エリアへの立ち入りといった事故の予兆を自動で検知して警告します。
さらに、過去の災害事例を基にしたリアルな事故を仮想空間で体験する安全教育も可能です。
これにより、人の注意力だけに頼るのではなく、データに基づいた客観的なリスク管理が実現し、事故を未然に防ぐ安全体制を構築できます。
このように、建設DXは「技術継承」「生産性」「安全性」という現場の三大課題を解決し、より付加価値の高い仕事に集中できる環境を生み出します。
建設DXを推進する5つのコア技術
建設DXは、複数のデジタル技術を組み合わせることでその真価を発揮します。
ここでは、建設DXを支える5つのコア技術について、それぞれの役割と特徴を解説します。
SaaS(クラウドサービス)
SaaS(Software as a Service)とは、インターネット経由でソフトウェア機能を利用するサービスのことです。
PCやサーバーにソフトウェアをインストールする必要がなく、スマートフォンやタブレットからいつでもどこでも情報にアクセスできるため、リアルタイムでの情報共有を実現します。
建設業では、施工管理アプリや図面共有ツールとして導入が進んでおり、現場とオフィスの間の情報格差をなくし、迅速な意思決定を支援します。
BIM/CIM
BIM/CIM(Building/Construction Information Modeling, Management)は、建物の3次元モデルに、資材やコスト、工程といった多様な情報を統合し、一元管理する仕組みです。
企画・設計段階から3Dモデルを構築することで、これまで施工段階で発覚していた配管の干渉などの問題点を事前に洗い出し、手戻りを防ぎます。
この「フロントローディング」により、プロジェクト全体の品質と生産性を大幅に向上させることが可能です。
IoT(Internet of Things)
IoTは、建機や資材、さらには作業員にセンサーを取り付け、インターネットを介してデータを収集・活用する技術です。
例えば、重機の稼働状況を遠隔で監視して最適な配置計画を立てたり、作業員のバイタルデータを取得して熱中症を予防したりできます。
物理的な現場の状況をリアルタイムで「見える化」し、データに基づいた客観的な現場管理を実現します。
AI(人工知能)
AIは、収集された膨大なデータを分析し、パターンを学習することで、人間のような判断や予測を行う技術です。
建設業では、ドローンで撮影した現場写真から工事の進捗状況を自動で判定したり、過去の労災データを分析して危険な作業を予測し、事前に警告したりする活用が進んでいます。
人の経験や勘に頼っていた業務を自動化・高度化し、より安全で効率的な施工計画の立案に貢献します。
AR/VR(XR)
XR(Extended Reality)は、AR(拡張現実)とVR(仮想現実)の総称で、デジタル情報を現実世界と融合させる技術です。
ARは、現実の風景にデジタル情報を重ねて表示する技術で、現場でタブレットをかざすと、壁の中に埋設される配管や鉄筋の位置を実寸大で確認できます。
VRは、仮想空間に3Dモデルを再現し、あたかもその場にいるかのような没入体験を可能にします。完成後の建物を歩き回ったり、危険な作業を安全にシミュレーションしたりできます。
XRは、BIM/CIMで作成したデジタルデータを、現場で最も直感的に活用するためのインターフェースとして、建設DXの可能性を大きく広げられるでしょう。
これらの技術は独立して機能するだけでなく、相互に連携することで相乗効果を生み出します。
建設DX導入における失敗しないための4ステップ
建設DXを試験的な導入で終わらせず、全社的な成果に繋げるためには、より計画的で戦略的なアプローチが不可欠です。
ここでは、本格的な導入を成功させるための、具体的な4つのステップを解説します。
STEP1:DXの目的と解決すべき課題を明確化する
最初のステップは、技術やツールありきで考えるのではなく、「DXによって何を達成したいのか」という目的(ビジョン)を明確にすることです。
例えば、「手戻り率を20%削減する」「書類作成に関わる残業時間を月10時間削減する」といった、具体的で測定可能な目標(KPI)を設定します。
そして、その目標達成のために最も解決すべき業務課題は何かを、経営層から現場の作業員までを交えて議論し、優先順位を決定することが重要です。
STEP2:現状の業務プロセスを可視化し、ツールを選定する
次に、定めた課題に関連する現在の業務プロセス(As-Is)を詳細に可視化・分析します。
「誰が、いつ、どこで、どのような作業をしているのか」「情報の流れはどうか」といった点を洗い出し、非効率な部分やボトルネックを特定します。
この分析結果に基づいて、課題解決に最適な機能を持つツールを選定します。
この際、将来的な拡張性や、他のシステムとの連携が可能かどうかも考慮に入れると、長期的な視点でのDX推進に繋がります。
STEP3:スモールスタートで導入し、効果を検証する
最適なツールを選定したら、いきなり全社に導入するのではなく、特定の部署や一つのプロジェクトに限定して試験的に導入します(スモールスタート)。
このパイロットプロジェクトを通じて、実際の業務におけるツールの有効性や課題点を洗い出します。
STEP1で設定したKPIを基に、「導入前後で生産性がどう変化したか」「現場の作業員がスムーズに使いこなせるか」といった点を客観的に評価し、導入効果を検証します。
STEP4:評価と改善を繰り返し、段階的に本格展開する
パイロットプロジェクトの結果を評価し、導入効果が確認できれば、いよいよ本格展開の計画を進めます。
試験導入で見つかった課題点を改善し、社内での運用ルールやマニュアルを整備した上で、対象部署やプロジェクトを段階的に拡大していきます。
また、導入後も定期的に効果測定と現場からのフィードバック収集を行い、継続的にプロセスを改善していくことが重要です。
建設DXは「導入して終わり」ではなく、この改善サイクルを回し続けることで、その効果を最大化できます。
このように、目的設定から評価・改善までの一連のプロセスを計画的に実行することが、建設DXを単なるツール導入から、企業の競争力を高める経営変革へと昇華させる鍵となります。
建設DXで注目されているXR技術とは
建設DXを構成する技術の中でも、XR技術(AR/VR)の活用が増えてきています。


SaaSやBIM/CIMが業務の効率化や情報の集約で活用される一方、そのデジタルデータを現場で最大限に活かすには、誰もが直感的に理解できるインターフェースが必要でした。
XR技術は、PC画面上の2Dの図面や複雑なデータを、ARで現実空間に重ね合わせたり、VRで仮想空間上で体感したりすることができます。
例えば、ARを使えば、設計図通りに鉄筋が組まれているかを、現実の鉄筋にBIMモデルを重ねてミリ単位で確認でき、施工品質を標準化し向上させます。
これにより、専門家でなくとも、誰もがデジタル情報を3次元空間で直感的に把握できるようになり、計画と現実の間のギャップを埋めることができます。
また、建設業の仕事は「その場に行かなければできない」という物理的な制約が常に伴っていましたが、XR技術によってこのような制約も解消できる可能性を秘めています。
ARによる遠隔支援は、熟練技術者がオフィスにいながら、複数の現場に的確な指示を出すことを可能にし、VRによる安全教育は、現実では再現不可能な危険な状況をどこにいても安全に体験させ、作業員の安全意識を高めることができます。
例えば、VR空間でクレーンの操作や高所作業をシミュレーションすることで、新人の作業員でも、実際の現場に出る前にリスクへの対処法を身体で覚えることが可能です。
これは、従来の教科書やビデオ学習では決して得られない、深いレベルでの技術と安全意識の習得に繋がります。
このようにXRは、建設業界における人的な課題から、現場の生産性に関わる課題まで幅広く活用されており、冒頭に上げた業界課題を解消する可能性を秘めています。
まとめ
本記事では、建設DXの基本的な概念から、業界が抱える課題、それを解決する主要技術、そして現場で始めるための具体的なステップまでを解説しました。
建設DXは、もはや一部の先進企業だけのものではなく、すべての建設事業者にとって重要な経営戦略になりつつあります。
従来の方法では解決が困難な人材不足や技術継承、過重労働、労働災害といった課題に対して、ぜひこの機会に、建設DXの活用を検討してみてはいかがでしょうか。
弊社では、建設業界を始めとした安全教育や業務支援マニュアルなど、お客様の課題やご要望に合わせたXRコンテンツの受託開発・運用支援を行っております。
貴社のご状況に応じた最適なXRソリューションを、柔軟に開発致します。
XRコンテンツの導入にご興味がある方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

 TWITTER
TWITTER
 FACEBOOK
FACEBOOK
 はてブ
はてブ