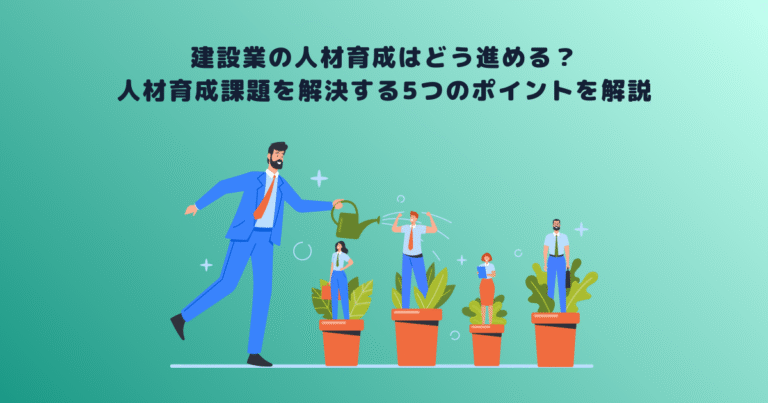「指導者によって若手の成長がバラバラ…」 「せっかく育てたのに、すぐに辞めてしまう…」
建設業の人材育成において、このような課題を感じてはいないでしょうか。
熟練技術者からの技術承継や「2024年問題」への対応が急務となる中、場当たり的なOJTに頼った人材育成は限界を迎えています。
属人化した指導は、若手の成長を妨げるだけでなく、モチベーションの低下や離職の引き金となり、企業の競争力そのものを揺るがしかねません。
今、建設業界で求められているのは、計画的かつ体系的な人材育成の「仕組み」を構築することです。
本記事では、建設業における人材育成が重要な背景から、多くの企業が陥りがちな人材育成課題、対策におけるポイント、人材育成の最新技術までを解説します。
この記事を最後まで読めば、人材育成の課題解決に向けた、具体的なヒントが得られるはずです。
建設業の人材育成が重要な背景
これまでのような、現場任せのOJTや個人の経験則に依存した指導方法では、企業の未来を築く人材を育てることは困難になりつつあります。
その背景には、大きく3つの理由が存在します。
理由①:技術継承問題と「2024年問題」への対応
第一に、喫緊の課題である「技術継承」と「2024年問題」への対応です。
建設業界では、全産業の平均を上回るペースで就業者の高齢化が進行しており、熟練技術者が持つ高度なスキルやノウハウの、若手への継承が追いついていません。
見て覚えるといった従来のOJTでは、複雑な「暗黙知」を効率的に若手へ伝えるには時間がかかりすぎ、技術が途絶えてしまうリスクがあります。
さらに、2024年4月から適用された時間外労働の上限規制、いわゆる「2024年問題」により、長時間労働を前提とした働き方は通用しなくなりました。
限られた時間の中で質の高い技術を伝承し、生産性を維持・向上させるためには、育成プロセスそのものを効率化・標準化する体系的な仕組みが必要になりつつあります。
理由②:若手・中堅社員の離職率低下
第二に、若手・中堅社員の定着率を向上させるためです。
国土交通省の調査によると、建設業における若年層の離職率は依然として高い水準にあります。
その大きな要因の一つが、「成長を実感できない」「将来のキャリアパスが見えない」という育成環境への不満です。
指導者によって言うことが違ったり、行き当たりばったりの業務をこなすだけでは、社員は自身の成長に確信を持てず、将来への不安を募らせてしまいます。
階層やスキルレベルに応じた育成ステップを用意し、明確なキャリアパスを示すことは、社員のエンゲージメントを高め、優秀な人材の流出を防ぐ上で非常に重要です。
理由③:会社の生産性・競争力の向上
第三に、会社全体の生産性と競争力を直接的に高めることに繋がる為です。
体系的な人材育成は、社員一人ひとりのスキルレベルを底上げし、業務品質の標準化を実現します。
これにより、「あのベテランしかできない」といった業務の属人化が解消され、組織として安定した施工品質を提供できるようになります。
また、計画的に多能工化を進めることで、現場の状況に応じて人員を柔軟に配置できるようになり、生産性が向上します。
個々のスキルアップが組織全体の技術力向上につながり、それが新たな受注機会の創出や顧客からの信頼獲得、つまり企業の競争力強化に直結します。
建設業の人材育成で効果を高める5つのポイント
体系的な人材育成の重要性を理解した上で、次はその効果を最大化するための具体的なポイントを見ていきましょう。
やみくもに研修制度を導入するだけでは、期待した成果は得られません。
建設業の人材育成を成功させるためには、以下の5つのポイントを連動させながら、総合的に取り組むことが重要です。
- 会社のビジョンと連動した育成目標を立てる
- OJTを「仕組み化」し属人化を防ぐ
- Off-JTを効果的に組み合わせる
- 社員の成長が実感できるキャリアパスを示す
- 経営層を巻き込み、全社で取り組む
それぞれについて、詳しく解説します。
ポイント①:会社のビジョンと連動した育成目標を立てる
まず最も重要なのは、人材育成を会社全体のビジョンや経営戦略と結びつけることです。
「3年後にBIM/CIMを活用したプロジェクトの受注を倍増させる」というビジョンがあるならば、育成目標は自ずと「BIM/CIMオペレーターを〇名育成し、プロジェクトマネージャーには必須スキルとして習得させる」といった具体的なものになります。
会社の進むべき方向と、社員に求めるスキルや人物像が明確にリンクすることで、育成への投資に一貫性が生まれ、社員も自身の成長が会社の成長にどう貢献するのかを理解しやすくなります。
まずは、「自社はどこへ向かうのか」「そのためにどんな人材が必要か」という育成の羅針盤を明確にすることから始めましょう。
ポイント②:OJTを「仕組み化」し属人化を防ぐ
次に、育成の基本となるOJT(On-the-Job Training)を仕組み化し、指導の属人化をなくすことです。
「あの先輩の指導は分かりやすいが、別の上司は見て覚えろと言うだけ」という状況では、新人の成長は運任せになってしまいます。
これを防ぐため、「OJT計画書」や「スキルチェックシート」などを活用し、「誰が」「いつまでに」「何を」「どのレベルまで」教えるのかを可視化・標準化することが不可欠です。
また、指導者側に指導スキルを身につけてもらう「トレーナー研修」の実施や、若手社員と先輩社員がペアを組む「メンター制度」の導入も、OJTの質を安定させ、組織全体の教育力を高める上で非常に効果的です。
ポイント③:Off-JTを効果的に組み合わせる
OJTで実践的なスキルを磨きつつ、Off-JT(Off-the-Job Training)で体系的な知識を補完することで、より従業員の成長へ繋がります。
OJTだけでは、どうしても知識が断片的・経験則的になりがちです。
例えば、現場で配筋作業を経験した若手が、Off-JTである集合研修やe-ラーニングを通じて構造力学の基礎を学ぶことで、なぜその作業が必要なのかを深く理解できるようになります。
このように、実践(OJT)と理論(Off-JT)を計画的に行き来させることで、一つひとつの業務に対する理解度が深まり、応用力の高い技術者へと成長させることができます。
ポイント④:社員の成長が実感できるキャリアパスを示す
社員が高いモチベーションを維持しながら働き続けるためには、「この会社で努力すれば、将来こうなれる」という成長の道筋、すなわちキャリアパスを明確に示すことが欠かせません。
単に「主任→係長→課長」といった役職のステップだけでなく、「施工管理を極めるスペシャリストコース」「複数の専門分野を持つゼネラリストコース」など、個々の適性や希望に応じた多様なキャリアモデルを提示することが理想です。
また、各ステップで求められるスキルや資格を明示し、資格取得支援制度などを連動させることで、社員は自らの目標を具体的に設定し、主体的にスキルアップに取り組むようになります。
ポイント⑤:経営層を巻き込み、全社で取り組む
最後に、人材育成は人事部や現場担当者だけに任せるのではなく、経営層が強いリーダーシップを発揮し、全社的な取り組みとして推進することが重要です。
人材育成は、成果が出るまでに時間とコストがかかる投資です。
短期的な業績を優先し、育成への投資を怠れば、数年後に企業の競争力が低下しかねません。
経営トップが自らの言葉で人材育成の重要性を繰り返し社内に発信し、育成の成果を人事評価に適切に反映させる、こうした経営層の本気度が現場に伝わることで、初めて人材育成が企業文化として根付いていくでしょう。
建設業の人材育成課題を解決する最新技術
建設業の人材育成では、従来の研修手法の課題を解決するため、XR(Extended Reality)と呼ばれる最新技術の活用が新たなトレンドになっています。
XRとは、VR(仮想現実)、AR(拡張現実)、MR(複合現実)の総称であり、現実世界と仮想世界を融合させることで、これまでにない学習体験を可能にする技術です。



ここでは、それぞれの技術の特性と、建設業の人材育成における具体的な活用シーンを紹介します。
VR(仮想現実):”危険”を”安全”に体験する
VRは、専用のヘッドセットを装着し、視界を360°覆うことで、完全にCGで構築された仮想空間へ没入する技術です。
この「現実から隔離された没入感」という特性を活かし、建設業では特に安全教育の分野で活用が進んでいます。
高所からの墜落、重機との接触、足場の倒壊といった、現実では決して試すことのできない労働災害を仮想空間でリアルに疑似体験させることが可能です。
座学で学ぶ知識とは異なり、いわゆる”体験学習”として危険を「自分事」として体感することで、安全意識を大きく向上させる効果が期待できます。
また、大型重機の操作シミュレーターとして活用すれば、天候や場所を選ばず、燃料費もかけずに、新人が納得いくまで繰り返し基本操作を練習できます。
例として、訓練環境の用意が難しい航空機の操縦訓練なども、VRを用いた操作シミュレーションが活用されています。
AR(拡張現実):”現実”に”情報”を重ねて作業を支援
ARは、スマートフォンやタブレット、スマートグラスなどを通して、目の前の現実の風景に、CGやテキストなどのデジタル情報を重ねて表示する技術です。
建設業では、現場での作業支援や技術指導に大きな力を発揮します。
例えば、タブレットをかざすと、まだ何もない空間にこれから設置する配管や電気配線のルートが3Dモデルで表示されたり、目の前の機械の正しい操作手順が矢印で示されたりします。
これにより、若手技術者でも図面との照合が容易になり、施工ミスを減らすことができます。
さらに、遠隔地にいる熟練技術者が、若手社員が見ている現場の映像にリアルタイムで指示を書き込んで指導する「遠隔臨場」も、ARの代表的な活用例です。
MR(複合現実):”現実”に”仮想”を融合させて操作する
MRは、ARをさらに発展させた技術で、現実空間に表示したCGなどのデジタル情報を、あたかもその場に実在するかのように表示し、実際に手で触れたり、動かしたりできるのが特徴です。
この「現実と仮想の融合とインタラクション(相互作用)」という特性を活かし、BIM/CIMデータの活用や施工シミュレーションで注目されています。
設計段階の3Dモデルを建設現場に実寸大で投影し、関係者全員が同じものを共有しながら、複数人で同時に設備や構造物の干渉チェックを行えます。
図面だけでは理解が難しい複雑な納まりも、MRを使えば若手でも直感的に理解することが可能です。
このように、VR・AR・MRはそれぞれの特性を活かし、建設業が抱える「安全」「技術継承」「生産性向上」といった課題を、従来の取り組みよりも高い効果をもって解決できる可能性を秘めています。
まとめ
本記事では、建設業が直面する課題を背景に、体系的な人材育成の重要性と、その効果を最大化するための5つの重要ポイント、そしてXRなどの最新技術トレンドについて解説しました。
熟練技術者の高齢化や2024年問題、若手人材の確保・定着など、建設業界を取り巻く環境は厳しさを増しています。
このような時代において、人材育成はもはや単なる福利厚生や教育担当者の業務ではありません。
今回ご紹介した5つのポイントを参考に、まずは自社の人材育成の現状を振り返り、どこに課題があるのかを洗い出すことから始めてみてはいかがでしょうか。
▼5つの重要ポイント
- 会社のビジョンと連動した育成目標を立てる
- OJTを「仕組み化」し属人化を防ぐ
- Off-JTを効果的に組み合わせる
- 社員の成長が実感できるキャリアパスを示す
- 経営層を巻き込み、全社で取り組む
一つひとつの課題に真摯に向き合い、計画的な人材育成に取り組むことが、技術力を高め、社員が持続的に働き続けられる「未来の顧客と従業員から選ばれ続ける企業」を築くための、最も確実な一手となるはずです。
弊社では、建設業の人材育成を始めとするXRコンテンツの受託開発を行っております。
ご要望に応じたXRコンテンツの開発が可能ですので、AR、VR、MRの導入にご興味がある方はぜひお問い合わせください。

 TWITTER
TWITTER
 FACEBOOK
FACEBOOK
 はてブ
はてブ