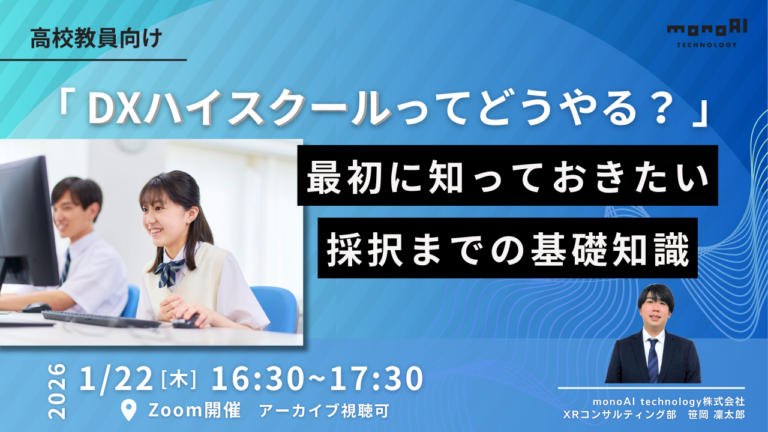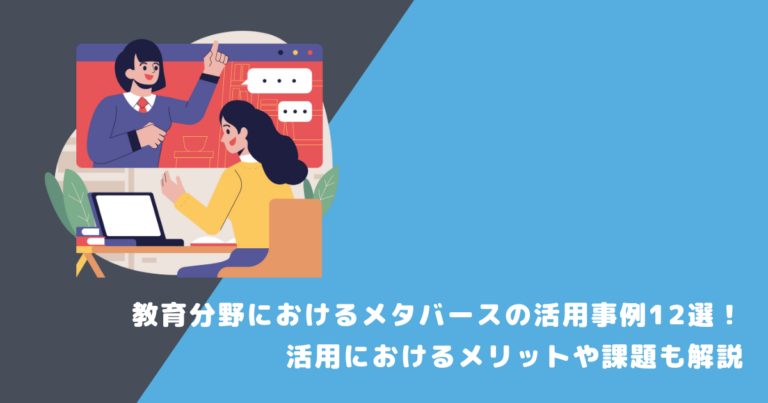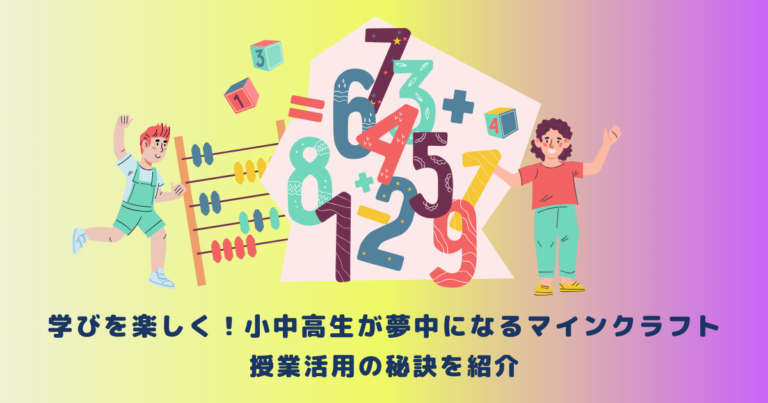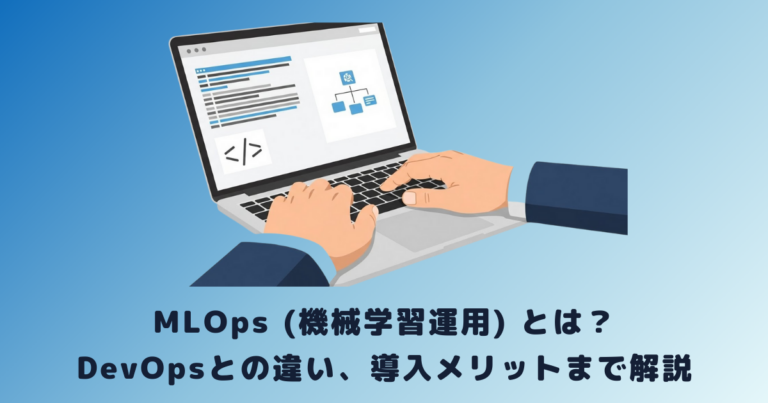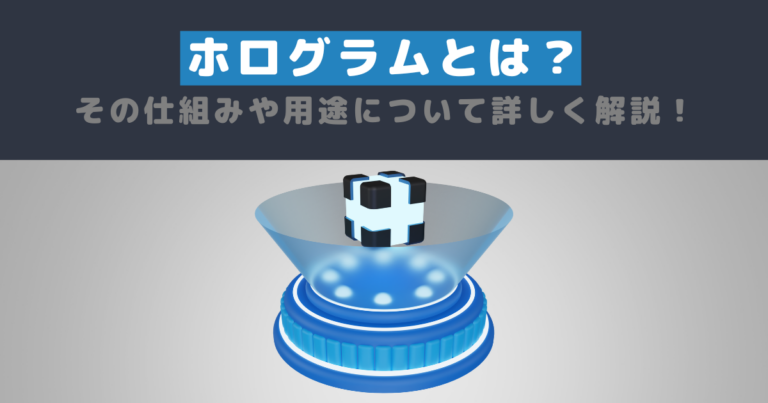現代の企業研修が抱えるエンゲージメント低下という課題に対し、ゲーミフィケーション研修が有効な解決策として注目されています。
Z世代の価値観の変化やリモートワークの普及により、従来の画一的な研修では参加者の主体的な学びを引き出すことが困難になっているためです。
この記事では、ゲーミフィケーション研修の基本概念やeラーニングとの違いを明確にし、その導入メリットを具体的な成功事例を交えて解説します。
企業研修におけるゲーミフィケーションの活用に興味がある方は、ぜひご覧ください。

学習意欲を引き出し、子どもが自ら学ぶメタバース×ゲーミフィケーションの教育!
メタバースを活用した学習メリットや『monoNITE』サービスの特徴をまとめた資料をご用意しました。

monoNITEサービス紹介資料の無料ダウンロードはこちら
資料をダウンロードする目次
ゲーミフィケーション研修とは? eラーニングとの違い
ゲーミフィケーション研修とは、研修にビデオゲームなどを単純に取り入れるのではなく、「ゲームが持つ構造的な要素」を活用して受講者のエンゲージメントと学習効果を最大化する、戦略的な人材育成手法です。
人間が本来持つ「目標を達成したい」「他者に認められたい」といった心理的な欲求を、クエスト、ポイント、ランキングといった仕組みで巧みに刺激します。
これにより、研修を「やらされ感のある義務」から「主体的に挑戦したい課題」へと転換させることが可能です。
ゲーミフィケーションとは?

ゲーミフィケーションとは、ゲームで活用される特有の要素や仕組みを、ビジネスや教育といったゲーム以外の分野に応用する手法のことです。
例えば、研修のゴールまでの道のりを細分化した明確な目標として「クエスト」が設定され、それを一つクリアするごとに「ポイント」や「バッジ」といった報酬が与えられます。
これにより、受講者は自身の進捗と成長をリアルタイムで実感できる、強力な即時フィードバックを得ることが可能です。
さらに、他者と成果を競い合う「ランキング」や、仲間と協力して課題に挑む「チームミッション」は、社会的なつながりや健全な競争意識を育み、学習プロセスそのものへの没入感を深めます。
従来のeラーニングや研修との違い
ゲーミフィケーション研修と、従来の研修やeラーニングとの決定的な違いは、目的にあります。
従来の研修は、講師から受講者へ知識や情報を一方的に「伝達」することが主な目的でした。
また、eラーニングは時間や場所を選ばずに学習できる利便性を持つ一方で、学習者のモチベーション維持は個人の裁量に委ねられがちという課題があります。
対してゲーミフィケーション研修は、学習者が主体的に課題へ取り組み、試行錯誤するプロセスを通じて、知識の「定着」と実践的な「行動変容」を促すことを最大の目的として設計されています。
つまり、ゲーミフィケーション研修は単なる知識のインプットに留まらず、学習体験そのものを再設計することで、受講者の自発的な成長を引き出す新しい研修なのです。
ゲーミフィケーション研修が注目される3つの背景
現代のビジネス環境の変化に伴い、ゲーミフィケーション研修への注目が急速に高まっています。
この背景には、新たな価値観を持つ「Z世代」の台頭、働き方の大きな変化である「リモートワーク」の普及、そしてより高い研修成果を求める企業側の要求という、3つの大きな変化が存在します。
やらされ感を嫌う「Z世代」の価値観の変化
第一に、「Z世代」の価値観の変化が挙げられます。
生まれた時からインターネットやSNSに触れているデジタルネイティブである彼らは、一方的に情報を受け取る受動的な学習を好みません。
自身の成長をリアルタイムで実感できる体験や、仕事そのものに対する意味、社会的な意義を重視する傾向が強いことが、多くの調査で指摘されています。
即時フィードバックや達成感の可視化、明確な目標設定といったゲーミフィケーションの特性は、このような彼らの内発的動機付けを引き出す上で、高い親和性を持っているのです。
一体感が生まれにくい「リモートワーク」の普及
第二に、リモートワークの定着による、組織内コミュニケーションの変化です。
物理的に離れた環境では、従来の集合研修で自然に生まれていた偶発的な対話や、チームとしての一体感を醸成することが非常に難しくなっています。
このコミュニケーションの希薄化は、従業員体験の低下や、企業文化の浸透を妨げる要因となり得ます。
オンライン上でチームを組み共通のミッションに挑むゲーミフィケーション研修は、物理的な距離を超えた協働体験を創出し、組織のエンゲージメントを再構築する強力なソリューションとなります。
学習内容の「定着」と求められる研修成果
第三に、人的資本経営の観点から、企業が研修に求める成果がより高度になっている点です。
もはや「研修を実施した」という事実だけでは評価されず、投資対効果(ROI)として、受講者の明確な「行動変容」と、それがもたらす業績への貢献が重視される時代になりました。
ドイツの心理学者ヘルマン・エビングハウスが提唱した「忘却曲線」によれば、人は学習した内容の多くをわずか1日後には忘れてしまうとされています。
この課題に対し、ゲーミフィケーションが促す「能動的な体験学習」は、知識の定着率を高め、実際の業務で活かせるスキルの習得を可能にします。
ゲーミフィケーション研修 3つのメリットと注意点
ゲーミフィケーション研修を導入することは、学習効果の向上、エンゲージメントの強化、そして実践的なソフトスキルの醸成という、組織にとって計測可能かつ価値あるメリットをもたらします。
これらのメリットは、脳科学や心理学の原則に基づき学習者の内発的動機を引き出し、従来の座学だけでは得られなかったリアルな体験を提供することで実現されます。
しかし、その効果を最大化するためには、設計段階で注意すべき重要なポイントも存在します。
①学習効果の向上
ゲーミフィケーションは、学習内容を長期記憶に定着させる上で非常に効果的です。
人が新しい情報を記憶する際、脳内の神経伝達物質「ドーパミン」が重要な役割を果たします。
目標を達成したり報酬を得たりすると放出されるドーパミンは、意欲を高め、記憶を強化する作用があることが知られています。
ゲーミフィケーション研修におけるポイント獲得やレベルアップといった仕組みは、このドーパミンサイクルを意図的に作り出し、学習内容を「覚えるべき情報」から「快感を伴う記憶」へと変化させるのです。
②エンゲージメント向上
研修に対する受講者の「やらされ感」を払拭し、高いエンゲージメントを生み出す点も大きなメリットです。
心理学者のミハイ・チクセントミハイが提唱した「フロー理論」によれば、人は自身のスキルレベルと課題の難易度が適度に釣り合った状態において、完全に集中し没入する「フロー状態」に入ります。
巧みに設計されたゲーミフィケーション研修は、徐々に難易度が上がるクエストなどを通じて、受講者をこのフロー状態へと自然に導きます。
その結果、「退屈な研修」から「時間を忘れて夢中になる体験」へと変わり、学習への主体性が劇的に向上します。
③ソフトスキルの醸成
コミュニケーション能力や問題解決能力といった、ビジネスに不可欠なソフトスキルは、知識として学ぶだけでは決して身につきません。
例えば、チームで課題解決に取り組むビジネスゲーム形式の研修では、参加者同士が自然な形で議論し、多様な意見を調整し、協力して意思決定を行うプロセスが求められます。
このような疑似的な業務体験は、座学では得られない実践的な学びの機会を提供し、リアルな状況で活かせるソフトスキルと強固なチームワークを効果的に育みます。
注意点:導入目的を間違えると「ただの遊び」で終わる可能性も
これら強力なメリットの一方で、導入には細心の注意が必要です。
最も多い失敗が、「ゲーミフィケーション」という手法の導入そのものが目的化してしまうケースです。
「楽しそうだから」「流行っているから」といった安易な導入は、一時的な盛り上がりで終わり、行動変容には繋がらない「ただの遊び」になってしまうリスクを孕んでいます。
結論として、ゲーミフィケーション研修の成功は、「誰の」「どのような行動を」「どう変えたいのか」という目的を明確に定義し、その目的達成の手段としてゲーム要素を戦略的に設計できるかにかかっているのです。
ゲーミフィケーション研修の活用事例
ここでは、代表的な3つの目的別に、どのような課題が解決されたのかを見ていきましょう。
【新人研修向け】早期離職を防ぎ、主体性を育む事例
新入社員研修における最大の課題は、企業理念の浸透と、同期との良好な関係構築による早期離職の防止です。
国内のある大手エンターテインメント企業では、自社の歴史や事業内容をテーマにしたビジネスゲームを新人研修に導入しました。
チームで協力してミッションに挑む中で、自然なコミュニケーションが生まれ、企業文化への理解が深まると同時に、同期との強固な絆が育まれています。
これにより、新入社員のエンゲージメント向上と定着率の改善に貢献しています。
【スキルアップ研修向け】複雑な知識・技術の習得を促す事例
専門的な知識や複雑なコンプライアンス規定を、効率的に、かつ確実に定着させることは多くの企業にとっての課題です。
世界的なコンサルティングファームであるデロイトでは、リーダーシップ開発のeラーニングにゲーミフィケーションを導入しました。
学習者はミッションをクリアするごとにバッジを獲得し、自身の進捗をSNS上で共有できる仕組みを取り入れたのです。
この仕組みが学習意欲を刺激し、学習プログラムの完了率が約50%向上したと報告されており、ゲーミフィケーションが自発的なスキル習得に非常に有効であることを示しています。
【管理職研修向け】リーダーシップや意思決定能力を養う事例
次世代リーダーに求められる戦略的思考や複雑な意思決定能力は、座学だけで養うことは困難です。
ある大手製造業では、管理職候補者向けに、市場の変化や競合の動きに対応しながら自社のリソースを最適配分する経営シミュレーション研修を実施しています。
参加者は、自身の意思決定が業績に直結する緊張感のある体験を通じて、大局的な視点とデータに基づいた戦略的意思決定のスキルを実践的に習得します。
これらの事例が示すように、ゲーミフィケーション研修は、各階層が抱える特有の課題に合わせて学習体験を設計することで、従来の研修では難しかった高い成果を生み出すポテンシャルを秘めているのです。
自社に合うのはどれ?研修タイプと思考整理の3ステップ
ゲーミフィケーション研修の効果を最大化するためには、まず自社の課題を正確に言語化し、その目的に合った最適な研修タイプを見極めることにあります。
ここでは、そのための思考整理に役立つ3つのステップを紹介します。
まずは研修の課題を言語化する
最初に、研修の目的を明確にするために、以下の3つの質問に具体的に答えてみましょう。
- WHO(対象は誰か?)
新入社員、中堅社員、管理職候補者など、研修の対象者を具体的に設定します。 - WHAT(何を学ぶか?)
研修を通じて、何を習得してほしいのか、企業理念の浸透、特定の製品知識、リーダーシップなど、学習目標を定義します。 - HOW(どう変わってほしいか?)
研修後、対象者の行動が具体的にどう変わってほしいのか、その変化を測定するための指標(KPI)も設定できると、より効果的です。
これらの問いへの答えが、後のステップでの重要な判断軸となります。
研修のタイプを知る(集合研修型、オンライン型、eラーニング型)
次に、ゲーミフィケーションを適用できる主な研修タイプの特徴を理解します。
- 集合研修型
参加者が一堂に会する対面形式。
一体感や熱量を醸成しやすく、複雑なビジネスゲームやチームビルディングに最適です。 - オンライン型
Zoomなどを活用し、リアルタイムで接続する形式。
物理的な制約がなく、全国の拠点を繋いだ研修が可能です。 - eラーニング型
個々人が好きな時間に学習を進める非同期形式。
知識のインプットや反復学習に強く、ゲーミフィケーション要素との親和性が非常に高いタイプです。
目的達成に最適なタイプを選ぶ
最後に、言語化した課題と各研修タイプの特徴を結びつけます。
例えば、「新入社員のチームビルディング(HOW)」が目的なら、一体感が生まれやすい「集合研修型」が最有力候補となるでしょう。
一方で、「全社員にコンプライアンス知識を定着させる(HOW)」のであれば、個人のペースで繰り返し学べる「eラーニング型」が最も効率的です。
このように、研修の目的を起点として論理的に選択肢を絞り込むことで、自社にとって本当に価値のあるゲーミフィケーション研修を設計することができます。
まとめ
いかがでしたでしょうか
本記事では、ゲーミフィケーション研修が現代の企業における人材育成の課題をいかに解決し得るか、その仕組みから具体的な導入ステップを解説しました。
ゲーミフィケーションは、人の「夢中になる力」を科学的に引き出し、Z世代の活躍推進やリモート環境下での組織力強化といった現代的な課題に効果を発揮します。
他社の成功事例は非常に魅力的ですが、その効果を最大化するためには、自社の課題を明確にし、適切な研修タイプを選び、戦略的なステップを踏んで導入することが不可欠です。
弊社では、法人向けのメタバースやXRコンテンツの開発を行っております。
ゲーミフィケーション要素を取り入れたコンテンツの開発も可能ですので、ご興味がある方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

学習意欲を引き出し、子どもが自ら学ぶメタバース×ゲーミフィケーションの教育!
メタバースを活用した学習メリットや『monoNITE』サービスの特徴をまとめた資料をご用意しました。

monoNITEサービス紹介資料の無料ダウンロードはこちら
資料をダウンロードする
 TWITTER
TWITTER
 FACEBOOK
FACEBOOK
 はてブ
はてブ