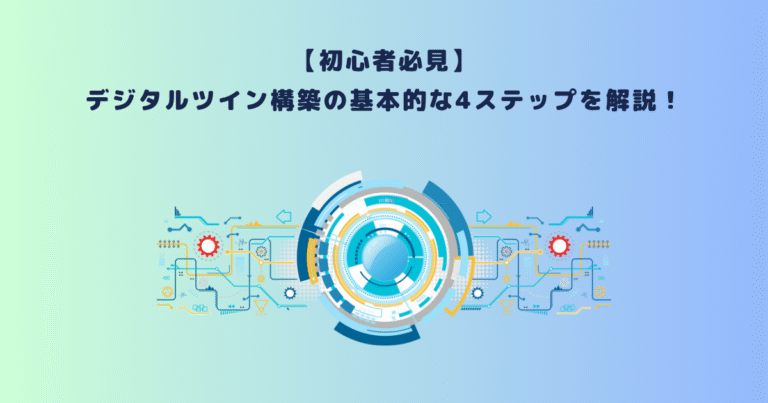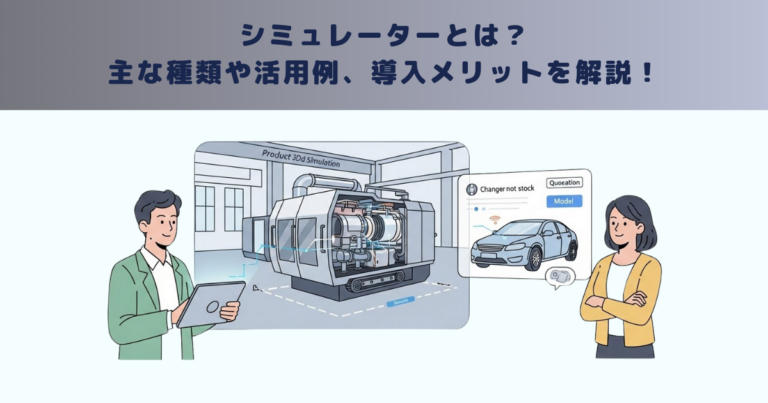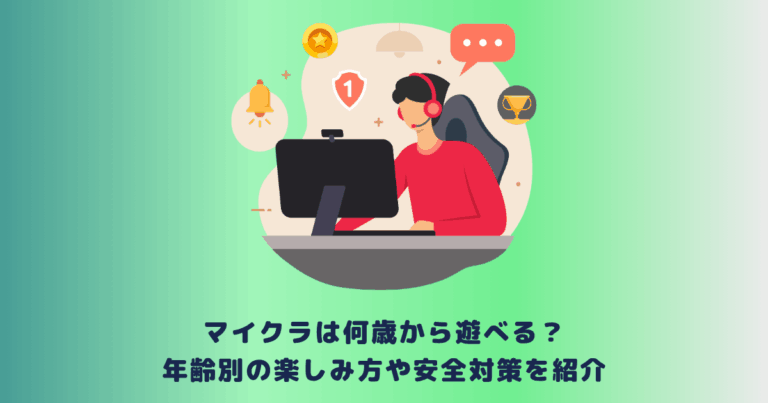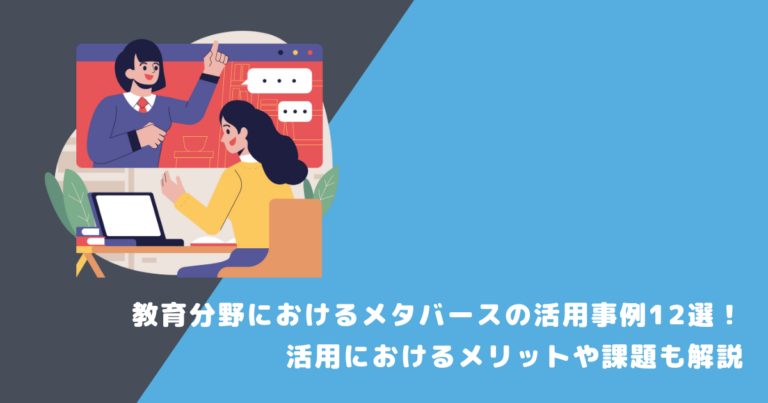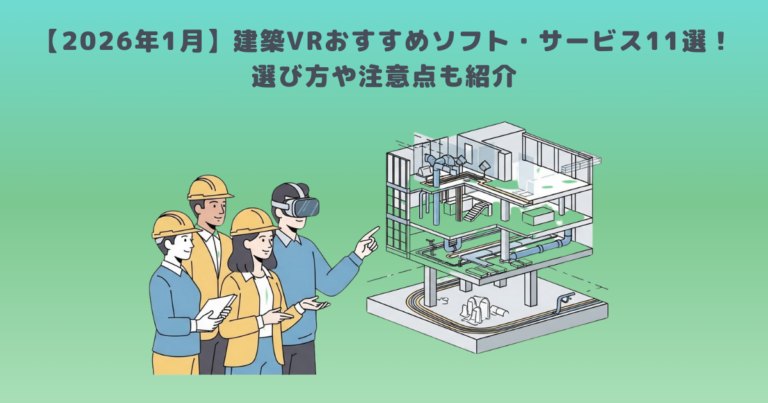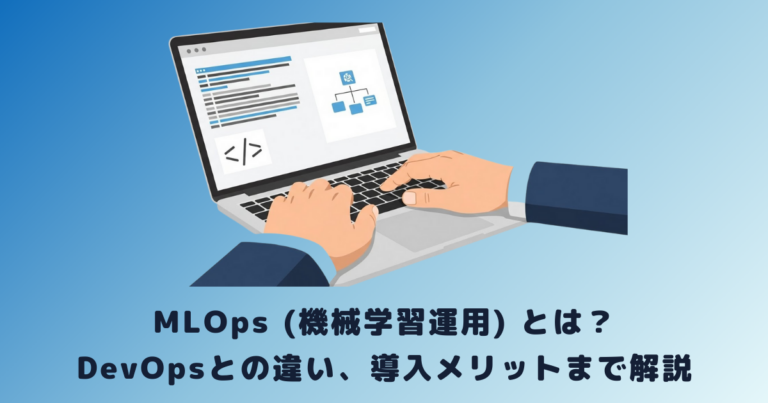デジタルツインという言葉をニュースや業界記事で目にする中で、技術の凄さに驚きつつも、具体的にどのようなステップで実現するのでしょうか。
「すごい技術だとは思うが、実際どうやって作るのか?」
「いきなり仮想空間を作るのか、それともデータ集めが先なのか?」
このように、導入までの具体的なステップがイメージできず、検討が進まないという方も多いかもしれません。
この記事では、デジタルツインが構築され、現場で活用されるまでの大まかなステップを、初心者の方にも分かりやすく4つのステップに分けて解説します。
製造・建設・物流業界の業務効率化と安全性を高める「デジタルツイン」
サービスの特徴や国内外の事例をまとめた資料をご用意しました。

デジタルツイン活用事例集の無料ダウンロードはこちら
資料をダウンロードする▼合わせて読みたいデジタルツイン関連記事


目次
そもそもデジタルツインとは?
本題のに入る前に、「そもそもデジタルツインとは何か」を簡潔に解説します。
デジタルツインとは、一言でいえば「現実世界から収集した様々な情報を、仮想空間上にそっくりそのまま再現する技術」のことです。
現実の工場、機械、設備、あるいは都市全体といった対象物と、瓜二つの「デジタルの双子」を仮想空間に構築するイメージです。
このデジタルツインの最大の特徴は、IoTセンサーなどを使って現実世界から「リアルタイムのデータ」を常に収集し続け、そのデータを仮想空間の双子に即座に反映させる点にあります。
従来のシミュレーションが「過去のデータ」や「仮の条件」に基づいて行われるのに対し、デジタルツインは「今、まさに現実で起きていること」とリアルタイムで同期する点で大きく異なります。
従って、デジタルツインには大きく3つのメリットがあります。
- 可視化(見える化)
遠隔地やオフィスのPCからでも、現場(例:工場)の稼働状況や進捗をリアルタイムかつ詳細に把握できます。 - シミュレーション(分析・予測)
「生産ラインの速度を変えたらどうなるか?」といった未来の予測や、「なぜ不良品が発生したか?」という過去の原因分析を、現実のラインを止めることなく仮想空間で安全に試すことができます。 - 最適化(制御)
シミュレーションで得られた最適な結果を、現実世界の機械や設備にフィードバックし、操作(制御)することも可能です。
では、どのようにデジタルツインの実現が進んでいくのか、基本的なステップを見ていきましょう。
デジタルツイン構築の基本的な4ステップ
デジタルツインの構築は、大きく分けて4つの基本的なステップで進められます。
具体的には、「①構想・計画」から始まり、「②データ収集」、「③モデル構築」、そして最後に「④連携・活用」へと続きます。
イメージがしにくいかもしれませんが、例えるならば家を建てる際の「設計図を描き、材料を集め、家を建て、住み始める」という流れに近しいでしょう。
それぞれ詳しく解説していきます。
ステップ1:構想・計画(何のために作るかを決める)
デジタルツイン構築の最初のステップは、技術的な作業ではなく、「構想・計画」です。
このステップが、プロジェクト全体の成否を左右する最も重要な分岐点となります。
デジタルツイン導入の「目的」を明確にする
まず行うべきは、「何のためにデジタルツインを導入するのか」という目的を徹底的に明確化することです。
なぜなら、この目的が曖昧なままでは、次のステップで「どのデータを集めるべきか」「どんな仮想モデルを作るべきか」が定まらないためです。
例えば、「競合が導入したから」といった漠然とした理由ではなく、「特定の製造ラインの不良品発生原因を特定し、不良率を〇%改善する」「熟練技術者の暗黙知となっている作業を可視化し、教育時間を〇%短縮する」といった、具体的かつ測定可能な目的を設定する必要があります。
この「目的の明確化」こそが、プロジェクトの方向性となります。
対象範囲を絞り「スモールスタート」で計画する
目的が明確になったら、次に対象範囲を絞り込み、「スモールスタート」で計画を立てます。
いきなり工場全体や全社規模での導入を目指すと、膨大なコストと時間がかかるだけでなく、課題に直面した際の軌道修正が困難になるためです。
まずは目的を達成できる最小限の範囲、例えば「特定の製造ライン1本」や「特に故障が頻発している設備1基」などに限定してPoC(概念実証)を行います。
小さく始めることで、初期投資を抑えつつ、デジタルツイン導入の効果と技術的な課題を素早く検証できます。
ステップ2:データ収集(現実世界の情報を集める)
構想・計画が固まった次のステップは、デジタルツインの材料となる現実世界の情報を集める「データ収集」です。
このステップは、ステップ1で定めた目的を達成するために必要な情報を、デジタルデータとして正確に取得することに主眼が置かれます。
必要なデータを選び、IoTセンサーなどで収集する
まず、ステップ1で明確化した「目的」に基づき、収集すべきデータを具体的に特定します。
なぜなら、目的と無関係なデータを闇雲に集めても、コストがかかるだけでノイズになってしまうためです。
例えば、「設備の故障予知」が目的ならば、その設備の「振動」「温度」「稼働音」「電力消費量」などのデータが必要になります。
「生産ラインの効率化」が目的なら、「各工程のタクトタイム」「設備の稼働・停止状況」「作業員の位置情報」などが対象となるでしょう。
これらのデータを収集する具体的な手段として、IoT(モノのインターネット)センサーやカメラを新たに取り付けたり、既存のPLC(Programmable Logic Controller)や生産管理システム(MES)からデータを抽出したりします。
集めたデータを蓄積・処理する基盤(プラットフォーム)を整える
次に、収集した膨大なデータを安全に蓄積し、高速に処理するための基盤を整えます。
IoTセンサーなどからはリアルタイムで膨大なデータ(ビッグデータ)が絶え間なく送られてくるため、それらを確実に受け止め、後続の分析や可視化に使える形で保存する「器」が必要になるからです。
一般的には、拡張性や柔軟性に優れたクラウドサービス(AWS、Microsoft Azure、Google Cloudなど)上に、データレイクやデータウェアハウスといったデータ基盤を構築するケースが多く見られます。
ステップ3:モデル構築(仮想空間に「双子」を作る)
データ収集の仕組みが整ったステップ3では、それらのデータを反映させる「器」として、仮想空間に現実世界の「双子」となるモデルを構築します。
このステップは、収集した数値やテキストデータだけでは直感的に把握しにくい現実世界の状況を、誰もが視覚的に理解できる形に変換するために不可欠です。
現実を再現する3Dモデルを作成する
まず、デジタルツインの「見た目」となる3Dモデルを作成します。
これは、仮想空間に、現実の工場、設備、機械、あるいは都市といった対象物の「形状」を忠実に再現するためです。
具体的な方法としては、設計時に作成されたCADデータやBIMデータを活用するほか、3Dレーザースキャナーやドローン搭載のカメラで現実の対象物をスキャンし、その点群データなどから3Dモデルを生成します。
この「形」の正確な再現が、後のシミュレーションや直感的な状況把握の土台となります。
ステップ2の「データ」と連携させ、動きを再現する仕組みを作る
次に、作成した静的な3Dモデルと、ステップ2で収集し続けているリアルタイムの「データ(状態)」を連携させる仕組みを構築します。
なぜなら、見た目がそっくりなだけの3Dモデルでは、現実世界の「今」の動きや変化を反映できず、デジタルツインとは言えないためです。
例えば、工場の3Dモデルに対し、「設備の稼働データ(ON/OFF)」「温度センサーのデータ(数値)」「コンベア上の製品の位置情報」などを紐付けます。
これにより、現実の機械が停止すれば仮想空間のモデルも色を変えて停止し、現実の温度が上昇すればモデル上のグラフが変動するなど、現実と仮想空間が同期して「動く」状態が初めて完成します。
ステップ4:連携・活用(シミュレーションとXRによる可視化)
最後のステップは、構築したデジタルツインを現実世界と連携させ、実際に「活用」するフェーズです。
このステップこそが、デジタルツインを導入する本来の目的であり、業務改善や意思決定の質を向上させる価値が生まれる瞬間です。
現実と仮想空間をリアルタイムで連携させ、シミュレーションを実行する
まず、ステップ2で収集したリアルタイムデータと、ステップ3で構築した仮想モデルを常時同期させます。
これにより、現実世界で起きている変化(例:設備の稼働、ラインの停止、温度の変化)が、即座に仮想空間の双子に反映される状態が完成します。
このリアルタイム連携の最大のメリットは、シミュレーションが可能になることです。
例えば、仮想空間上で「もし、このラインの速度を10%上げたらどうなるか?」「もし、この部品の材質を変えたら耐久性は?」といった”What-if”(もし〜したら)のシナリオを、現実の工場を止めることなく安全に試すことができます。
また、蓄積したデータから異常の兆候をAIが検知し、仮想空間上で「3日後にこのモーターが故障する可能性が高い」といった未来予測を行うことも可能になります。
このように、現実と連携したシミュレーションの実行が、デジタルツイン活用の核となります。
XR(VR/AR)技術を用いた活用例
デジタルツインで得られたシミュレーション結果やリアルタイムの稼働状況は、PCのモニター上でグラフや数値として確認するだけではありません。
例えば、VR(仮想現実)やAR(拡張現実)のようなXR技術と組み合わせることで、データをより直感的に「体験」できるようになります。
具体的な活用例としては、以下のようなものがあります。
- VR(仮想現実)による活用
VRゴーグルを装着し、仮想空間(デジタルツイン)の工場内を自由に歩き回ることができます。
遠隔地にいながら、まるで現場にいるかのように設備の稼働状況を確認したり、新設ラインのレイアウトをシミュレーションし、作業動線に無理がないかを「体験」したりすることが可能です。 - AR(拡張現実)による活用
現実の機械設備にスマートフォンやARグラスをかざすと、その機械のデジタルツイン情報(現在の温度、稼働率、過去のメンテナンス履歴、故障予測など)が、現実の映像に重ねて(拡張して)表示されます。
これにより、作業員は目の前の機器の「見えない情報」を直感的に把握できます。
このように、ステップ4ではデジタルツインを動かし、XRのような最新技術でその価値を最大化することで、初めて「構想・計画」段階で設定した目的の達成へと繋がります。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
デジタルツインの導入を成功させるためには、その構築ステップ(全体像)を正しく理解することが不可欠です。
本記事で解説したように、デジタルツインの構築は「①構想・計画」「②データ収集」「③モデル構築」「④連携・活用」という4つのステップを順番に踏んで進められます。
いきなり高度な3Dモデル作成やXR技術(VR/AR)の導入を考えるのではなく、まずは「何(どの課題)を解決したいのか」という目的(ステップ1)を明確にすることが、プロジェクトの成否を分ける最も重要なポイントです。
この全体像とステップを把握することで、自社が今どの段階にいるのか、次に何をすべきか、どの部分にリソースを割くべきかが見えてきます。
弊社では、メタバースやXR技術を活用したデジタルツインの開発も行っております。
PoCやシミュレーションなど、デジタルツインにご興味がある方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。
製造・建設・物流業界の業務効率化と安全性を高める「デジタルツイン」
サービスの特徴や国内外の事例をまとめた資料をご用意しました。

デジタルツイン活用事例集の無料ダウンロードはこちら
資料をダウンロードする
 TWITTER
TWITTER
 FACEBOOK
FACEBOOK
 はてブ
はてブ