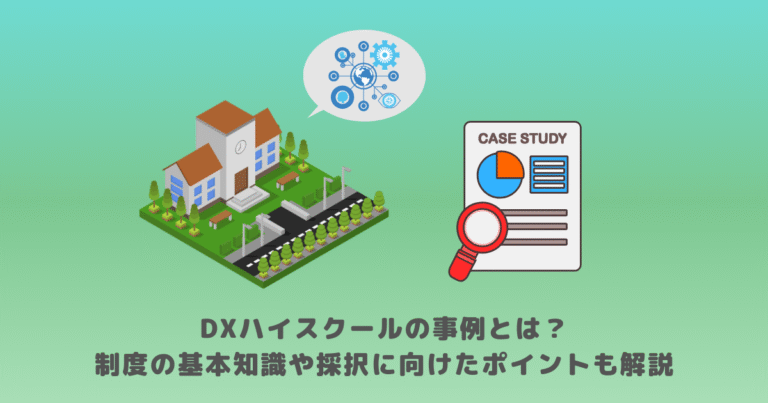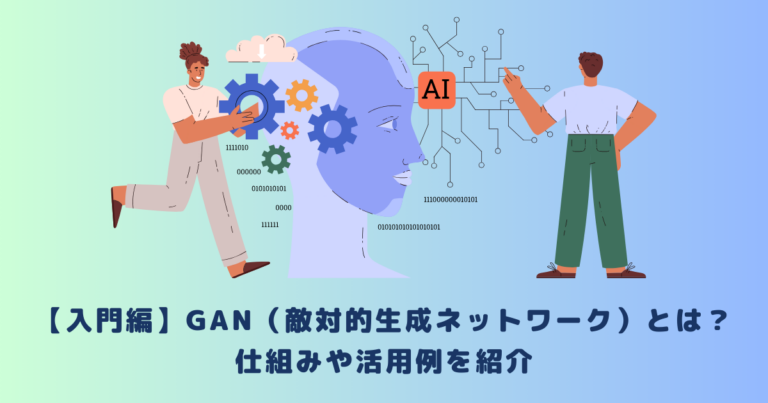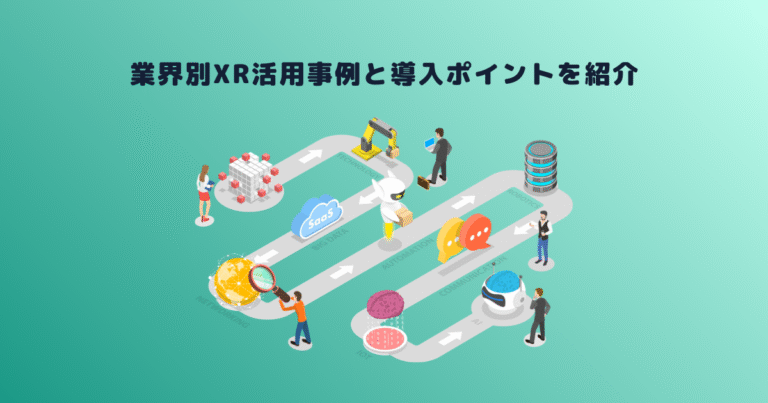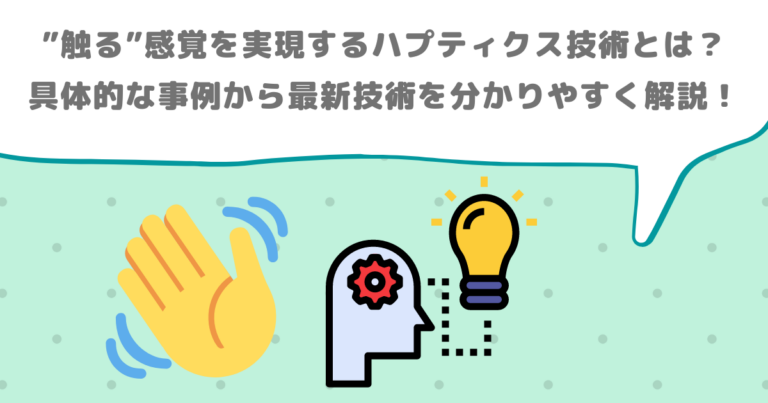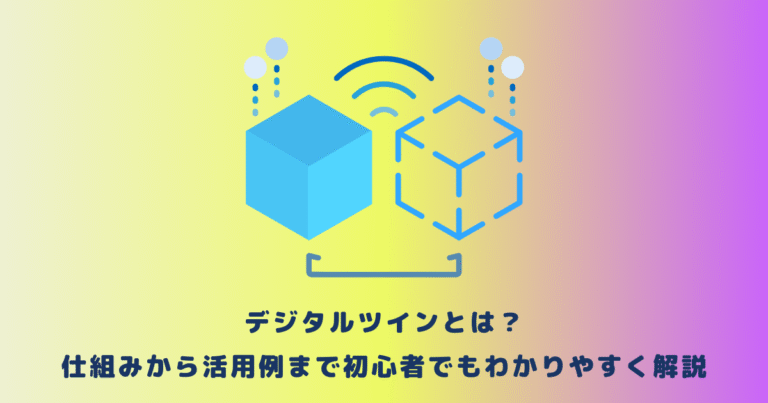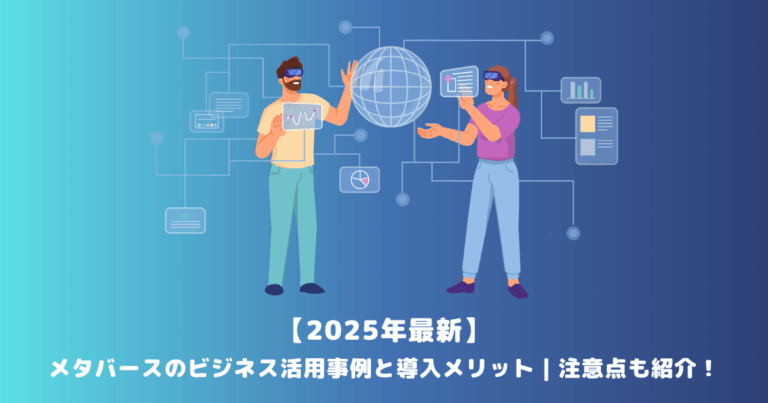「DXハイスクールの活用に興味があるが、具体的にどんな機材を導入し、どのような授業を計画すればよいのか分からない」と悩んではいませんか。
他校の先進的な取り組みを調べても、高度な研究事例ばかりが目につき、自校のレベルで実現できるのか不安を感じている教員の方も少なくありません。
本記事では、文部科学省が公開している資料の中から、公立・私立を問わず明日から真似できるDXハイスクールの採択事例を踏まえて、解説します。
学習意欲を引き出し、子どもが自ら学ぶメタバース×ゲーミフィケーションの教育!
メタバースを活用した学習メリットや『monoNITE』サービスの特徴をまとめた資料をご用意しました。

monoNITEサービス紹介資料の無料ダウンロードはこちら
資料をダウンロードするDXハイスクールとはどんな制度?
DXハイスクール(高等学校DX加速化推進事業)は、高校段階でのデジタル人材育成を加速させる文部科学省の支援制度です。
1校あたり1,000万円を上限に補助し、ハイスペックPCなどのICT環境整備と、情報Ⅱや探究学習といったカリキュラムの高度化を支援します。
一部の進学校に限らず、全国の高校のデジタル環境を底上げすることを目的としています。
SSH(スーパーサイエンスハイスクール)とは違う「底上げ」の目的
教育現場でよく比較されるのが、長年にわたり実施されている「スーパーサイエンスハイスクール(SSH)」です。
SSHは、科学技術や理数系教育に特化した研究開発を行う学校を指定するもので、求められる成果やカリキュラムの専門性は非常に高く設定されています。
一方で、DXハイスクール(高等学校DX加速化推進事業)は、その名の通り「加速化」を目的としており、これからデジタル教育を本格化させたい学校を支援する制度です。
つまり、現時点で高度な実績がなくても、「これから環境を整えて、生徒に新しい学びを提供したい」という明確なビジョンと計画があれば、採択される可能性はあります。
【実例】採択校はどう活用している?3つの事例を紹介
ここでは、公立・私立、普通科・専門学科という異なる背景を持つ3つの学校の実例を紐解き、明日から真似できるモデルケースとして紹介します。
埼玉県立飯能高校:デジタル顕微鏡×生成AIで「生物」と「情報」を連携
公立・普通科である埼玉県立飯能高等学校の事例は、既存の教科指導をベースにした「教科横断型」の取り組みとして非常に参考になります 。
同校では、生物の授業と「情報Ⅱ」の授業を連携させ、デジタルデータを活用した探究活動を実施しています 。
導入した主な機材は「デジタル顕微鏡」「プロジェクター」「電子黒板」といった、理科教育のICT化に直結するものです 。
具体的な授業の流れとしては、まず生物の授業で生徒がデジタル顕微鏡を使用し、細胞分裂の様子などを高解像度の画像データとして取得します 。
次に、「情報Ⅱ」を選択している生徒たちが、その画像データを受け取り、生成AIや画像解析プログラムを用いて、細胞周期の分類や特徴抽出といった分析を行います 。
これにより、生物選択者は感覚的な観察から脱却してデータを扱う重要性を学び、情報選択者はプログラミングが実社会(研究)でどう役立つかを体験できます 。
特別な新設科目を立ち上げずとも、既存の機材をデジタル化し、教員間で連携するだけで高度なDX教育が実現できるという、導入ハードルの低い事例です。
富士見丘中学高等学校:3Dプリンタ×メタバースで「探究学習」を高度化
私立の女子校である富士見丘中学高等学校では、「情報技術を知り、社会実装を考える」をテーマに、ものづくりと仮想空間を組み合わせた先進的なカリキュラムを展開しています 。
同校が補助金で導入したのは、「3Dプリンタ」「3D制作物生成用のノートPC」といったハードウェアに加え、脳波計などの生体計測機器も含まれています 。
特筆すべきは、生成AIで作成したデザインをCADに取り込み、実際に3Dプリンタで出力するという「AI×モノづくり」の実践です 。
生徒はプロンプトエンジニアリング(AIへの指示出し)を学びながら、データが物理的なモノになるプロセスを体験します 。
また、「メタバースコミュニケーションとエンジニアリング」という講座も設けられており、アバターを用いたコミュニケーションの課題解決や、独自ワールドの設計に取り組んでいます 。
さらに、脳波計を用いた「ニューロフィードバック」の体験など、生徒の興味を惹きつける先端技術を積極的に取り入れている点も特徴です 。
山形県立酒田光陵高校:モーションキャプチャ導入で「地域のSTEAM拠点」へ
工業科や情報科を有する山形県立酒田光陵高等学校は、専門学科の強みを活かし、地域全体を巻き込んだ「STEAM教育の拠点化」を目指しています 。
同校が整備したのは、3Dプリンタやレーザーカッターを備えた「デジタルファブリケーションルーム」と、本格的な動画配信が可能な「スタジオ環境」です 。
特にスタジオには「モーションキャプチャ」「カメラ」「スイッチャー」「グリーンバック」といったプロ仕様の機材が導入されています 。
これらの設備は、校内の授業だけでなく、地域の小中学生を対象とした「デジタル教室」や「プログラミングラボ」としても開放されています 。
高校生が学んだ技術を活かして小中学生に教えるという循環を作ることで、地域全体のデジタルリテラシー向上に貢献しています 。
申請書において「地域連携」や「社会貢献」は大きな加点要素となります。
自校の生徒だけでなく、地域の教育資源として機材を活用するという視点は、採択を勝ち取るための強力な武器となるでしょう。
「課題別」の推奨機材パターン
ここでは、多くの学校現場が抱えている共通の悩み別に、それを解消するための推奨機材パターンを紹介します。
事例校の要素を上手く組み合わせることで、自校の弱点を補い、強みに変えるための投資計画が見えてくるはずです。
課題A「理科室や実験設備が古い・足りない」→ VRゴーグルで仮想実験
都市部の学校や設立の古い学校では、理科室の数が足りなかったり、設備が老朽化していたりと、物理的な環境制約が探究学習の足かせになることがあります。
こうした課題を抱えている場合に最も有効なのが、「VR(仮想現実)ゴーグル」を中心とした仮想実験環境の整備です。
例えば、危険を伴う化学反応の実験や、高価な実験器具が必要な物理実験も、VR空間内であれば安全かつ低コストで何度でも実施可能です。
先ほどの富士見丘中学高等学校の事例でも、メタバース空間の活用が挙げられていましたが 、これを理数教育に応用する考え方です。
物理的な実験室を増築するには莫大な費用と工期がかかりますが、VRゴーグルであれば教室の片隅や空き教室を「無限の実験室」に変えることができます。
機材選定の際は、スタンドアローン型(PC不要)のVRゴーグルだけでなく、より高度な処理が可能なPC接続型のハイエンドモデルを数台混ぜておくと、将来的なコンテンツ制作にも対応できるためおすすめです。
課題B「情報科の専門教員が不足している」→ 遠隔講義システム・生成AI
「情報Ⅱ」や「データサイエンス」を教えられる専門的な教員がいないことは、多くの学校にとって切実な悩みです。
この課題を「教員の採用」だけで解決しようとせず、「テクノロジー」で補完する視点が重要です。
推奨されるのは、外部の専門家を教室に呼び込むための「遠隔講義システム」の整備です。
具体的には、教室の四隅に配置する高音質スピーカー、講師の表情を等身大で映し出す大型電子黒板、そして教室全体の様子を配信するための自動追尾カメラなどが挙げられます。
実際、埼玉県立飯能高校では早稲田大学の教員を招いたり 、山形県立酒田光陵高校ではAIエンジニアと連携したり と、外部リソースを積極的に活用しています。
また、教員の補助役として「生成AI」を活用できる環境(有料版アカウントの契約など)を整えることも有効です。
富士見丘中学高等学校のように、生成AIの特性やプロンプトエンジニアリング自体を学ぶ対象とすることで 、教員が一方的に教えるのではなく、生徒と共に学ぶスタイルへと授業を変革できます。
課題C「生徒のモチベーションが低い」→ ゲーミングPC・メタバース制作
「せっかく機材を導入しても、生徒が興味を持ってくれるか不安だ」という悩みもよく聞かれます。
生徒の能動的な学び(アクティブラーニング)を引き出すための最も強力なフックは、「楽しそう」「かっこいい」という直感的な感情です。
そこで推奨されるのが、いわゆる「ゲーミングPC」スペックのハイスペック端末と、それを活用した「メタバース制作」や「動画編集」の環境整備です。
山形県立酒田光陵高校がスタジオやモーションキャプチャを導入したように 、クリエイティブな機材は生徒の創作意欲を強く刺激します。
単にエクセルやワードを学ぶためのPCではなく、3Dグラフィックスをグリグリ動かせる環境を用意することで、生徒は遊びの延長線上で3Dモデリングやプログラミングに没頭し始めます。
eスポーツ部での活用や、文化祭でのメタバース展示など、生徒自身が主役になれる出口(発表の場)を用意しやすいのも、このパターンの大きなメリットです。
外部企業との連携の進め方
DXハイスクールの採択要件には「外部機関(企業や大学)との連携」が含まれていますが、この項目に戸惑ってしまうケースもありがちです。
文部科学省の事例を見ても、必ずしも契約書を交わすような腰の重い提携ばかりではなく、より実務的な連携が認められていることが分かります。
ここでは、外部企業との連携事例の作り方を解説します。
地元企業や大学と連携する「探究学習」のモデルケース
最も王道かつ採択されやすいのは、探究学習のプロセスの一部に外部の専門家を招き入れるパターンです。
例えば、埼玉県立飯能高等学校では、早稲田大学の教員や学生を講師として招き、生徒が立てた仮説に対してフィードバックをもらうという連携を行っています 。
また、山形県立酒田光陵高等学校では、夏休みに「データサイエンスサマーキャンプ」を実施し、スタートアップ企業のエンジニアから直接指導を受ける機会を設けています 。
このように、通年での連携が難しくても、「スポット(単発)の特別講義」や「夏休みの集中講座」であれば、依頼のハードルはぐっと下がります。
申請書には、「○○大学の准教授を招聘し、年○回の特別講義を実施する」「地元のIT企業××社によるプログラミング実習を行う」といった具体的な固有名詞と頻度を記載することで、実現可能性が高い計画として評価されます。
地元の大学や商工会議所に相談し、「生徒に話をしてくれる大人」を探すところから始めてみてください。
企業のプラットフォーム(XRクラウド等)を活用した手軽な連携
もし、近くに連携できそうな大学や企業が見つからない場合は、教育ソリューションを提供している企業の「プログラム」を活用するのも一つの手です。
実際に富士見丘中学高等学校の事例では、大手印刷会社(DNP)が提供するオンライン講座や対面講座をカリキュラムに組み込み、生成AIや3Dプリンタの技術指導を受けています 。
また、飯能高等学校でも、ソフトバンク株式会社による「生成AI使用に関するガイダンス」を実施するなど、企業のパッケージ化された教育プログラムをうまく活用しています 。
これは、XR(VR/メタバース)分野においても同様のことが言えます。
例えば、私たちが提供しているような「XRプラットフォーム」を導入し、その運用サポートや出張授業を企業に依頼することも、立派な「企業連携」の一つです。
「株式会社〇〇が提供するメタバースプラットフォームを活用し、技術指導および空間設計の助言を受ける」と申請書に記載すれば、それは単なる物品購入を超えた、教育的な連携体制として認められます。
「連携先を一から開拓する」のではなく、「教育サービスを提供しているパートナー企業と組む」という発想転換が、採択への近道となるでしょう。
まとめ
本記事では、文部科学省の公開資料に基づき、DXハイスクールの具体的な採択事例を紹介してきました。
最後に、これから申請準備を始める先生方に強くお伝えしたいのは、「独自性にこだわりすぎる必要はない」ということです。
これまでの教育現場では「本校独自の取り組み」が重視されがちでしたが、DXハイスクールにおいては、まず「環境を整えること」が最優先です。
成功している学校の事例(モデル)を素直に「模倣(TTP:徹底的にパクる)」し、そこに自校の生徒の実情に合わせて少しアレンジを加える。 これこそが、最短距離で採択を勝ち取り、かつ失敗のリスクを最小限に抑える賢い戦略です。
学習意欲を引き出し、子どもが自ら学ぶメタバース×ゲーミフィケーションの教育!
メタバースを活用した学習メリットや『monoNITE』サービスの特徴をまとめた資料をご用意しました。

monoNITEサービス紹介資料の無料ダウンロードはこちら
資料をダウンロードする
 TWITTER
TWITTER
 FACEBOOK
FACEBOOK
 はてブ
はてブ