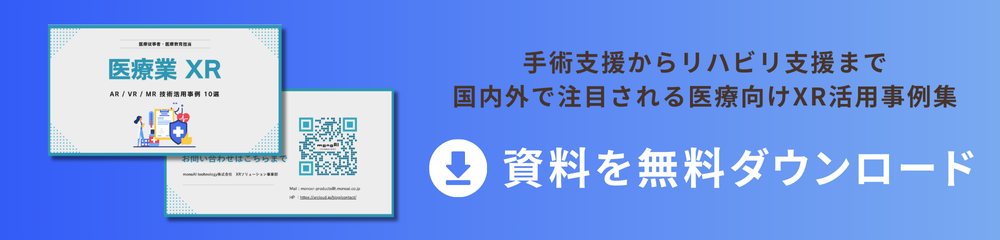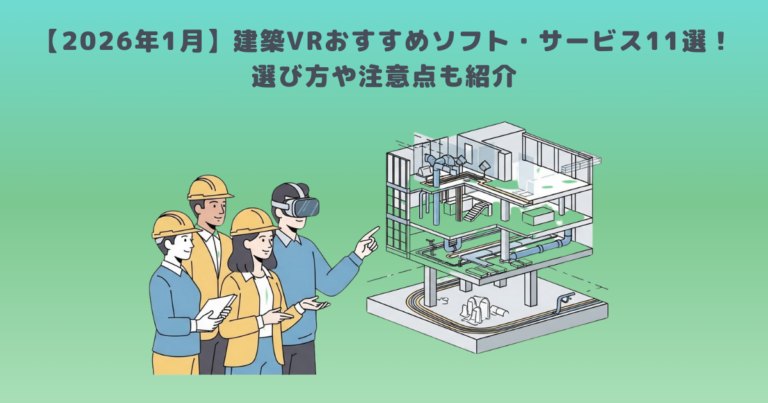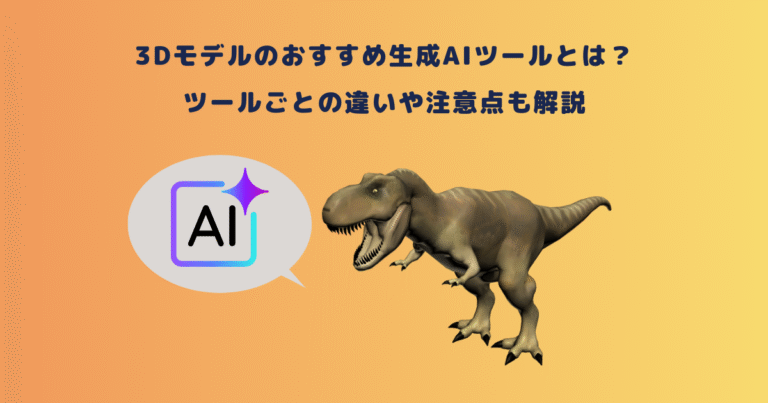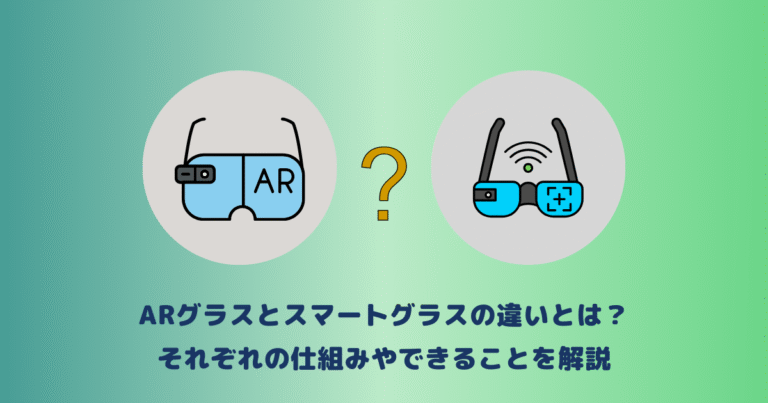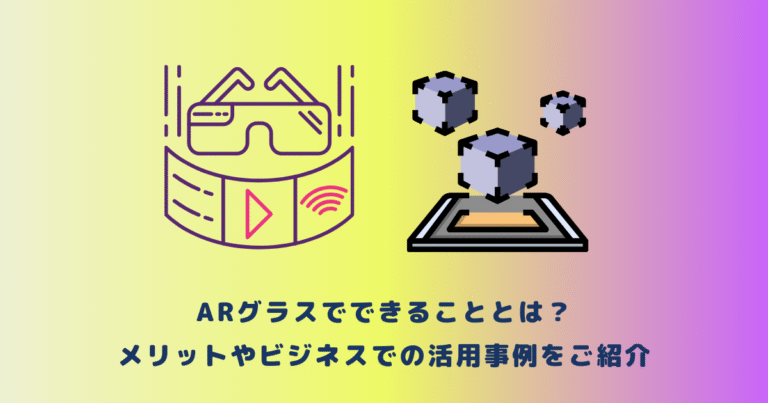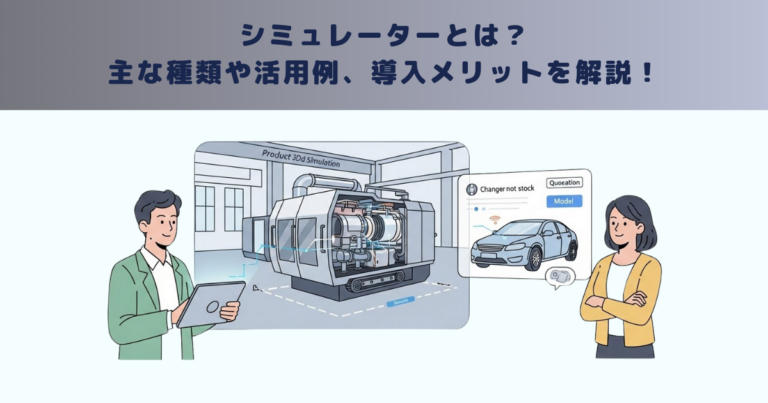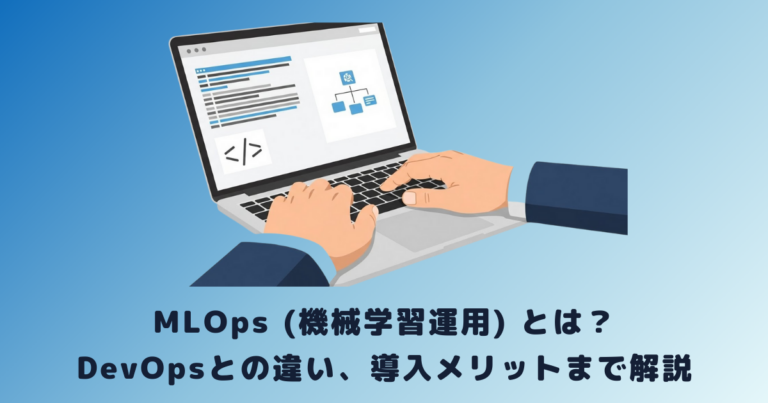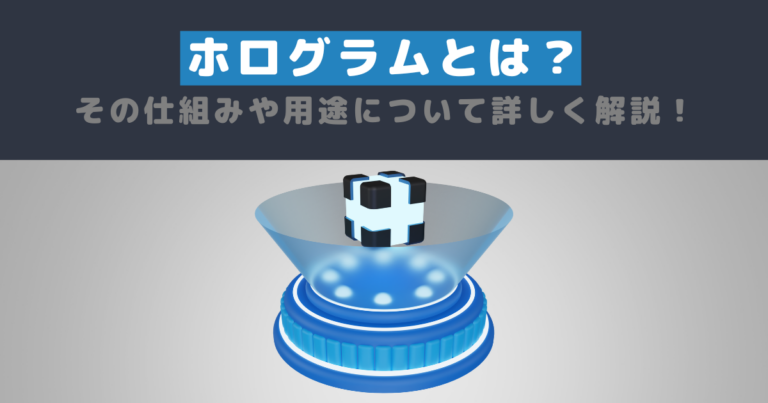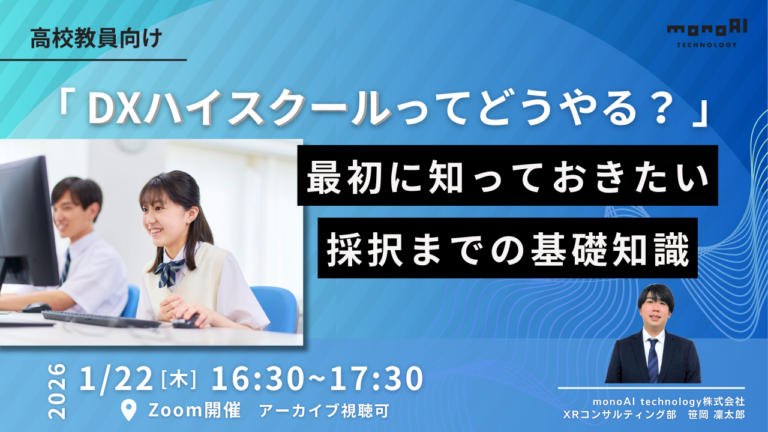昨今のARやVR技術の浸透に伴い、これらの技術はゲームなどのエンタメ領域のようなToC向けから、医療、製造、建設などToB向けの分野まで様々に活用されています。
本記事では、AR/VR技術の基本的な解説から、ARやVRが実際の医療現場でどのように活用されているかを、今後の展望も含めて詳しく解説しています。
この記事を読んで頂ければ、AR・VRがどのように医療現場で利用されているのかを、すぐに理解することができます。
専門知識のない方でも気軽に読める内容ですので、ぜひ最後までご覧ください。

目次
|そもそもARやVRとは?違いも解説
ARとVRは似たような意味合いで解釈されがちですが、それぞれ意味が違います。
AR技術とは
ARとは、「Augmented Reality(アグメンティッド・リアリティ)」の略語で、一般的に「拡張現実」といわれています。
そしてAR技術の中でも、以下の種類が存在しています。
ロケーションベースAR(位置情報)
ロケーションベースとは、デバイスに内蔵されているGPSの位置情報を基に、様々なセンサーを用いてデジタル情報を表示させる仕組みです。
代表的なもので言えば、「ポケモンGO」のゲームがイメージしやすいでしょう。
ポケモンGOは、スマホを通して特定の位置をカメラで表示すると、まるで自分の前に本物のポケモンが出現したような認識を与えてくれます。
ビジョンベースAR(マーカー型・マーカーレス型)
ビジョンベースとは、現実世界に配置される図形(マーカー)をデバイスのカメラで読み取ったり、実際の風景を空間認識して、特定の場所にデジタル情報を表示させる仕組みです。
マーカー型であれば作品や商品にデザインされたQRコードで読み込ませるものや、マーカーレス型であればAmazonの配置レビュー機能などが、代表的な例です。
このように、スマホのようなデバイスを通じてデジタル情報を現実世界に付加する技術をARといいます。

VR技術とは
対してVRとは、「Virtual Reality(バーチャル・リアリティ)」の略語で、一般的に「仮想現実」といわれています。
現在のVRの一般的な体験方法は、VRゴーグルといった専用のデバイスを装着することです。
VRゴーグルの中では、人間の視覚を応用した360度の映像と立体音響によって、現実世界にいるにも関わらず、あたかも別世界に来たかのような仮想空間体験をすることができます。
専用のVRゴーグルを通して、実際に仮想空間に存在しているような認識をもたらすことのできる技術をVRといいます。

|医療現場におけるAR/VR技術の活用メリット
拡張現実や仮想現実を体験できるAR/VR技術ですが、医療分野ではどういったメリットがあるのでしょうか。
その主なメリットは以下になります。
診察・診断のサポートによる遠隔治療の精度向上
画像認識の技術を応用し、患者の患部をARやVRを活用して診察することで、遠隔からでも診断が可能になります。
また、より遠隔地にいる専門医から、医療行為をリアルタイムでサポートしたりすることも可能です。
医療従事者の教育・研修の質向上
様々な医療機器の取り扱いや治療方法、患者対応が求められる中で、ARやVR技術でのマニュアルの可視化は非常に有効です。
複雑な手順や何度も試せない演習をシュミレーションとして視覚的に学習できるのは、AR/VRならではのメリットでしょう。
リハビリの効果上昇
ARやVRといった技術は、ゲームのようなエンタメ領域でも幅広く活用されており、そのゲーミフィケーション要素をリハビリにも活用することが可能です。
単調になりがちなリハビリプログラムも、ARやVRを活用することでゲーミフィケーション要素を加え、患者のモチベーションアップに寄与できるでしょう。
|医療現場におけるAR/VR技術活用シーン
実際の医療現場では、現在どのようなことにARやVR技術が使われているのでしょうか。
ここでは、実際の医療現場で使用されている具体例を7つ厳選して紹介します。
VR技術の活用例
リハビリ
1つ目の使用例は、VRを活用したリハビリです。
具体的には、VRゴーグルのようなHMD(ヘッドマウントディスプレイ)を患者が装着することで、患者のリハビリに適したバーチャル空間でリハビリを行います。
これにより、施設までいくのが大変なお年寄りでも、自宅でリハビリを行うことが可能になります。
その他にも、今までのリハビリ情報を数値に可視化して効率的にリハビリが行えたり、同じことの繰り返しで退屈に感じるリハビリに、ゲーム要素を追加することで、リハビリを楽しく行うことも可能になっています。
高齢化に歯止めがきかない日本にとっては、今後も研究が期待されている分野といえます。
医療研修・教育
2つ目の使用例は、VRを活用した医療研修です。
例えば、バーチャル空間で人間の心臓や脳を正確に映し出すことが可能になれば、現実の心臓や脳を実際に触らずとも、細かい血管や作りを肌で感じることができます。
医師を志す人にとって、実際の心臓や脳をみて触れる機会は非常に貴重な機会です。
ですが、授業の中でそのようなカリキュラムを組み込むことは、容易なことではありませんでした。
VR技術を活用することで、医師にとって重要な「本物を触って学習する」機会を増やし、医師の全体的な技術面の向上を図ることが可能になります。
現在も、IT大国アメリカが主導する形で、この分野の研究が進められています。
精神疾患への治療補助
3つ目の使用例は、VRを活用した精神疾患に対する治療補助です。
例えば、コミュニケーションや言語の発達に難があり、行動や興味に偏りが生じてしまう「自閉症(自閉スペクトラム症) 」の患者に向けた「Floreo(フロレオ)」というVRアプリがあります。
このアプリは、自閉症の患者に興味を持ってもらえるようなポップな世界観が、バーチャル空間上で表現されています。
患者は、このバーチャル空間をゲーム感覚で遊ぶことで、人とのコミュニケーションの仕方や言語の使い方を効率的に学ぶことができます。
患者がみている映像を、タブレット端末を通して親御さんや医師が確認することもでき、バーチャル空間上でコミュニケーションをとることも可能です。
もちろん、アスペルガー症候群や広汎性発達障害の方達にも、Floreoの効果は期待できます。
Floreoだけでなく、他にも多くのアプリが現在開発されており、今まで専門的な知識と経験が必要だった精神治療の分野にとって、まさに希望の光といえる技術といえます。
AR技術の活用例
遠隔医療
4つ目は、ARを活用した遠隔医療です。
従来までの遠隔医療では、通信速度が遅すぎて患者の急激な容体の変化に対応することが難しく、カメラを通して医療行為を行わなければならなかったため、実用性に乏しいとされていました。
しかし、5G回線とAR技術の革新により、それらの問題が解消される可能性が出てきています。
例えば、NECソリューションイノベータ社が発表した「電子聴診器とスマートグラスを用いた遠隔診療ソリューション」があります。
これは、患者の元を訪れた看護師がスマートグラスを装着して、電子聴診器で患者を聴診します。
同時に、遠方の医師がカメラを確認しながらヘッドホンで心音や呼吸音を聞き取ることで、患者の元にいなくとも診察を可能にしています。
遠隔医療が他国よりも必要とされている日本を中心に、研究開発が活発化している分野です。
高精度な画像診断
5つ目は、ARを活用した画像診断です。
画像を使った診断は、MRIやレントゲンなどに代表されるように、以前から一般的に普及していましたが、検査で得られる画像を理解するには、その画像をもとに医師の脳内で構造を組み立てる必要がありました。
その作業をAR技術が補うことで、より正確な診断を行うことが可能になり、誤診の可能性を飛躍的に少なくすることが期待されています。
代表的なものとして、カナダのアルバータ大学の研究チームが開発した「ProjectDR」があります。
ProjectDRは、MRIやレントゲンで撮影した画像データを、患者本人の体に投影し、専用のスマートグラスを装着することで、医師の作業を支援することができるデバイスです。
このように、ARを利用した画像診断を利用することで、医療行為がより正確になり、医師の負担を和らげることができます。
3D解剖モデルを用いた研修
6つ目は、ARを活用した3D解剖モデルによる研修です。
前項で少し触れましたが、医師の研修に必要な解剖には、実際に人間の器官を用意する必要があります。
従来では、頻繁に行うことのできなかった解剖も、ARを活用した3D解剖モデルが登場したことで、その問題を解消することができます。
例えば、VISIBLE BODY社が提供する「ヒューマン・アナトミー・アトラス」は、人体における主要な臓器を、男女の違いも明確に3Dモデルで確認できる学習ツールです。
今まで本や映像でしか確認できなかった人体の複雑な構造を、AR技術を利用した3Dモデルをデバイス上に投影することで、より本質的な理解を可能にしています。
手術のサポート
7つ目は、ARを活用した手術です。
従来の手術は、当然のことですが、手術の前に患者の身体の中を実際に目視することは不可能でした。
しかし、AR技術を活用すれば、手術前に患者の体の中を立体的にシミュレートすることができ、手術の精度を大幅に向上させることができます。
実際の医療現場でも既にこの手法は導入されていて、徳島大学大学病院の整形外科では、AR顕微鏡を用いた脊椎手術が既に実用されています。
AR顕微鏡と最先端医療ロボットを使うことで、従来の手術よりも約14%正確性が向上したとのことです。

|医療現場でのVRやARの今後は?
医療現場でのVRやAR技術の導入は、今後も積極的に進むことが予想されています。
しかし、課題も多く残されているのが現状になります。
例えば、現在使用が検討されている頭に装着するタイプのVRゴーグルでは、重すぎて長時間の手術には対応できないといわれています。
他にも、複数のVR・AR技術を各病院がそれぞれ取り入れてしまうと、病院によってシステムの操作方法が変わってきてしまい、医師の負担が大きくなり過ぎてしまうことなどが指摘されています。
医療現場では、失敗は許されません。
そのため、今後も多くのVR・ARを利用した臨床試験が実施されていくはずですが、浸透するにはまだ多くの時間が必要になるでしょう。
|VR・AR医療のまとめ
本記事では、VR・ARを活用した医療の現在を、具体例も交えて紹介しました。
VRやARは、ゲームやエンタメ業界でのニュースが目につきがちですが、医療分野でも積極的に研究が進められていることがわかって頂けたかと思います。
VR・ARを医療に活用する技術は、多くの命を救う可能性が秘められており、今後も注目しておきたい分野です。
弊社では、医療業界を始めとする産業用のXRコンテンツを開発しています。
安全教育やシュミレーション、その他のXRの活用にご興味がある方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

 TWITTER
TWITTER
 FACEBOOK
FACEBOOK
 はてブ
はてブ