近年、教育現場でも活用が進んでいるVR(仮想現実)技術を皆さんはご存じでしょうか。
従来の教科書や授業では限界があった、実際に現地に行くことが困難な場所や、危険な実験・実習などを、VRを活用することで、よりリアルな体験ができるようになり、学習の効果を高めることができます。
本記事では、VRの教育現場への活用のメリットやデメリット、導入事例について紹介します。
VR技術の進化により、ますます教育現場での活用が期待される中、この機会にぜひ知識を深めてみてください。
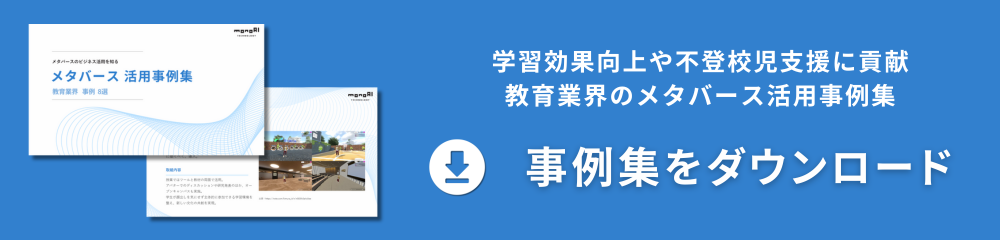
|VR教育とは?

VRとは
VR(バーチャルリアリティ)とは、3DCGなどを用いて、人工的に作り出された仮想空間を、現実のように体験できる技術のことです。
内側にディスプレイを備えたVRゴーグルを装着することで、リアルな360°映像と立体音響により、創られた仮想世界が視界全体に広がります。
現実的には訪れるのが難しい場所や、現実に存在しない場所でも、VRによる仮想世界によって没入体験することが可能です。

VR教育とは
そしてVR教育とは、そのようなVR技術を教育の現場に活用したものです。
VR空間内で歴史的建造物や遺跡を訪れたり、数理系で図形や構造物を3Dで学習したり、危険を伴う科学実験を安全に行ったりと、現実では再現が難しいような状況を疑似体験できます。
教科書や通常の授業では得られない、体験学習による深い学びを提供できるのが大きな特徴です。
昨今は徐々にVR教育の導入や運用が進められており、今後、VRは技術の発展と共にますます身近になっていくと予想され、教育分野においてもその活用が注目されているのです。
|VR教育によるメリットや効果
ではなぜ、VR教育は注目されているのでしょうか。
VR教育におけるメリットを、それぞれ詳しくみていきましょう。
体験型学習による学習効率の向上
VRを活用した教育での最大のメリットは、体験型学習が可能になることです。
仮想空間内で実際に体験しながら学ぶことにより、知識の定着が促進されます。
また、複雑な概念や抽象的なアイデアも、図解やイメージ図など、視覚的に理解しやすい形で提示できるため、深い理解につながります。
さらに、VR空間内では何度でも失敗できるため、試行錯誤しながら繰り返し学べます。
このような体験型学習は、従来の授業のような受動的な学習よりも能動的に学べ、学んだ内容を長期的に記憶に残しやすくなるのです。
学習のモチベーションを高める
VR空間内での臨場感ある体験は、生徒の興味や関心を引き付け、能動的な学習を促進します。
ゲーム感覚で学べるコンテンツも多く、楽しみながら学習を進められるのも大きな魅力です。
自分のペースで繰り返し学習できるため、苦手意識の克服にもつながります。
このように、VR教育は主体的な学びをサポートし、生徒の学習意欲を高めます。

場所・時間を問わずに学習できる
VR教育は、場所や時間を問いません。
インターネット接続とVR機器さえあれば、どこでも好きな時間に学習を進められます。
例えば、海外の学校の授業を受けることも可能になり、個々の学習スタイルに合わせた柔軟な学び方もできます。
通学時間の削減や、時間を有効活用できる点も大きなメリットです。
VR教育は、場所と時間の壁を越えて、より多くの人に学びの機会を提供できることが大きな魅力です。
現実にはできない体験が可能になる
VR教育は、現実では難しい体験を可能にします。
VRは人工的に作り出すデジタル空間であるため、自由自在に体験を創造できます。
例えば、歴史上の出来事を疑似体験したり、宇宙空間や深海など、人が立ち入ることが困難な環境を再現したり、VR空間内なら安全に体験ができます。
他にも、マンネリ化しがちな防災訓練などでも、火災や地震、津波といった緊急時をリアルに再現できるため、より緊張感を持った訓練へと効果を発揮します。
このように、VR教育は現実の制約を超えて、より幅広い学習体験ができます。
|VR教育のデメリット
VR教育は多くのメリットがありますが、いいことばかりではありません。
それぞれ詳しくみていきましょう。
導入コストがかかる
VR教育を導入する際の大きな障壁の一つが、コストの問題です。
VR機器やソフトウェアの購入、インフラ整備などに初期投資が必要となります。
VRゴーグルだけでも、一般的なもので3万円から5万円程度。
スマホを利用した安価なものもありますが、生徒全員分揃えるとなると、かなりの費用がかかってしまいます。
さらに、教材となるコンテンツも一から作成するとなると、外注すれば数十万円レベル。
自作するとしても膨大な時間と専門スキルが必要となります。
こうした費用負担は、学校や教育機関にとって大きな課題となりうる為、補助金制度の活用などは検討しておく必要があります。
長時間の学習は困難
VR教育は、体験型で学習効率が高い反面、長時間の使用は生徒への負担が大きくなります。
装着するVRゴーグルは、ディスプレイや各種センサーを内蔵しており、比較的重量があるものが多いため、長時間の装着で首や肩への負担を感じてしまいます。
また、VR酔い(乗り物酔いのような症状)になる生徒もいるかもしれません。
そのため、一度の学習セッションを短めに設定し、こまめに休憩を取る必要があります。
VR教育を効果的に活用するには、生徒の健康面への配慮と、適切な学習時間の設定に注意しましょう。
五感を全てを使った学習はできない
VR教育は視覚、聴覚を活用した学習体験を提供しますが、嗅覚や味覚については再現が難しいのが現状です。
例えば、化学の実験で薬品の臭いを嗅ぐことや、調理実習で料理の味を確かめることなどは、VR空間内では困難です。
また、触覚についても、専用のデバイスが必要なことや、繊細な感触や温度の違いなどを正確に再現することは技術的に難しい面があります。
現実世界でのリアルな体験とは異なる点を理解しつつ、VR教育の特性を活かした学習設計が求められます。
ITリテラシーが必要
VR機器を扱うには専用デバイスや利用環境についてのITリテラシーが必要になってきます。
教える側は、VR機器の設置や操作、トラブルシューティングなど、学習環境を整えるための技術的な知識が求められます。
また、生徒がスムーズにVR学習に取り組めるよう、わかりやすい操作方法の指導や、仮想空間内でのルールの説明なども必要でしょう。
教員のITリテラシーが十分でないと、せっかくのVR教育のメリットを十分に引き出せない可能性があります。
VR教育をするには、まずは教える側がある程度のITリテラシーを身につける必要があるでしょう。
|VR教育の活用事例
ここまでVR教育のメリット・デメリットについて解説してきましたが、なかなか実際のイメージが湧きにくいと思います。
ここでは、実際にVRを教育現場に取り入れた実例をご紹介します。
世界遺産を社会科見学|Bronx Latin School
米国ニューヨークのBronx Latin Schoolでは、社会科の授業でVRを活用した社会科見学を実施しました。
実際に生徒たち全員で訪れることが困難な世界遺産をVR空間で見学。
生徒たちは教室にいながらにして、現地に行ったかのような体験に興奮気味で、それぞれ能動的に学びました。
体験では、イタリアのヴェローナを訪れ、ロミオとジュリエットにまつわる場所を見学したり、万里の長城を歩いたりと、普段は行くことのできない場所を疑似体験しました。
VRを通して世界中の様々な場所を訪れることで、生徒たちの好奇心を刺激し、学習意欲を高めることができました。
子供達からは「学びを体験できる!」「百聞は一見にしかず」「行きたい場所が山ほどあるけどこれなら!」といった感想が聞かれました。
この取り組みは、教科書や写真だけでは得られない、生き生きとした学びを生徒たちに提供した一例です。
高校でVR授業|角川ドワンゴ学園
角川ドワンゴ学園は、VRを活用した最先端のオンライン学習を取り入れた高等学校を運営している学校法人です。
2021年からスタートした普通科プレミアムコースでは、VRを活用した最先端の教育を展開しています。
VR機器を生徒全員に配布し、バーチャル空間での学習を可能にしました。
VR教材では、今まで写真でしか見られなかった化石を、VR空間で立体的に観察できるなど、体験型学習を実現。
ただ映像を視聴するのとは異なり、VR空間では他の生徒のアバターと一緒に授業を受けているような体験ができ、仲間と共有できます。
ニコニコ動画のようなコメント機能で、非同期でのコミュニケーションも可能です。
このように、角川ドワンゴ学園では、VRの特性を活かし、これまでにない学習体験を提供することで、新しい教育のあり方を模索しています。
大学でVR講義「Virtual People」|スタンフォード大学
スタンフォード大学では、Meta社が開発した「Virtual People」と呼ばれるVRシステムを教育カリキュラムに導入しています。
2021年にスタートしたこのプログラムには、すでに数百人規模の学生が参加し、年間150日程度の授業がメタバース空間で行われています。
学生はMeta Quest 2を使用し、宇宙空間を漂ったり、海中でサンゴ礁を観察したりと、教科書や映像だけでは得られない没入感のある授業を受けられます。
メタバースを活用した教育は、現実世界では体験できない貴重な視点と相互のコミュニケーションを提供し、教育の可能性を大きく広げています。
VR演習室「Hello,World.」設立|関西外国語大学
関西外国語大学では、2023年4月に外国語学部に「英語・デジタルコミュニケーション学科」を新設し、文系大学では全国初となる本格的なVR演習室「Hello,World.」を開設しました。
この施設は、メタバース空間とつながることができ、授業や海外スピーカーの講演、オープンスペースでの課題に取り組むなど、様々な使い方ができます。
壁一面に設けられた大型LEDビジョンからは、臨場感あふれるメタバース空間が映し出され、迫力ある授業が展開されます。
この空間は、英語・デジタルコミュニケーション学科の授業だけでなく、海外ゲストのリモート講演や国際シンポジウムなどでも活用され、新しい学びのスタイルを創り出しています。
VRで沖縄の歴史教育|NTTコミュニケーションズ
NTTコミュニケーションズは、沖縄の歴史教育のVRコンテンツを配信する実証実験を実施しました。
三山時代の今帰仁城を再現した高精細4KVRコンテンツを、5G通信を利用して遠隔講義を行いました。
生徒たちは、VRゴーグルやタブレットを通して、まるでその場にいるかのような臨場感を味わいながら、当時の情景を専門家による解説付きで体験。
この取り組みは、修学旅行生や観光客向けの教育・観光コンテンツとしての発展も期待されています。
VRを活用することで、沖縄の歴史をより身近に、印象深い学びを大勢の人に届けられます。
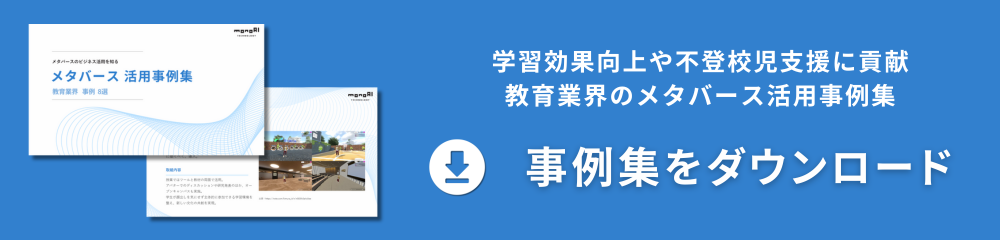
| VR教育コンテンツ
ここからは、実際にVRを教育に活用するためのコンテンツを紹介します。
emou
「emou」とは、ジョリーグッドが提供する発達障がい支援サービスです。
従来のソーシャルスキルトレーニングでは、訓練する人が自分自身としてその場面を捉えることが難しく、場面をイメージするだけで限界がありました。
しかし、「emou」では、VR技術を使用して、よりリアルな場面体験が可能になりました。
これにより、自分自身の体験だと認識することができ、体験を通じて、気づきや学びを得ることができます。
「emou」は、小学校低学年から高校生までのライフステージに合わせたコンテンツが豊富であり、また就労支援にも対応しています。
そのため、支援対象者の年齢や支援目的に合わせて利用できる効果的なVR教育コンテンツと言えるでしょう。
Lifeliqe
Lifeliqeは、VR技術を駆使し、インタラクティブな学習体験を提供するアメリカのスタートアップ企業です。
同社の提供する学習プラットフォームは、恐竜のスケールを実感したり、宇宙遊泳を体験したり、身体の仕組みを3Dで学ぶことができるなど、様々な分野にわたる学習コンテンツを提供しています。
Lifeliqeが提供する学習体験は、通常の教科書の読み込みに比べて、より身近で身体的、視覚的な体験を通じて学ぶことができるため、学生たちにとって非常に魅力的な学習手段となっています。
zSpace
zSpaceは、教育現場でのVR活用を専門とする企業で、教育用のVRシステムを提供しています。
この仮想空間では、生物学や物理学などの科目を学べます。
例えば、生物学の授業では、3Dの人体モデルを操作することができ、身体の内部構造をより深く理解できます。
また、物理学の授業では、現実では危険な実験を安全に行うことが可能です。
|VR教育の基本的な導入ステップ
VR教育の導入を検討する際には、計画的な準備が不可欠です。
ここでは、教育現場でVRを導入するための基本的な4つのステップをご紹介します。
ステップ1:目的と課題の明確化
まずは「なぜVRを導入するのか」という目的を具体的に設定します。
「生徒の学習意欲を高めたい」「危険な化学実験を安全に体験させたい」「海外の姉妹校とリアルな交流を行いたい」など、自校が抱える教育課題と結びつけて目的を明確にすることが重要です。
この目的が、後のコンテンツや機材選定の軸となります。
ステップ2:コンテンツと機材の選定
設定した目的に最適なVRコンテンツを選びます。
市場には多様な教育用VRコンテンツが存在するため、まずは既製品で対応できるか検討しましょう。
より専門的な内容や、独自の教育プログラムを実施したい場合は、オリジナルコンテンツの開発も視野に入れます。
同時に、そのコンテンツを快適に動作させるためのVRゴーグルやPC、必要な周辺機器も予算に応じて選定しておきましょう。
ステップ3:環境整備とカリキュラムへの統合
生徒が安全にVRを体験できる物理的なスペースを確保し、安定したインターネット環境を整備します。次に、VR学習をどの教科のどの単元で、年間指導計画のどこに位置づけるのかを検討し、既存のカリキュラムへスムーズに組み込む計画を立てます。
教員向けの研修もこの段階で計画しておくと、導入がより円滑に進みます。
ステップ4:試験導入と効果測定
いきなり全校展開するのではなく、まずは特定の学年やクラスで試験的に導入し、運用上の課題を洗い出します。
生徒や教員からアンケートやヒアリングを通じてフィードバックを収集し、
「学習意欲がどう変化したか」「学習内容の理解度が深まったか」といった教育効果を測定します。
この結果を基に改善を重ね、本格導入へと繋げていきましょう。
|まとめ
いかがでしたでしょうか。
本記事では、VR教育について、その概要からメリット・デメリット、実践事例、そして将来の可能性まで幅広く解説してきました。
VR教育は、没入感のある学習体験により学習意欲を高め、時間と場所の制約を越えた学びを可能にします。
一方で、コストや健康面への影響といった課題もあることを理解することが重要です。
VR教育は、従来の教育を完全に置き換えるものではありませんが、リアルな教育とのベストミックスを見出すことで、より効果的で魅力的な学習環境の創出が期待できるでしょう。
本記事が、読者の皆様のVR教育に対する理解を深め、教育の可能性を広げる一助となれば幸いです。
弊社では、VR教育を始めとする、ビジネス向けのXRコンテンツを受託開発しております。
XRコンテンツの導入にご興味がある方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

 TWITTER
TWITTER
 FACEBOOK
FACEBOOK
 はてブ
はてブ



































