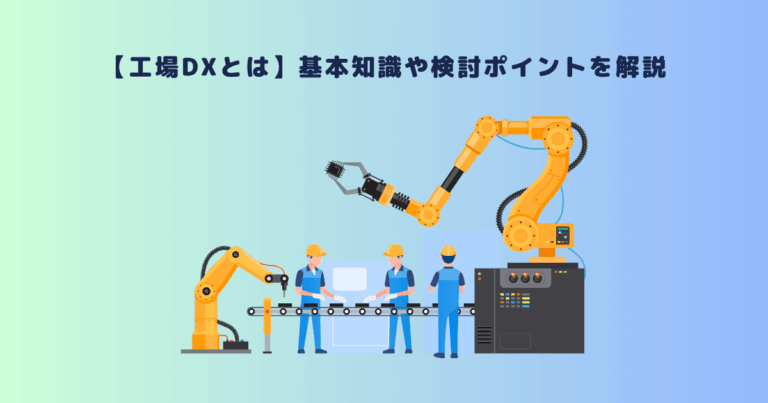工場のような現場で、生産性向上や業務改善、自動化など、様々な課題に日々悩まされてはいませんか?
様々なデジタル技術を活用しDX化していくことで、その悩みが解消できるかもしれません。
「DX」という言葉に興味はあるが、「曖昧なイメージで実際のところよく分かってない」
「具体的にどのような用途で使われているか知らない」という方も多いのではないでしょうか。
DXという言葉は広く浸透しつつある現状ですが、きちんと理解の上で検討できている方は多くないでしょう。
そこで今回は、工場DXについての基本知識や導入方法、活用事例を踏まえて、検討ポイントをご紹介します。
工場DXにご興味のある方は、ぜひご覧ください。
|DXとは

DXとは、 Digital Transformation(デジタル トランスフォメーション)の略で、経済産業省では、DXを下記の通り定義しています。
企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること。
デジタルガバナンス・コード2.0
つまり、企業活動において、データやデジタル技術を活用し現状よりもより良い状態を目指していく取り組みとして、使われている言葉です。
それぞれの企業の状況や性質によって目指す未来は異なりますが、今回は特に製造業などの工場におけるDXにスポットを当てて、解説していきます。
|工場DXの基本知識
なぜ工場DXが注目されているのか
製造業などの現場作業が求められる分野では、人手不足や熟練技術者の減少などの人材に関わる課題が進行しています。
日本は特に少子高齢化という非常に大きな社会課題を抱えている為、若年層の採用が年々困難となり、労働力の確保は勿論、長年の経験や勘といった属人的な技術の継承も課題となっています。
また、グローバル競争が激化する中で、日本の製造業が国際的な優位性を保つためには、高品質を維持もしくは向上させつつ、生産性をさらに高めていかなければなりません。
人材や生産性の課題は主なものですが、他にも、より環境に配慮した工場運営が実現できるようなサスティナブルな観点や、より現代の消費者一人ひとりに合う商品設計の実現ができるようなマーケティング的な観点など、様々な観点からDXの可能性が注目されているのです。
工場DXで解決できる5つの現場課題
では、実際に工場DXを実現することで、どのような課題が解決できるのでしょうか。
DXの導入により解決できる、5つの現場課題をご紹介します。
1.属人化による技術継承の課題
現場作業において何かしらの業務マニュアルを用意している企業は多いでしょう。
しかし、内容によってはどうしても熟練技術者の経験と勘に品質担保を頼ってしまう作業もあり、そういった技術や業務は属人化しがちです。
DXの例としては、AIを活用して熟練者の作業プロセスをデジタルデータとして記録し、そのノウハウを形式化させたり、ARやVRなどのXR技術を活用して、熟練者の作業を視覚的に教育したりといったことが可能です。
2. 品質管理の安定・効率化
人間の目視検査はミスが起こりやすく、作業員の負担も大きい課題です。
確認フローを確立できている現場は勿論ありますが、DXによりシステマチックに検査作業を行うことで、品質管理をより安定化・効率化させることが可能です。
DXの例としては、AIによる画像認識技術や音声認識技術などを活用することで、製品の欠陥を高精度かつ迅速に自動検知できます。
これにより、品質を安定させながら、人件費削減にも繋がります。
3. 生産管理の最適化
経験に頼った需給予測では、過剰生産や機会損失に繋がりかねません。
DXの例としては、過去の販売データや市場動向をAIが分析し、高精度な需要予測を行うことが可能です。
これにより、適切な在庫管理体制が構築でき、不要在庫の削減や適正な生産管理も実現できるでしょう。
4. 設備トラブルの防止
設備の故障は、生産ライン全体の停止を招き、大きな損失に繋がります。
DXでは、IoTセンサーで設備の稼働状況や温度、振動データをリアルタイムで収集し、AIが故障の予兆を検知します。
これにより、故障前に予防保全を行えるため、ダウンタイムを最小限に抑えられたり、事故や故障を未然に防ぐ適切なメンテナンス体制の構築に繋がります。
5. 生産状況の可視化
「今、工場で何が起きているか」をリアルタイムで把握できないと、迅速な意思決定ができません。
DXでは、IoTを活用して生産ラインの稼働状況や進捗データを一元管理し、ダッシュボードで「見える化」します。
これにより、ボトルネックの特定や改善が容易になります。
|工場DXで活用される主な先端技術
上記ではDXで解決できる課題をご紹介しましたが、実際にどういった先端技術が活用されているのでしょうか。
ここでは、工場DXにまつわる主な先端技術をご紹介します。
XR技術(AR/VR)
XR技術とは、拡張現実と呼ばれるAR技術や、仮想現実と呼ばれるVR技術を指します。
例えば、VRを使って新しい生産ラインをシミュレーションしたり、ARでタブレットをかざすと機械の操作手順やメンテナンス情報が表示されるようにしたりすることで、作業員の教育や技術継承に関する課題に対応することができます。
AR技術やVR技術の詳細については、ぜひ下記の記事をご覧ください。


AI・機械学習
昨今話題になっているAI(人工知能)や機械学習も、工場のDXで最も重要な技術の一つです。
具体的には、熟練工の勘や経験に頼っていた不良品の検品を自動化したり、過去の生産データから未来の需要を予測して生産管理を最適化したり、設備の予知保全を実現したりと、非常に幅広い活用シーンがあります。
前後で紹介している様々な技術とも、連携して活用されることが多い技術です。
ロボティクス
人手不足の解消や作業効率の向上に欠かせないのがロボットです。
単純作業をロボットによって自動化したり、危険が伴うような作業をロボットで代替することで安全に作業を行ったり、システマチックな作業でヒューマンエラーを無くしたりと、労働力の課題に対して様々な恩恵があります。
IoT (Internet of Things)
IoT(Internet of Things)は「モノのインターネット」とも言われ、インターネットにセンサーなどを備えた”モノ”が接続され、相互に情報交換を行う仕組みを指します。
例えば、工場内の様々な設備や機械にセンサーを取り付け、インターネットでデータを収集・可視化することが可能です。
これにより、作業員はPCやタブレットで機械の稼働状況や温度、振動などのデータを確認し、異常を早期に発見したり、生産ライン全体の効率を分析したりすることができます。
5G
高速・大容量、低遅延という特徴を持つ5Gは、工場のDXを加速させるインフラ技術です。
大量のIoTセンサーから送られてくるデータを瞬時に処理したり、ロボットやAGV(無人搬送車)を遅延なく制御したりすることが可能になります。
これにより、工場のワイヤレス化が進み、IoTやXR技術などの活用の幅もより広げることが可能です。
|工場のDX導入方法
「工場のDX」が何を指すか、ご理解いただけたでしょうか。
ここからは、工場のDX導入方法を分かりやすく5ステップでご紹介します。
DX導入に躊躇している方や実際の導入に向けて動き出したい方は必見です。
1.現場を正しく理解
まずは、現状を知り課題を洗い出すことが重要です。
ご自身の会社の一番の課題は何か、その課題をクリアにすることでどういうメリットがあるのか、逆にクリアにしたことで起こるデメリットは何か、この3点を軸に考えていきましょう。
軸を作ることで、判断に迷った時に根本の課題に立ち戻ることができたり、方向性がズレた時に軌道修正ができます。
この軸を固めることが、DXを効率よく導入するための近道になります。
2.解決したい課題の明確化
現状を知り、課題の軸がしっかり固まったら、課題を深掘りしていきましょう。
深掘りするためには、事務作業であれば実務担当者に、工場作業であれば現場担当者に、ヒヤリングやアンケートなど、担当者の考えを聞くことが課題解決の近道です。
ステップ1の課題を細分化し、担当者ベースに落とし込み、優先順位を付けて取り組む形を作っていきましょう。
細分化した中には、すぐに解決できそうなこともあれば、時間を要してしまうこともあるでしょう。
そういった時は、いつまでに解決したいか、もしくは解決をしなければならないかを、進行管理できる計画表を作ることをおすすめします。
3.人材確保やツールの選定
具体的な課題が見えてきたら、計画を実行する人材を決め、ツール選定をしましょう。
ツールが優秀でも使いこなせる人材がいなければ、いくらツールが優秀でもゴミ同然になってしまいます。
それを避けるためにも、実際に作業する人のPCスキルやITリテラシーを把握することが大切です。
とりあえず、作業者であれば誰でもいいというわけでもありませんので注意しましょう。
人材確保とツール選定をする時は、そのサービスを提供している企業担当者がどれくらいの支援をしてくれるのかも重要になってきます。
4.データ収集、現実との齟齬を確認
人材とツールが決まったら、データを収集し、運用して問題ないか検証していきましょう。
データ収集と検証することは、ステップ5のシステム運用を開始させる前の準備段階です。
この準備段階で、検証がスムーズにいかない場合はトライアンドエラーを繰り返し、検証後の問題点をクリアにします。
この作業で手を抜いてしまうと、これまでの使った時間が水の泡になってしまいます。
そうならないためにも、基準を決めてその基準をクリアするまでは運用開始することは控えましょう。
5.システム運用開始
ここまできたら、実際にシステムを運用していきます。
運用開始当初は、システムに慣れていないため残業も発生してしまうことでしょう。
しかし、これまでと違う作業をしているので時間がかかってしまうのは当然です。
多少の負荷が掛かってしまうことを見越して、閑散期などの落ち着いている時期に運用開始し、従業員にかかるストレスを少しでも減らすことをおすすめします。
何か新しいことを取り入れると、不満の声があがっています。満足の声も大事ですが、不満の声が次の解決すべき課題になり、会社の財産になるかもしれません。
|工場のDX導入への課題
ここまで工場でのDX導入方法についてご紹介しました。
しかし、実際にはDXの導入はそう簡単にいくものではありません。
導入に際してありがちな、注意すべきポイントを3つご紹介します。
1. 目的とゴールの明確化
DXは単なるツール導入に留まるものではありません。
「なぜDXをやるのか」「何を達成したいのか」といった目的を明確にしなければ、導入に対して適切に評価が行えず、費用対効果が見合わない投資に終わりがちです。
「生産性を〇%向上させる」「不良品率を〇%削減する」といった具体的な目標を設定することが重要です。
2. スモールスタートでの段階的な導入
最初から工場全体のDX化を試みると、莫大なコストと時間がかかって思い通りにいかず、当初の目的を見失って失敗するケースもあります。
DXの導入により運用に関する新たな課題が出てくる可能性もあるため、まずは特定の生産ラインや部署など、課題が明確な範囲で小さく始めて、成功事例を積み重ねていくことが重要です。
その成功体験をもとに、徐々に適用範囲を広げていくのが効果的でしょう。
3. 現場を巻き込む組織づくり
DXは経営層だけでなく、実際にシステムを使う現場の理解と協力が不可欠です。
トップダウンの一方的な導入では、「現場を理解していないくせに」「現場を知らないくせに」といったように現場の反発を招き、定着しない可能性があります。
現場の意見を吸い上げ、課題解決に繋がるシステムを共に検討することで、従業員のエンゲージメントを高め、DXを成功へと導くことができます。
|工場のDX導入事例

ここでは、DXを導入している3業種の事例をご紹介します。
実際の企業がどのように取り入れているか導入事例を中心にご紹介しますので、ぜひ参考になさってください。
機械装置メーカー・工作機械メーカー
機械メーカーで用いられたケースは、生産管理システムのDX化です。
時代に追いつくためにシステムを導入したのは良いものの、それぞれの部署で使っているツールのメーカーが違うため連携ができなかったり、連携ができたとしても手間がかかったり、と問題点も多いようです。
他部署との連携にもそれぞれのツールにログインして確認したり、上手くデータが読み込めずに文字化けしたりするなどの声もあります。
そこで、DX化で一つのシステムに統合することで、これまでかかっていた余分な時間を他の作業に使え、残業代をカットできます。
一定の作業が終わるとアラートが飛ぶように設定すれば、うっかりミスを防ぐことも可能となるでしょう。
電気機器メーカー
電気機器メーカーでのケースは、DXを用いて業務の見える化を実現しました。
製造過程のみもならず、注文を受けて納品するまでの業務を見える化し、どの製品が今どういった工程まで進んでいるのか、簡単に把握できるようになります。
また、簡素化に取り組むうえで工程を見つめ直し、改善が容易になり、生産性の向上や現場の働きやすさにつながります。
データも見える化することで、今後の予測が立てやすくなり、蓄積されたデータを元に新製品の開発や人材補給のタイミングなどあらゆる面で効果をあげてくれるでしょう。
部品製造メーカー・部品加工メーカー
部品メーカでのケースは、自社分析に活用した事例です。
DXを用いて、データを蓄積し分析することで、外部環境や競合との優位性、自社の強みや弱み、脅威などを明確に区別することが可能になります。
現状、どこに注力したらよいのかを考える際にも、製造におけるコスト削減なのか、営業活動に力を入れるべきなのか、受注が落ち込んできている理由は何なのか、そういった分析にも一役買ってくれます。
他2つのの事例とも重なるところがありますが、データを分析し今後の見通しを立てることで、品質の維持や向上にも役立ち、新しい人材の雇用時や教育時間の短縮にも活用し、残業時間の削減にもつながるでしょう。
|まとめ
いかがでしたでしょうか。
今回はDXに関して基本的な知識や検討ポイントをご紹介しました。
一口にDXといえど、それぞれの企業によって悩みや改善したい課題やその背景が異なるため、様々な取り組み方があると理解していただけたかと思います。
DXにまつわるデジタル技術は日々進歩しており、活用の幅も目まぐるしい速さで広がっています。
弊社は、ARやVRコンテンツの開発及びコンサルティングを行っています。
産業XRを活用したDXの導入にご興味がある方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

 TWITTER
TWITTER
 FACEBOOK
FACEBOOK
 はてブ
はてブ