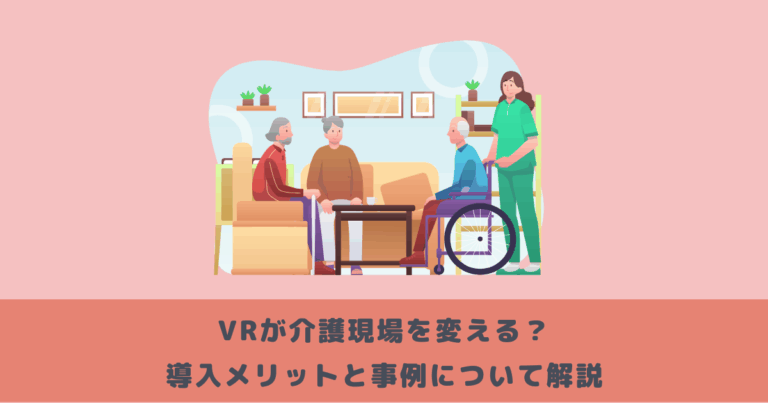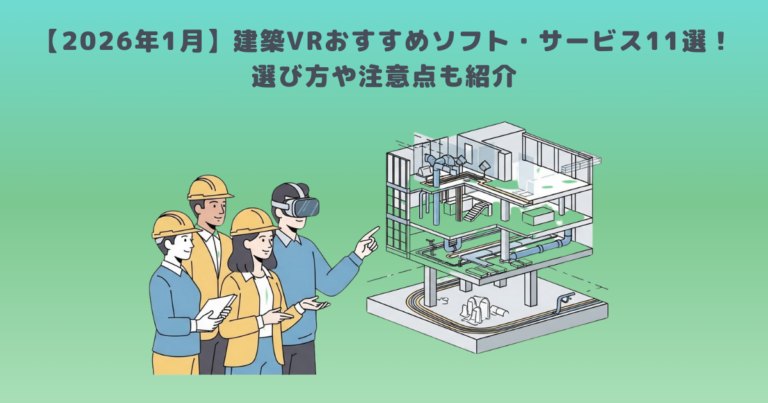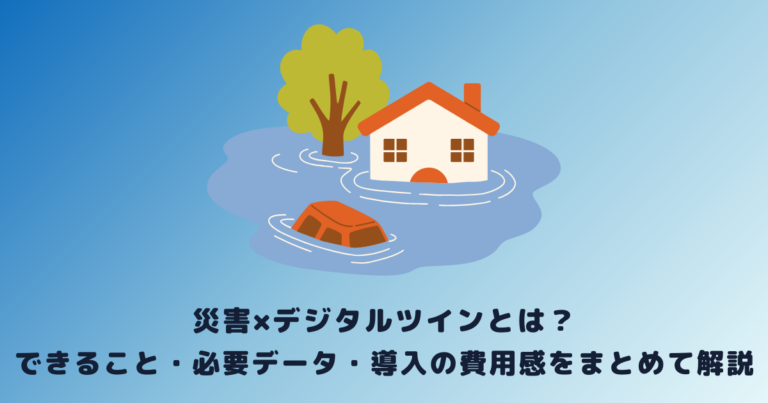介護現場において、VR技術の活用が注目され始めているのをご存じでしょうか。
VR介護は、被介護者の方々が日常生活や社会参加をより充実させることができる一方、介護者側にとっても効率的かつ安全な業務をこなすことができるため、ストレスや負荷の軽減に繋がる一手として期待されつつあります。
本記事では、VR技術のメリットや事例をご紹介します。
介護業界におけるVR技術の導入にご興味がある方は、ぜひご覧ください。
目次
|VRとは

VR技術(Virtual Reality)とは、「仮想現実」とも呼ばれ、CG上で作られた仮想空間に身を置き、まるでその仮想世界の中にいるかのような臨場感を体験できる技術です。
ユーザーはVRゴーグルのような専用のデバイスを使用し、HMD(ヘッドマウントディスプレイ)やコントローラーなどの機器を使用して疑似体験できます。
VRゴーグルの中で再生される360度の3D映像と、立体音響、振動などの様々な刺激を組み合わせることで、没入感ある体験ができるため、ゲームのようなエンタメ分野の他、教育、医療、製造などの産業分野でも活用が進められています。

|介護現場におけるVR技術の主な活用シーン
では、VR技術は介護現場においてどのように活用されているのでしょうか。
主な活用シーンをご紹介します。
VR介護研修
VR介護研修は、介護現場で働くスタッフの研修において、広く活用されるようになってきています。
従来の研修では、人手不足で研修に行けない、座学が主体で実践的な学習が出来ていない、といった課題がありました。
介護業務では、臨機応変な対応が求められることも非常に多いですが、VRを用いた介護研修では、様々なシーンを想定した複数のシナリオと、時間や場所の制約なく研修を受けることができます。
また、実際の現場をVRでリアルに体験できたり、要介護者の疑似体験も行えることから、より実践的なスキルの習得が期待できます。
VRリハビリ
リハビリテーションにおいても、VRの活用は有効です。
要介護者によっては、苦痛に思われがちなリハビリも、VRの持つゲーム要素などを取り入れることで、モチベーションを向上させることができます。
勿論、要介護者の症状に合ったリハビリメニューをカスタマイズすることもできるため、施設のような広めの空間を想定したコンテンツから、自宅での狭い空間を想定したコンテンツまで、幅広くメニューを作成することが可能です。
VR旅行・レクリエーション
主に身体的な制限がある被介護者にとって、外出や旅行が難しい状況でも、VRなら仮想空間上で旅行体験が可能です。
自宅や施設の中にいながら、遠く離れた様々な観光地を訪れることができます。
例えば、VRの仮想世界で世界遺産を巡ったり、日本全国の観光地を巡ったりなど、実際に足を運ぶことが難しい場所でも、VRを利用することで疑似的に旅行体験することができます。
VR旅行により新鮮な体験や刺激を提供し、レクリエーションの一つとして介護生活の質の向上に繋がります。
|VRを介護現場に採用するメリット
VRが介護現場において活用されている中で、どのようなメリットをもたらしているのでしょうか。
以下で詳しく説明していきます。
教育コストの削減
先ほどもご紹介したVRを用いた研修は、その介護施設に応じた状況を様々にシュミレーションすることが可能です。
VR研修は時間や場所を問わず、且つ何度も繰り返しのトレーニングが可能なため、スタッフは要介護者への失敗を恐れることなく、反復練習が可能になります。
また、VRの持つ「没入感」という特徴を生かして、例えば認知症の視覚・聴覚体験を再現し、より要介護者の状況を体験学習させることも可能です。
勿論、実技研修も決してスキップできるものではありませんが、その前段階の業務理解としての研修に活用でき、OJTにかかるトータルの時間やコストの削減と、研修の質を均一化することができます。
時間や場所を選ばない体験
介護者の研修然り、要介護者のレクリエーション然りと、VRは時間や場所の制約を軽減することが可能です。
従来の介護研修では、研修会場に集まる必要があり、トレーナーや参加者のスケジュールに合わせて時間を調整する必要がありました。
介護現場の深刻な人手不足から、十分な時間を研修に当てられないケースもしばしば見受けられます。
しかし、VRを使用すれば、いつでもどこでも様々なケースやシミュレーションの研修が受けられるようになります。
また、研修のスケジュールが合わなくても、後から研修の映像を見返すことができるため、いつでも研修内容をチェックできる柔軟性もメリットに挙げられます。
多様な状況を想定したシミュレーション
介護現場では、被介護者の身体状況に合わせて様々なケアが必要となりますが、その際には危険がつきものです。
具体的には、転倒や誤嚥、急病などが挙げられますが、従来の研修では、これらの危険を実際に再現することは困難でした。
しかし、VR研修では、そのようなシチュエーションも1つのシナリオとして、再現することが可能になります。
例えば、被介護者が転倒した場合の対応、誤嚥した時の応急処置などは、口頭や座学のみでは介護者のイメージに限界がありますが、VRは体験としてイメージを共有できます。
このように、VRの持つカスタマイズ性の高さも、介護業界におけるメリットの一つです。
|VR×介護サービスの事例
ここまで、VR介護による効果について理解を深めてきました。
それでは、実際に行われているVRを活用した介護サービスの具体的な事例をご紹介します。
VRを介護の現場で活用したい、と検討している方は、ぜひ参考になさってください。
リハまる
株式会社テクリコによって提供されている「リハまる」は、VRやMR(複合現実:現実世界にデジタル映像が存在するかのように投影する技術)を用いた3Dリハビリソフトウェア・システムです。
理学療法、作業療法、ミラー療法が受けられ、それぞれ運動リハビリや脳トレ、片麻痺患者が左右対称に同じ動きをできるように練習するトレーニングなどが可能です。
HMDを使用して、仮想空間上で迷路を楽しめるコンテンツや、舞う紙吹雪をコップですくうなど、身体を動かせるコンテンツがあります。
広いスペースがなくても、遠隔地にある自宅や施設の限られた場所で気軽に行えることも特徴的です。
価格は公開されていませんが、管理用デバイスと被介護者用のHMDの用意が必要です。
MindMotion
スイスに本社を置くMindMaze社が開発したリハビリテーション療養システムです。
脳卒中などで運動機能が低下した被介護者のために、神経リハビリテーションを提供しています。
VRゴーグルを装着するタイプとは違い、光学式マーカーレス技術による全身モーションキャプチャで取り込み、仮想空間で身体の動きを映し出せるようになっています。
遠隔でセラピストがモニタリングし、リアルタイムでフィードバックが受けられます。
具体的には、被介護者の正面のモニターにリハビリテーションプログラムと連動したゲームが表示され、その指示にあわせて被介護者がマーカーを装着した上肢を動かしてリハビリを行っていきます。
Floreo
米Floreo社が開発した「Floreo」は、自閉症スペクトラム、ADHD、不安神経症などの神経多様性を持つ子どもたちに、遊び、学び、成長する機会を提供するVRベースの教育プラットフォームです。
VRゴーグルを装着して、ゲーム感覚で人とのかかわり方、日常生活で直面する様々な課題に直面する疑似体験を提供し、生活上のルールを学ぶことができます。
特筆すべきはそのコンテンツの豊富さです。
交通や学校でのルール、レストランでの会話など、具体的な場面を想定したレッスンを繰り返し受けることができます。
さらに、新しいスキルを習得するのを支援するだけでなく、彼らが感じる不安やストレスなどの感情にも対処しており、子どもたちがより良い生活を送ることを支援しています。
認知症VR
千葉県の「株式会社シルバーウッド」が提供する「認知症VR」は、レビー小体型認知症の幻視や、認知症の中核症状を一人称視点で体験できるサービスです。
「認知症VR」は、認知症の症状を体験することで、認知症に対する理解を深め、介護現場のスタッフのトレーニングに活用されるVRコンテンツです。
認知症になると自己表現が不十分になり、徘徊や帰宅願望、介護抵抗、暴力・暴言、妄想などの様々な症状が出現します。
これを「認知症だから」と一掃せず、被介護者を取り巻く周囲の理解やコミュニケーションが大きく影響していることを、一人称視点で体験して理解につなげることを目的としたプログラムです。
体験した症状に応じて、適切なアプローチやコミュニケーション方法を学ぶことができます。
mediVRカグラ
株式会社mediVR(大阪府)によって提供されている自力運動訓練装置で、“自分らしい暮らしを取り戻したい”と願う方に向けたVRリハビリテーション医療機器です。
具体的には、歩行に必要な運動機能と姿勢バランス、認知機能を総合的に評価するための測定機能付の装置で、 仮想現実及び三次元空間トラッキング技術を応用しています。
VRゴーグルを装着して仮想空間内の様々な観光地を散策することで、歩行訓練や腕の基本動作、反射動作を繰り返し行う訓練に使用されます。
背景がシンプルで認知負荷が低い「水平ゲーム」「落下ゲーム」、ゲーム注意障害を惹起するよう認知負荷性を高めた「水戸黄門ゲーム」「野菜ゲーム」「果物ゲーム」などがあり、楽しみながらリハビリを行うことができます。
emou
株式会社ジョリーグッド(東京)が提供するソーシャルスキルトレーニング用のコンテンツです。
emouは、発達障害者が直面する社会的・感情的な問題をテーマにしたストーリー型のVR体験型発達障害支援プログラムです。
具体的には、学校生活や職場などの日常生活の中で欠かせないソーシャルスキルを、VRのリアルな仮想空間内で何度でも体験トレーニングを行うことができます。
会話や表情などをはじめ、これまでのワークシートやロールプレイでは再現が難しかった社会生活における様々な場面を、リアルな空間で体験しているかのように、何度でもトレーニングすることができます。
基礎的な学習の他、就労移行支援への活用も期待されています。
東京福祉保育専門学校
東京福祉保育専門学校は、VR技術を活用した介護現場における研修を導入しています。
同専門学校では、介護福祉士体験コンテンツやシミュレーション研修を実施し、学生たちに実践的な介護技術を身に付けさせています。
介護福祉士の仕事をリアルに体験することによって介護業界への理解度が深まり、イメージがより掴みやすくなります。
また、学生たちがVR技術を用いて、介護の現場で起こりうるさまざまなシチュエーションに対応する訓練を行うことでリスクマネジメントについての理解も深まります。
さらに、VRによる被介護者の一人称体験により、学生たちが被介護者の立場になって考えることで、より人間性豊かな介護者としての心構えを養うことが期待できます。
|まとめ
いかがでしたでしょうか。
今回は、介護業界におけるVR技術のメリットや事例についてご紹介しました。
これらの技術は、被介護者の理解を深めたり、継続的なリハビリに取り組んだり、外出が難しい方にも疑似体験を提供することができ、介護現場の改善において新しい可能性を秘めています。
今後ますます進化する介護VRを導入することで、介護現場のスタッフの技術力向上や、被介護者のQOLの向上につながることに期待していきましょう。
弊社では、VRを始めとする様々なXRコンテンツを開発しております。
ARやVRのビジネス導入にご興味がある方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

 TWITTER
TWITTER
 FACEBOOK
FACEBOOK
 はてブ
はてブ