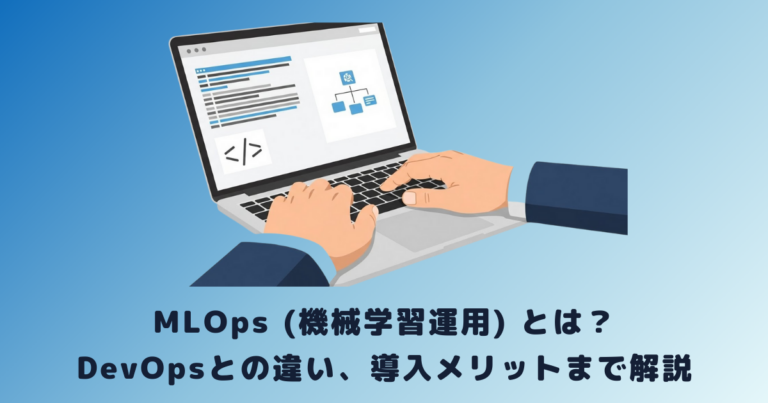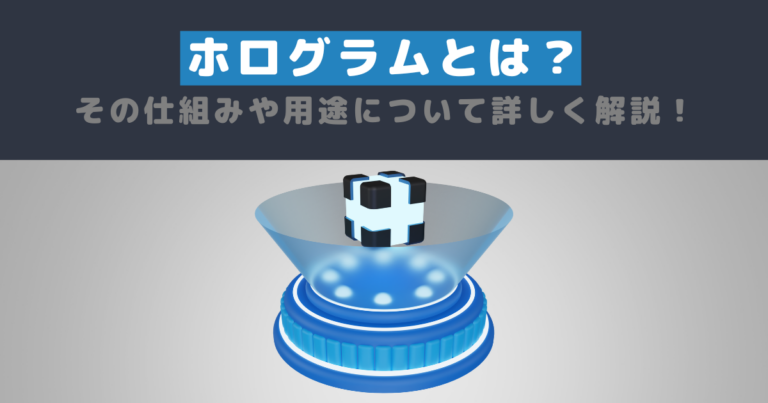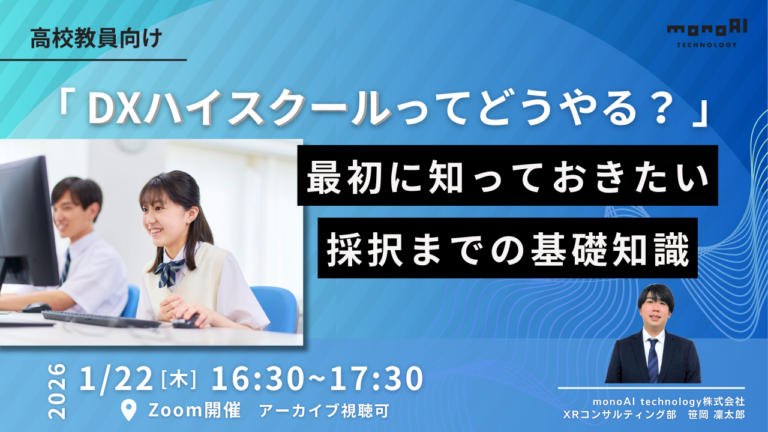今や日本の農業の市場規模は2兆円を突破し、ビジネス面だけでなく国民の生活や生命を守る上でも衰退は許されない存在といえるでしょう。
ところが現実には、世界一の勢いで加速する高齢化、農家の担い手の減少、著しい気候変動など、農業界ではかつてないほどの逆風が吹き荒れています。
そこで注目されているのが「農業DX」です。
本記事では、デジタル力で農業に変革をもたらすDXと、その事例や課題について詳しく解説します。
目次
|DXとは

DXとは「デジタルトランスフォーメーション」の略です。
デジタル技術を活用して、従来のビジネスモデルや業界の常識にとらわれることなく、業務や組織、プロセス、企業文化を根底から変革して競争力を強化することを意味します。
単なるデジタル化ではありません。
「ヒト」「モノ・サービス」「カネ」「情報」の流れをデジタルやデータの力を使って高次元にシフトさせ、高い収益を確保すべく次世代に向けて新たな体質に昇華させることが目的です。
レガシー化した旧式のコンピューターシステムがあまりに多く、その環境に慣れきっている状態ではいずれ世界で通用しなくなります。
その危機的状況を回避するための最重要課題といってよいでしょう。
|農業DXとは
AIやIoT、ビッグデータといったデジタルの力を農業にも最大限活用し、生産から消費にいたる全プロセスに変革をもたらそうとするのが「農業DX」です。
少子高齢化、農家の担い手の減少、耕作放棄地の増加、気候変動と、農業を取り巻く環境は厳しさを増す一方です。
しかも自給率は40%を下回っている状況で、このままでは農業のみならず食品業界でも競争力の低下を招き、国民の食生活に深刻な影響を与えかねません。
さらに大量の食品廃棄の問題も無視できず、持続可能性を実現するためにも食品製造・加工、物流、流通といったバリューチェーンにおける総合的な改革が喫緊の課題です。
そのソリューションの一つが農業DXといえるでしょう。
農業DXとスマート農業の違い
農業DXと似た概念に「スマート農業」があります。両者はしばしば混同されがちですが、その意味も背景も大きく異なります。
ITやロボットを活用して、省力化や高品質な農産物を効率よく生産することを目的とするのが、「スマート農業」です。
その意味では、多くの農家や関連業界がずい分以前から大きな意味でのスマート農業に取り組んできたといえるでしょう。
かたや農業DXは、スマート農業に加えて食の改良や流通、販売、ブランディング、さらに国民の健康や廃棄処理問題にまで踏み込んで、消費者が農作物の高い価値と持続可能性の向上を実感できる域まで変革することを目指す、2021年(令和3年)に農林水産省から提唱された概念です。
農林水産省は「農業DX構想」を発表
農業DXは、農林水産省が発表された「農業DX構想」によって具体化されました。
農業DX構想は、47のプロジェクトからなります。それらが、
- 生産現場におけるデジタル技術の活用や農業経営、農村振興、流通、食品産業などの「現場系」
- 農林水産省が主体の、実務の抜本見直し、農業者データ活用促進、農業DX情報発信、農林水産省働き方改革といった「行政実務系」
- 現場と農林水産省をつなぐ、農林水産省共通申請サービスeMAFFの地図やアプリ、農業分野オープンデータ・オープンソース推進などの「基盤整備」
以上の3つに分類の上で、「農業DX構想〜「農業×デジタル」で食と農の未来を切り拓く」という資料にして公開されました。
|なぜ農業DXは必要か
今なぜ農業DXが必要なのか、ここで改めて掘り下げていきましょう。
様々な理由が考えられますが、今回は中でも以下の3点に絞って詳しく解説します。
- 担い手の高齢化・後継者不足
- 食料自給率の低下
- コストカット
担い手の高齢化、後継者不足
農林水産省の資料では、2000年に約389万人だった農業就業人口が、2019年には約168万人と約20年間のうちに6割近くも減少しています。
さらに農業を自営で行っている基幹的農業従事者の平均年齢は、2121年の時点で67.9歳と著しく高くなっているのが現実です。
67歳といえば、一般的な企業ではすでに定年を迎えている年齢で、それが平均ということは、その深刻さが理解できるでしょう。その大きな一因が、後継者不足です。
近年の新規就農者数は、年間で約5〜6万人。一方、引退や廃業する人の数はそれを上回るので、全体では多く年で20万人近く、少ない年でも約6〜7万人ずつ減っており、業界としてはジリ貧状態です。
食料自給率の低下
国内のカロリーベースの食料自給率は、2000年に約40%近くに落ち込んで以降、現在までその前後の数値を維持している状況です。
ちなみに、1946年に88%だったことを考えると、その激減ぶりがうかがえます。
他の先進国では、2013年の農水省の試算でアメリカが130%、フランスが127%、カナダにいたっては224%という高い数値をマークしています。
しかも最近では、新型コロナの世界的流行やロシアによるウクライナ侵攻などにより、サプライチェーンが分断されるなどして輸出入事情は激変しました。
この影響で食料を輸入に依存している我が国は、物価高の憂き目に直面。食料自給率向上の重要性を強く実感している状況です。
コストカット
農業では、以下のようにさまざまなコストが必要となります。
- 農機具
- 農用建物の建設やメンテナンス
- 燃料・光熱費
- 田畑など土地の賃借料や購入費
- 肥料
- 農薬・害虫駆除費用
- 梱包材
- 人件費
- その他
しかも天候や気候変動によって収穫量が大幅に落ち込むリスクを常にはらみます。
また一年を通してほぼ毎日重労働を強いられるため、怪我や病気の恐れも少なくありません。
もし主要人材が健康面の理由で動けなくなると、その労力を補うのは容易ではないでしょう。
加えて、農家は一般的な企業のように退職金がないため、その分の貯蓄も確保する必要があります。
これらのことを鑑みると、農家におけるコストカットは、非常に重要な課題となります。
|農業DXによってできること
農業DXによってできることは非常に多岐にわたり、すでにさまざまな分野で成果があがりつつあります。
本記事では、その中でも、
- 生産効率向上
- 環境保護
- コスト削減
以上の3点について具体的に紹介しましょう。
生産効率向上
AIやIoT、ドローン、センサーといったデジタル技術やロボットの導入により、生産効率を飛躍的に向上させることができます。
例えば、
- AIによる野菜のベストな収穫期の判別
- ドローンによる農薬散布
- 野菜収穫ロボットによる収穫作業の効率化
- AIによる病害感染リスクの予測
- 自動運転トラクターによる耕運や草刈り、収穫物の運搬
といったことが可能となります。
生産効率を向上させるには、少ない人手によって、できるだけ多くの作業を短時間でこなすことが大切です。
そこで上記のようなツールを活用すると、タブレットによる遠隔操作や自動作業が可能なため、長距離を移動したり、作物の状況を一つずつ見て回ったりする手間も省けます。
環境保護
農業DXにより、無農薬や減農薬でも農薬使用時と同程度の収穫量の確保が期待できるようになります。
いったん農薬で汚染されると、土壌を元に戻すにはかなりの時間が必要になります。
しかし、農薬の使用が抑えられると土壌汚染が減るため、人体への影響だけでなく、土壌に住む虫やそれを食する動物の保護にもつながるでしょう。
またデジタル技術を駆使した太陽光、風力などの再生可能エネルギーを農業に利用することにより脱炭素にも寄与します。
これらのサステナブルな動きにより農家や農作物への評価が高まると、新たなビジネスチャンスを国内外から呼び込むきっかけにもなり、さらに地球環境保護の好循環を生み出すことが可能となるでしょう。
コスト削減
農業DXにより現場作業が自動化できると大幅な省人化がすすむため、人的コストを削減することが可能になります。品質が向上すれば廃棄率も低下するでしょう。
またトラック配送システムを導入すると、最小限のトラック台数による最短ルートを経由しての輸配送も実現します。
近年のトラックドライバーの減少と高齢化は深刻で、配送料金の高騰に加え、トラックの積載率の低さ(荷物を積むスペースが余っている状態での運行)も問題視されています。
多くのトラックを使い、輸送回数が増えれば、その分コストは膨大になりかねません。
しかし、デジタル化によって農作物や加工食品の物流が効率化すれば、上記の問題の多くが解消されると期待できます。
|農業DXの推進事例
ここからは農業DXの推進事例を具体的に紹介しましょう。
いずれもデジタル技術や専用のツールを開発したり活用したりして、省人化や品質向上、販売ルートの拡大や効率化、売上高の向上などに成功した例ばかりです。
水門管理の自動化
富山県高岡市の「有限会社スタファーム」では、水門管理の自動化でDXに成功しました。
同社では、約70ha(東京ドーム約15個分)の農地をわずか4人で運営しています。
しかもそのうちの15haは7kmも離れた場所にあるため、毎日出向いて管理するのが体力的にかなりの負担でした。
そこで補助金を利用して60台の水門管理自動化システムを導入。
スマホやタブレットなどのデバイス1台でタイマー機能や水位センサーを操作し、全水門の自動開閉を実現させたのです。
1日3回の水門の見回りが3日に1回で済むようになり、1人の2ヶ月分の労力を節約。
収穫量は1割増、雑草が減り、除草剤のコストも削減できて、絶大な効果がありました。
ハウス内の環境制御
ハウス栽培によるキュウリやピーマンの栽培が盛んな宮崎県。
上質な野菜を育てるには、ハウス内の温度と湿度、水分、養分等の調節が欠かせません。
これには上記の重要指標のデータを測定できる専用機器の導入が極めて有効ですが、なかなか普及するまでに至りませんでした。
ところが2014年、この測定機器を導入した農業者から同県農業改良普及センターに使い方についての相談があったことをきっかけに勉強会を発足。
データ分析の仕方やデータの栽培への活用技術を指導すると、参加者らの平均単収が20%以上も増加し、測定機器のコストを1年で回収。
他にも長年かかると言われるベテラン農家の収量にわずか数年で追いついた例も見られました。
ECサイトとの連携
生産者の直販支援や地産品プロモーションを手がける株式会社雨風太陽(岩手県花巻市)が、静岡県と連携して、産直ECの活用と県産食材のプロモーション支援を行っています。
具体的には、
- 県産農産物の送料無料
- 特設ECサイトにおける県産農産物の紹介
- 県内の農家に向けた出品説明会
といった内容です。
静岡県内で生産される農林水産物は1,143品(県の独自調査)と、全国でもトップクラスを誇ります。
しかし生産者だけの力では、その知名度やシェアを増やすことには限界があります。
そこで同社のようなECサービスと販売ノウハウに長けたサポート役が仲介することによって顧客層を大幅に広げ、売上を大きく伸ばすことが可能となります。
経営支援に特化したクラウドサービス
インターネットがあれば利用できる農業クラウドサービスもDXの代表的ツールです。
経験が少ない場合でも、熟練農家の栽培方法やコツをデータ提供し、実際に栽培をしている状況をモニタリングの上、マニュアルから外れた項目があれば指摘して対策が打てるようにフォローしてくれます。
農業クラウドには富士通やNECといった大手ベンダーも積極参入しており、栽培だけでなく、材料調達から出荷、消費者への販売に至るまでをサポートするサービスを提供している例もあります。
家族経営が多くを占める農家では、栽培と出荷作業だけで手一杯というのが実情です。
それ以外の領域をサポートするクラウドはまさにDXの名に相応しいといえるでしょう。
|日本の農業DX推進の課題
全体の規模を考えると、日本の農業DXの進み具合はまだ一部にすぎません。
その理由は複数ありますが、特に
- 日本全体のデジタル化が遅れている
- 専門的な知識を持つDX人材がいない
の2点について解説しましょう。
日本全体のデジタル化が遅れている
日本では世界の先進国と比べるとデジタル化が非常に遅れており、これが農業DXの推進を大きく阻んでいる原因といえます。
かつては下位に位置していた国々にも、年を追うごとに明らかに追い越されている状況にあります。
理由としては、
- IT人材が少ない
- IT人材を育成できるシステムが整備されていない
- 中高年者を中心にデジタルへの苦手意識が強い
- 裁量権のある中高年者がIT投資に消極的
といったことが考えられます。
製造業や小売業、サービス、医療といった第二次・三次産業でもIT化の遅れが強く指摘されている状況のため、ましてや第一次産業で高齢者の占める割合が大きい農業では、さらにデジタルの普及が困難というのが実情です。
専門的な知識を持つDX人材がいない
厳密にいうとIT人材とDX人材というのは、別物です。
DX人材はITについての知見やスキルが必要なため、DX人材という時点でIT人材であることが多いといえるでしょう。
しかしDXを推進するためには、以下の5つの人材が必要とされています。
- ビジネスアーキテクト
- ソフトエンジニアリング
- データサイエンティスト
- サーバーセキュリティ
- デザイナー
とくにビジネスアーキテクトは非常に重要で、DXの目的を見据えて、それに相応しい環境や人材を集め、各者をうまく連携させながらゴールに到達できるように仕向ける役割があります。
そう考えると、IT人材が少ない中で、いかにDX人材を輩出するのが難しいかが理解できるでしょう。
|まとめ
農業DXには、生産効率の向上やコストカット、環境保護など数多くのメリットがあります。
同時に、高齢化や後継者不足といった日本の農業が抱える深刻な課題を解決する糸口にもなるでしょう。
しかし現状は、国全体のデジタル化の遅延やDX人材不足などによって、思うように農業DXが進んでいません。
これらの問題を官民が協力して克服することで農業DXが推進できる余地は大きく残っているため、今後の農業の発展が楽しみです。

 TWITTER
TWITTER
 FACEBOOK
FACEBOOK
 はてブ
はてブ