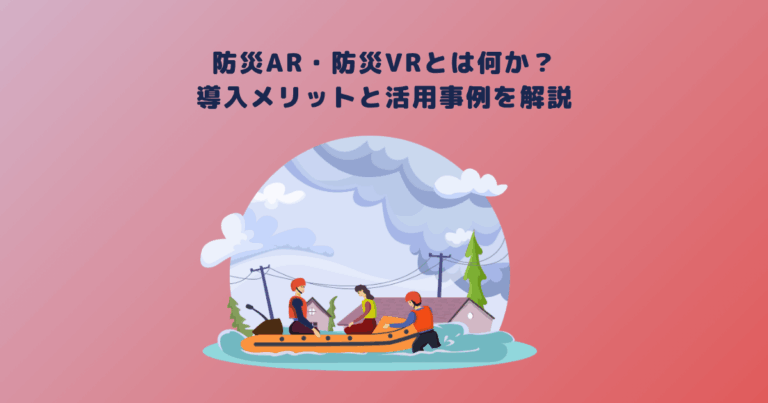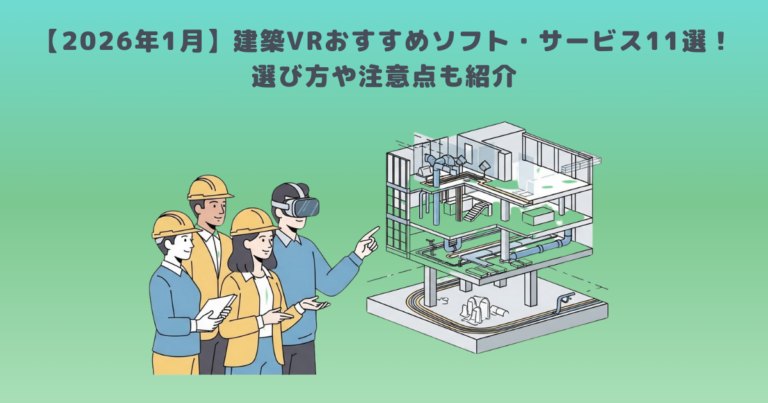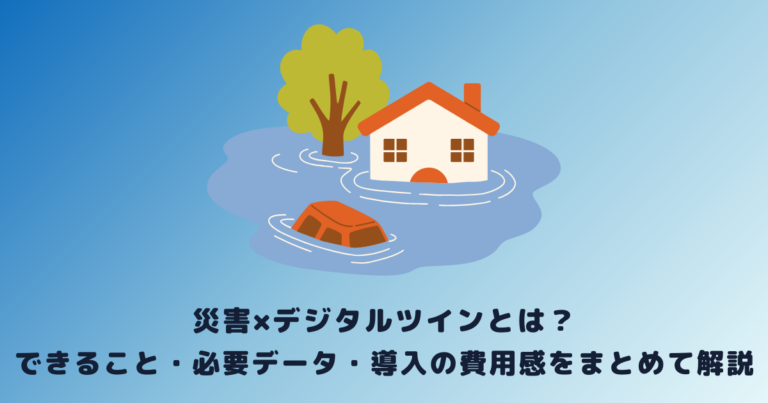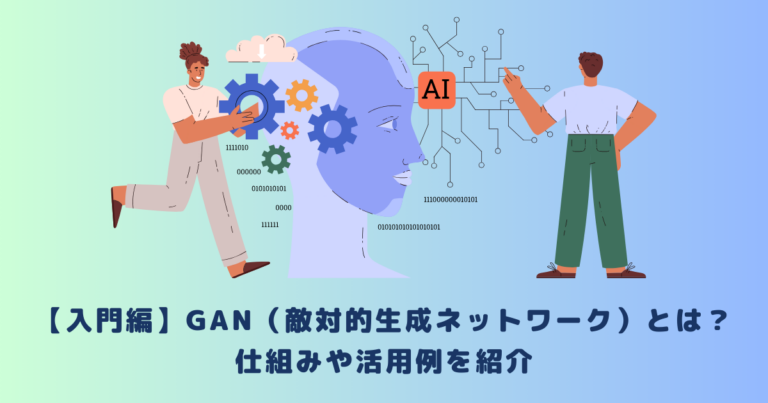昨今のARやVRを始めとするXR技術は、エンターテイメント分野に留まらず、幅広い分野での活用が進んでいます。
防災の分野もその一つであり、より防災訓練の質を高める手法として、注目されています。
本記事では、AR/VRの基本知識から、それらのXR技術がもたらすメリット、防災における活用事例まで詳しく解説します。
防災におけるAR、VR技術の活用に関してご興味がある方は、ぜひご覧ください。
目次
|AR・VRの概要
今回のテーマの解説に入る前に、前提となるAR・VRの技術について押さえておきましょう。
|ARとは

AR(Augmented Reality:拡張現実)は、現実世界にデジタル情報などの仮想的な要素を重ね合わせて、”現実を拡張させる”技術です。
仕組みとしては、スマートフォンやARデバイスに内蔵されているカメラを通じて、映像として表示される現実世界に、3Dオブジェクトなどを重ねて表示させ、あたかも目の前に仮想のコンテンツが出現したかのような体験ができます。
有名な例を挙げると、「ポケモンGO」やAmazonの配置レビュー機能などがイメージしやすいでしょう。
今やほとんどの人が所持しているスマートフォンで体験が可能な技術な為、エンタメコンテンツを始めとする様々な分野で活用されています。

|VRとは

一方でVR(Virtual Reality:仮想現実)は、専用デバイスを通して、ユーザーを”現実世界から仮想世界へ没入体験させる”技術です。
仕組みとしては、VRゴーグルやHMD(ヘッドマウントディスプレイ)と呼ばれる専用のデバイスを装着し、デバイス内で再生される360度の立体映像と立体音響によって、仮想空間を体験することができます。
また、デバイスに備わっているコントローラーやハンドトラッキング機能によって、仮想空間内でも操作や行動が可能であり、ユーザーはより仮想空間への没入感を体験できるでしょう。
VRはさまざまな業界での応用が期待されており、エンタメを始めとして観光、医療、建築など多岐にわたる領域で活躍しています。

|防災におけるARとVRの主な活用方法
防災におけるARやVRの主なユースケースをご紹介します。
勿論、地域や団体などに応じて内容が異なりますので、参考としてご覧ください。
ARの主な活用方法
ARが持つ現実世界にデジタル情報を重ねるという特徴を生かし、主に以下のような活用がされています。
- ハザードマップのデジタル化: スマートフォンやタブレットをかざすと、現実の街並みに土砂災害警戒区域や浸水想定区域などのハザード情報を重ねて表示させることができます。
またGPS情報と連動することで、近くの避難所への経路情報であったり、災害時の危険地域などの情報を表示したりと、ハザードマップの情報を補足することが可能です。 - 災害のシュミレーション: 上記のようなハザードマップの情報以外にも、実際の街中をAR機能で認識させ、その場で起こり得る被災の状況なども仮想で再現することが可能です。
自分の住んでいる地域の被災時にはどのようなことが起こり得るのかという、住民へ強いイメージを持たせることが可能です。
VRの主な活用方法
VRが持つ高い没入体験が可能という特徴を生かし、以下のような活用がされています。
- 災害シミュレーション: 実際の街中を再現し、地震による建物の倒壊や津波の発生、火災の状況などをリアルに再現します。シュミレーションの体験者は、被災時に近しい緊迫した状況を疑似体験できるため、より危機感を体験することで、防災訓練としての効果を高めます。
- 防災知識の学習: 災害発生時の行動、消火器の取扱方法、AEDの使い方などをVR空間で再現し、繰り返し実践できます。
座学だけでは身につきにくい知識も、実際に目の前に防災器具を再現して順序通りに体験を通して効率的に習得できます。
これらの技術は、防災訓練の質を高めるだけでなく、参加者の興味関心やモチベーション向上にも繋がるため、今後はさらに多くの自治体や企業で活用が広がっていくことが期待されます。
|防災でAR・VRが注目されている背景
ではARやVR技術が防災分野において注目されている背景には、どのようなものがあるでしょうか。
以下では、これらの技術が防災に活用され始めている3つの背景をご紹介します。
リアル感のある災害体験が可能
AR(拡張現実)やVR(仮想現実)は、シチュエーションの再現が可能な特徴から、よりリアル感のある災害体験を可能にします。
例えば、VRを使用した地震シミュレーションでは、揺れや崩壊する建物の映像や音声をリアルに再現し、被災時の状況を体験することができます。
また、ARを活用した防災訓練では、実際の環境に仮想的な災害要素を重ねることで、避難経路の確認や緊急時の行動パターンをトレーニングすることができます。
AR/VRのリアル感ある災害体験は、安全な環境で何度も繰り返し実施することができるため、リアルな危機感で防災意識を高める、高い防災効果が期待できます。
災害発生時のイメージができる
AR/VRは災害発生時のイメージをリアルに再現することが可能です。
例えば、ARを活用すると、現実の風景や建物に仮想的な災害の映像を重ねることができます。
地震や洪水、火災などの災害シミュレーションでは、揺れや水の浸入、炎の広がりなどをリアルに体感することができます。
また、VRを使用すると、災害発生時の状況や被災地のリアルな再現が可能です。
被害を受けた建物や街並みを仮想空間で再現し、被災者の視点から現実に近い体験を提供します。
これにより、避難経路や避難所の確認、救助活動のシミュレーションなど、災害時の対応や行動計画の立案に役立ちます。
AR/VRの技術を活用することで、人々は災害発生時の状況やリスクをより具体的にイメージすることができます。
これにより、災害への備えや避難計画の策定において、現実に即した判断と行動を促すことができます。
災害発生時のイメージをAR/VRを通じて体験することは、防災・減災意識の向上と、効果的な対策の推進につながる貴重な手段です。
いざという時にも対応できる
AR/VRは災害発生時のいざという時にも有効な対応が可能です。
例えば、ARを活用すると、現実の状況に情報を重ねて表示することができます。
これにより、被災地の現状把握や避難経路の案内、救助要請の送信などがスムーズに行えます。
また、VRを使用すると、被災地のリアルな再現やシミュレーションが可能です。
避難訓練や救助活動のトレーニングに活用することで、実際の災害発生時に必要なスキルや判断力を養うことができます。
また、避難所や医療施設の配置、物資の配布計画などを仮想空間でシミュレーションし、効果的な運営を検討することも可能です。
AR/VRの技術は、被災時における情報の正確性や効率性を向上させるだけでなく、災害対応における迅速かつ的確な行動を促進します。
災害発生時には混乱や制約が生じる場合がありますが、AR/VRを活用することで、リアルタイムな情報共有や適切な指示の伝達が可能となります。
これにより、被災者の救助や避難、被害範囲の把握などの対応が円滑化し、効果的な災害対策が実現できます。
|AR/VRを防災に活用している事例
防災訓練では、ARを活用して地震時の建物崩壊や火災のシミュレーションを体験できます。
避難経路や避難所情報をリアルタイムに提供し、参加者の意識向上に貢献しています。
VRを利用した防災教育では、学校や企業で災害体験を実施しています。
地震や津波などの被災状況をリアルに再現し、避難行動や救助活動のトレーニングを行い、災害対策の重要性を啓発しています。
災害復興支援においても、ARを活用して被災地の復興計画や仮設住宅の配置をシミュレーションを行っています。
効率的な都市再建や住民の意見反映に役立ち、復興のスピードを加速させています。
ウェザーニューズ
「ウェザーニューズ」は、AR/VRを活用した防災・減災に取り組んでいます。
彼らは、台風や豪雨などの気象災害に関する情報をリアルタイムに提供するだけでなく、AR技術を使用して雨や雪、浸水被害が疑似体験できる「ARお天気シミュレーター」のアプリ提供を行っています。
ユーザーはスマートフォンのカメラを通じて現実の風景に仮想的な災害情報を重ねることで、洪水や土砂災害などの被害を身近に感じることができます。
また、VRを活用して避難訓練や災害時の状況体験も行っており、被災者や救助者の視点を体感することで、より実践的な防災対策の普及と意識の向上に貢献しています。
東京消防庁
東京消防庁では、VRを活用して防災・減災対策に取り組んでいます。
VRを活用した訓練や災害体験も行っています。
B-VRという360度動画を使用し、首都直下地震のシミュレーションを体験することで、訓練効果を高めています。
さらに、VR防災体験車というVRを活用した煙や火災のリアルな再現により、被災者への適切な対応力や冷静な判断力の養成にも役立っています。
東京消防庁のAR/VR活用は、訓練効果の向上や現場での迅速な対応を支援し、防災・減災への取り組みを強化しています。
NHK
NHKは、AR/VRを活用した防災・減災に積極的に取り組んでいます。
例えば、震災体験VRを通じて、東日本大震災の被災地を再現し、被災者の視点での体験を提供しています。
被災地の現実感ある映像と臨場感溢れる音声により、災害の緊迫感や避難の重要性を伝え、防災意識を高めています。
また、防災情報のリアルタイムな提供にも取り組んでおり、ARを活用して災害情報の視覚化を行っています。
スマートフォンやタブレット上に、実際の地図や街並みに災害情報を重ねて表示することで、ユーザーにより具体的な状況認識を促し、迅速な行動へとつなげています。
NHKのAR/VR活用は、災害体験のリアリティや情報の可視化により、一般の視聴者に対しても防災・減災の重要性を訴えています。
これにより、視聴者の防災意識の向上や適切な行動の促進に寄与しています。
東京海上日動
東京海上日動のAR/VRを活用した具体的な事例として、東京海上日動が開発したARアプリ「災害体験AR」を利用し、地震や台風などの自然災害時における被害想定シミュレーションを行っています。
ユーザーはスマートフォンやタブレットを通じて現実の風景に災害の被害や影響範囲を仮想的に重ねることで、リアルな災害状況の把握や適切な対応策の検討が可能となります。
また、東京海上日動はVRを活用して防災教育を展開しています。VRを用いた避難訓練や災害体験により、参加者は仮想空間で実際の災害状況を体験し、適切な避難行動や対応力を身につけることができます。
これらのAR/VR技術を活用した取り組みにより、東京海上日動は防災意識の向上や災害時の適切な対応能力の向上を支援しています。
また、保険会社としても、災害発生時の情報提供や被災者支援など、総合的な防災・減災対策に貢献しています。
明治安田生命
明治安田生命はVRを活用した防災訓練を実施しています。
VRヘッドセットを使用して、災害時の避難訓練や避難所の体験を行うことで、参加者は実際の状況に近い形で適切な行動を学びます。
600名以上の従業員に配布し備蓄倉庫のVR研修を2021年9月、避難訓練のVR研修を2021年11月から実際に訓練を行っています。
これらのVR技術を活用した取り組みにより、明治安田生命は防災意識の向上や適切な行動への備えを促進しています。
また、保険会社としても、災害時の情報提供や被災者支援など、総合的な防災・減災対策に取り組むことで、社会全体の安心・安全を支えています。
理経
理経は「VR地震体験システム」といったVRを活用した製品を提供しています。
VRヘッドセットを使用し、地震などの災害状況をリアルに再現し、映像を通して、地震の際の行動や事前の備えとして学習することが可能な製品になっています。
これにより、現実の災害発生時に冷静な判断力や適切な行動力を身につけることが可能となります。
理経のVR技術の活用により、防災・減災の意識向上や迅速な対応能力の強化が図られています。
仙台市
仙台市はVRを活用した災害体験プログラムも提供しています。
VRヘッドセットを使用して、地震や津波などの災害状況をリアルに再現し、参加者が適切な行動や避難訓練を体験することができます。
これにより、実際の災害発生時における状況認識や対応力を高めることができます。
仙台市のVR技術の活用により、市民の防災意識の向上や適切な避難行動の普及が図られています。
また、地域の防災力の向上や災害時の迅速な情報提供にも貢献しています。
アイデアクラウド
アイデアクラウドはVR・ARで災害体験ができる「防災VR」「防災AR」を提供しています。
VRヘッドセットを使用して地震や火災などの災害シミュレーションを行います。
参加者は仮想空間で災害現場を体験し、適切な行動や対応策を学ぶことができます。
また、アイデアクラウドはARを活用して、消化体験や避難訓練、地震体験、浸水体験ができます。
これらのAR/VR技術の活用により、アイデアクラウドは防災意識の向上や適切な行動力の育成に貢献しています。
また、企業や学校、自治体などさまざまな組織に対して、防災訓練や災害対策の支援を提供しています。
アイデアクラウドの取り組みは、より安全で強固な社会の実現に向けた重要な一翼を担っています。
日本防災技術センター
日本防災技術センターは「AR火災煙体験アプリ」を提供しています。
消化訓練ができ、火災発報の確認から消火避難に至る行動をリアル映像で学ぶことができます。
現実の災害発生時における対応力や判断力の向上が期待されます。
日本防災技術センターのAR/VR技術の活用により、防災意識の高まりや適切な行動の促進が図られています。
さまざまな組織や個人に対して、防災教育や訓練の機会を提供しています。
日本防災技術センターの取り組みは、安全で持続可能な社会の構築に向けた重要な貢献となっています。
白山工業
白山工業は、AR/VRを活用した防災・減災の取り組みで注目されています。
同社が提供する「SyncVR」というVRを活用した映像で、地震や火災などの災害状況をリアルに再現し、参加者が避難訓練を体験します。
VRヘッドセットを使用して仮想現実の中で災害シミュレーションを行うことで、実際の災害発生時における状況判断や行動力を向上させます。
現実の空間に仮想の火災を重ねて表示し、参加者が適切な消火や避難行動を学ぶことができます。
これらのAR/VR技術の活用により、白山工業は従業員や関係者の防災意識の向上や迅速な対応力の養成に貢献しています。
また、災害リスクの低減や安全な職場環境の実現にも取り組んでいます。
白山工業の取り組みは、企業の防災・減災意識の高まりと共に、社会全体の安全性の向上に寄与しています。
|まとめ
AR/VRは防災・減災にも活用される技術であり、その有効性がますます認識されています。
防災・減災の重要性が高まる中、AR/VRは緊張感ある災害体験や災害発生時のイメージ形成、訓練・教育の効果的な実施、現場での対応力強化などで役立っています。
さまざまな事例が存在し、ウェザーニューズや東京消防庁、NHKなどがAR/VRを活用しています。
これからも防災・減災においてAR/VRは重要なツールとして活躍することが期待されます。

 TWITTER
TWITTER
 FACEBOOK
FACEBOOK
 はてブ
はてブ