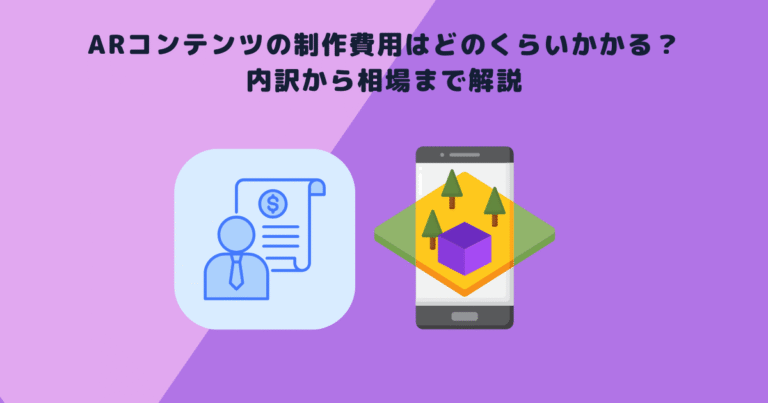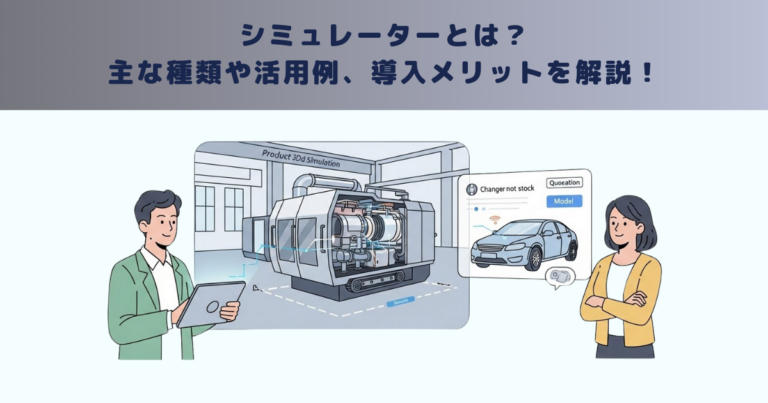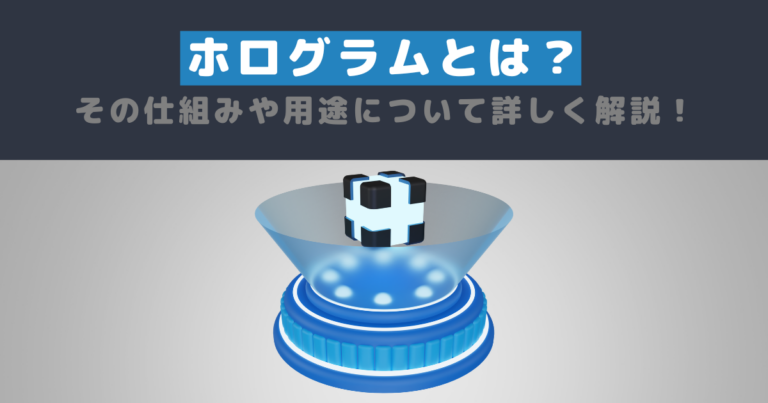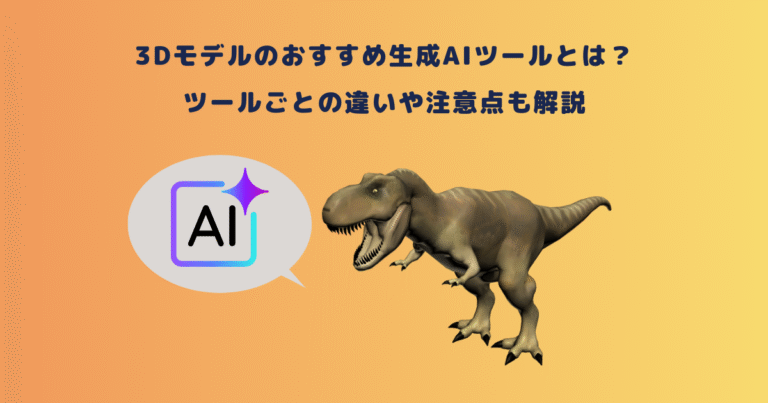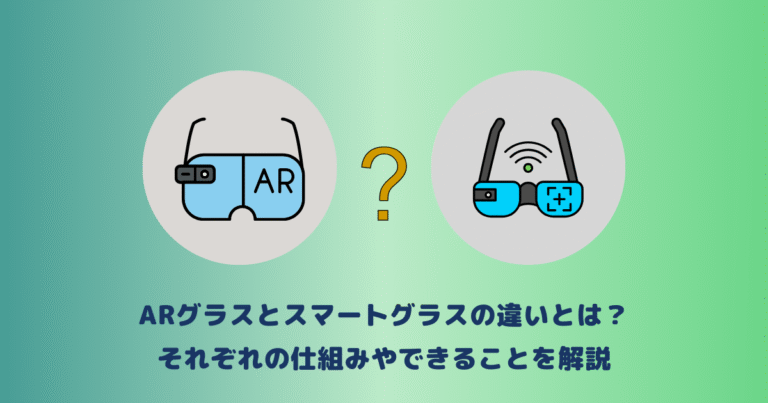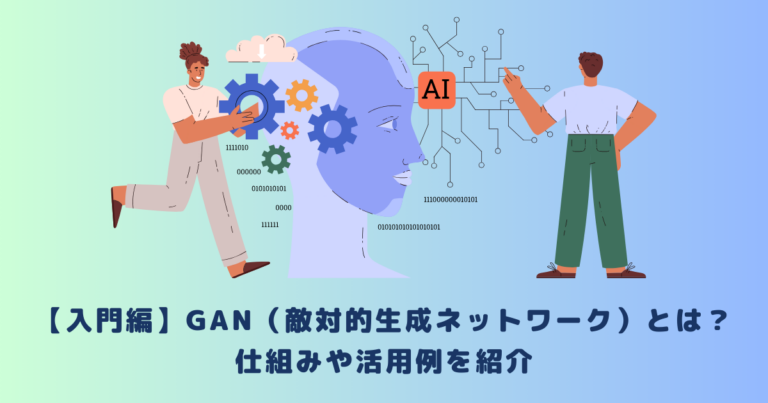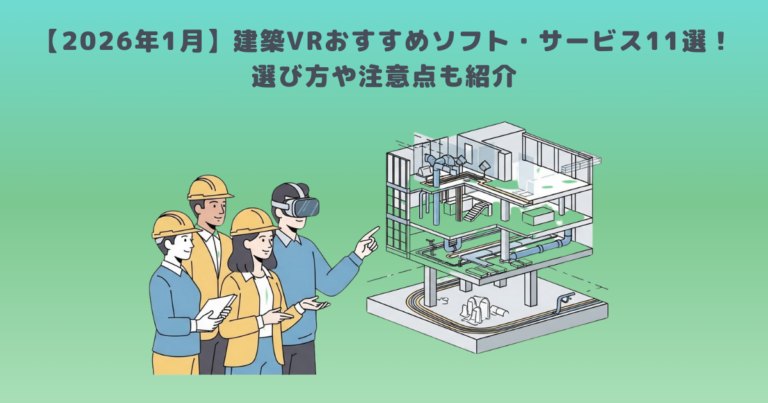「競合他社が商品プロモーションでARを使っているが、自社で導入する場合の費用感が全く分からない」 「上司にARの開発について聞かれ、まずは概算コストを把握したい」
このようなARについて悩む担当者の方もいらっしゃるのではないでしょうか。
AR開発の費用がこれほど変動する理由は、提供方法が大きく2つに分かれるためです。
具体的には、ユーザーにアプリのダウンロードを求める「ネイティブアプリ型」か、スマートフォンのブラウザ(Web)で手軽に体験できる「WebAR型」か、という根本的な違いがあります。
この記事では、AR開発の費用に関する全体像を掴んでいただくため、以下の点を中心に解説していきます。
- 「WebAR」と「アプリAR」それぞれの費用相場
- 開発手法(SaaS利用 vs スクラッチ開発)の違い
- 見積もりを構成する費用の内訳
- コストを抑えてAR開発を進める現実的なコツ
この記事を読めば、自社の目的に合ったAR開発の手法と、その予算感の「当たり」をつけるための基礎知識が身につきます。
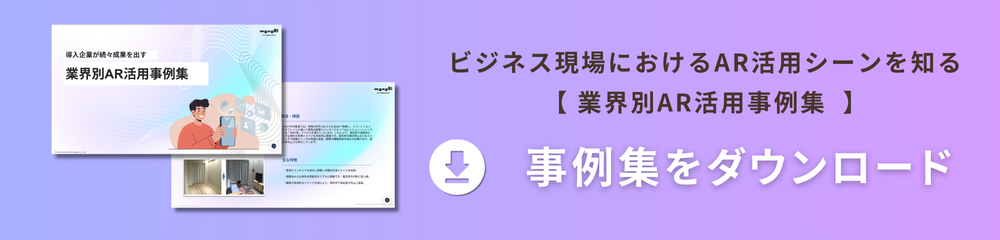
ARコンテンツ制作!自社開発による柔軟性でお客様のビジネスをリードする『monoAR』
サービスの特徴や導入事例をまとめた資料をご用意しました。

monoARサービス紹介資料の無料ダウンロードはこちら
資料をダウンロードするAR開発の費用はどう決まる?
AR開発にかかる費用は、結論「月額数万円から500万円以上」と、非常に大きな価格差があります。
これほど費用に幅がある理由は、ARを実現するための「開発手法」が複数存在する為です。
特にコストを左右する大きな分岐点は、以下の2点に集約されます。
- 提供形態:「①WebAR(ブラウザ)」か「ネイティブアプリ」
ユーザーにアプリのダウンロードを要求するか、Webブラウザ上で手軽に体験させるかで、開発の規模が異なります。 - 開発手法:「②SaaSツール」か「スクラッチ開発」
既存のAR作成ツール(SaaS)を利用して安価に構築するか、ゼロからオーダーメイドで開発(スクラッチ)するかで、必要な工数(人件費)が全く変わってきます。
例えば、プロモーション目的で短期間だけARを使いたい場合、WebARに対応したSaaSツールを利用すれば、月額数万円程度からスピーディに導入することが可能です。
一方で、デバイスのカメラ性能やセンサーを最大限に活かした高機能なARゲームアプリをゼロから開発する場合、500万円以上の大規模なプロジェクトになることも珍しくありません。
このように、AR開発の費用は「何を実現したいか」以前に、「どう実現するか」という手法の選定に大きく依存することを、まずは把握しておく必要があります。
【手法別】AR開発の費用相場
AR開発の費用は、前述の「提供形態(Web/アプリ)」と「開発手法(SaaS/スクラッチ)」の組み合わせによって具体的に決まります。
ここでは、代表的な3つの開発手法について、それぞれの費用相場とメリット・デメリットを解説します。
【月額数万円~】WebAR × SaaSツール利用
これは、既存のAR作成プラットフォーム(SaaS)を利用し、Webブラウザ上で動作する「WebAR」を構築する手法です。
費用相場は初期費用が0円~数十万円、月額利用料が数万円からと、最も安価にARを導入できます。
メリット
最大の利点は、ユーザーがアプリをダウンロードする必要がなく、QRコードやURLから即座にAR体験へ誘導できる手軽さです。
また、SaaSのパッケージ化された機能を利用するため、開発期間も最短数日~と非常にスピーディで、コストを劇的に抑えられます。 期間限定のプロモーションやイベント、商品カタログとの連動などに最適です。
デメリット
SaaS側で用意された機能の範囲内での開発となるため、独自の複雑な機能(例:基幹システムとの連携)や、極めて高品質なグラフィック表現は難しい場合があります。
【100万円~】WebAR × スクラッチ開発
これは、WebARの手軽さを維持しつつ、SaaSでは実現できない独自の機能をゼロから開発(スクラッチ開発)する手法です。 費用相場は100万円程度からが目安となります。
メリット
アプリのダウンロードが不要というWebARの利点を持ちながら、オーダーメイドで必要な機能を実装できます。 例えば、自社のECサイトと連携させた「バーチャル試着・試し置き」からの「そのまま購入」といった、決済システムとの連携も可能です。
デメリット
ゼロから開発するため、SaaS利用に比べて開発期間(数ヶ月~)と費用(エンジニアの人件費)が発生します。 また、Webブラウザの性能に依存するため、ネイティブアプリほど高度な処理は限界があります。
【300万円~】ネイティブアプリAR × スクラッチ開発
これは、App StoreやGoogle Playで配布する「ネイティブアプリ」として、AR機能をゼロから開発する手法です。
費用相場は300万円からとなり、機能の複雑さによっては1,000万円を超えるケースもあります。
メリット
スマートフォンやタブレットのOS(iOS/Android)に最適化されるため、デバイスのGPS、ジャイロセンサー、高性能カメラ(LiDARスキャナなど)の性能を最大限に引き出した、最も高機能で高品質なAR体験(例:ARゲーム、高度な業務支援ツール)を実装できます。
デメリット
費用が最も高額になる点に加え、iOSとAndroidの両方に対応する場合は、それぞれの開発コストが別途発生する可能性があります。
また、ユーザーに「アプリを検索し、ダウンロード・インストールしてもらう」という高いハードルが存在します。
AR開発費用の内訳について
AR開発の見積もりを取得した際、その金額が何によって構成されているかを理解することは、発注先の選定やコストの妥当性を判断する上で不可欠です。
AR開発の費用は、主に以下の4つの項目から成り立っています。
①企画・ディレクション費
これは、ARを通じてユーザーに「どのような体験を提供するか」「それによって何を達成するか」というプロジェクトの根幹を設計し、全体の進行を管理するための費用です。
プロジェクトマネージャーやディレクターの人件費が該当します。
ARは「ただ3Dモデルが出る」だけでは意味がなく、プロモーションや業務改善といった目的を達成するための「体験シナリオ」が重要です。 この企画の質がAR施策の成果を直接左右するため、安易に削減すべきではないコストと言えます。
②コンテンツ制作費(3DCG、動画、画像など)
これは、AR空間に出現させる「モノ」そのものを制作するための費用です。 具体的には、商品の3DCGモデル、キャラクターのアニメーション、再生させる動画、表示するテキストや画像(テクスチャ)などが含まれます。
特に3DCGモデルは、そのクオリティ(精細さ)や制作する数によって費用が大きく変動します。 例えば、家具の「試し置き」ARであれば、実物にいかに忠実なCGを用意できるかが鍵となり、専門のデザイナーによる工数が発生します。
③システム開発費(SaaS利用料 または スクラッチ開発費)
これは、ARを実現するための「システム」構築にかかる費用であり、先のセクションで解説した開発手法によって中身が大きく異なります。
- SaaSツール利用の場合
プラットフォームの「初期費用」および「月額利用料」が該当します。
開発工数が少ないため安価です。 - スクラッチ開発の場合
エンジニアやプログラマーがゼロから開発するための「人件費(人月単価)」が該当します。
オーダーメイドのため、高額になりやすいです。
見積もり上、この項目が「利用料」なのか「開発人件費」なのかは、総額を比較する上で最大のポイントとなります。
④保守・運用費(サーバー代・ライセンス料など)
これは、開発したARコンテンツを「公開し続ける」ために必要なランニングコストです。
開発費(初期費用)だけでなく、この運用費も予算に含める必要があります。
- WebARの場合
コンテンツを配置する「Webサーバーの維持費」や、特定のAR開発エンジン(例:8th Wall)を利用する場合の「ライセンス料」がかかります。 - ネイティブアプリの場合
App StoreやGoogle Playの開発者アカウント「年間登録料」や、不具合修正・OSアップデート対応などの「保守費用」が発生します。
【4ステップ】AR開発の流れとは
AR開発を初めて発注する際、どのようなプロセスでプロジェクトが進むのか、イメージが湧きにくいかもしれません。
ここでは、AR開発を依頼してからユーザーに届けられる(公開される)までの一般的な流れを、4つの簡単なステップに分けて解説します。
STEP1:企画・要件定義
これは、プロジェクトの成功を左右する最も重要な出発点です。
まず発注者側(自社)が「ARで何をしたいのか」「誰にどのような体験を届けたいのか」という目的を開発会社と共有します。
AR開発特有のポイントとして、この段階で「開発手法」を選定する必要があります。
例えば、「プロモーション目的で、予算を抑えて短期間でリリースしたい」のであれば「WebAR × SaaSツール」が適切かもしれませんし、「高機能な業務アプリが必須」であれば「ネイティブアプリ × スクラッチ開発」を選ぶことになります。
この目的に対する手法の選定が、後の予算とスケジュールを決定づけます。
STEP2:コンテンツ制作(3DCGや動画の作成)
企画が固まったら、AR空間に出現させる「コンテンツ(素材)」を制作するフェーズに入ります。 商品パッケージをマーカーにするための画像デザインや、出現させる3Dモデルの制作、再生するためのプロモーション動画の編集などがこれに該当します。
特に3DCGモデルは、スマートフォンのブラウザ(WebAR)でも滑らかに表示できるよう、ポリゴン数(データ容量)を最適化するといった専門的な調整が必要になる場合があります。
STEP3:開発・実装(ツール設定、プログラミング)
制作したコンテンツ素材を、ARとして動作するシステムに組み込んでいくフェーズです。
この工程は、STEP1で選んだ手法によって作業内容が大きく異なります。
- SaaSツール利用の場合
開発会社の担当者が、ツールの管理画面上で「どのマーカーを認識したら、どの3DCGを表示するか」といった設定作業を行います。プログラミングが不要なため短期間で完了します。 - スクラッチ開発の場合
エンジニアが、ARKit(iOS)やARCore(Android)などの開発環境を用いて、ゼロからプログラミングを行い、必要な機能を実装していきます。
STEP4:テスト・公開
システムへの実装が完了したら、最終的な動作確認(テスト)を行います。
実際のスマートフォン端末を使用し、「マーカーは正しく認識されるか」「3DCGモデルは意図した位置に出現するか」「動作は重くないか」などを、様々な環境(OSのバージョン、機種など)で検証します。
ここで発見された不具合(バグ)を修正し、発注者側の最終確認を経て、問題がなければ「公開」となります。
WebARであればWebサーバーへのアップロード、ネイティブアプリであればApp StoreやGoogle Playへの申請・公開をもって、プロジェクトは完了となります。
AR開発の費用を抑えるポイントとは?
AR開発の費用は、選ぶ手法によって大きく変動しますが、特にプロモーション目的で「コストを抑えつつ、スピーディに導入したい」場合は、最適な選択肢が存在します。
それは、「WebAR」と「SaaSツール」を組み合わせて活用することです。
ここでは、この手法がなぜコスト削減に直結するのか、その理由を3つのポイントから解説します。
アプリ開発・運用コストを丸ごと削減できる
まず、「WebAR」を採用する最大のメリットは、ネイティブアプリ開発にかかる費用とハードルを根本的に解消できる点にあります。
ネイティブアプリ開発で発生する高額な開発費(iOS/Android両対応の場合はさらに増加)や、App Store/Google Playの年間登録料、OSアップデートに伴う保守費用が一切不要になります。
また、ユーザー側に「アプリをダウンロードしてもらう」というマーケティング上の最大の障壁が存在しないため、QRコードやURLから即座に体験してもらえるという導入の手軽さも、施策の成功率を高める上で大きな利点となります。
スクラッチ開発に比べ、開発費・期間を大幅に短縮
次に、「SaaSツール」を利用することで、ゼロから開発する「スクラッチ開発」に比べて、開発費用(人件費)とプロジェクト期間を劇的に圧縮できます。
SaaSプラットフォームには、ARを実現するための基本的な機能(マーカー認識、3DCG表示、動画再生など)が既にパッケージ化されています。
これにより、本来であればエンジニアが数ヶ月かけてプログラミングする工数を、ツールの「設定作業」で代替することが可能になります。
結果として、初期費用を抑えながら、企画から公開までのリードタイムを最短数日レベルまで短縮することも可能です。
補助金・助成金を活用する
AR技術の導入は、企業の販売促進活動の強化や、業務プロセスのデジタル化(DX推進)の一環として、国や地方自治体が管轄する補助金・助成金の支援対象となるケースがあります。
例えば、「IT導入補助金」や「事業再構築補助金」といった制度が活用できる可能性があります。
これらの制度を利用できれば、開発費用の数分の一の補助を受けられる場合があり、実質的な負担を大幅に軽減できます。
開発会社側で補助金の申請サポートを専門に行っている場合も多いため、発注先に相談してみてもいいかもしれません。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
今回はAR開発の費用相場について、開発手法ごとの違い(Web/アプリ、SaaS/スクラッチ)や、費用の内訳、コスト削減のコツまでを解説してきました。
「月額数万円」から「数百万円」まで、どの手法を選ぶかで費用が大きく変わることをご理解いただけたかと思います。
弊社では、ARを始めとするXRコンテンツの受託開発を行っております。
ARの導入にご興味がある方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。
ARコンテンツ制作!自社開発による柔軟性でお客様のビジネスをリードする『monoAR』
サービスの特徴や導入事例をまとめた資料をご用意しました。

monoARサービス紹介資料の無料ダウンロードはこちら
資料をダウンロードする
 TWITTER
TWITTER
 FACEBOOK
FACEBOOK
 はてブ
はてブ