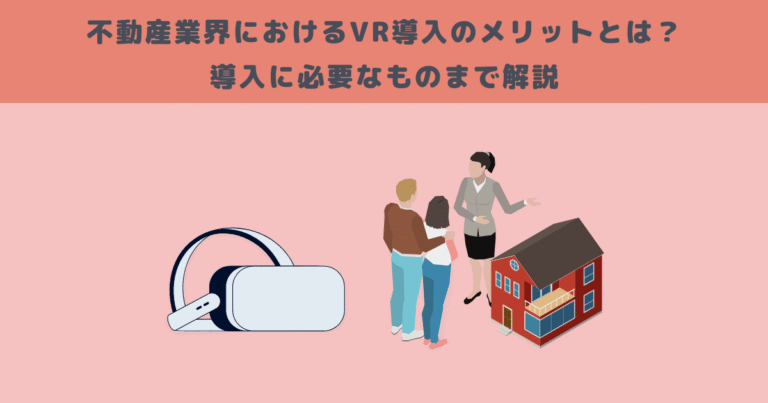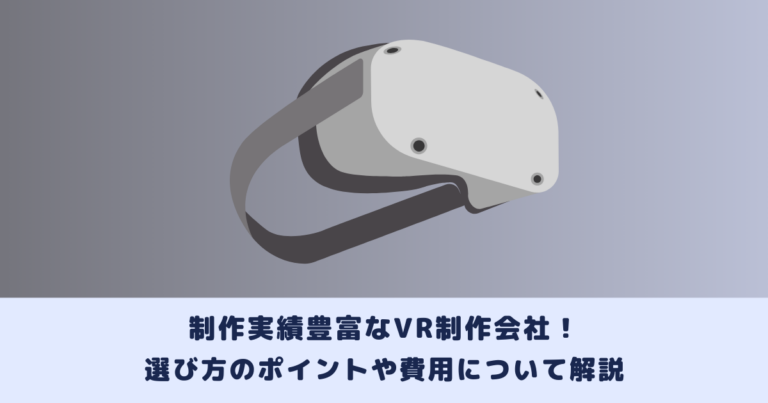内見のスケジュール調整や遠方のお客様への対応に、課題を感じていませんか?
「現地を見ないと決められない」という物理的な壁を越える技術として、現在VR内見のような不動産業界におけるVR活用が注目されています。
VRと聞くと、専用のゴーグルが必要な高額で難しい技術だと思われがちですが、実はWebブラウザだけで完結する手軽なサービスも増えています。
本記事では、不動産業界におけるVRのメリットから、基礎的な仕組み、360度画像とメタバースの違いなど網羅的にご紹介します。
目次
不動産業界におけるVR技術とは?
一般的に「VR」と聞くと、ヘッドセットを装着して体験するゲームのようなものを想像する方が多いかもしれません。
しかし、現在の不動産業界で主流となっているVRは、PCやスマートフォン、タブレットなどの画面上で手軽に操作できるものがほとんどです。
現地に行かずに内見体験ができる技術
不動産業界におけるVRの本質は、物理的な移動を伴わずに、まるでその場にいるかのような空間体験を顧客に提供できる点にあります。
従来の静止画や動画では、撮影者が切り取ったアングルしか見ることができませんでした。
一方でVRは、ユーザー自身が見たい方向を自由に操作し、360度見渡すことができるため、空間の広がりや奥行きを直感的に把握することが可能です。
特に近年では、専用のアプリケーションをダウンロードする必要がなく、Webブラウザ上でURLを開くだけで閲覧できる「WebVR」と呼ばれる形式も一般的になっています。
これにより、営業担当者がメールやLINEでURLを送付するだけで、顧客は即座に内見体験を開始できるため、強力な営業支援ツールとして定着しつつあります。
写真(パノラマ)とCG(バーチャル)の違い
一口にVRと言っても、その生成手法によって大きく「パノラマVR」と「CG VR」の2種類に分けられます。
まず「パノラマVR」は、実在する物件を360度カメラなどで撮影し、その複数の写真を球体状につなぎ合わせて作成するものです。
ありのままの現況を映し出すため、賃貸仲介や中古物件の販売など、すでに建物が存在する場合に適しています。
次に「CG VR」は、コンピュータグラフィックスを用いて仮想空間上に建物を構築するものです。
こちらは、未完成の新築マンションや、これからリノベーションを行う物件の完成イメージを見せる際に重宝されます。
また、実写ではないため、家具の配置を自由に変えるシミュレーションや、現実には不可能な演出を加えることも可能です。
不動産会社がVRを導入する3つのメリット
ここでは、不動産会社がVRを導入することで得られる、主要な3つのメリットについて詳しく解説します。
内見業務の効率化とコスト削減
最大のメリットは、現場スタッフの負担となっている「内見業務」の大幅な効率化です。
従来の内見業務では、鍵の手配や現地までの往復移動、立ち会いなど、1件の案内に数時間の拘束時間が発生していました。
特に、契約に至らない「とりあえず見てみたい」という段階の顧客への対応は、営業効率を下げる大きな要因となっていました。
しかし、VR内見を導入することで、顧客は手持ちのスマートフォンで予習ができるため、確度の低い内見希望を事前にフィルタリングすることが可能になります。
その結果、現地案内は「最終確認」のフェーズにある顧客だけに集中させることができるようになります。
移動コストや人件費を削減しつつ、営業リソースを成約に近い顧客へ集中投下できる点は、非常に大きなメリットと言えます。
遠隔地の顧客へのアプローチと成約率向上
VRを活用することで、物理的な距離の制約がなくなり、遠隔地に住む顧客へのアプローチが可能になります。
例えば、転勤や進学で遠方から物件を探している顧客にとって、何度も現地へ足を運ぶことは金銭的にも時間的にも大きな負担になります。
写真だけでは伝わりにくい「天井の高さ」や「部屋の広さ」、「生活動線」をVRで正確に伝えることで、現地に行けない顧客の不安を解消することができます。
これにより、来店前の段階で物件の絞り込みが完了するため、初回の問い合わせから成約までのリードタイムが短縮される傾向にあります。
また、事前にVRで詳細を確認している顧客は、現地内見時の「イメージと違った」というミスマッチが起こりにくくなります。
結果として、無駄な内見が減り、実内見からの成約率が向上するという好循環を作り出すことができるでしょう。
Webサイトの滞在時間伸長によるSEO効果
営業効率や成約率といった直接的な効果に加え、実はWebマーケティングの側面でもVRは効果を発揮します。
具体的には、自社WebサイトにVRコンテンツを埋め込むことで、ユーザーのページ滞在時間が伸び、SEO(検索エンジン最適化)に良い影響を与える可能性があります。
一般的な物件詳細ページでは、画像とテキストを流し読みする程度で離脱してしまうユーザーも少なくありません。
しかし、VRコンテンツはユーザー自身が能動的にクリックやスワイプを行い、空間内を移動して閲覧するため、必然的にそのページに留まる時間が長くなります。
Googleなどの検索エンジンは、ユーザーが長く滞在するページを「質の高いコンテンツ」と判断する傾向があります。
つまり、VRコンテンツを充実させることは、顧客満足度を高めるだけでなく、検索順位の向上による自然検索流入の増加にも寄与するのです。
不動産業界で活用できるVRの種類
不動産VRの導入を検討する際、多くの担当者が混乱するのが「ツールの種類」と「技術用語」です。
市場には様々なサービスが存在しますが、大きく分けると「360度パノラマ画像」と「メタバース・CG空間」の2つに分類できます。
さらに、これらを包括する上位概念として「XR(クロスリアリティ)」という言葉があります。
ここでは、それぞれの特徴と関係性について、整理していきます。
手軽に導入できる「360度パノラマ画像」
現在、不動産ポータルサイトやホームページで最もよく目にするのが、この「360度パノラマ画像」タイプです。
これは専用カメラで撮影した写真を、球体状につなぎ合わせて表示する技術です。
Googleストリートビューをイメージしていただくと分かりやすいでしょう。
代表的なツールには「Matterport(マーターポート)」や「スペースリー」などがあります。
このタイプの最大の特徴は、実写ベースであるため、部屋の汚れや日当たりなどの「ありのままの現況」をリアルに伝えられる点です。
撮影も比較的簡単で、導入コストも安価なため、賃貸仲介や中古売買の現場で広く普及しています。
ただし、基本的には撮影した定点(スポット)から見渡す形式であり、空間内を自由に歩き回ったり、家具を動かしたりといったインタラクティブな操作には不向きです。
自由な移動と接客ができる「メタバース・CG空間」
パノラマ画像よりもさらに自由度が高く、体験価値を重視したものが「メタバース・CG空間」タイプです。
こちらは写真を貼り合わせるのではなく、コンピュータグラフィックス(CG)で仮想空間そのものを構築します。
そのため、ユーザーはゲームのように空間内を自由に歩き回ることが可能です。
最大の特徴は、単なる「閲覧」にとどまらず、コミュニケーションを含めた「体験」が可能になる点です。
例えば、営業担当者がアバターとして空間内に入り込み、お客様のアバターを案内しながら音声で会話をする「バーチャル接客」が実現できます。
また、壁紙の色を瞬時に切り替えたり、何もない部屋にバーチャル家具を配置して生活イメージをシミュレーションしたりすることも可能でしょう。
新築マンションのモデルルームや、大規模な住宅展示場のイベントなど、ブランドイメージや顧客体験を重視するシーンで特に力を発揮します。
これらを包括するXR技術と不動産業の関連性
XRとは「Cross Reality(クロスリアリティ)」または「Extended Reality(エクステンデッドリアリティ)」の略称で、現実世界と仮想世界を融合させる技術の総称です。
少し難しく聞こえるかもしれませんが、シンプルに言えば「VR・AR・MRなどをまとめた呼び名」だと考えてください。
具体的には、以下のような技術が含まれます。
- VR(仮想現実):これまで解説した通り、仮想空間に入り込む技術(例:バーチャル内見)。
- AR(拡張現実):現実世界にデジタル情報を重ねる技術(例:スマートフォンのカメラを通して、何もない部屋に実寸大の家具を試し置きする)。
- MR(複合現実):現実世界と仮想世界を密接に融合させる技術(例:専用グラスをかけると、建築予定地に完成後の建物が実寸大で現れ、中に入って確認できる)。
近年では、VRのみならず、これらを組み合わせて活用する事例も増えてきています。
例えば、自宅にいながらVRでモデルルームを見学し(VR)、気に入った家具があれば自分の部屋にARで試し置きをする(AR)、といったシームレスな体験です。
単に「画像を見せる」だけでなく、「XR技術を使って顧客体験全体をどう向上させるか」という視点を持つことが、競合他社との差別化に繋がります。
導入には何が必要? 機材と費用の目安
不動産VRの導入を検討する際、多くの担当者が「専用の高価なカメラが必要なのではないか」「システム利用料が高いのではないか」という不安を抱きがちです。
しかし、技術の進歩により、現在ではスモールスタートが可能な環境が整っています。
ここでは、実際に導入する際に必要となる機材やツール、そして費用の考え方について解説します。
撮影機材:スマホで十分? それとも360度カメラが必要?
結論から申し上げますと、商用利用として顧客提供するのであれば、「360度カメラ」の利用が良いでしょう。
もちろん、スマートフォンに広角レンズキットを装着し、専用アプリで撮影する方法も存在します。
しかし、スマートフォンでの撮影は、複数枚の写真を撮影して合成する手間がかかる上、つなぎ目がズレてしまうリスクが高いです。
部屋の隅が歪んで見えたり、画質が粗かったりすると、かえって物件の印象を悪くしてしまう可能性があります。
一方で、「RICOH THETA(シータ)」や「Insta360」といった一般的な360度カメラであれば、シャッターを一度押すだけで空間全体を撮影できます。
価格もエントリーモデルであれば3万円〜5万円程度で購入可能です。
撮影にかかる人件費や、出来上がりのクオリティを考慮すれば、専用カメラへの投資は十分に回収できるコストパフォーマンスと言えます。
ツール比較:無料ツールと有料ツールの決定的な違い
撮影したデータをVRコンテンツとして閲覧できるようにするためには、作成ツールの利用が必要です。
これにも「無料」のものと「有料」のものがありますが、ビジネスで利用する場合は、有料ツールの導入が必須に近いと言えます。
無料のツールやプランは、あくまで「お試し」としての位置付けが多く、公開できる物件数に制限があったり、画質が低く設定されていたりします。
また、自社のWebサイトに埋め込んだ際に、無関係な広告が表示されてしまうケースもあり、企業としての信頼性を損なう恐れがあります。
一方、有料ツール(月額制のクラウドサービスなど)では、撮影画像のつなぎ合わせ処理が自動化されていたり、間取り図と連動させる機能が使えたりします。
さらに、パスワード制限などのセキュリティ機能や、アクセス解析機能が充実している点も大きな違いです。
月額数千円〜数万円程度で利用できるサービスが多いため、必要な機能と予算を照らし合わせて選定しましょう。
制作コスト:自社制作と外注の使い分け
最後に、VRコンテンツを「自社で作る(内製)」か、「プロに依頼する(外注)」かという判断基準についてお伝えします。
この判断は、「質」と「量」のどちらを優先するかで決まります。
賃貸物件や中古売買のように、物件の回転が速く、数多くの物件を掲載したい場合は、「自社制作」が適しています。
一方で、高級マンションのモデルルームや、企業のショールーム、大規模なメタバースイベントなどは、「外注」を検討すべきです。
メタバース空間やVRコンテンツを一から構築する場合、専門的なCG制作スキルが必要となるため、制作会社への依頼が一般的です。
まずは手軽な物件から自社で撮影を始め、ここぞという勝負物件だけ外注するなど、使い分けるのが賢い運用方法です。
自社に合うのはどっち? 目的別の選び方
ここまで解説してきた通り、VRには様々な種類や価格帯のサービスが存在します。
「結局、うちの会社にはどれが合っているのか?」と迷ってしまう方も多いでしょう。
重要なのは、ツールの知名度や価格だけで選ぶのではなく、自社のビジネスモデルや解決したい課題に合わせて選ぶことです。
ここでは、大きく2つの目的に分けて、推奨されるツールのタイプをご紹介します。
とにかく物件数を多く見せたい場合
賃貸仲介や中古物件の売買を行っている企業であれば、「数」と「スピード」が最優先事項になります。
取り扱う物件の入れ替わりが激しいため、1つのコンテンツ制作に時間やコストをかけ過ぎると、運用が回らなくなってしまいます。
このようなケースでは、撮影から公開までの手順が簡略化された、SaaS型のパノラマVRツールが最適です。
専用アプリと360度カメラを連携させれば、現場で撮影したデータをその場でクラウドにアップロードし、帰社する頃にはVRコンテンツが完成している、といったスピード感での運用が可能です。
誰でも簡単に扱えて、1件あたりの制作コストを安く抑えられるツールを選ぶことが、継続的な運用の鍵となります。
ブランドイメージや接客体験を重視したい場合
一方で、新築マンションのデベロッパーや、注文住宅、リノベーション事業などの場合は、「質」と「体験」が重要視されます。
商品は物件そのものだけでなく、そこに住むことで得られる「ライフスタイル」や「世界観」だからです。
安っぽい画像ではブランドイメージを損なう恐れがあるため、高画質な「Matterport(マーターポート)」や、高品質なCG制作サービスの利用が推奨されます。
また、単に見せるだけでなく、顧客との対話を重視したい場合は、メタバース型のプラットフォームが有効です。
モデルルームでの接客と同じように、お客様の反応を見ながら補足説明をしたり、質問に答えたりすることが可能です。
「Webサイトを見てもらう」という一方通行な関係から、「バーチャル空間でおもてなしをする」という双方向のコミュニケーションへ進化させることで、成約率や顧客満足度の向上が期待できます。
まとめ
本記事では、不動産VRの基礎知識から、具体的な導入メリット、そして最新のXR技術との関係性について解説しました。
一昔前までは「未来の技術」と思われていたVRですが、今や不動産ビジネスにおいて役立つ実務ツールとなりつつあります。
内見業務の効率化や、遠隔地のお客様への成約率向上など、様々な導入成果が期待できます。
しかし、いきなり高額な機材を揃えたり、大規模なシステム開発を行ったりする必要はありません。
まずは自社の課題が「数の確保」なのか、「質の向上」なのかを見極め、適切なツールからスモールスタートを切ることが成功への近道です。
弊社では、メタバース、XR技術を活用したコンテンツの受託開発を行っております。
ビジネスへの導入にご興味がある方は、ぜひお気軽にお問い合わせくださいませ。

 TWITTER
TWITTER
 FACEBOOK
FACEBOOK
 はてブ
はてブ