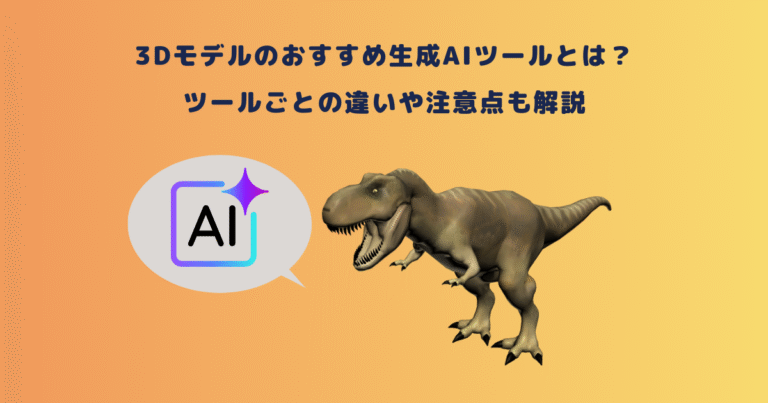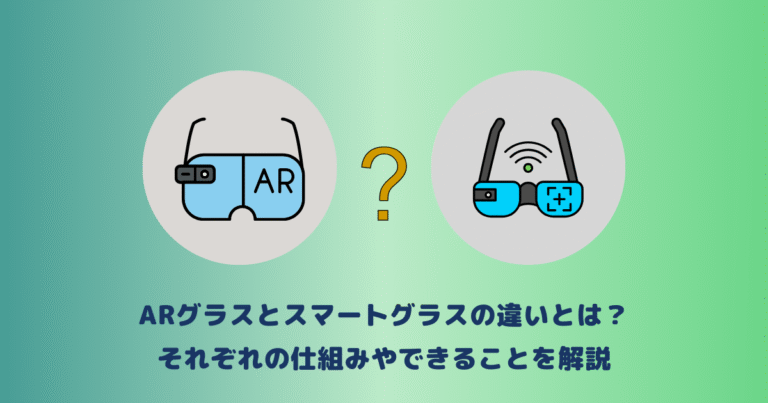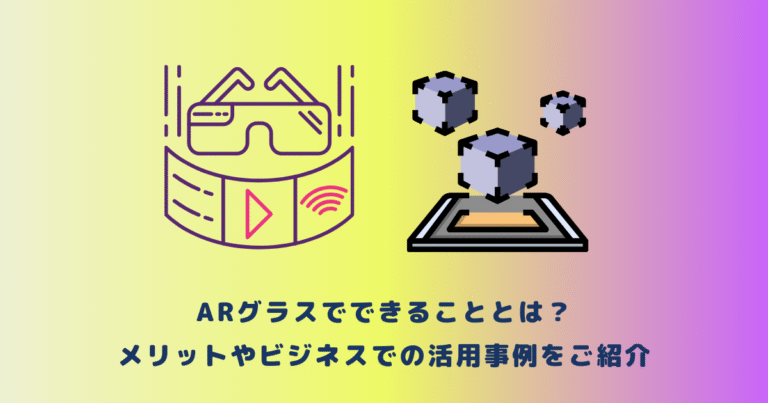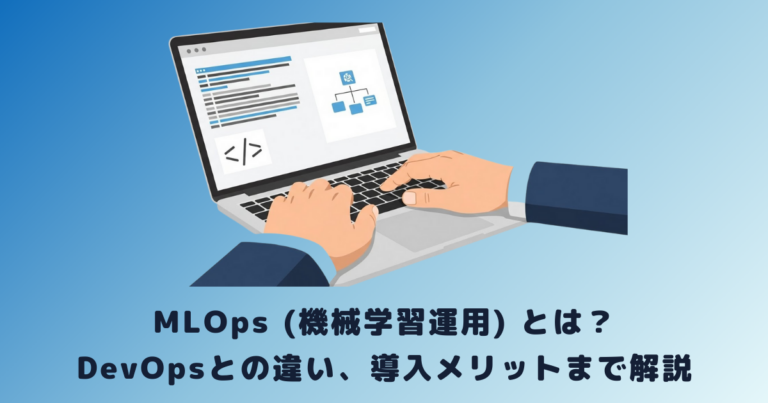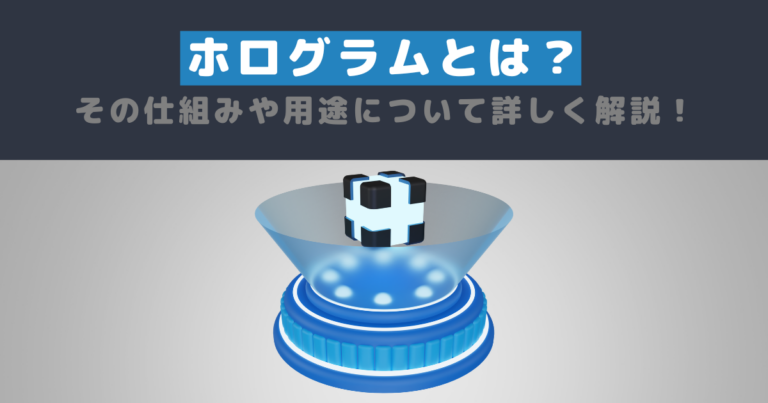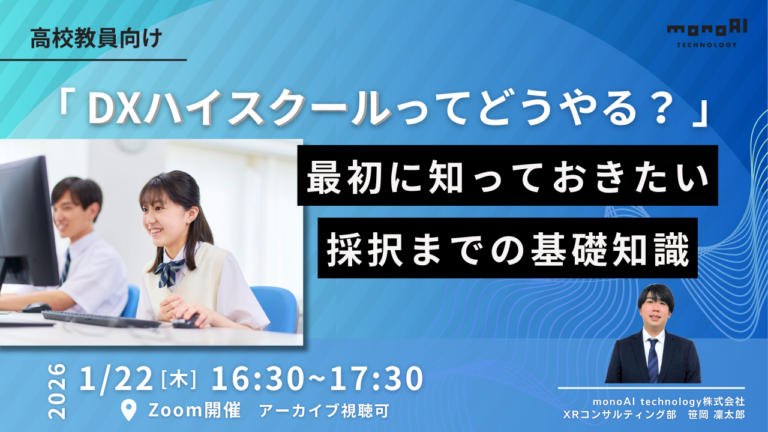AIやIoT、XRのような先端技術を活用した「スマート農業」という取り組みや考え方をご存じでしょうか。
近年、スマート農業の一環として、VR技術の活用が注目を浴びています。
ゲームなどのエンタメ体験で耳にしがちなVR技術ですが、本記事ではVR技術が農業にもたらすメリットや、具体的な活用事例を9つご紹介します。
スキマ時間で読み切れる内容になっているので、農業におけるVR活用に興味を持つ方は、ぜひご一読ください。
「医療研修に時間やコストがかかりすぎる…」その悩みをVRで効率化!
コストを抑えながら反復練習が可能な事例を含む『monoVR』サービスの資料をダウンロードいただけます。

monoVRサービス紹介資料の無料ダウンロードはこちら
資料をダウンロードする目次
- 1 |話題のVR技術とは
- 2 |VR技術の農業への導入背景
- 3 |農業の未来を変える!スマート農業とは?
- 4 |農業にVRを上手く活用した事例9選!
- 4.1 事例①:VRで巡るTOKYO農業 – 都市農業の紹介と体験
- 4.2 事例②:VRでの農産物直売所ツアー – 仮想農産物マーケット探索
- 4.3 事例③:農作業事故を軽減 – VR安全トレーニング
- 4.4 事例④:ARで農機具を販売 – 拡張現実での農機具展示
- 4.5 事例⑤:学生に農業の魅力を知ってもらう -ぶどう栽培VR学習システム
- 4.6 事例⑥:農業・農村体験コンテンツ – YouTubeを活用
- 4.7 事例⑦:シャインマスカット狩り体験 – 自治体初のバーチャルイベント
- 4.8 事例⑧:農業大国オーストラリア産農業VR「ファームVR」 – 販売から人材育成
- 4.9 事例⑨:桃の畑を“VR空間”に再現する研究 – VRでの農業環境シミュレーション
- 5 |まとめ
|話題のVR技術とは
VRとは「Virtual Reality(仮想現実)」の略称であり、3DCGで作られた仮想の空間を専用デバイスで体験できる技術です。
3D映像や立体音響が作り出す仮想空間によって生み出される「没入感」が最大の特徴であり、非現実的な空間体験や、距離制限を超えた空間体験が可能になります。
昨今のVR技術は、ゲームや映画などのエンターテインメント分野のみならず、製造や医療、教育など産業分野での活用も進んでおり、様々な利用シーンが増えています。
|VR技術の農業への導入背景
農林水産省が2023年に公表したデータによると、日本の食料自給率はカロリーベースで38%と、先進国の中でも最も低い水準という結果になっています。
2025年には米騒動の話題もあり、都市部への人口集中も問題として指摘されている昨今、農村部では過疎化に歯止めが効かない苦しい状況も報告されています。
そんな苦しい現状の中、現在スマート農業の一環として注目されているのが「農業×VR」なのです。
ここでは、日本の農業が抱える問題を踏まえ、解決策となりうるVR技術のメリットや活用事例について詳しく解説します。

農業の現状と課題
日本の農業は、地方の過疎化と都市集中、少子高齢化などにより徐々に縮小傾向にあります。
加えて以下のような課題にも直面し、農業の現場では新しい技術による打開策が求められています。
課題①人手不足
日本の農業では、就業者の約7割が65歳以上と高齢化が進行し、特に労働人口の要である若年層の就農率も低下しています。
人手不足は単純な作業効率の低下や収穫の遅延を招き、生産性に大きな影響を与えているため、現場では若年層の就農率向上は勿論、省人化技術や技能継承支援も重要になっています。
課題②気候変動の影響
近年の地球温暖化の影響による異常気象が頻発するようになり、豪雨や猛暑で収穫量の不安定化が深刻な問題となっています。
気候により収穫量が不安定化してしまうことで、消費者に対しても価格や品質の不安定化に繋がりかねません。
このような気候変動にも対応した栽培管理技術も求められています。
課題③生産コストの増加
肥料や燃料、農業機材の価格高騰により、農家の経営負担が年々重くなっています。
これによる生産コストの上昇が消費者への価格転嫁に直結してしまい、農家と消費者両方とも苦しい現状となっています。
また、特に中小規模農家では、コスト増に見合う収益を確保するのが難しく、経営継続の障害となっています。
これらの課題を克服し、農業をより持続可能なものとして継続していくためには、新しい技術や方法の導入が不可欠です。
そして、こういった状況の中で近年注目を浴びているのが、VR技術の導入です。
次のセクションでは、VR技術の主な活用ケースや、VR技術が農業にもたらすメリットについて詳しく解説します。
スマート農業におけるVR技術の主な活用方法
後に具体的な活用事例をご紹介しますが、VR技術の主な活用パターンとしては以下があります。
- プロモーションでの活用
- 教育や研修での活用
リアルな空間を再現できることに強みを持つVRを活用することで、例えば農業体験をコンテンツ化して若者への農業学習や観光体験を促したり、実際の作業で起こり得る事故をVR上に再現することで安全教育を実現したり、と幅広い活用が可能です。
ではこのような活用パターンがある中で、VR技術にはどのようなメリットがあるのでしょうか。
VR技術の農業への導入のメリット
VR技術は、リアルタイムで仮想空間を体験する技術として、多くの分野でその効果を発揮しています。
以下では、その主なメリットを紹介します。
メリット①:効率的かつ安全な教育・トレーニング
農業においては専門的なスキルや知識が要求される場面が多いですが、VRを使用することで実際の作業現場に居なくとも、仮想空間上での実践的なトレーニングが可能となります。
例えば農機具の取り扱いの手順を学んだり、重機で実際に起こり得る事故を再現して事故防止の重要性を学んだりと、幅広い学習内容のカスタマイズが可能です。
これにより、安全かつ短時間で効果的なスキルアップが期待できます。
メリット②:様々なシュミレーション
農地の配置や建築物の設計をVR上で再現することで、事前に最適な配置や設計を検討することができます。
設計図のみで検討する場合、実際にはどのような出来栄えになるのかを検討メンバーで正しくイメージ共有し議論をするのは、簡単なことではありません。
VR上にこれらをシュミレーションすることで、どのような設計が最適になるのかといった検討や議論をより効果的に促し、実際の施設設計や土地利用の失敗の可能性を減らすことが可能です。
また、異常気象や病害虫の発生といったリスクもシュミレーションすることができるため、予めリスクに備えた対応策も検討できるでしょう。
メリット③:消費者とのコミュニケーション強化
実際の農場をVR上にリアルに再現することで、消費者の五感へ直に農業の雰囲気を訴えかけることができます。
それにより、例えばVR上の収穫体験や観光体験などをコンテンツとして提供することで、実際に足を運ぶのが難しい場所からでも、興味関心の獲得に繋げることが可能です。
メリット④:リアルタイムな情報収集と分析
VRとセンサーテクノロジーを組み合わせることで、農地の気象情報や土壌の状態などをリアルタイムで収集・分析することが可能となります。
所謂「デジタルツイン」と呼ばれる技術と総称されることも多いですが、これにより、最適な農作業手順のタイミングや方法を状況に応じて的確に判断でき、より再現性の高いシステマチックな農作業を実現することができます。

これらのメリットを活かすことで、農業はより効率的かつ持続可能なものとなり、現代のさまざまな課題にも対応することができるようになります。
このように、VR技術は農業の未来を大きく変える可能性を秘めています。
|農業の未来を変える!スマート農業とは?
農業におけるVR技術についてご紹介しましたが、改めて「スマート農業」という新しい農業の考え方についても簡単に知っておきましょう。
「スマート農業」とは一体どういうものなのでしょうか。
データドリブンな農作業管理
スマート農業の中心にあるのは、気象情報、収穫量、リソースといった多岐にわたる膨大な「データ」です。
農業におけるデータ分析の最大の魅力は、効率と生産性の大幅な向上を可能にすることです。
従来、多くの農家は経験や直感に基づいて作業を行っていましたが、現代のスマート農業では、センサーやドローンから得られるリアルタイムのデータをもとに、最適な作物の種類や施肥のタイミング、収穫の時期を科学的に判断します。
例えば、土壌センサーが土の湿度や養分をリアルタイムでモニタリングし、それに基づいて最適な水や肥料の量を自動的に供給するシステムなどが登場しています。
また、気象データを解析して、病害虫の発生や収穫の最適なタイミングを予測することも可能です。
自動化と効率化の推進
農業においても自動化が進み、作業の効率化や省人化など生産性の向上に大きく貢献しています。
自動化技術もスマート農業の中心的な特徴であり、従来時間と人手を要していた多くの作業を、高速かつ的確に行う手段として注目されています。
また、ロボティクスの進化は、特に農業分野での自動化の推進に不可欠です。
例えば、収穫ロボットはカメラやセンサーを使用して成熟した果物や野菜を識別し、傷つけることなく繊細に収穫することができます。
他にも、除草ロボットは、害虫や雑草を特定し、人手を使うよりも圧倒的に効率よく作業を終わらすことが可能です。
実際、自動化技術を導入した農場では、作業時間の短縮や労働コストの削減、そして生産量の増加など、多くの利点が報告されています。
このように「スマート農業」は、VR技術は勿論、データ活用やロボティクスなどの先端技術を用いた持続可能な農業の確立を目指し、次世代の農業のモデルとして注目されているのです。
|農業にVRを上手く活用した事例9選!
農業にVR技術のような先進技術を活用するメリットについてはご理解いただけたかと思います。
では、スマート農業ではどのようにVRを活用しているのでしょうか。
ここでは、農業にVRを上手く活用した事例を9つ厳選してご紹介します。
事例①:VRで巡るTOKYO農業 – 都市農業の紹介と体験
東京といえば、煌びやかなネオン街やモダンな高層ビルの景観が目に浮かびますが、その中には知られざる緑豊かな農地も点在しています。
都会の喧騒からは想像もつかない、この隠れた農業の魅力を伝えるために、JA共済連の東京都本部は一風変わったイベントを開催しました。
イベント名は「VRで巡るTOKYO農業〜360°の驚きの体験〜」。
専用のVRゴーグルを装着すると、参加者は3分半の間、スカイツリー周辺の住宅街に秘密のように佇む野菜畑や小さな田園を旅することができます。
映像内では、都市部に存在する農地の魅力や役割がナレーションとともにPRされ、都会と農業が共存する東京の魅力を存分に伝えてくれます。
さらに、映像中で出題されるクイズに正解すると、JA共済オリジナルキャラクター「ひとのわグマ」のグッズが贈られるという仕掛けも。
参加者からは、「東京にこんなに豊かな自然や田畑があるなんて知らなかった!」という声も多く聞かれました。
東京都心の意外な一面を、VR技術を駆使して伝えたこの取り組みは、新しい技術の導入と地域の魅力発信をうまく組み合わせた事例といえるでしょう。
事例②:VRでの農産物直売所ツアー – 仮想農産物マーケット探索
茨城県常総市の「農産物直売所みんなの市場VRツアー」は、360°のパノラマ画像を活用して、農産物直売所の実際の雰囲気や、その周囲の風景をバーチャル空間上で体験できるもの。
実際の売り場や、そこで取り扱われている新鮮な野菜や果物を、まるでその場にいるかのように眺めることができます。
この取り組みの最大の魅力は、遠方に住む人々でも、直売所の雰囲気や地域の魅力を感じることができる点にあります。
特に、都市部の住民など、なかなか直売所に足を運べない人たちが、このVRツアーを通じて、地方の農産物の魅力や新鮮さを実感できるのは大きなメリットといえるでしょう。
さらに、このヴァーチャルツアーを経験したことで、実際に直売所を訪れる動機付けに繋がっているという報告もあり、VR技術が地域資源のPRや観光誘致に効果的であることが示されています。
常総市の取り組みは、今後の農業PRや地域振興のモデルケースとして、他の地域や事業者の参考にできるのではないでしょうか。
事例③:農作業事故を軽減 – VR安全トレーニング
イメージが付きにくいかもしれませんが、農業の現場では危険がつきものです。
特に家族経営の農家や小規模経営の生産者は、事故が個人の責任とされやすく、大規模な教育研修の実施が難しいのが現状。
これを解決すべく、2021年6月に農林水産省の企画と、NTTテクノクロス及びNTTラーニングシステムズの共同制作により、事故防止のための研修用VRコンテンツが公開されました。
この研修コンテンツは、畜産から水産業、林業にかけての4つの業界をカバー。
合計6つの映像を通じて、事故の状況を非常にリアルに体感できる内容となっています。
これにより、臨場感あふれるVR体験を通じて、事故の恐ろしさや予防の重要性を強く感じることができます。
このVR研修方法は、家族経営の農家や小規模経営者にとって、事故防止対策を実現する重要なツールとなりうるでしょう。
事例④:ARで農機具を販売 – 拡張現実での農機具展示
IHIアグリテックは、第34回国際農業機械展in帯広にて、農業機械のAR展示を実施し、来場者にARの可能性を示しました。
展示会では、展示スペースの制約や大型農機具の物理的な制約を乗り越え、AR技術を駆使して農機具の機能や特徴を紹介。
特に、大型の農業機械である細断型ベーララッパ、ジャイロテッダ、大型ハイドロマニュアスプレッダを、実寸大や縮小しての展示、アニメーションによる機能紹介をARで実施。
また、ARをアフターサービスにも応用するコンセプトを提案。
具体的には、部品の形状認識を利用して、部品の内部構造や詳細な情報をARで視覚的に確認できるようにしました。
さらに、IoTとの連携を通じて、故障箇所の確認などの新たなサービスも提案されたとのことです。
この取り組みは、3D CADデータの新たな活用方法としても注目され、AR技術を活用することで、農業機械の販売やサポートの新しい可能性が広がっていることを示しているでしょう。
事例⑤:学生に農業の魅力を知ってもらう -ぶどう栽培VR学習システム
農業業界は若手人材の参入が減少し続けている中、新たな取り組みとしてぶどう栽培のVR学習システムが導入されました。
この取り組みは学生をターゲットに、都市部の学校での授業中や課外活動として利用されています。
VRゴーグルをつけると、まるで実際のぶどう畑に立っているかのような体験ができ、季節ごとの作業やぶどうの生育過程をリアルタイムで学ぶことが可能です。
利点としては、学生たちは実際に畑を訪れることなく、農業の魅力や手間を感じることができ、現実の栽培環境とは異なる条件でのシミュレーションも可能となり、異なる環境下でのぶどうの成長を観察することができる点です。
この体験を通して、多くの学生が農業への関心を持つようになり、将来的には農業へ参入してもらうことが目的になります。
過疎化が進みつつある農村部としては、このような事例は積極的に取り入れるべきでしょう。
事例⑥:農業・農村体験コンテンツ – YouTubeを活用
農村振興局が推進する農業・農村体験動画コンテンツは、都市生活者や学生に対して、VR技術を用いて農業や農村の魅力を伝える取り組みです。
このプロジェクトでは、日常で接触することの少ない農業や農村の風景を、YouTube上の360°動画やフライトシミュレーションを介して、どこでも手軽に体験することができます。
例えば、農産物の成長に必須な水資源の役割や仕組みを空から見る「そらからダムを見てみよう!」、宇宙の端から水のサイクルを追体験する「宇宙の端からダムを通って食卓まで」など、ユーザーが興味を持って取り組めるコンテンツが充実。
さらに、「”自動運転”田植機に乗ってみよう!」のような先端技術を活用した農業の未来を体験できるVR体験も用意されており、農業の効率化や技術革新への期待を高める役割を果たしています。
PCやスマートフォン、またはVRゴーグルを使用して、実際に現地を訪れることなく、よりリアルな農業・農村の体験が可能になるので、若い世代に興味を持ってもらうための良い取り組みなのではないでしょうか。
事例⑦:シャインマスカット狩り体験 – 自治体初のバーチャルイベント
岡山県笠岡市は、コロナ禍の中、旅行制限や対面の制約を乗り越え、VRを活用して自治体初となるふるさと納税イベントを開催しました。
イベントでは、市の代表的なふるさと納税品であるシャインマスカット「たたらみねらるシャインマスカット」をフィーチャーし、実際の果物狩りのような体験を仮想空間上で実現。
仮想空間の中では、360°の画像や映像を駆使して果樹園の雰囲気を再現。
アバターを通じた双方向のコミュニケーションを可能にし、参加者が果物狩りの楽しみや、シャインマスカットの魅力を深く知ることができたとのこと。
イベントの企画や運営には、Yahoo! JAPANが運営するオープンコラボレーションハブ「LODGE」との連携が取られ、最先端の技術やノウハウが活用されています。
VRの利点を存分に活かした例として、注目すべき事例といえるでしょう。
事例⑧:農業大国オーストラリア産農業VR「ファームVR」 – 販売から人材育成
農業大国オーストラリアの農業・畜産業界は、VR技術の多様な活用を進めています。
中でも農業機械のリーディングカンパニー、ケースIHは、VRを研修のツールとして導入。
これにより、国や地域を問わず、指導者と生の状態で製品を見ながら対話することが可能となりました。
販売においてもVRの効果は顕著です。
Eldersという農業ビジネス企業は、家畜や農機具の販売の際、360度の動画を活用。
これまでの家畜の写真撮影の際にはバイヤーへの説明が不可欠でしたが、VR技術の導入により、家畜の全体像を直感的に把握することが可能になりました。
さらに、次世代への啓蒙という視点からもVRの取り組みが行われています。
Farm VRというプロジェクトを主導するTim Gentle氏は、学生への教育啓発のため、VRヘッドセットを装備したバスを運行。
学生たちに農業の現場を直接、バーチャルな視点から体験させることで、農業に対する興味や理解を深めています。
特に、牛肉の生産工程をVRで体験することで、食の原点に対する認識を新たにする生徒も少なくありません。
このような取り組みを通じて、オーストラリアはVR技術を農業・畜産業のさまざまな分野に適応させ、その潜在的な可能性を引き出しています。
事例⑨:桃の畑を“VR空間”に再現する研究 – VRでの農業環境シミュレーション
福島大学の髙田大輔准教授は、桃の歴史、生産、そして販売を専門とする研究者です。
彼が取り組んでいる興味深い研究の一つに、桃の畑をVR空間に再現する試みがあります。
その背景には、果樹の“樹形図”を理解する難しさという課題がありました。
通常、3次元の樹を2次元の図に描写することにより、新米の農家や学生にとってその構造を把握するのは難しいのです。
髙田先生の考える解決策は、立体的に樹を表現できるVRツールの開発でした。
このVR空間では、果実の情報とその位置情報を連動させて保存することができます。
これにより、どの位置の果実が特に美味しかったのかや、甘かったのかといった経年情報を視覚的に確認できるのです。
さらに、果樹栽培において練習の機会が少ないという問題にも対処。VR空間でのシミュレーションにより、実際の栽培前に練習や体験を行うことができるのです。
しかし、このVRツールを実際の農業現場で広く導入するには、まだコストの問題が残っています。
髙田先生はこの問題の克服を目指し、農家たちがこのVR空間をより手軽に活用できる日を目指して研究を続けていくとのことです。
|まとめ
いかがでしたでしょうか。
本記事では、日本の農業におけるVR技術との関わりから、実際の活用事例までをご紹介しました。
これらの事例から、VRは農業現場における業務改善から安全教育、そして消費者体験の強化など、多岐にわたる領域での活用が進められていることがわかったかと思います。
現在、日本の農業は多くの課題を抱えていますが、VR技術の導入はその課題解決の重要な一手となり得るでしょう。
今後のVRの技術革新と農業の現場を繋ぐ取り組みの推進を期待したいところです。
弊社では、農業のような作業現場の安全教育、業務改善などを実現する”産業XRコンテンツ”の開発を行っております。
ARやVR技術の導入にご興味がある方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。
VRを活用した業務改善!
予算やスケジュールに応じた柔軟な開発を可能にする『monoVR』サービス資料を無料でダウンロードいただけます。

monoVRサービス紹介資料の無料ダウンロードはこちら
資料をダウンロードする
 TWITTER
TWITTER
 FACEBOOK
FACEBOOK
 はてブ
はてブ